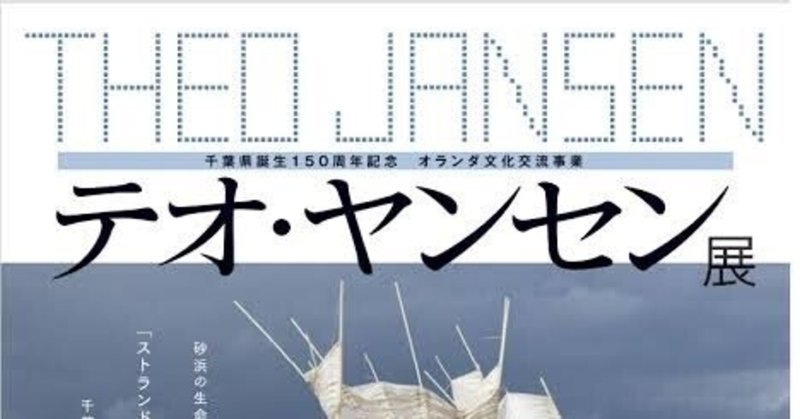
千葉県立美術館「テオ・ヤンセン展」へ行ってきたとのこと
埴輪や仏像、ロボットもそうか。無機物に生命・魂が宿ったような状態に、何か特別な感情を抱くのは人間の根源的な心性に思う。
テオ・ヤンセンの作品、いや、生み出した生物もそうした一連に連なると言えよう。
風を喰みながら自らの体を駆動させる姿は愛らしい事この上ない。美しく、そして、どこか愛おしい、そして、かっこいい、だろう?
しかし、千葉県立美術館で開催された「テオ・ヤンセン展」には心底ガッカリした。
「ストランド・ビースト」が屋外で動く姿が見られるイベントが開催されると知った俺は、自宅から1時間30分かけて現地へ赴いたのだが……。

きたこれ。
イベントは事前申し込み制。時間帯によっては、満員御礼となっており、人気の高さが窺える。

だが……美術館の中庭を歩くストランド・ビーストには、なんら生命が宿っていない。風によって命が吹き込まれる生物にもかかわらず、せっかくのイベントにもかかわらずストランド・ビーストは人力での牽引によって動かされるのだ。

現場に居た担当の方に話を聞くと、この中庭で自らストランド・ビーストが動いたことはないという。千葉の海岸でストランド・ビーストが動いたことはあるらしいので、その際の姿を見られていれば展覧会への印象も変わったかもしれない。
とはいえ。スポット的にしか、要は千葉の海岸でイベントが開催されているときでなければ、作品の魅力を味わえないとなると、いや、はたして、それはどうなのか。展覧会として、どうなのか。作品をベストな環境で見せられていない、どころか、会場では、テオ・ヤンセンが生み出した生物がーーそのままの意味でーー安置されているのはどうなのか。はるか昔に絶滅した生物の化石のようにピクリとも動かない姿は哀しさすら抱く。

いや、死んでいたとしても、作品を間近で見て「へー」だの「ほー」だのと独りごちる博物館的な楽しみはあった。

しかし、俺にとってのテオ・ヤンセンの魅力はーー創造の目的のドライ/ウエットの差はあれどーーフランケンシュタインよろしく、いい意味で頭のぶっ飛んだ人物・キャラクターが“生き物”を産み出し、その姿を見た人間がどのように感情を揺すられるのか、産み出された生き物が何を表象しているのかを楽しむという点にある。
「この動物がわたしから完全に独立して生きることをわたしは夢見ています。まだこの夢は実現していないんです」とテオ・ヤンセンは言う。
アティチュードの表明に過ぎない発言だとしても、その日はなかなか来そうにないし、ヤンセンの態様とは真逆の展示・イベントなっているじゃねえのと痛切させられたのが千葉県立美術館で開催されたテオ・ヤンセン展だった。

なお、会場で販売されていたプラモデル(貧乏な俺は3つを買うのが限界)は、組み上げる楽しさはもちろん、生命を吹き込んでいるかのような錯覚すら覚える。サイコー。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
