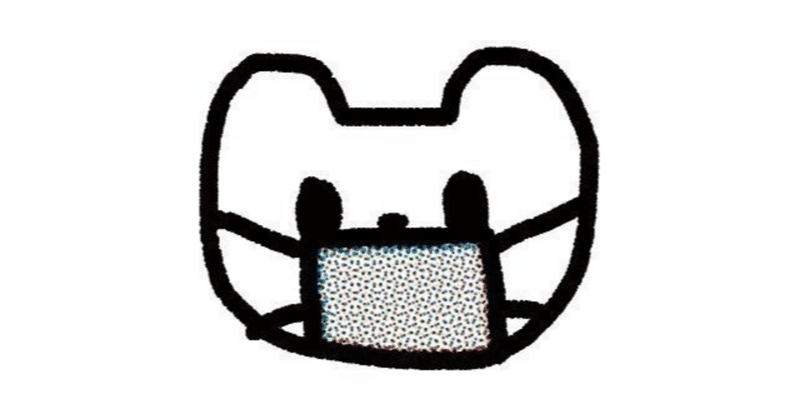
信仰は風邪にかかるのと似てる
現代日本において、「信仰」というのはあまり肯定的に見られない風潮がある。「○○という宗教を信仰しています」と公言すると、「へ~…」と距離を取られることも多い。
それは、ある程度年代が上の人なら「オウム真理教」が起こした数々の事件が記憶にあるだろうし、最近なら旧 統一教会の件や宗教二世の問題が念頭にあるからだろう。とかく「信仰」は悪者にされやすい現在の風潮を感じる。
ただ、上座部仏教を「信仰」している私の目からすれば、「科学的根拠があります」と言われたら何でも盲信する人たちは「科学教」の信仰者のように見えるのだが、まあ今回の記事の本筋から逸れるのでそれは一旦置こう。
現代のように科学が信頼性を増してきた中で、特定の宗教を信仰する人はなぜ信仰するのか。信仰する、とはどういう現象なのか。
私というサンプルを基に、私なりに考える「信仰という現象」について書いてみよう。
いきなり結論だが、「信仰は風邪にかかるのと似ている」というのが私の持論である。突飛すぎて理解できないと思うので順を追って説明しよう。
まず、何らかの宗教を信仰している人には、その宗教と出会ったきっかけがあるだろう。
自身が人生において解決困難な問題に直面したとか、親族に不幸があったとか、人生の意味に悩んだとか、その宗教の教義に学問的な興味が湧いて学んでみたくなったとか、親しい人がその宗教の信徒だったとか。そのきっかけは人の数だけあるだろう。
そして出会ったのちにその宗教および宗教実践者たちとの関わりによって信仰の道に歩むことになる。その過程も千差万別で、ある瞬間にパッと信仰心が芽生える人もいれば、関わりを深めていく中でだんだんと信仰する心が強まる人もいる。
そして大事なのは、本人が自覚的に信仰しているにしろ無自覚であるにしろ、「信仰」という方向に舵が切られた根本的な理由というのは、本人には自覚できないということだ。
例えば私の場合、上座部仏教に出会い、その教えと実践法に興味を持ち、実践していく中で「私には仏教が必要だ」という思いを強めていって信仰するようになった。
だから私は「これこれこういう理由があるから仏教を信仰している」と言葉で説明できると思っているが(そして事実、人から問われれば言葉で説明するだろうが)、では、「○○」という要素がある、他の優れた宗教やメソッドを知ったら私は仏教から乗りかえるのかというと、答えは「No」だ。
私の場合、「瞑想」という実践法と、全ての事象は相互に依存し絶えず変化するという「縁起」の教えに惹かれた。
しかし、瞑想という実践法なら、アメリカで発達し日本にも近年輸入された「マインドフルネス」という技法は、仏教の瞑想から宗教色を取り払い、宗教に抵抗がある人にも実践できるようにしたものなので、それで代用可能である。
縁起の教えにしても、仏教で学ぶ場合、「輪廻転生」という実証不可能な要素についても信じなければならないので、別の同類の哲学、例えば現象学などを学ぶことで代用可能であろう(完全に代替可能ではないが)。
では私は、仏教という「非科学的な教え」を信仰することを止め、マインドフルネス瞑想の実践と現象学等の哲学や心理メソッドという「科学的な方法論」を学ぶことを選ぶかというと、それはない(将来どうなるかは分からないが)。
仏教から乗りかえない理由はなんだろう。その理由は言葉でいくらでも説明できる気がする。例えば仏教は私が信頼している人が勧めてくれたからだとか、出会った僧侶の方の人間力に惹かれたとか、自分が実践していく中で自分の苦しみが減じていく実感を得たとか。
しかし、ではそれらが本当に私が信仰している理由か、と問われると「それが一番ってわけでもないんだけどな…」という気持ちになる。「本当の理由」に関して「これです!」と言えるものはない。ただ「縁」としか言いようがない。要するに、なんで乗りかえる気にならないのか、本当のところ私にも分からないのだ。
この機微は人が風邪にかかるのに構造として似ている。
風邪にかかるのは、菌やウイルスに体が負けてしまったからだ(近年は異説があるが、とりあえず本記事ではそういうことにする)。では、菌やウイルスが一番の原因か、というと、同じ菌やウイルスがいる環境でもかかる人とかからない人がいる。じゃあかかる側の人間の身体が原因か、というと、身体が丈夫な人でも、とても疲れていて体調が悪ければかかる。また心が落ち込んでいる時は免疫力が落ちて風邪にかかりやすい、ということもあるだろう。
このように風邪にかかる原因は一つではなく、自分の内と外のさまざまな要因が重なって「結果として」風邪にかかるのであって、「これが風邪にかかる唯一の原因だ!」と言えるものはない。
なんでかかったか、原因になりそうなことはいくつかあるけど、結局のところなんでかかったのか分からない。かかってしまったのだからしょうがない、というものだ。
信仰もこれに似ていて、自分の内と外のさまざまな要因が重なって「結果として」信仰してしまうのであって、「これが私が信仰する理由です!」と言えるものはない、と思う。もし「これが私が信仰する理由です!」と言っている人がいたら、本当にその唯一の理由で信仰しているのかもしれないが、単純に他の要因に気付いていない可能性も高い。
余談ながらひとつ思うのは、信仰の理由が唯一の場合は、その理由が失われた場合はその人は棄教してしまうんだろうな、ということだ。「尊敬している人がいるから信仰してます!」だと、その尊敬している人がいなくなったら離れる、というように。
というわけで、「信仰」というものは自分の意識で何とかできる範疇を超えているものだ。
語弊を恐れずに言えば、「信仰しようと思って信仰しているわけではない」のだ、信仰者たちは。「信仰せずにはいられないから信仰している」というのが実態に近いと思う。
これは人が「信じる」という心境になる時に一般的に当てはまることだと思う。多くの人がなにがしかの思想、信条、人生哲学、価値基準を採用していることだろう。「人生は楽しいのが一番」という人もいれば「人の役に立ってこその人生」という人もいるし、「自分が納得できることこそ大事」という人もいるだろう。
その各人が持っているその思想などをその人が「是」とするのは、その人にとっては必然だったのだろう。それら異なる思想はお互いに間違っているわけでなくて、本人の気質だとか性格だとか、家庭環境だとか育った環境だとか、地域性とか何らかの事件に出会ったとかいったさまざまな要因が重なって生じたものだろう。どれか一つだけがその思想等を採用した原因ではないだろうが、どれか一つでも欠けていると採用する思想が変わっていた可能性はある。
そして「人生は楽しいのが一番」という価値基準を採用するのと同じように「この教えに帰依することが生きるうえで大事だ」という人もいるのだ。
何が言いたいかというと、信仰を持っている人も持っていない人も、「信じる」という根本で起きているメカニズムは一緒だよ、ということだ。何を信じているかは違うけど、「信じる」という過程で起きていることは同じだ。
だから、もし「この科学が発展した時代に非科学的な宗教に走るなんて愚かだ」という人がいるなら、その人は人間に対する理解が浅いと言わざるを得ない。その人は自分が「信じている」ものが何なのか、自覚できていないのだから。
そうは言っても、この時代にわざわざ特定の宗教を信仰することは、かなりハードルが高い。そういう人は「なぜ私はこの宗教を信仰するのか」ということを考えることになると思う。だから、私は特定の宗教を信仰している、と公言している人は好きだ。そういう人は私が上記で述べていることは大体考えたことがある人たちなので、話の通りがいい。
宗教の悪い側面ばかりが強調される現代で、少しは宗教に対する見方が良いものになれば良いなと、1人の信仰者として願っている。
本日は以上です。最後まで読んでくださりありがとうございました!
スキやコメントいただけると嬉しいです。
