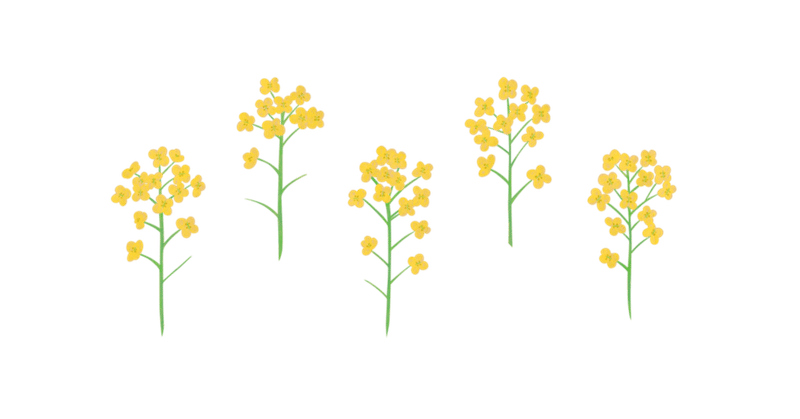
奈良博 『空海展』後期行ってみた
奈良国立博物館で開催中の『空海』展。
いよいよ後期がはじまったので行ってきました。
最近色々宣伝されているようで、なかなかの混雑!
京都や東京に比べたらまだぜんぜんましですけど、でもそれなりに人がいました。
行く方は前売り買って行ってくださいね。
一番行列ができていたのがチケット売り場です…。
さて、展示替えがあった部分を重点的に拝見したのですけど、今回一番私が度肝を抜かれたのは『両界曼荼羅』でした。
5・久修園院 両界曼荼羅
前期では、和歌山・金剛峯寺さんの曼荼羅がかかっていたところに、大阪・久修園院さんの曼荼羅が登場。
これが素晴らしかった。
まず、江戸時代のものなので鮮やかできれいなんです。
さすが江戸時代。
曼荼羅はとにかく絵が細かくて情報量が多いのですけど、それらがとても良く見える。
かすれてたり、線が見えなくなっていないから、曼荼羅の持つ凄さ・パワーを存分に感じることができました。
そしてこれが江戸時代に作られたということは、密教の呪法が脈々と伝わり、江戸時代も受け継がれていたというなによりの証拠です。
密教が生きていた・使われていた、ということが肌で感じられて、それがすごくよかった。
今、この令和の時代に新しく曼荼羅を写す、なんてことしてる所あるのでしょうか?
多くが明治の頃に断絶して、その後消えてしまった、わからなくなってしまった、ということがあるのですが、最近奈良では古式の復興をがんばっているお寺も多くあって、そういうことへも思いがつながる展示でした。
そうそう、曼荼羅の中にカニさんいましたよ。サソリも。
確認してみて下さい。
8・十二天像
十二天像の中の毘沙門天さま。
甲冑に注目です。
Yの字を使ったような模様がありますが、これは奈良の信貴山・朝護孫子寺のマークにもなっています。

この甲冑を身に着けているということは、毘沙門天様ということなのですよ。
他にも宝塔を持っているというのもありますが、甲冑模様チェックしてみて下さい。
10・五大尊像
前期では東寺の五大尊像がお出ましになってて、独特の背景描写とかとても好きだったのですけど、今回は「ザ・密教スター☆醍醐寺」ならではの作品でした。
縦のサイズ180センチとかある巨大すぎる画像。
これだけでも、この仏画にどれだけの気合が入っているか…
これを安置するのはいったいどこなのか…
そういうことを想像するだけでも目がギラギラします。
だって、こんなきょだいなものを架けられる壁って、そうとう背が高く広くないとだめなわけですよ。
でもそういうところを用意して、儀式をしていたのですよ。
そして今回の展示の後ろの方に、この「絵をかけて儀式していた場所の図」が展示されていて、ものすごく参考になりました。(85 年中行事絵巻模本)
火炎に包まれて大迫力の五大尊像。
その細かな模様は、図録ではもう小さすぎるので、現場でじっくり見て下さい。
最初の不動明王は、お付きの童子たちがめちゃ可愛い。
特に向かって左側の制多迦童子は、ちょっと顔をキッと見上げて、まるでお不動さんの真似しているみたいではないですか。ふだんは優しい矜羯羅童子も、ちょっといかめしい感じ。
顔の感じを不動明王様に寄せてきている最高のボーイズです。
降三世明王は、ヒンドゥー教のシヴァ神とその后を仏教に改宗させたという逸話があり、まさに足元に夫妻を踏んでいます。
でも后の方はなんか軽々とおみ足を支えているのが笑える。
そしてシヴァ神の方は、完全に踏まれてて、ひしゃげたお顔が「サザエさん」のアナゴさんみたい(笑)
ここも爆笑ポイントでした。
一番のお気にいりは軍荼利明王。
蛇がまきついているのですけど、よく見ると正面向いている蛇がいる!
蛇の造形で正面って…初めて見ました。
なんかディズニーのキャラみたいじゃないですか??
大威徳明王は、ドクロをいっぱいつけているのですけど、そのドクロの目に紐がとおってネックレスにしているのがなんともすごい。
そして杖を持った手の指先がすっと伸びて、とても健やかな造形美を感じました。
儀式をする部屋の中では、きっと薄暗くろうそくの炎などでもって浮かび上がる尊像たちは、素晴らしく現実味を帯びたことでしょう。
38・三教指帰
前期では空海様の書が素晴らしすぎて、何度も足を運びながら最終的にずっとずっと見ていたのは書でした。
その一文字一文字が素晴らしすぎて、もう見ているだけで芸術という言葉が降ってきて、あこがれと尊敬と、空海さまその人に会っているような幸福を噛み締めていました。
今回その代表であった「聾瞽指帰」がお帰りになってしまって、涙にくれていたのですが、…でも、まだ、俺達には『三教指帰』がある!ということで、三教指帰です。
流麗な文字は本当に素晴らしい!
でもやっぱり聾瞽指帰がいい。もう一度拝みたい。
43・真言七祖像 恵果
前期でも空海様へつながる真言宗の大家たちの肖像画がありました。
空海様のお師匠様・恵果阿闍梨の肖像画・東寺さんのが出ていました。
正直、もう絵はほとんどわかりません。
中国で宮廷画家によって描かれ、日本へ持ち帰られてさらに年月が経っているのですから、空海さまご自身よりも年上の宝物です。残らなくって当然です。童子のほうだけいやにくっきり残っているのは、修復でしょう。
これを眺めていて、正直全然見えないし、絵としての役割はもう終えているとも言えるのですけど、でもこの一幅にどれほど価値があるのかと思うと慄然としました。
ここには、空海様がもたらしたという出来事に加えて、恵果阿闍梨という方が中国でたいへん尊敬されていたこと。恵果阿闍梨なくして空海様はありえず、それは日本の密教がありえず、そこに頼ってきた日本の政治や、貴族たちや、人々の暮らしすら変わってしまうという…何重にも何重にもかけがえのないものが詰まっています。
絵の上部に、空海様の筆と考えられる文字が残っており、これを書く時空海様はどんなことを思ったのか…
価値がある、というのは一体どういうことなのか。
きれいだから、分かるから、役目を果たしているから価値があるのか?
決してそんなことはない。そのもの、そこにあるだけで奇跡的な価値を生んでいるものがある。
そういうことを知らされた作品でした。
72・尺牘(久隔帖)
空海様と同時代の聖人として、まっさきに名前が上がるのは最澄さまでしょう。
今回、その最澄さまの唯一の真筆が出ています。
尺牘(せきとく)とは漢文の書状のこと。
久隔帖(きゅうかくじょう)とは、書き出しが「久隔清音」で始まるので「久隔帖」と呼ばれています。
このお手紙がほんとに素晴らしくて、展覧会の説明文に現代語訳が書いていたので、それを写します。
久しく音信が途絶え とても思い煩われます。
安和にすごしていると伝え聞き まずは安心しました。
大阿闍梨の示された五言八句の詩の序の中に
一百二十礼仏 方円図 註義 などの名があります
今和詩を奉ろうとしてますがその礼仏図というものを知りません
伏してお願いします。
阿闍梨にに伝えて新しく撰述した 方円図などの図や内容を知らせて下さい。
和詩はすぐには作れずまた一度著した文章は後では改められません。
詳しい内容をお示し頂ければ必ず和詩を作り奉ります。
謹んで貞聡に託して申し上げます。
和南
空海さまからお手紙を頂いた最澄さまが、お礼に和詩を作って贈ろうと思う。
しかし、空海様が引用されていた本を知らず、読んでないのでお返事が書けない。
その内容を知らずは書けないので、どうか教えてほしい…って。
最澄さま。あなたはどれだけ、どれだけ、きちんとしていて、真面目で、誠実で、丁寧なんですかっ
まず読んでからお返事を書かないと失礼にあたる…って…
たまたま、この展示の周辺にいた方が
「最澄ってさ、空海より年上なんだよね。でもすごいへりくだってるね(ワラ)」
ってなことを申しておりましてな…
いやいやいやいやいやいやいや
それは違うんでは?
最澄さまは最初からこういう人なのでは?
年下でも同年でも、丁寧に接する人なのでは?
だいたいこれは、自分の弟子に頼んでいるんだし。
弟子にもきちんとしてるって人なんじゃないの??
と切実に思いましたよ…
92・二荒山碑文(ふたらさんひぶん)
日光の二荒山を修験道の道場として開山した下野国の僧侶、勝道。
彼の事績を称える文章を空海様がお書きになっています。
空海様は書がうまいのは知れ渡っていますが、文章もとてもとても巧みで、色んな人から文章を書いてほしいと頼まれまくっていたそうです。
初めて中国にいって、船があらぬところに漂着して、現地民にボートピープル扱いされたときにも、空海様の卓越した書と文章で現地役人を納得させましたからな…
今回のこの碑文が、その才能を豊かに表現しているので、解説文から引用して紹介します。
(中略)
水面の丸い月を見れば普賢菩薩の澄み切った悟りの知恵を知り
空に輝く太陽を仰ぎ見れば仏のあまねく悟りの知恵が
間近にあるように感じられる
勝道はこの景勝地に寺院を建立し神宮外苑と名付けた
水面に浮かぶお月さまを見て、普賢菩薩の悟りを想像します??
太陽の光が仏の悟りの知恵と連想されます??
同じものを見ても、我々と空海さまではぜんぜん違ったんでしょうね…
97・性霊集残巻
空海様の著作を集めた『性霊集』その写本です。
これのスゴイところは、見えない「裏」です。
実はこれは、『日本書紀』の写本を使って書かれているのです。
なので、うっすらと裏側にしてる方の文字が透けて見えます。
当時は紙が大変貴重なもので、その貴重な紙に、貴重な日本書紀を写し、さらに性霊集を写しているのです。
『古事記』とか『日本書紀』とか。
国家が作った本でさえ、そのオリジナルは残っていません。
全部後世の写本なのです。
そして写本というとてつもなく手間暇のかかることをしてくれた人がいたから、私達は古代の記録を読めるのです。
『性霊集』だって、書き写してくれた人がいたからこそ今読めるわけで、そのことをすごさ、ありがたさをもっともっと噛み締めたいと思います。
108・金剛峯寺根本縁起 後醍醐天皇御手印並御跋
またオマエ(後醍醐天皇)かーーーー
と叫びたくなる後醍醐天皇の手の印つき書状。
金剛峯寺には、空海さまが書いたとされる縁起があり、それを見た後醍醐天皇は、「今後、これは門外不出! かわりにこれを拝め!」と自分が書いて自分が手の印をつけたものを作ったそうな…
これ、前期も似たようなのありましたネ
四天王寺にもあるし、いったいあんた(後醍醐天皇)いくつ作ったんだ…
展示品の感想は以上です。
下記はおまけ、全体的な感想です。
ここから書く感想が読みたいかた、忠内香織を支援してもっと色々見てレポート書いて楽しませてちょうだい!と思ってくださる方は、500円でご購入下さい。ありがとうございました。
おまけ 全体的な感想
ここから先は
¥ 500
奈良でガイドをしています。これからもっとあちこち回っておもしろいガイドを提供します。ご支援どうぞお願いいたします。
