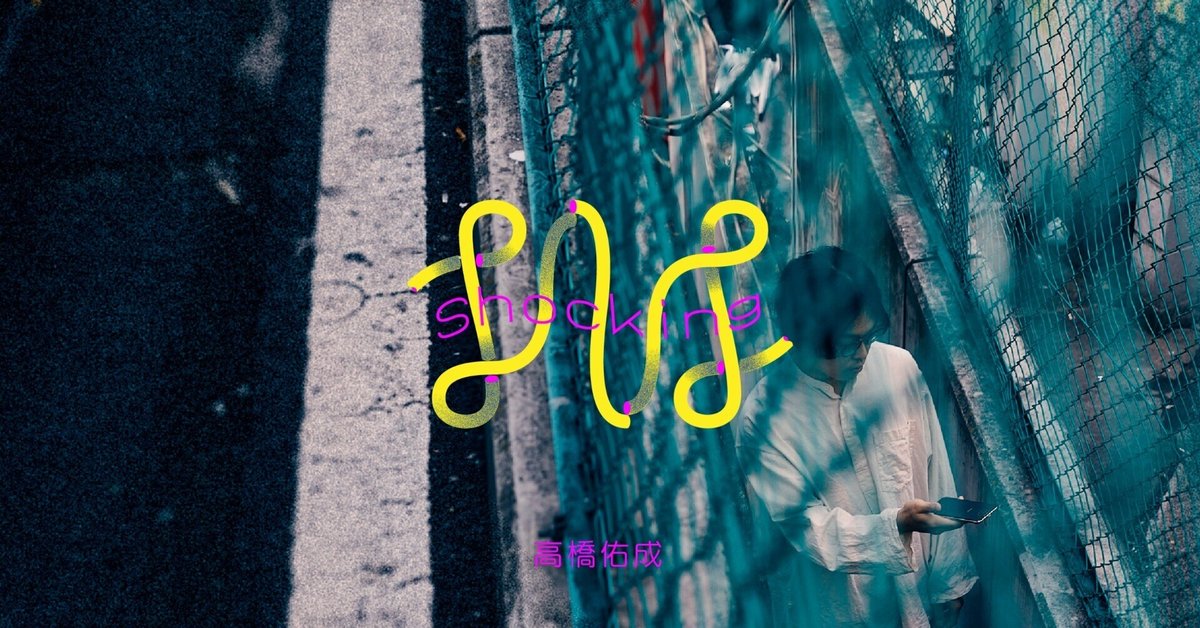
SNS Shocking#3「創造は具象と抽象にゆらめきぬ」(ゲスト:高橋佑成)

Awich「GILA GILA feat. JP THE WAVY, YZERR (Prod. Chaki Zulu)」の<Mステ出たから何? ヒットなきゃ続きはない~>におけるラップのリズムは2小節を12等分する、いわゆる2拍3連(12連/8拍)ではない。それよりも約8%遅い2小節を11等分する、敢えていえば2拍2.75連(11連/8拍)だ。これは非常に興味深い現象なのだが、ほぼほぼ議論されずにスルーされている。
それはさておき、Mステ出演とユニークな音楽創造とで本リリックを体現するジャズミュージシャンが実在する。本企画「SNS Shocking」3回目に話を聞いたのは、MPCプレイヤー・STUTSが主宰するMirage Collectiveなどに参加する傍ら、日野皓正Quintet や自身の音楽ユニット・秘密基地でプレイする高橋佑成。
前回ゲスト・細井徳太郎をして「同世代のなかでも桁違い」と言わしめた彼は鍵盤や譜面、ヒップホップやジャズのビートなどの具象的表現に根ざしつつ、プラグインを使わないアナログシンセ、クオンタイズやグリッドのないリズムなどアブストラクトな音楽領域の探求にも余念がない。さらにICレコーダーを持ち歩いて街のサウンドスケイプ収集もするというから、根っからの変わり者である。
影響源のひとりは坂本龍一氏。確かに70年代末のカクトウギ・セッションやイエロー・マジック・オーケストラ、ソロ作品、映画音楽、ジャズからロック、現代音楽に至るまでのクラシック、ポップス、テクノなど音楽的な横断を体現した教授と似た何かを感じた。
さらに高橋の創作は具象と抽象とに揺れているのだというから、一筋縄ではいかなそうだ。だからこそ我々も知的好奇心を掻き立てられる。では彼のクリエイティヴィティの裏側に迫っていこう。
(写真:西村満、サムネイル:徳山史典、ジングル/BGM:sakairyo)
高橋佑成 ( たかはし・ゆうせい )
1994年東京生まれ。明治学院大学文学部芸術学科卒業。13歳の頃からジャズに興味を持ち独学でジャズを始める。その後中学生対象の世田谷ドリームジャズバンドに加入。日野皓正氏を始めとしたジャズミュージシャンに触れ音楽を学ぶ。現在は世田谷トリオ(岩見継吾(b)、吉良創太(ds))、 m°fe(松丸契(as) , 落合康介(b))、日野皓正Quintet 、自身が主宰する音楽ユニット”秘密基地“、STUTSや七尾旅人のバンドに参加などジャズに限らず多岐に渡って活動している。
Note:https://note.com/ystkhs_art
Twitter:@yusei_T84
Instagram:@yusei_takahashi_music


理論より感覚、でもただ自由なだけじゃない
――高橋さんのジャズ原体験は小学校5年生の時、日野皓正氏のライブを観たことだったとか。まずは、その時のことを教えてください。
高橋:単純にカッコいいなと思いましたね。あとはフリー寄りな演奏だったのもあり、よく理解できなかったのが正直なところです。当時やっていたエレクトーンの大会ではPE'Zを演奏したり。徐々に気持ちがジャズに向いていきましたが、幅広い音楽に触れられたのは今の自分のスタイルに影響していると思いますよ。
――ピアニストのビル・エヴァンスにも刺激を受けたそうですね。
高橋:エレクトーンを辞めようかと考えている時に「Waltz For Debby」を聴いて「鍵盤ってこんなことができるんだ!」とジャズピアノに目覚めました。耳コピは得意でしたが習得は難しかったですね。石井彰さんにも習って音楽理論を主に教わりました。とはいえ音大出身者のように詳しい訳ではなく、スケールやヴォイシングも感覚が強くて、それを確かめるために理論を使うイメージ。譜面も基本的には得意ではありません。
練習に関しては色々な考え方があると思いますが、イメージした音や雰囲気の通りに弾けるようにすることを念頭に取り組みます。始めて間もない頃は、使いたい道具(フレーズ、スケール、音の鳴らし方)を探すこと、またそれが自分の表現にしっくりくるように使いこなせるように、たくさん音源を聞いて好きなフレーズをコピーしました。
あとは、それをしっかり弾けるようにするため、石若駿くんに教えてもらったコルトーの「ピアノメトード」という教本を使い、指を分離して動かすことは心がけていましたね。どんな演奏がしたくて、そのために何が必要かということはいつも心がけています。

――演奏時はどんなことを考えているのですか?
高橋:何を考えているんですかね(笑)。バンドによってまちまちです。
――例えば、私が高橋さんを知ったのは類家心平さんと一緒に池袋・KAKULULUの3周年パーティでウェイン・ショーター「Speak No Evil」を演奏する映像でした。リズムの刻み方や抜き方のセンスがいいなと。この時は?
高橋:デュオ編成でリズム的にも自分に比重があったので自由に崩しつつ、キープするところはしようという意識があったと記憶しています。演奏についての心構えについては日野さんのバンドに入ってから鍛えられたことが多いですね。
技術だけでなく、他の演奏者とどうコミュニケーションするかを求められるし、そのためには精神的に自立していないといけないので。誰かがやったことに付いていくだけだと面白くないし、それぞれのアイデアが混ざり合うことで様々な方向に発展させられるので。
高橋:特に「俺が何をしても、おまえは出したい音を出せ。後で俺が怒ったとしても、自分で説明できるならそれでいい」という日野さんの言葉はよく覚えています。とはいえ、やり続けて怒られることもありましたけど(笑)。
昔から観ていて憧れで、自分も参加してみたいと思っていましたが、日野さんは厳しい一面もある方なのでお腹が痛い時もありました。でもリズムセクションとしてテンポを出しながら遊ぶ、ただ自由なだけじゃない、といった学びは今に至る自分の演奏とって大きかったです。
――怒られて腹が立ったり、理不尽だなと思うことはありませんでしたか。
高橋:正直あります。でも「この部分は正しいな。でもこの部分は同意できないな」と冷静に考えようと心がけてはいました。


シンセサイザーにおけるアコースティックな音
――なるほど。また現在はシンセサイザーのも熱を入れておられますが、これについては?
高橋:2016年くらいにNHKの番組「スコラ 坂本龍一 音楽の学校」で坂本さんがシンセ・EMSを演奏しているのを見てカッコいいと思ったんです。真剣な顔でゆっくりレバーを倒しているけど「ビビビビ…」だけのシュールな画でした(笑)。それをきっかけに調べ始めたのが最初。高価なので同じ楽器は無理でしたが、似た音が出せるREON・driftboxを買ったんです。
シンセの魅力は自分で音を作れるところ。ピアノだと弾き方で音色を調節可能なのですが、実際に弦に触れられないので音を作りづらいんですよ。現代アートの展示で流れているような電子音楽も好きだったのもあり、鍵盤とセットできるなと始めやすかったのもありました。
――好きな音色のイメージを教えてください。
高橋:あまり加工されていないサイン波ですね。カールハインツ・シュトックハウゼンの初期みたいな原始的な電子音が好きなんです。ジャズも含め音源は図書館でよく借りて聴いていました。


――アコースティック/エレクトリックの楽器について相違を感じますか。
高橋:ないですね。モジュラーシンセを使っているのですが、電気のなかの原始的な音、つまりアコースティックみたいな音がするんですよ。なので音色に差は感じません。その一方でピアノの方が伝えたいことを楽器に込めることができる気がしますね。シンセはその部分もすべて音作りしないといけないので、技術的な差はあるかもしれません。だから両方を合わせるとちょうどいいのかなと。
――またYouTubeに挙げているアブストラクトな世界観の「Etude」シリーズについては? 音楽だけでなく映像もご自分で担当されているのが興味深いのですが。
高橋:単純に自分の作品を発信したかったのとモデュラーで色々やってみたくて作ったんです。ピアノとシンセの一緒に使う時は音色を混ぜて一体化させるのは難しいですが、あまりにかけ離れないようには心がけています。
ビデオアートも好きなんですよ。映像と音楽が同期しているような、していないようなものが面白そうだなとチャレンジしたのが最初の『Tower』です。美術作品や自分で写真を撮って日常が別の風景に見えたりすることにもインスパイアされることもあります。ジャクソン・ポロックやフランシス・ベーコンの絵画も好きです。
作曲と即興のはざまへ
――YMOのアメリカツアーでステージ中央にある「タンス」こと「Moog Synthesizer IIIc」もそうですが、たくさんケーブルが刺さったシンセにはジャクソン・ポロックみがあります。高橋幸宏さん逝去のニュースもありましたが、YMOはどう思いますか?
高橋:YMOよりも電子音とピアノのバランス感などが参考になるので、聴くことが多かったのは坂本龍一さんのソロ作品でしたね。特に好きなのは『async』。あれをイメージしつつ、似ないように頑張っている感じです。
――あの作品を出した時に坂本さんのトークセッションを取材したことがあります。「アンチ・シンクロナイゼーション(async)」について「世界の音楽は、99パーセントがひとつの時間軸と同期しています。だから、そうでない音楽はできないかと(思って作りました)」と発言されてました。また00年代には菊地成孔さんも同じような試みをされていたことも思い出されます。
高橋:そうですね。菊地さんのダブセクステットも好きで、TSUTAYAでCDを借りて聴いていました。「どうやってこの音を出してるんだ?」とダブ処理について調べたり、サンプラーに興味を持ったんですよ。60年代のマイルス・デイヴィス的な演奏と機械的な処理の組み合わせが面白かったですね。
――個人的に『async』はフリージャズの方法論に似ているなと感じます。一方で日本におけるフリージャズにはアブストラクトなフリーインプロヴィゼーション的なもの、山下洋輔さん的な息を合わせるアプローチの伝統などがありますが、それについては感じることは?
高橋:個人的にどれもいいと思ってはいます。ただ僕はアブストラクトなだけでも、みんなでわっとやるだけでもなく、バランスよくできたらと。
――またSTUTSさんのMirage Collectiveのメンバーとしての活動についても聞きたいです。彼とはどのようにして出会いましたか。
高橋:ベーシスト・岩見継吾さんの紹介ですね。ちょうど鍵盤の人を探しているということで彼とSTUTSくんの家でセッションして、そこから一緒に演奏するようになりました。日本のヒップホップはスチャダラパーなどを聴いていましたが、最近の曲は知らなかったですね。
でもSTUTSくんと出会ってから聴くようになって、すんなり受け入れられました。鎮座DOPENESSさんはインプロヴァイザーとして本当にすごい。ジャズに近い感覚で言葉を操る人がいるんだなと驚きました。
――最後に今後探求したいことなど教えてください。
高橋:モジュラーシンセとピアノを使って、ちゃんとした自分の作品を作りたいですね。ある程度は作曲されていて、かつ自由な空間も担保されているようなものを構想しています。


次回のゲストは・・・
「SNS Shocking」第3回目。幅広い興味関心のもとで音楽をクリエイトする高橋さんとの話にチャクラがたくさん開かれた気がします。坂本龍一さんの話題も納得感が満載でした。これからもMステに出ながらアブストラクトな方向性を探求するような、複数のベクトルでクリエイトしてほしいなと個人的に期待。
彼が紹介してくれた次のゲストはパーカッション奏者・宮坂遼太郎さん。折坂悠太(合奏)、South Penguin、蓮沼執太フルフィルなどでプレイしながら、大学院で少女漫画の研究を学ぶという彼の謎の生態について迫っていく所存です。次回もお楽しみに。(小池直也)
<写真>
西村満
HP:http://mitsurunishimura.com
Instagram:@mitsuru.nishimura
<サムネイル>
徳山史典
HP:https://unquote.jp/
Twitter:@toquyama
Instagram:@toqu
<ラジオジングル・BGM「D.N.D」>
sakairyo
Twitter:@s_aka_i
Instagram:@s.aka.i
YouTube:https://t.co/kq3T1zhbVL
※本記事は無料ですが、最後の余白に投げ銭として有料エリアを設けました。集まった金額は企画存続のため&ZINE化のために使用されます。お気持ちのある方は宜しくお願い致します!
ここから先は
¥ 500
この記事が参加している募集
活動継続のための投げ銭をいただけると幸いです!
