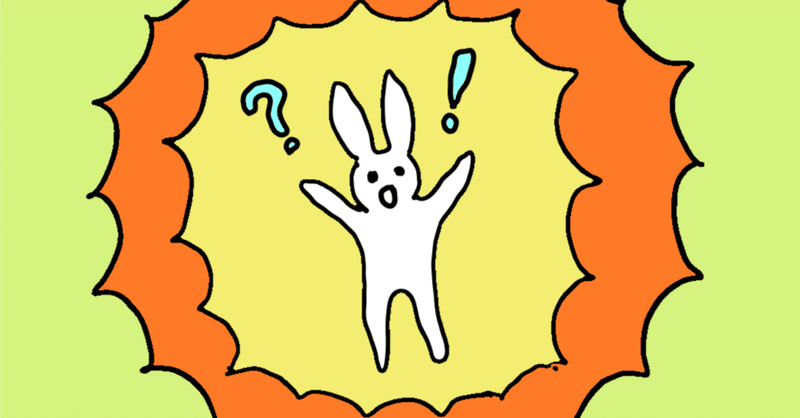
【マガジン】好奇心をどうやって伸ばすか
子どもを見ていると、本当に好奇心・探究心の塊です。
未知な物に対して、見てみたい、触れてみたい、食べてみたいという欲求。
これはすごい物だなと。
赤ちゃんの時の動きのモチベーションは、お腹が減った、うんちがしたい、気持ち悪いなどの快・不快の感覚が中心ですが、それ以外に関しては好奇心以外にないのでは?と思ってしまいます。
覚醒が下がると好奇心も下がります。
ですから、好奇心は覚醒と関連してそうですし、逆に起きていれば何かしら興味があるものを探しているのが生き物なのかも知れません。
動物の進化を考えてみても、未知な物に対する恐怖と同じくらい好奇心が優った場合に、新しい環境へ足を踏み出し新たな能力を獲得したのが進化なのかも知れません。
野生動物を見ても、人間に遭遇した場合、怖がって逃げるのが常ですが、中には興味を持って恐る恐る近づいてくるものもいます。
特に子どもがそうですが、怖いという感情と好奇心はおそらく相反していて、恐怖心は保守に、好奇心は冒険に繋がっているのでしょう。
仕方なく環境の変動によって進化が起こったこともありますが、中には好奇心で進化を起こしたケースもあるのでは?と淡いロマンを覚えてしまいます。
好奇心に関しては、大人と子どもも比較すると面白いです。
基本的に人間の子どもは好奇心旺盛です。
未知なものへは恐怖よりも好奇心が勝ります。
だらこそ、怪我もしますし客観的な状況判断ができなため危険を犯してしまうこともあります。
ただ、好奇心を保持し続けている人は大人になって新しい何かを作り出したいり、発見したりという人類としての進化を作っていく人になるのではないでしょうか。
今回は、イノベーションや変革の元である好奇心をどう伸ばすのかという点について考えてみたいと思います。
ここから先は
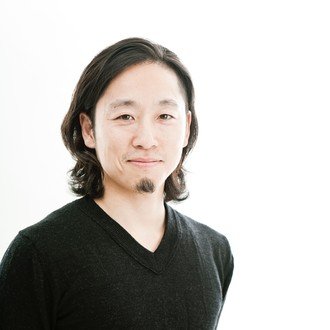
中村尚人の仕事術〜肩書きよりも個人という生き方〜
ヨガ・ピラティスインストラクター、理学療法士、温泉利用指導者、株式会社の代表取締役など様々な立場で、色々なことをしている中村尚人の、考え方…
よろしければサポートをお願いします。私自身ではまだまだ微力です。当たり前の選択や情報を得ることができていない方々に、予防医学の視点で、知らなかったことで損した方を少しでも減らすよう、有益な情報を発信していきます。皆様の応援を励みに、より精進して行きます。応援ありがとうございます。
