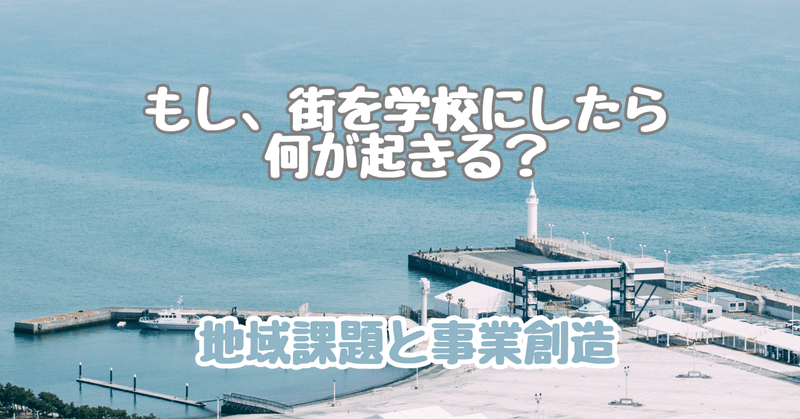
もし、街を学校にしたら何が起きる?・地域課題と事業創造
株式会社いろどり
①自然しかない→自然がある
②おばあちゃんしかいない→おばあちゃんがいる
→都会の飲食店で使う葉の販売。
DCセントラルキッチン
レストラン経営→協会→スーパーから購入→ホームレス
セントラルキッチンで働くボランティア
・キッチンで働けば飯がくえる
・事業計画書は書いたら人に見せられる。
→巻き込む時に、
どこにいる、どんな人が、何人くらい、どんな状態で困っているの?
◯商店街が寂れている
課題の現在の様子
出店数、退店数、経年変化
5年後にどこまで良くなったら良いか?
言葉をブレイクダウン。
→形容詞じゃなくて数字で表す。
→将来のトレンドを予測する。
日本から16年間で1300万人の人口が減る
データを元に分析する
お店を出す人が少ない
・観光客が少ない
・人口が少ない
・イオンみたいな便利なものができた
・生産とか売るものがない
・他の魅力がない
・根差したものとの掛け合わせがない
・補助金があるか?
・マルシェとか、とかイベントとか
・データが表に出てる。
・土地代が高い
・店舗を売る必要がない→どうしたら家賃を下げられる
・市場流通してない不動産
・オーナーの知り合いだったら変な人じゃなければ入れる。
・近場にもっといいテナントがある
・オタクやマニア向けビジネス。
・クラフトや趣味性の高いものは立地が関係ない。
伝統工芸は、逆にイオンではなく、商店街にあった方が良いのでは?
→交流を求めている人が減っている。
高齢になると、自分の小学校区だけの移動範囲になるのでは?→高齢者は他に移動ができないから近くの地域のイベントに来てもらいやすい
辞める人が増えてる
・仕入れに対して利益が出なくなった
・時代で人が来なくなった
・儲かってないから継がない
・客側の世代交代→客側もいなくなっていく
・商店街の魅力を今の世代向けに表現しきれていない
・商店街に若者がない
・イベントがない。
・なぜ吉祥寺がにぎやかなのか?
→古着、ラウンドワン、招き猫、NIKE、マック
◯後継マッチングサービス
◯ショッピングカートを持ってモールや商店街を回るサービス→高齢者向けのサービス。

・土壌の汚染を解決する
→土地を借りる
→植物で土壌を綺麗にする。
・商店街はチラシを打たない
・商店街には、ガラスや扉があるから入れない。
・まちゼミ
→もの買わなくていいからうち来ない??
→実費以外は取らない。
→まちで学びを得ることができる
→講座に来た人には売り込みはしない。
→自分以外の講座をお勧めする。
相手のコンテンツを教え合う会
ZANSHI NOTE
第一生命のノベルティーにも採用。
ビジネスの手法・視点で持続可能なものになる。
→ビジネスも社会性を取り入れることで支持される。
ホールフーズマーケット
・ほぼ無農薬
・近隣の家対象に、無農薬な作物の教育を行う
・計画的に取られた魚しか扱っていない証明書
・抗生物質を使っていない証明書
・ナッツが量り売り
・オーガニック
・フードマイレージ
→エコバックひとつにつき10セントを地元の学校に寄付
→マーケティング&ドネーション担当が各店舗に配置
学び感想
①教育を手段に支援する。
②未来の課題を数字で提起する。
③ソーシャルグットを支持に繋げる。
教育を手段に、ホームレスや、店舗でのゼミのような形で街の人が一緒になって盛り上げていくことが大切。
そして、どうしたいかの未来を言葉以上に明確な数字で提起することが大切。形容詞ではなく、それを構成する要素を分解する。ソーシャルグッドが良いという認識はあるが、やはりこれからの時代そういったソーシャルグッとを武器に市場で戦うことで既存のマーケットを壊していくことが大切だなと感じた。
最後に、
このnoteでは、
『響かせるって素敵』をテーマに、
自由に、自分の色(声、姿、想い)を、響かせる(共感を生む)ことのできる未来を創りたい。
という思いで、
ずぼらさんでも、誰でも、生活の役に立ったり、心の支えになるような発信や、日常の何気ないものを、言葉に紡いでます。
またYouTubeでも同様の発信をしているので是非ご覧ください!!👇
それでは皆さんが、ありたい自分で共感を創れる未来のために、
#自分の色を響かせろ !!
また明日!
#emc #アントレプレナーシップ学部 #武蔵野 #YouTube
#色レポート #日記 #エッセイ #毎日note #スキしてみて #note #毎日更新
#人生 #毎日投稿 #日常 #つぶやき #いま私にできること #ひとりごと #note攻略 #note運用 #はじめましてと #noteの書き方
#仕事
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
