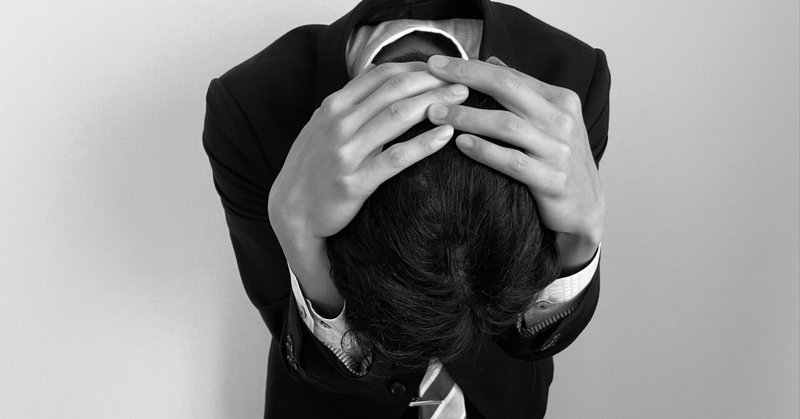
なぜ、僕らは、みんなに嫌われるのが怖いのか。
人は相手を正しく完全には理解することはできない
理解するのは不可能なのだから、そんな人間関係に消耗しても仕方ないし、自分が誰かに嫌われても仕方ないじゃないかと頭では割り切りたいのに
周りから嫌われるのが怖いという感情から抗えない理由を今から話していく。
感情的に動くのにも理由がある。
人は理屈ではなく、感情で判断する生き物である。
どんなに理屈が優れていても感情で納得しなければ、人は行動しない。
人を動かすのは感情だ、良くも悪くも、
「理屈では分かるが、納得できない」ことがあるように。
感情を理解するのには対象となる過去から今の情報が必要になる。
過去にあった出来事から現在までの相手の情報を取り入れてコミュニケーションを円滑させる、この能力こそが共感性だ。
共感性が重要な理由は、相手の行動を脳内で模倣することで、相手が抱く感情を自分事として理解し「相手がどう感じるか」を推測しようとすることができるからだ。
人類の歴史上、生存率を高めるためには、「相手の動きを推測する」ことが必要だったから。
そう、感情で動くのはここがポイントだ。
たとえば、相手を嫌うということは、人間の生存にとって危険なものを避けるために出てきた扁桃体のアラートによるものだ。
理由もなく人は好き嫌いを判断しない。
過去から現在のプロセスを得ている脳の記憶が本質的にこの人は危険だと推測したから嫌いになるのだ。
そして、嫌いという感情は非言語的なサインで気づかれる。
たとえば、視線を合わせない、話しかけようとする素振りを見せるとすぐに、それを察知したかのようにいなくなるなど、人は嫌いな人を避けるようになる。
どんなに言葉で相手に対して、優しくしてもこの非言語サインはごまかすことができない。
だからなんとなく嫌われたように感じられるわけだ。
もちろん、これは、扁桃体が誤差を起こしている可能性もあるから、必ず正しいとはいえない。
嫌われるのを恐れるのは本能的に、群れから敵とみなされ、群れから外され、生きていけない状態に陥るから。
味方と判断されるためには共感性という、相手の動きを推測する能力が必要だから備わっている。
つまり、異質な者を排除しようと動くのは、群れの危険性を取り除くための防衛本能になる。
だからこそ人間関係は重要なのだ。
特にストレスを受けるのは、人間関係の中で起きやすい。
ストレスに長い間さらされ続け、精神を消耗するとうつ病などの精神疾患の発症リスクを高めてしまう。
ハーバード大学75年の研究結果より、健康を保つためには「良好な人間関係」を築いていることが明らかになっている。
「良質な人間関係」とは配偶者やパートナーがいるかや、友人の数で決まるのではなく、身近な人間関係の親密性が重要なのだという。
人間社会に生きている以上、誰ともかかわらずに生きていくことは限りなく不可能に近い。
だからこそ、相手を理解しようとする姿勢が重要であり、コミュニケーション能力は大事なのだ。
では、一瞬、ASDなどのコミュニケーション障害を持つ者には、無理じゃないかと思われた人もいるかもしれない。
しかし、脳科学の観点から見れば、「ミラーニューロン」というネットワークを働かせることによって、空気を読む力を高められることが分かっている。
実際に、空気を読む能力を高めるには、どうすればいいのかというと「空気が読めると思える人の行動をまねる」こと、すなわち、観察能力を高めることが大事である。
また、まねることはできなくとも、「あの人だったら、こういう時、どういう行動を取るのか」という想像も有効である。
ぜひ、試してほしい。
という私もASDなのだが
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
