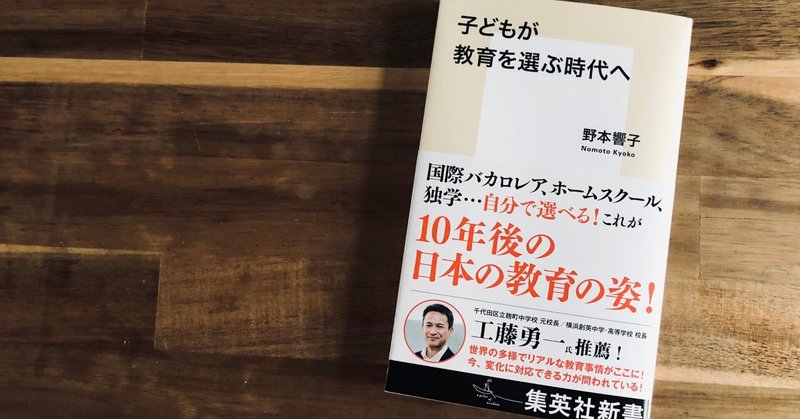
「子どもが教育を選ぶ時代へ」に寄稿させていただきました
タイトル通り、野本響子さん、通算4冊目になる「子どもが教育を選ぶ時代へ」に寄稿させていただきました。
私が野本さんを知ったのはnoteを介してからです。それから「日本人はやめる練習が足りていない」を読んだ時、自分が既にオランダに来ていたこともあって、首がもげてしまうんじゃないかと思うくらい頷きました。周囲を見ていても「ハッピーじゃないからやめる」を正当な理由としてぶつけてくる人だらけの社会だったからです。(やめる練習めちゃくちゃしてる〜)
さて、最新のこの本では、コラムを含めて10回ほど登場させていただいています。主にはオランダの教育についてですが、現職時代に目の前の高校生から聞いた言葉なんかも載せていただきました(もちろん日本の高校生の総意ではないですが)。本では書ききれなかったこと(いや、そもそも野本さんの本なんだから当然。笑)について少し言及したいと思います。
不登校はヒューマンエラーじゃなくて、システムエラー
不登校約20万人を抱える国、日本。これにプラスして労働市場から離脱せざるを得なくなった「引きこもり」と呼ばれる人たちを合わせると、一体どれだけの人たちが社会の中で「生きにくさ」を感じているのでしょうか。
本の中でも紹介していますが、オランダには日本のような不登校という概念がありません。その理由は様々ですが、まず1つ確かなのは「学校に行けない/行けない権利」よりも、「子どもが教育を受ける権利」を強く認めているからです。
「そもそも学校に行く意味があるのか?」という議論もあるようですが、比較的「自由な国」として知られるオランダは、ホームスクーリングは原則禁止の国です。保護者は「必ず」子どもを学校に在籍させなければいけませんし、最悪の場合、罰金刑となります。
それはなぜか?
同性婚を世界で初めて認め、大麻は5g以下なら非犯罪化、学校教育において性教育と市民教育は義務化されている一方で、教育内容はほぼ学校裁量…そんな「自由」が尊重される国で何故、ホームスクーリングが原則禁止なのかというと、それは「学校こそが子どもたちにとって多様性を学ぶ場所」だと考えられているからだと先生たちは言います。また、「多様性をバックグラウンドに対話の方法やその重要性を学ぶ場所」が学校だと言います。
つまり、オランダの教育はホームスクーリングを許可した時、「保護者の力量」が試されることを危惧しています。より多様化しているオランダという国で「うちの子さえよければ」と我が子を教育しようとする意識が加速してしまうことで、社会が分断されることを危惧しているのかもしれません。
そういった意味では、オランダの現状はマレーシアとは異なるのかもしれません。野本さんも本に書いていらっしゃるように、オランダ(特にヨーロッパ諸国)は移民の流入がより多く、さらに多様性に富んだ国だと言えるため、「どこを制度として固めておくか」がポイントになってきます。同質性が低く、簡単に分断を生みだしてしまえるからこそ、こういった制度になっているのだということがわかります。
教育を選ぶ権利と、教育を受ける権利
さて、学区制のないオランダでは、住民票(住所登録)に基づいて自治体に学校が決定されるということがありません。それはつまり「学校を選ぶ権利」が認められているということでもあります。
その一方で、学校を選ぶことは「権利」というよりは「義務」です。自由と責任は表裏一体…まさにそれを体現していると言えます。オランダにおいて、「学校に在籍することを選ばない」ということはほとんど認められません。つまり、「誰しも学校に属さないといけない」ということです。
では、一方で一度通った学校で、
「学校に行きたくない」となった場合はどうすれば良いのでしょうか?
どこに原因があるのか?を探り、解決するのは保護者と学校と自治体の仕事
学校を選ぶ権利があるというということは、もちろん転校も認められるということです。しかし、その前に一度属した学校に留まれないというのは、それはそれで問題です。
そこで、オランダでは子どもが「学校に行きたくない」となった場合、学校がそれに対しての対応を怠ることは認められません。何より大切なのは、子ども一人ひとりが「安心安全な学校」を享受できていること。
そのために、その生徒の周囲にいる保護者、学校、自治体がその解決に向けて動くのです。
「子ども」を中心にする教育とは
野本さんの著書にもある通り、これまでは「既存の教育」があり、そこに当てはまることができる子どもたちを育てることが大筋の目標で、何とかそこに当てはまるように子どもたちをドライブしていたように思います。
そこに「当てはまることができる子」と「そうでない子」を色濃く分け、「そうでない子」にされた子どもたちが行き場を失う…そんな状況が積もりに積もった結果、その数が不登校20万人となってしまったのではないでしょうか。
その根底に抜けているのは「どんな子どもにも教育を受ける権利がある」という権利意識の欠落だと思います。そして、それをヒューマンエラーとして片付けることで、システムを見直さないところに原因があるのかもしれません。
学校が変化するために必要なのは、「学校だけの力ではない」ということを私はオランダの教育を見つめながら感じてきました。学校だけの力には限界があります。やはり、社会で生きる大人一人ひとりがどれくらいこの問題を「自分ごと」として捉えられるかがポイントになってくると思います。
学校は社会に対してもっと助けを求め、その助けに対して社会が手を差し伸べる必要があります。そこに関わるのは、学校関係者だけでなく、企業や自治体、保護者、そして子どもたち一人ひとりだという認識を強く取り戻す必要があるのかもしれない。この本を通して、そんなことを考えさせてもらっています。
私たちの活動内容に賛同いただける方々からのサポートをお待ちしています。ご協力いただいたサポートは、インタビューさせていただいた方々へのお礼や、交通費等として使わせていただきます。よろしくお願いいたします!
