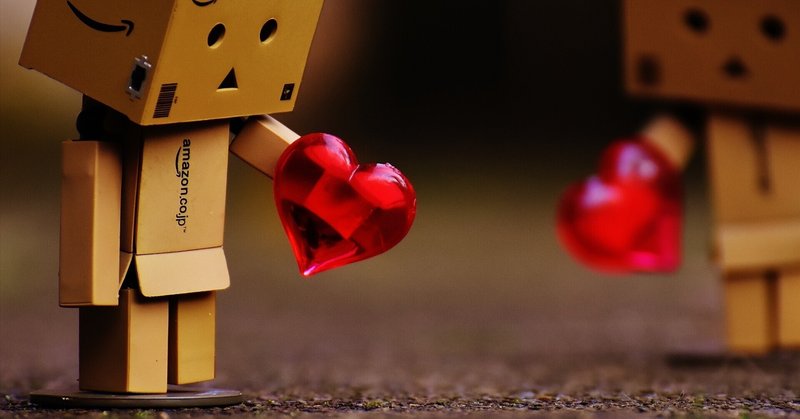
「愛は放っておいても育たないのに」
こんにちは。少しずつ寒さが増してきたオランダ。街はすっかりクリスマスモードです。「良い年末年始を」という声も聞こえるようになってきた今日この頃…
そんな中、先日、少し離れたところに住むオランダ人の友人から離婚するという話を打ち明けられました。娘と2歳くらい離れた子どもが2人いる彼ら夫婦はうまくやっていると思っていたのですが、どうやら違ったようです。そして、話を聞くとその核心にあったのは、生活の中で看過され続けてきた「忙しさ」でした。
※本人の許可も得て、この記事を書いています。
「先生」という仕事
実は、その友人Annet(仮名)は中高の学校の先生です。仕事熱心な彼女はここまで、一生懸命に仕事をしてきました。私から見ても"面倒見の良い教師"そのものの彼女。会えばいつも仕事や生徒の話をしてくれます。大学を卒業してからずっと教師という仕事を続けてきた彼女は私よりも少し年上ですが、「この仕事が大好き」と言ってきました。子どもが生まれるまではフルタイムで働いていた彼女でしたが、周囲のオランダ人がそうであるように、子どもが生まれてからは少し勤務時間を減らして、子育てと仕事が両立できるような暮らしにシフトチェンジしてきたそうです。
オランダの中高には日本のような部活動はないところがほとんどですが、それでも業務量は(彼ら曰く)多いようで、彼女自身もパートタイムで働いていてもフルタイムで働いているようなものだと言っていました。特に、熱心に仕事をする彼女にとっては、教職とはそういう仕事なのかもしれません。
忙しいパートナー
一方で、パートナーのJohn(仮名)は一般企業に勤めていますが、私から見ても忙しく働いていたように見えます。
「Johnは転職をして忙しくなってしまって、時々帰ってくるのも20時を過ぎることがあるの。私もどちらかというと仕事を熱心にしてしまう方だから気持ちはわかるけれど、平日に家族4人で過ごす時間が少なくなってしまっていて、少し寂しい。」
今思えばAnnetは時々、少し悲しそうにそう漏らしていました。
周囲を見ていても、子を持つオランダ人の「すべて」の保護者が働き方をセーブできて、毎日家族で夕食を共にできているとは思いません。しかし、お迎えの様子を見ていれば、パートナー同士でその分担を分け合えるくらい、この国では"仕事と育児のバランスが取れている"という景色が比較的多くあるように思います。
一方で、Annetは2人の子どものお迎えや習い事の送迎などを、実家の両親と分担してやりくりしていました。そして、夜遅くに帰宅することも多くなった忙しいパートナーとのすれ違いによって「今は別々のベッドで寝ている」という言葉を数ヶ月前に口にしていました。その時、私は物事が良くない方向へ進んでいるのではないかと察しました。
別々のベッドが意味するもの
日本では「合理的選択」という考えのもと、パートナー同士が別々のベッドで寝ること自体にそこまで深い意味はないかもしれません。一方で、こちらの飲み会の席で聞いた話によると、パートナーが「同じベッドで寝ること」は当然のことなのだとか。私の周囲に限っては、良好なパートナーシップを築いている夫婦が別々のベッドで寝ているという話は聞いたことがありません。
単純に文化の違いと言えるかもしれませんが、子どもを含め「川の字」で寝るようなことがほとんどあり得ないこの文化。自立という観点からも妊娠が発覚したら子ども部屋を用意し、その部屋に用意されたベッドで1人で寝かせることが一般的だと考える人は多いように思います。子どもが自立してからもずっと続くパートナーシップ。その関係をずっと大切にするための意志の表れが"ベッド"とも言えるのかもしれない人々にとって、パートナー同士が別々のベッドで寝るというのは、不穏な空気感を漂わせます。
私はそれを聞いた時、それとなく「関係は良好なの?」と聞きましたが、彼女は「えぇ、大丈夫。今はそうするしか方法がない」と言っていたことが気がかりでした。
コミュニケーションが不足する生活
それでも週末になると、家族で出かけたりしているという明るい話を聞いていました。しかし、最終的に彼女が口にしたのは
「両方の仕事が忙しかった時期が重なったり、慢性的に通勤時間がかかることによって、夫婦間のコミュニケーションが圧倒的に減っていった」
ということでした。
「子どもの教育のことや、何気ない毎日のこと、家族のイベントやこれからのこと、仕事や友人のこと。子どもが生まれてから忙しくなっても、仕事がセーブできていた間は、自分たちで何とかやりくりして"話す時間を確保しよう!"ってなっていたはずだった。でも、Johnの仕事が忙しくなって、私もそれをそれとなく"仕方がない"と思うことが普通になっていってしまって、いつの間にか"2人の関係を何とか力を合わせて維持しよう"という気持ちがお互いから消えていってしまっていたのかもしれない。"所詮、結婚生活とはこんなものか"とお互い諦めていくようになっていったのかもしれない。」
と、悲しそうに彼女は振り返りました。
「愛は放っておいたって、育たないのに」
「そういう意味では、2人のパートナーシップにおける"愛"は放置されたのかもしれない。"家があって、子どもいるから"という事実だけが2人を繋ぎ止めていて、肝心な"私たちパートナーとしての純粋な愛"を育てないという選択を無意識に2人でしてしまっていたのかも。
愛は放っておいても育たないってことがわかっていた頃は、2人とも何とか2人の関係を維持するための努力を重ねていたのに、忙しさを理由にそれを怠り始めた時、私たちの関係は悪い方向に変化し始めたように思う。でも、その時は自分たちがそんな選択をしているなんて気づいていなかったのだろうけれど。でも、振り返ってみれば私もJohnも、どこかでそれに気づきながら簡単に見過ごしていたってことなんだろうと思う」
彼女の言葉は重く、でも冷静に自分たち2人のこれまでを振り返っていました。
「価値観の擦り合わせが面倒くさい」と言う人たち
良好なパートナーシップを築けていると自負している私の周囲のパートナー同士は、自分たちが日々変化しているということをとても強く自覚しているように思います。
職場で人と話をしたり、友人と話をしたり、子どもの成長を見守る中で、人の価値観は年齢とともに変化していきます。そう自覚しようともせずとも、私たちは少しずつ老いていく中で身体も心も変化していきます。自分の両親も老いていくし、周囲の人々も自分と同じように歳を重ねていくのが当然です。
一緒に「暮らし」を重ねるパートナーも同様であることを自覚すれば、一番身近な人に訪れる「変化」をキャッチアップすることが、家族というチームを良い状態で維持するために必要なことかもしれません。身体の変化を打ち明けたり、キャリアへの悩み、子どもの教育のことや価値観の変化などは、脳内にあったとしても、言葉にしてシェアされなければ相手には届きません。
そういった意味で、「対話する力」や「対話できる時間」は良い関係を維持するために必要なもので、わざわざ確保しなければいけないものですが、どうやらそういったことを話し合うことさえも"面倒くさい"と思うパートナーシップが存在するということを、日本で様々な人と話をする中で気がつきました。
"忙しさ"は人々からたくさんのものを奪っていく
Annetと話をして改めて感じたのは、いかに"忙しさ"が簡単に人々から余裕や当たり前を奪っていくかということでした。先日、知人からもらった「先生がいなくなる(PHP新書)」本を読み終えました。そこでは、公立学校教員を取り巻く「給特法」という法律に起因する長時間労働について書かれているのですが、その著者の1人である小室淑恵さんという方がグロービス大学院でお話しされていた、長時間労働とWell-being、そして睡眠時間との関係について振り返りました。※学校教員に関しては37分頃から
少し離れた話に聞こえるかもしれませんが、社会における"忙しさ"はその人だけでなく、その人の周囲にあるものからもたくさんのものを奪っていこうとするのだと感じました。かく言う私も、この夏に一時帰国した時には義則に「ちょっと働きすぎじゃない?」という声をかけられてハッと立ち止まった1人です。
私の場合、信頼するパートナーである義則がちゃんと声をかけてくれたことによって我に返ることができ、彼と対話することができました。そして私が彼の声に耳を傾けようと思えたのは、普段から彼との対話を大切にしてこようと思える環境を何とか一緒に作ってきたからなのだとAnnetは教えてくれました。
放っておいては育たない愛やパートナーとの関係をよりよく維持するためには、いかにお互いが忙しさを排除する努力をしようしているかにかかっているのかもしれません。
「お互いに"2人の時間を大切にしようとしない姿勢"が見え始めた時、私たちはちゃんと立ち止まらなくてはいけなかったのに、2人とも忙しさや疲れを言い訳にして向き合おうとしなかった」
私は離婚すること自体を否定したいのではありません。むしろ、Annetの言うことは私たち夫婦にだって簡単に忍び寄る影のように思えました。「どこでボタンをかけちがえてしまったのだろう」と回顧しても、もうその日々は遠く昔に置き去りになったままで、彼らはもう取りに帰ることが出来ない…彼女の言葉からはそんな印象を受けたのでした。
離婚の原因は必ずしも"忙しさ"に起因するものではないと思います。忙しくないパートナー関係でも、離婚に達することはあると思います。
一方で、良い意味でも悪い意味でも変化していく自分たちの価値観を擦り合わせる"時間"さえも確保できなかったら、やっぱり状況が好転する契機を見出せないのではないかと思います。「私たち最近おかしいよ?」「ちゃんと話をしようよ」とさえ口から出ないような疲労感や倦怠感に苛まれる毎日から、何かを見出すことができるのか…
もう既に大きな波を越えたように落ち着いた様子のAnnetですが、これからはJohnと離れた暮らしの中で、育児を分担して生きていく生活が始まります。生まれてしまった別々の価値観。もう二度と同じ屋根の下で暮らすことはない彼らですが、どうか「家族」というチームとして、せめて良い関係を維持し続けてくれたら良いなと願っています。
私たちの活動内容に賛同いただける方々からのサポートをお待ちしています。ご協力いただいたサポートは、インタビューさせていただいた方々へのお礼や、交通費等として使わせていただきます。よろしくお願いいたします!
