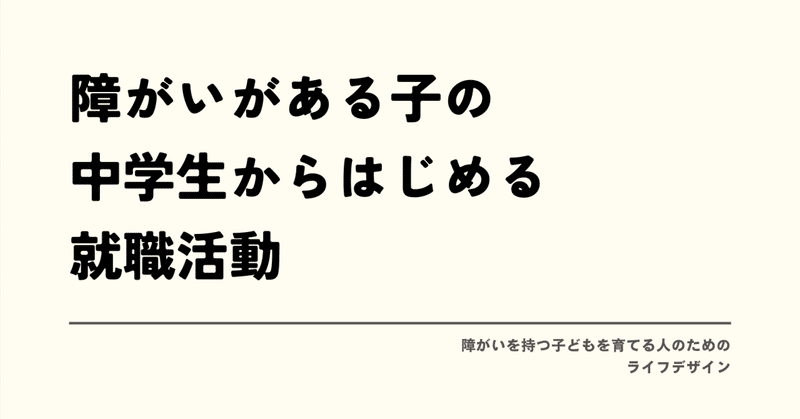
障がいがある子の、中学生からはじめる就職活動
就職して、できたら一人暮らしを経験させてあげたい。
子どもに対してそう思うのは、子どものためでもあり、親自身が安心したいという気持ちのせいかもしれません。
障がいがある子どもにとって、働くことは経済的価値以外にも、様々な意味があります。
子どもが就職して収入を得ることができるようになれば、お金を使った色々な体験ができるようになり、子ども自身の生活は充実します。
また高校卒業後も社会との接点を持ち続けるので、社会的孤立を免れたり新しい人間関係への出会いを期待することができるのです。
就職の準備は中学校から既に始まっています。
なぜなら、就職の可能性を拡げるための第一選択は、就職サポートが充実している高等支援学校に進学することだからです。
そのためには近隣にどのような高等支援学校があるか調べておく必要があります。
僕の子どもの場合、自宅から通学可能な高等支援学校は4ヶ所。その中でも企業へのインターン実習が最も充実している学校の倍率が最も高いという状況でした。
人気がある高等支援学校は入試の倍率も他の学校に比べて高めです。
そのため、受験に際しては一般の受験生と同じように勉強や過去問などの試験対策をする必要がありました。
受験に際して重要なのは、勉強をする意味を子ども自身が理解しているかどうかということです。
何のために勉強するのかを置き去りにしたまま、勉強に取り組むことはできません。
しかし知的に遅れがある場合、進学の必要性や学校の良さを言葉を使って説明したとしても、子どもにとっては理解が難しいことがあります。
大切なのは、子どもと一緒に実際に複数の高等支援学校を見学し、子ども自身に進学先を選んでもらうということからスタートすることです。
また良い学校は遠方にあることもあるので、中学生のうちから公共交通機関を使用する機会も作っておくと、進学の選択肢を広げることに繋がります。
高等支援学校に入学後、就職活動が活発な学校だと1年目からインターン実習が始まり、3年に進学直後にはある程度就職先を絞っていきます。
僕の子どもが通った学校は、3年のインターン実習で行った場所が就職先の候補になり、卒業前に内定をもらってそのまま卒業後に就職という流れでした。
就職先は先生方が提案してくれるのですが、その中に思うような就職先がない場合、親が直接探すようになります。
就職先を親自身で探す方法は2つあります。
一つ目は市役所などで福祉就労(就労支援A型・B型)のリストをもらって調べる方法。
二つ目は実際にハローワークに行き、障害者の求人募集を調べることです。
その中で子どもに向いていそうな場所が見つかれば、学校の就労支援担当の先生に見学の希望を伝えて、学校からアポイントメントをとってもらい、実際に見学に行きます。
就職先を実際に見学に行くことは必須です。
障がいがある子どもが、その雰囲気に馴染めそうなのか、仕事をサポートする支援員の対応はどうなのか、ということを実際に目で見て確認できるからです。
これは学校の先生にお聞きした話なのですが、給料が良いという理由で就職しても一年以内に辞めてしまうということが珍しくないそうです。
そのため、長く勤めることができそうかどうかということを軽視しないように教えていただきました。
僕はこの就職先(実習先)を探すのにかなりの労力を割きました。
子どもと一緒に一般企業の障害者雇用とA型就労支援継続施設を複数の場所で見学を行い、どういう条件で決めるのかについて時間をかけて子どもと話し合いました。
その中で子ども自身も親である僕も「ここなら」と思える場所が見つかり、実習を経て無事に就職に漕ぎつけたのです。
その甲斐あってか子どもはこの1年、全く仕事を休むことなく勤めることができています。
子どもが毎日仕事に行ってくれること。
それは親に想像以上の安堵をもたらします。
自分の力で得た収入の一部は生活費として家計に入れてくれ、残りのお金で好きなものを買ったり食べに行ったりしているのを見ると、今までの努力が報われたような穏やかな気持ちになります。
ハンディキャップを持って生まれた子どもには、生き方を自分で選択する機会はほとんど与えられません。
進学と就職は子どもにとって人生における貴重な選択の機会になります。
この機会にどのような選択肢を提示することができるのか。
このことは障害児の親として最も重要なミッションなのではないかと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
