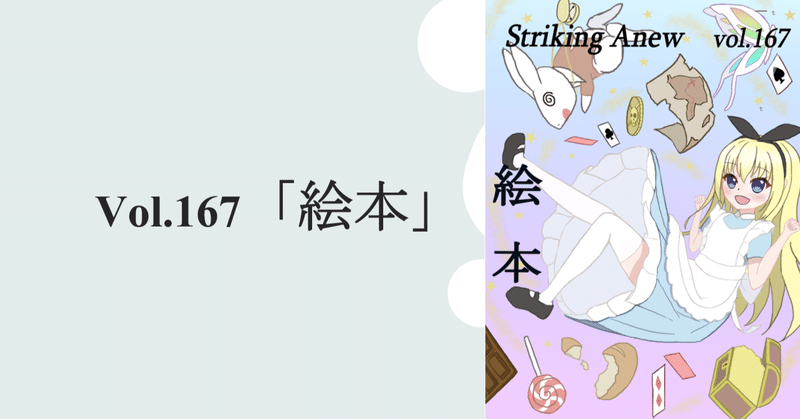
Striking Anew vol.167 テーマ「絵本」
Striking Anew vol. 167「絵本」です。
*作者からの許諾が得られた作品のみ掲載しています。

テーマ作品
李音 「わたしの王子様」
絵本に出てくる王子様ってどうしても格好良く見えて幼い時に憧れる存在。主人公のどんなピンチにも逃げ出さないで、戦って最後には主人公を魔の手から助けるっていうお決まりのストーリーだからだと思う。これは、物語に出てくる王子様と正反対の私の初恋の王子様のお話。
「僕さ、明日香と付き合うことになったんだ。」と幼馴染の宮橋萩生(みやはししゅうせい)と近藤明日香(こんどうあすか)が突然カミグアウトしてきた。
そしたら、隣から、「えーーまじで!!」と叫ばれた。私は泉川胡桃(いずみかわくるみ)といい、隣で叫んでいるのは幼馴染であり、萩生の弟の橙生(ゆづき)である。
私達四人は家が近所であるため、幼馴染として過ごしてきた。そんな二人からの突然の告白は、驚きはしたが、納得する部分が多くあった。
なぜなら、昔から二人を知っているなら、二人が好き合ってることは知っていたから。
「どうして、なんで、兄貴と明日香ちゃんが付き合うことになったの??」と二人に気持ちの全く気づいていなかっただろう橙生が疑問を投げかける。
「別に僕が彼女と付き合ってはいけないなんてことはないだろう。もしかして、橙生も明日香のこと好きとかいうつもりかな。」と挑発気味の萩生が問いかける。
「そんなわけないし」と橙生が言う。すると、「そうだよね。橙生はずっと好きな子いるもんねーー。」と萩生が答える。その発言に驚いたのは私の方だった。
橙生ってずっと好きな子いたんだ。そうだよね。いるよね。私はそんな相槌しか打てなかった。私はずっと橙生のことが好きだった。彼があの日言ってくれた言葉を聞いてから、ずっとね。
昔のこと、それこそ記憶に残っているのかどうかぐらいの時の出来事。その日は、親戚のお姉さんの結婚式で3歳か4歳ぐらいの私には正直言って、暇で仕方のない日だった。
だって、親は子供そっちのけで親戚の挨拶回りをしたり、主役の二人に「おめでとう」を言いに行ったり、ほとんど相手にしてくれなかったから。
萩生と橙生の親戚のお兄さんの式でもあったから、私達三人は親に言われて一緒に遊んでいたのだろう。実際、彼らと一緒にいたおかげで、暇と思う時間はほとんどなくなったわけで……。
そんな時、祝いの席で酔っ払ったおじさんが絡んできたのだ。私は、ただ驚いて固まってしまった。すると、橙生が
「大丈夫だから。胡桃ちゃんのことは僕が守るから」と言ってくれたのだ。
私には、その瞬間彼が、物語の王子様に重なって見えたのだ。今では、生意気ばかりでそんな面影は全くないが、あの時はそんな一面が存在していたのだ。
兄貴が明日香さんと付き合うことになったと聞かされた時、俺は本当に驚いた。そして、次の瞬間には隣にいる胡桃の存在が気になった。なぜかって、それは胡桃が兄貴のことが好きなはずだからだ。
確かに、兄貴は昔から明日香さんの事が好きで、それをあいつも承知していたとは思うが……。
すると兄貴が、胡桃の前で俺に昔から好きな人がいることを暴露しやがった。本当に勘弁してほしい。よりにもよって、本人の前で言う事はないだろう。
俺は昔から胡桃のことが好きだった。最初は隣に可愛い子が引っ越してきたなとという感覚だった。いつからか胡桃のことを一人の女性として意識するようになっていったのだ。本人には言えていないが……。
私が昔のことを回想していると、隣から「お前は兄貴たちを祝福してやれるのかよ。」と言われた。祝福できるに決まっている。二人が幸せになれるのなら。ずっとお兄ちゃんのように慕ってきた萩生君に幸せになってほしいのに。
どうしてそんなことを聞くのだろうか。
すると、橙生がおもむろに口を開いて、「だって、胡桃は兄貴のこと好きだろう?」と言ってきた。
私は急なことに頭が混乱してきたが、発言の意味を考えると、だんだんと苛立ってきた。どうして、橙生がそんなことを言うのだろう。私が好きなのはずっと昔から橙生なのに……。
生意気だけど、私が困ってる時には必ず助けてくれるところは本当に王子様みたいでかっこいいから、橙生は……。
俺が、兄貴への気持ちのことを聞いてから、胡桃は全く反応してくれなくなった。なんか悪いこと言ったかな、俺。
昔から胡桃は兄貴のことを頼ってばかりだった。だから、いつしか胡桃は兄貴のことが好きなんだろうと考えるようになった。まぁ、それで俺は失恋かなとも思っていた。
「どうして、橙生がそんなこと言うの?よりにもよって、どうしてあなたがそんなことを言うのよ!私が好きなのは、萩生君じゃない!私が好きなのは橙生なのに。」
私は好きな人の前で好きな人を言うという最悪のことをしてしまった。
でも、このメンバーなら、本人以外は私の好きな人はバレているし。
え……。胡桃が俺のことを好きって言ったのか?本当に?嘘じゃないよな?なら、俺の気持ち言ってもいいよな。
「俺も胡桃のことが好きなんだ!ずっと前から。だから、胡桃さえよかったら、俺と付き合ってくれませんか?」
伝わったかな?俺の気持ち。
橙生が私のことを好きだって言ったの?それも昔からって……。嬉しい!その感情しか浮かばなかった。気づいたら、頬に涙が伝っていた。
橙生が「おいおい、泣いてたら、どっちがいいかわからないじゃん!それとも俺のこと本当は好きじゃなかった?ねぇ、どっち?」と言ってるのが聞こえる。
でも、なかなか私が泣き止まないものだから、彼もだんだん自信がなさそうになっていく。
だから、私は重い口を開いて、「お願いします。」と言った。
すると、彼が破顔して嬉しそうに「よかった」と呟くのが聞こえた。
いつまでも私の、私だけの王子様でいてね。 完
再掲作品
登校は登山「愛しき隣人」
その朝、ある文豪が郵便箱の音と共に目を覚ましたのは、普段よりは一時間も早い時間だった。男は元より新聞は取っていなかったし、この現代に態々手紙で連絡をよこすような人も居なかった。それ故に、男はその事実に少し気掛かりな感じを覚えながら、まず水を一杯飲み干し、顎の髭を剃り、自慢のミルで挽いた豆でコーヒーを淹れ、トーストと共に飲み、それからようやく郵便箱の確認へと向かった。
果たして、男が郵便箱から取り上げたのは一つの茶封筒だった。切手も、消印も、差出人の名前すら無い事からして、誰かが直接投函したのだろう。男はもう長いこと作家をしていて、古い時代には出版社を通して住所が誰でも分かるような物になっていたから、それも特段犯罪を疑うようなことでも無かった。大方、ファンレターのような物だろう。しかしそうだとしても、そういう物は一度出版社に送られ、それから自分の元に届くのが常だったので、やはりどこか奇妙だった。
無差別なセールスなら捨てれば良い、何か怪しい内容なら警察か消費者庁にでも相談でもすれば良いかしら、等と考えながら、男は二杯目のコーヒーを片手に茶封筒を破った。
第一の手紙
あるところに、アランという作家がおりました。アランの書く小説は、少し恐ろしくて、不思議で、しかし心温まる、そういう物語でした。アランの元には、彼の書いた物語が大好きな人から毎日のように手紙が届きます。それを読みながら朝を過ごすのが、アランの日課でした。
『夜、眠れない息子のためにあなたの本を読んでいます。彼はいつも全部読む前に眠ってしまうから、物語の結末を知りません。ただ、怖いばかりの話だと思っています。息子がもう少し大きくなって、自分で全部を読めるようになったら、この物語について語り合って、そうしているうちに少し夜更かしをして、少し笑って、それから眠るような日が訪れるはずです。そういう日を、私は楽しみにしています』
こんな手紙が何通も届いた日には、アランはもうたまらなく嬉しくなって、踊るような足取りでその日を過ごすのでした。
そんなアランには、誰も知らない秘密がありました。
毎朝、アランがポストの手紙を受け取ったあとやることは、彼のペットのお世話でした。でも、そのペットが少し普通ではないのです。真っ黒の毛に覆われた、一つ目の毛むくじゃら。それが、アランの家のペットでした。初めは猫だと思って、そのまま「真っ黒」と呼んで可愛がっていたのですが、しばらくお世話をするとすぐに大きくなり、猫の大きさはとっくに超してしまいました。そうしてどんどん大きくなって、今ではアランの倍は大きな体を持っています。そして、一番不思議なことには、この子がどこから来たのか、まったく見当が付かないのです。いつの間にか家にいた、という他にないのです。
それでも、アランとその真っ黒は仲良しでした。最初は気味が悪かったし、今でも少し怖いのですが、真っ黒もまさかアランを食べてしまうようなこともなく、いつもは部屋の隅っこでじっとしていて、朝と晩にパンとミルクを用意してやるととても喜ぶ、それだけでした。
そうして一番の秘密は、アランの書く小説は、アラン自身がこの真っ黒と過ごした体験を、もっと面白くなるように飾った物だということでした。アランの小説に出てくる不思議な生き物は、すべてこの真っ黒がモデルになっていました。
だからアランは、真っ黒に感謝していました。売れない作家だったアランを、人気の作家まで押し上げてくれたのは真っ黒でした。
それなのに、その日は何かが違いました。
その日アランが目を覚ますと、家がいつもよりしんと静まっているのに気がつきました。アランには一緒に暮らす人はいませんでしたが、それでも真っ黒が寝ている声や、あるいは起きていたらご飯をねだる声が聞こえてくるはずでした。それなのに、その日は何の音もせずに、ただ静まりかえっているだけでした。
通りに出てみると、ちょうどその日は蚤の市がやっていて人で溢れていましたから、そんな所に真っ黒が居るはずもありませんでした。ペルシアでしょうか、きらびやかな金の刺繍の入った上等な真っ赤の絨毯、賑やかなブリキの機械人形、そうしてそれを売って、また欲しいものを買いにゆく人々が目に入りました。活気に満ち満ちた町が、アランをいっそう焦らせました。
少し歩いて、アランは町の外れの方まで来ました。このあたりにはひとつひっそりと湖のあるだけで、すぐ奥には鬱蒼とした森が町を閉じ込めるように広がっていますから、誰も彼も気味悪がって、なかなか近づくような人は居ないのでした。
その湖のほとりに、どうしたことか、今日は一人男が立っていました。「やあ、珍しいですね。こんなところに」
くしゃくしゃの山高帽を被った男は、男と言うよりは老人と呼んだ方が正しい出で立ちで、腰は曲がり、鼻は折れ、帽子の隙間からは真っ白な髪が覗いていました。老人はアランを見ると、そう呼びかけながらこちらへ徐に近付いて来ました。
「ここいらは、そら、そこの森を怖がって人が来ませんから」
そう言って、老人はその方を杖で指すと、咳き込むように少し笑いました。それから、アランの顔をじっと覗いて、
「何かお探しですか。そういう顔だ。犬か、猫か。何か逃げましたね。そういう顔をしている」
アランはにわかにこの老人が恐ろしくなって、振り払うように「いえ」と答えました。それから、しかしあまり違わないのだと思い直して、「猫でも、犬でも無いのです」と付け加えました。
「真っ黒で、私の倍ほどの大きさの、一つ大きな瞳のある毛むくじゃらの奴を見ませんでしたか。私は、それを探しているのです」
老人はそれを冗談と思ったのでしょうか、少しのけぞって、「そんな恐ろしい生き物は聞いたことが無い」と言って笑いました。
「ええ、私にも恐ろしい。しかし、私はもはや、奴なしでは生きてゆけないのです。疎ましいのに、奴が居なければ生活が立ちゆかないのです」
老人は曲がった眉を一層顰めました。
「ははあ、冗談では無いと見える。あなた、気を違えたか。」
「なに、そんな訳がないでしょう」
アランはむっとして言い返しました。
「居もしないものを恐れて、それなのに、そいつを探し求めている。わたしから見れば、あなたは立派な気違いだ。あなた、医者へお行きなさい。それで、しばらくは静かに過ごしていなさい」
老人は哀れむようにそう言うと、アランの肩にそっと手を置きました。老人が去って行った後も、アランはしばらくそこに立ったままでいました。
どこを探してみても、どこにも真っ黒は居ませんでした。人にどんな物を探しているか尋ねられても、あの老人の事を思い出すと、誰にも言えませんでした。そうして、疲れ果ててまた誰も居ない部屋に帰ってくると、その日は夕食も食べないまま眠ってしまいました。
翌朝、アランが目を覚ましてみても、やっぱり真っ黒は居ませんでした。アランは息を一つ吐いて、それからポストの手紙を確認に行きました。そこには、いくつかの手紙に合わせて、アランの小説を印刷して売り出している会社からのものがありました。いろいろと難しいことが書いてありましたが、要するに、そろそろ新しい小説を書いて下さい、という事でした。
アランは困ってしまいました。小説の元になる真っ黒との暮らしは、もうありません。そうすると、アランは小説が書けません。小説が書けないと、アランは暮らしてゆけません。暮らしてゆけないのは困ります。でも、小説は書けないのです。アランは、二日の間にして、真っ黒を失った悲しみと、暮らしてゆけなくなる苦しみの二つを抱えることになってしまいました。
アランは悩みました。どうしたら良いだろう、と考えて、眠って、また考えて、眠って、ポストの手紙を確認する暇もない程考えて、それから一つの事を思いつきました。
自分を主人公にするのです。
突然不思議な生き物を家に見つけて、その暮らしを面白く書いた小説で人気になったのに、ある日その生き物を失ってしまった、悲しい作家の話を書くのです。
アランはどうにかそれを書き終えると、「もうこれ以上小説は書けません」と言って、会社にそれを渡しました。
それからアランはすっかり塞ぎ込んでしまって、今はこれまでの小説が売れたお金の残りと、会社から送られてくる最後の小説が売れた少しのお金を頼りに、一人でとても貧しい暮らしをしています。真っ黒が戻ってくる日は、来るのでしょうか。
第二の手紙
拝啓。
突然お手紙を送りつける無礼を、まずはお許し下さい。助けて欲しいのです。書けなくなってしまいました。アランは、私です。何を書こうとも、筆が動かないのです。これだって、昔の文豪ぶって、音声入力で口述筆記の真似事なんかしているのです。
はじめから、順を追って、お話しします。
私は、売れない作家でした。自分で言っても悲しくない程に、売れない作家です。地方の大学に入って、それにも禄に行かないまま中退して、他にできることが無いから筆を執ったような、どうしようもない奴です。
元より、文章を書くことそのものは、私にとって数少ない人並みにできる事でした。生活の中で生まれた、不安や、誰も居ないのに急かされるような心地、爪の間に入り込んだクレヨンのような不快、或いは、水の中に墨を一滴落として、それが広がっていくような気味の悪さを言葉に起こしているうちに、ある程度は人間並みの事としてできるようになって、それが私のなけなしの自尊心の支えにもなっていました。
それが、書けなくなったのです。
すこし前に、貯金が底をつきました。親族からも見放されたと見えて、仕送りも無くなっていました。これでは生きてゆけないので、物を書く合間にアルバイトを始めます。すると、それですっかり疲れ切ってしまって、それが終わると、シャワーも浴びないままに泥のように眠って、それからまた次のシフトの前に起きて、人前に立つのですから当然シャワーを浴びて、働いて、眠っての繰り返しです。
勿論、休みの日はあります。それなのに、体が弱いのでしょうか、眠って、疲れを取って、物を書く気力も無いのでぼうっと天井を眺めていたりすると、それで休みが終わってしまいます。
ここまでお話しして、身に合わない労働で心身疲弊した男の話だとお思いでしょう。しかし、そうでは無いのです。むしろ、逆なのです。
確かに、働いた後は疲れています。しかし、私にはその疲れがむしろ心地よいとすら感じているのです。ランナーズ・ハイとかそういう物なのでございましょうか、要するには、不安という物が無くなってしまったのです。
私の創作を支えていた物は、不安でした。真っ黒とは、それです。いつの間にか私の心に居着いたそれについて感ずるままに、心が動くのにまかせて書いていれば、ある程度の物が書けました。私は、そう自負していました。
売れないのだから、どうせ自己満足の作です。それでも、その自己満足が私を人間たらしめていました。それが、消えてしまったのです。それで、何も書けなくなりました。
漫然と生活に堕している人間は、無価値です。生きてて偉いなんて言葉は、あれは嘘だ。とんでもない大嘘だ。夏目漱石をご存じでしょう。「精神的に向上心のない者はばかだ」。あれは、恋愛と、自己研鑽の話ですが、人間なにもそれだけじゃない。とにかく、そのばかに、身を窶してしまいました。何も書けないのです。ただ、日々労働に明け暮れて、ただ生き延びるだけの金を稼いで、それをすり減らして生きているだけになってしまいました。私を人間たらしめる自己満足が、消え失せてしまったのです。
それが、すこし前までの話です。今は、少しだけなら清貧な暮らしができるだけの金を貯めたので、仕事を休んでいます。来月にはまた働き始めるか、飢えて死んでいるでしょう。封したのが、絵本の脚本にでもなれば良いと思って書いた、私の話です。これ以上に、もう何も書けません。長く私に暗いもやをかけていた不安は、実際のところ、私の最愛の隣人ですらあったのです。物が書けないという不安は、私にそれ以上の何も齎してくれないのです。私は、どうしたらいいのでしょうか。
とりとめの無いことを書きました。汚い文章だと分かっているから、読み返さず送ります。お許し下さい。 敬具
第三の手紙
拝復。気取った悩みですね、と、きっと太宰治がお好きなのでしょうから返しておきます。実際私も、あなたに同情するような所はありません。そんなことをしなくても、あなたは人間以上の何物でも無く、また人間以下の何物でも無いでしょう。
古代思想をお学びになって、エピクロスや、老子や荘子をたずねてご覧なさい。
自分を守るために自分の世界を狭くするという事は、きっとあなたが思っているより悪いことでは無いのですよ。その言葉にあなたが霹靂を云々と、とにかく、それがあなたの支えになれば良いのですが。
それに、それだけ書ければ上等でしょう。
貴方が苦しまずにいられることを、隣人として祈っております。不尽。
自由作品
連載●ストニュー部分部●第二回
尾井あおい「タイトルの『意図』の部分」
ストニュー部分部、第二回です。さっそくご投稿作品を見ていきましょう。
割引除外品の「ヨガ」と「遺品」の部分/かこい
分離液状の「利益」の部分/かこい
transport の「sport」の部分/かこい
ルサンチマンの「産地」の部分/登校は登山
インターネットの「種」の部分/登校は登山
GIDの「自慰」の部分と「慈愛」の部分/登校は登山
もったいないの「体内」の部分/ドクダミ
宇宙船の「抽選」の部分/ドクダミ
ここまでがご投稿いただいた部分です。
〈割引除外品の「ヨガ」と「遺品」の部分〉には哀愁が漂っていて、割引シールのけばけばしさを忌避する生活を送ってきた淑女の影が窺えます。すでに故人となった彼女の愛用していたヨガマットは当然割引除外品で、遺品となったそれが部屋の片隅に残されているシーンが浮かびます。
〈インターネットの「種」の部分〉は、見てくれのいい部分です。カタカナ七文字から見出された漢字一文字、それぞれの単語から連想される多寡の印象も対になっているようで、ひじょうに面白い構造をしています。
〈もったいないの「体内」の部分〉と〈宇宙船の「抽選」の部分〉については、作者のコメントに、「もったいないの「体内」は、もったいないので食べてしまうイメージで考えました。宇宙船の「抽選」は、宇宙旅行に行く人が将来的には抽選で選ばれるようなイメージで考えました」とありました。どちらも明確な文脈を伴った部分となっており、面白いです。
次に、僕の部分をご覧いただきます。
ビフィックスヨーグルトの「尽くすよー」の部分
リラックスジャスミンティーの「尽くすし休みん」の部分
アルコール消毒の「コールしよ」の部分
ドライマンゴーの「今ンゴ」の部分
細菌対策の「菌体」の部分
情報提供の「法廷」の部分
ジェルボールの「エルボー」の部分
チョコレート効果の「溶こうか?」の部分
小豆最中の「キモ」い部分
更年期の「往年」の部分
蓄膿症の「苦悩しよう」の部分
2WAYマルチ鍋の「ウェイマルチ」の部分
レコーディングの「拘泥」の部分
爽快メッシュの「壊滅」の部分
中島敦の「鹿島アツ」の部分
【ストニュー部分部の「入部」の部分】
入部条件:部分のご投稿
活動内容:部分を投稿し、部分を読む
ご投稿はこちらから(随時募集中)
↓
https://forms.gle/Cs9r6LjvuBZFYDhr8
横澤フルーツポンチ「キラキラの魔法」
六年二組の集合写真の中央では、マリちゃんが白い歯を見せて笑っている。
マリちゃんはかわいい。美人で着ている服もおしゃれだし、ハートや星など、毎日違う形のパッチン留めをしてくる。特に仲のいい友達だとは言えないけれど、名簿番号が近いからか、このあいだの工場見学で一緒に見学路を歩いていた時はよく私に話しかけてくれた。そのマリちゃんの隣に並んでいる私は、また上手く笑えていない。私は写真が好きじゃない。一人で鏡の前で笑ってみても、他の人みたいにきれいな笑顔だとは思えない。誰に言われたわけでもないけれど、気持ち悪い。そう思って、少し下を向く。
「カーコーちゃん!」
明るい声が響いた。私の意識は、一枚の集合写真の中から教室の背面黒板の前に引き戻された。振り向くとそこにはいつの間にか、かわいいマリちゃんが立っていた。
「何してるの?」
「……写真を、見てたんだよ」
「写真? ああ、これねー。私また目つむっちゃった」
「え?」
私は写真のマリちゃんの顔をもう一度よく見てみた。言われてみると確かに、両目がかなり細くなっている。目をつむっているように見えなくもないのかもしれない。
「でも、これって笑ってるからでしょ? 笑えば誰でも目が細くなるよ」
「でもさぁ~、こんな糸目じゃイヤ。やっぱり、写真撮るときは目開けていたいじゃん?」
「それは……確かにそうかもしれないけど……」
私はどう返していいのかわからなくて、マリちゃんから視線を逸らした。
マリちゃんは黙っていた。しばらくして、マリちゃんはじっと私の顔を覗き込むかのように身を傾けて言った。
「カコちゃん、プリクラ撮ってみない?」
「……プリクラ?」
「今度の日曜日に撮りに行くんだよ。アカネと、ユイナと、あとサキっぺも誘おうと思ってる。一緒に行こ~」
こうして私は、今まで怖くて入れなかったゲームセンターの奥『キラキラの森』に足を踏み入れることになった。林立する大きな機械、垂れ下がる幕と幕の決して広いとは言えない間を、みんなで路地裏を歩くようにすり抜けていく。どの幕の中でも、美形のお姉さんが微笑んでいる。みんなお人形さんみたいに色が白くて、顔面どアップでも信じられないくらいに映りがいい。そのお姉さんたちがしゃべりかけてくるかのような音声、広告、そしてどこかで聞いたことがあるような無いようなBGM。いくらマリちゃんたちと一緒だとは言え、自分がこんなところにいるなんて場違いなんじゃないかという気がして、私はなかなか落ち着かない。そもそもみんなはおしゃれな服を着ているのにもかかわらず、自分はいつものジーパンを履いてきてしまった。一方で、みんなは目を輝かせながら『プリ機』を選別している。
「これ新しいやつじゃない~?」
「あーそれ結構ケバくなるよ」
「ねえ、こっちにしよ~」
『お金を入れてね』と機械がしゃべった。コイン投入口のそばにはハート形のシールに『¥400』と書かれている。私たちはジャンケンをして、一人勝ちしたアカネちゃん以外は全員一人ずつ百円玉を投入していった。撮影人数、シールの枚数、分割、背景などを選択し、広告は瞬時にスキップ。真っ白いブースに入って荷物を置いたら、軽快なBGMとともにさっそく撮影がスタートする。
サキちゃんが私の肩を押し出しながら言った。
「カコちゃん初めてなんだから前行きなよ!」
「え、私後ろでいいよ」
「遠慮しないでほら、前へ前へ」
「あ、もう始まってる!」
『サン、ニイ、イチ……』
カシャッ。
と音がしたと思ったら、目の前にモデルが五人いるかのような写真がスクリーンに大きく映し出された。
「ちょ、あたし見切れてるんだけど?!」
「もっと詰めて!」
「やっぱ五人は狭いな」
今度は両手で頬を覆って、両サイドに視線を向けているお姉さん二人組が画面に浮かび上がった。
『次は、目線を外して撮ってみよ~う! サン、ニイ……』
意外とテンポが速い。隣のマリちゃんがお手本と同じポーズを取るのを見て、私も急いで真似をしてみる。
「ウチやっぱ眼鏡外すわ~」
「早くして!!!」
カシャッ。
そしてまた、目線を外した五人のモデルが目の前に浮かび上がる。
「うわっ、横向きすぎた!」
みんなが一斉にこっちを見たので、私は自分が思わず叫んでしまったのだということに気がついて恥ずかしくなった。ただそれほど、自分だけ黒目が一割くらいしか映っていないことが衝撃的だったのだ。目線を外すことがこんなに難しいとは思わなかった。
『次は、ほっぺにチュウして撮ってみよ~う!』
後列の三人がにやにやしながら
「どうぞどうぞ」
と勧めた。私は焦ったが、
「やんないよ、ばか」
というマリちゃんのお叱りを受けてその場は収まり、とりあえずみんなでピースをした。
撮影が終わって落書きをしていると、ユイナちゃんが
「あ、目つむってる。サングラスかけとこ」
と言って、自分の目に丸渕の黒いサングラスを載せた。目をつむっていてもかわいいのに、勿体ないなぁと思っていたら、ユイナちゃんはそのサングラスの上から突然リボンのスタンプを被せたので、私は思い切り吹いてしまった。それに気づいたみんながユイナちゃんのらくがきを覗き込んで、
「ちょ、ユイナやばいことになってる」
「何してんの」
と爆笑した。
ユイナちゃんは言った。
「カコちゃんも事故写真あったでしょ。サングラスいる?」
「あ、じゃあ、お願いします」
ユイナちゃんは目線外しに失敗した私の顔を拡大して、両目を覆い隠すように黒色の長方形のスタンプを押した。
印刷されたシールを見た時、私は自分がそれなりにきれいに映っていることに感動した。少なくともみんなに引け目を取らない程度には映っていることに感動した。そしてさすが、マリちゃんの顔はあまり変わっていない。肌の白さや頬が少しピンク色になっているところは変わっているが、顔立ちはほぼ現実のマリちゃんと相違ない。そこがマリちゃんの凄いところだ。そんなマリちゃんに
「初プリどうだった?」
と聞かれた。私は喜んでほしくて
「マリちゃん、あんまり変わらないね!」
と言ったら、マリちゃんはちょっと苦い顔をした。あれ? プリクラの顔と現実の顔が変わらないというのは、誉め言葉ではないのだろうか?
家に帰ってベッドにどさりと倒れ、出来上がったプリクラを眺めてみる。自分はこんなに目が大きい覚えはないし、こんなにシュッとした顔立ちをしている覚えもない。でも自分の面影はあるから判別はつく。みんなの顔を見ていても、大体そんな感じだ。
写真を楽しいと思ったのは初めてだった。あの真っ白いブースの中は、魔法のようだった。プリクラの中の私は、私だけれど私じゃない。上手く笑えるかなんて気にせずに、純粋に写真を楽しむことができる。最後まで疑問だったが、ガオガオポーズっていったい何なんだろう。
マリちゃんには高校生のお姉さんがいるらしく、そのためか色々なことを知っていた。先生に見つからない程度のマニキュア、アクセサリー、いい香りのする制汗剤。私の知らないものばかりだった。私はマリちゃんの影響を受けて、ドラッグストアで初めて色付きのリップクリームを買った。早速塗って学校に行ったけれど、色が異様に赤かったので、先生に没収されてしまった。家にも電話が入って、今までそんな気配のなかった娘が学校に色付きリップを持ち込むなんて! と、俗っぽいものに対して厳しい母にこっぴどく叱られた。それでも私はやっぱりマリちゃんみたいになりたくて、もっと薄いピンク色のリップを買い直した。それを塗って学校に行ったら、
「前の赤い色付きリップでも、塗り方によっては自然に見えると思うよ」
と、マリちゃんに女子トイレの鏡の前で正しい塗り方を教えてもらった。
卒業式を迎えてアルバムを受け取った時、私はやっぱり自分の写真が気に入らなかった。私の個人写真を見たマリちゃんは
「カコかわいいじゃん」
と言った。マリちゃんはそう言うけれど、実際にマリちゃんのかわいさと、そこに立っているだけで周りの空気がキラキラして見えるその存在感を目の当たりにしてしまうと、私はどうしても信じられなくて、とりあえず
「ありがとう。マリちゃんもかわいいよ」
と返しておいた。そして、卒業記念にみんなでプリクラを撮りに行った。
中学校に入学したばかりの頃、私は新しい友達作りに苦戦していた。自分に話しかけてくれる人なんて誰もいなくて、かといって自分から話しかけに行くにも緊張してしまって。とはいえ、六月にユイナと一緒にバレーボール部に入ったら、ほぼ強制的にメンバーと仲良くなれたので安心した。よく関わってみると、中学校では見た目に気を遣っている人が小学校にいた時と比べてかなり多いということがわかった。中学校に上がった途端、遊びに行くときの服装がなぜか急にみんな大人っぽくなる。ランニングの後に乱れまくった前髪を整えるようになる。トイレの鏡の前でたむろする女子生徒が増える。いらない化粧品を交換するようになる。友達同士で「かわいい」を言い合うようになる。引退する三年生の先輩が私服のままコーチに挨拶に来た時は、フリルのついた丈の長いスカートやファッション雑誌から飛び出してきたみたいな流行の服など、いつもの練習着とは打って変わって着飾っていて、部員みんなでびっくりしたことがあった。
私はマリちゃんたちとの付き合いがあったおかげか、みんなのそういう流れについていくことができた。『カワイイ至上主義』的な空気に、必死で喰らいついていった。
一方でマリちゃんはよくモテた。私が知っているだけでも、三年間で十回以上は男の子から告白を受けていた気がする。ここまでモテると、告白してきた人たちの中にはやはり変な人も何人かいて、私とユイナたち三人は、我こそはマリちゃんの護衛だと言わんばかりにマリちゃんに近寄る変な奴らを追っ払った。それが思いのほか楽しかった。
マリちゃんが生徒会の副会長に立候補したことがあった。もう一人の立候補者は学年で十番以内に入るほど頭がいいという情報を耳にして、マリちゃんは非常に心配していた。そんなマリちゃんをみんなは
「マリちゃんかわいいから大丈夫だよ~。私マリちゃんに票入れるよ~」
と慰めていた。私はどこか引っ掛かるものがあって、
「選挙にかわいさって関係あるの?」
と後でユイナに聞いてみた。ユイナは少しうーんと唸ってから、こう答えた。
「マリちゃんには言えないけどさ、選挙なんて、あんなの人気投票でしょ。給食の後に演説やるんだよ? 立候補してる人には悪いけど、みんな眠くて聞いてないって」
私は確かに納得した。『この人がいい』と明確に決まっていればいい。けれど私もよく演説中に睡魔と格闘している。そんな状況で選べと言われても、誰でもいいだろうと思ってしまう。
「友達とか知ってる人が出てたらまだしも、知らない人が出てたら私、顔で選んでるもん」
「顔で選んでるんかい」
あけっぴろげに言うユイナにそう突っ込んでやったが、自分も無意識のうちに顔で選んでいないとは言えないと思った。
マリちゃんが見事当選した時、
「マリちゃんおめでとう!」
とみんなで喜んで、いつものメンバーでショッピングモールに行った。そして、半透明のプリクラが撮れると話題の最新機種で記念撮影をした。
卒業アルバムの個人写真撮影の日、私は薄く化粧をして、髪型も変えて、事前に笑顔の練習もして撮影に臨んだ。けれど、カメラマンのおじさんの
「はァァァ~イ!」
という掛け声に妙な癖があるせいで、笑ってはいけないと思いつつも笑いをこらえきれないでいる変な顔の写真になってしまった。この写真が二百余名の手に渡ったことは少しトラウマになった。それでもマリちゃんは私の写真を見て、
「カコかわいいよ」
と言った。気持ちはありがたいのだけれど、やっぱり私にはマリちゃんは眩しすぎて、小学校の卒業式の時と同じ返事をしてしまった。
中学校を卒業してマリちゃん、アカネ、サキとは離れてしまったが、同じ高校に進学したユイナとは付き合いが続いた。
この頃の私はスマホを持てるようになって、加工アプリにどっぷりと浸かった。真っ白いブースで友達とプリを撮り、らくがきブースで目の大きさ、口、顎、特に一番気になる鼻筋を加工し、家でもさらに加工する。何度も自撮りをして、自分が盛れる角度・盛れない角度を研究する。加工に加工を重ねて最大限に盛れた『カワイイ』を追求して、やっとインスタに載せる(学生証の写真は上手くいかなかったけれど)。
高校に入ると、みんながどんどん垢抜けていくのがわかった。幸いウチの高校は校則が緩い。多少毛先を巻いてメイクして、マニキュアを塗った程度では、先生は何も言ってこない。メイクはしないにしても、よく見ればストレートパーマをかけていたり、睫毛がカールしていたりといったことは日常茶飯事だ。今の私は、みんなのスピードについていくことができている。むしろ余裕でついていける。とあるクラスメイトに私の知っているヘアオイルを紹介したら、気に入ったととても喜んでもらえて嬉しかった。別のクラスメイトからも、
「プリクラの顔があんまり盛れないの、ちょっと悩んでるんだよね~」
という軽い相談を受けた。実際のプリクラを見せてもらうと一瞬、誰だ??? と思うほどの別人が映っていて、
「ほら、あんまり変わらないでしょう?」
私は本当に何と返せばいいのかわからなかった。たぶん人生で二番目くらいに返事に困った。この出来事を後でユイナに話したらゲラゲラと笑われて、
「カコよくがんばったね。それは私もなんて返せばいいのかわからないwww」
と言われた。
「別に、あの相談に来た子をブスだとは思わないんだよ? むしろかわいいと思う。でもあの子の場合は、プリクラで補正されるような種類のかわいさとは違うと思うんだよね」
「ああ、そういう子いるよね~。とりあえず『そうだね』って言って笑っておけばいいと思うよ。だからカコ正解だよw」
廊下の壁一面に掲示された体育祭の写真を眺めていた時、突然ユイナが声を上げた。
「うお! このカコめっちゃいい顔してんじゃん!!!」
ユイナの指さす写真を見てみると、応援席でバレーボール部のメンバーと笑っている私がいた。その写真の中の私はメイクも何もしていない。正確に言えば、メイクはしていったけれど汗で全部落ちてしまって、水道水で洗い流した後だったはずだ。もちろん加工もされていない。私の顔にはたくさん皺が寄っていて、お世辞にもきれいとは言えない口の開き方をしている。
「えー、でも結構クシャっとした顔だよ?」
「これがいいんだって! いつもの笑ってるカコだって! きれいに撮れてるし、超いい写真だよ~」
その時、私は急に両脚の力がふっと抜けた気がした。どうしてそうなったのか自分でも驚いた。私の脚は折り畳まれるように屈折して、そのまま廊下にしゃがみこんでしまった。今まで求めていたものがやっと手に入ったような気がして、その時を待っていたかのように、私の目からぼろぼろと涙がこぼれてきた。
「え、何? カコどうしたの?!」
ユイナの混乱する声が、どんどん遠のいていった。
涙が収まってから、私はその場で思いついたことをすべて打ち明けた。ある程度吐き出すと、私はもうそれ以上何も思いつかなくなった。ユイナがうーんと唸って口を開いた。
「カコはさ、小六の時と比べたらだいぶノリ良くなったし、笑うようになったよ。私はカコの笑ってる顔かわいいと思うし、笑ってなくてもかわいいと思う。でも自分の写真って、誰が何と言おうと自分がいちばん気になるんだよね。私も彼氏できるまではヤバいくらい悩んでたから、あんまり人のこと言えないけどさ、まあ、その……気にしないほうがいいよ。ていうか、気にする必要ないよ」
「……ユイナ、彼氏いたの?」
「え? ……あ」
「私、知らなかったよ? なんで教えてくれなかったの……???」
私はユイナの彼氏について徹底的に尋問した。その間、私を慰めてくれたユイナの言葉が何度も耳の中でこだましていた。ユイナの言葉を体が吸収していく。拒否反応を起こさずに受け入れていっている。体がじんわりと温かくなっていくのが、確かに感じられた。
卒業アルバムの個人写真撮影の日、私はパイプ椅子にさっと座り、にこりと歯を見せて笑って、
「はぁい、おっけ~」
というカメラマンの声を合図にそそくさと退いた。とりあえず笑っておいた方が早く終わる、そう思っていたからだ。
式を迎えてアルバムを確認した限りでは、わたしの笑顔はぎこちない感じがした。けれど今は自分の写真映りが以前ほど気にならない。よく見たら、私のようにぎこちない笑顔の人はたくさんいた。
「カコー、お客さんだよ~」
顔を上げると、ユイナが右手を振りながら誰かを引き連れて教室に入ってきた。
「この子、シズクっていうんだ。カコと話したいって言うから、連れて来たよ」
自分よりも頭一つ分背の小さい女の子。話したことはないけれど、よく思い返してみれば廊下で何度かすれ違っていたかもしれない。
「あっ、あの、突然押しかけてごめんなさい、六組の佐藤シズクです。よくユイナちゃんから話聞いていました、面白くてかわいくていい子だよって。今まで話しかけられなかったんだけど、実はカコちゃんにずっと憧れてて、お友達になりたかったです……」
私は一瞬、何が起きたのかわからなかった。それはとても細くて弱いけれど、確かな意志を感じられる声だった。
「あ、憧れ……?! え、どうしよう、めっちゃ嬉しい! ありがとう! とにかく私とはもう友達だからさ、よろしくね! あ、そうだ。式が終わったら、みんなでプリ撮りに行こ! ね!」
「あ……、ぜひとも、よろしくお願いいたします……!」
シズクちゃんは深々と頭を下げた。私ははっとした。自分を抑制するような声、表情、仕草、言葉遣い。
あのときマリちゃんは何を思っていたのだろう。今ならマリちゃんの気持ちが、なんとなくわかる気がした。
怜悧「断崖と浮遊」
以下に著述するのは、私の象徴的な一群の経験である。
或る種の神話や寓意などではなく、反省的事実であり、
真に生きられた経験である。
従って、誠に残念なことに、この文章は読者にとって何事をも示しはしない。
卒
業式が終わった。先ほどの事だ。
連日の暴風が桜を散らし、春の暖気に肌寒い冷気を混ぜ込んでいる。
卒業式などと言われれば何か大変なことのように思われる。
私はこの一大事をどうにかして重大なものに思おうと努めたがどれも意味をなさなかった。
全ての事が全き日常の様相の内に過ぎていった。
先ず私達は会場の内に互い違いに整然と並べられたパイプ椅子に座らされた。
上から見た百余人の黒服は金属結合で結ばれた無数の分子のようにでも見えたかもしれない。
暫くして、慇懃な風貌の馴染みのない眼鏡の教師が私たちの前方に立った。
彼は勿体つけた風にそれ自体ではあまり意味のない定型表現を一頻り言い終え、開会を宣言した。
その後私たちは彼の言うがまま、起立と着席とを繰り返した。
次に恰幅の良い柔和そうな老教師が緩慢な仕草で演壇上に登り、方々に礼をした。
校長である。
去年に以前の校長と交代で赴任してきたのだった。
私たちはこの間、起立した儘である。
そして、卒業生のうちの一人であろう名が眼鏡教師によって呼ばれ、一人の生徒が
ゼンマイを巻きすぎたかのような奇妙に溌溂とした角ばった足取りで遠回りをして壇上へと向かった。
校長は手元の紙を文節ごとに区切って、これ以上なく鯱張って読み上げその紙を、壇上の生徒のほうに両手で差し出した。生徒のほうも腰を海老のようにして折り曲げつつ両手で以て恭しくこれを受け取った。
卒業証書のようである。
という事は、この儀礼的な受け渡しを全員分繰り返すのかと、中学校の卒業式を思い出しつつ、愕然とし、気の遠くなる思いだった。
しかし、僥倖なことに私たちの卒業証書は彼の代理の元一括で授与された。
私は壇上の海老になった自分を思い浮かべつつ、密かに安堵した。
しかし、私のこの安堵はここで立たされている私達全員の安堵でもあったろうと思う。
代理の生徒が引っ込むと校長は懐から別の紙を取り出して、広げ、式辞を始めた。
正に学校の長たる学校長としての名演であった。
ゆっくりと、時間が流れないようにして流れる。
校長の声が響いていなかったならば時間が経っていることも気付かなかったかもしれないほどである。
陽気さを少しだけ取り戻した春の太陽に薄い雲がかかり、時折会場の明るさが移ろっていく。
前方に掲示された式次第に目をやると式はまだ折り返しにも差し掛かっていなかった。
ここにきて足のしびれと後頭部の頭痛とに気づいた。
校長が式辞を終えて礼をすると、今度は又別の生徒が壇上へと向かった。
私は今度の生徒を知っていた。柚津さんであった。
彼女は壇上で校長と相対し、一礼し、手元の紙を大きく広げた。
柚
津さんと私と同クラスであった。
私達はよく話をしたが、友人というわけでもなく、当然それ以上でもなかった。
彼女は清流のような人であり、目で多くを語る人だった。
彼女は宇宙開発に携わるという壮大な野望を有しており、彼女自身の自覚する才能と野望との乖離で絶えず揺らめいていた。
その容姿、学業成績、人望その他の点についても取り立てて秀でたところはなかったように見受けられたが、それでも彼女は可能的な世界に留まっている複数の自己を眺め、絶えず自らそれを選択する意志であろうとしていたように思う。
彼女とは清流のように一途な明晰さであり、またそうであろうという情熱であった。この点に於いて、彼女は他の生徒とは一線を画していた。
ところで、ここまで書くと、読者の中には、彼女に向けられた私の眼差しの内に、特別な感慨を読み取ろうとする人があるかもしれない。
しかし、私は自分の脳裏の現象につい単純な記述で説明することは差し控えておく。
理由は二つある
一つに物語上の人物について、明解な関係や態度を期待するのは悪癖であると思う。
意識の中身は各瞬間において総体的で連続的な一つの無限な直観であり、
人間の精神は繊細微妙である。
私は自分の意識内容を明解なものに分割したくないからである。
そしてもう一方で、そのような悪癖も今回の場合に関しては、あながち間違いではないのかもしれないからでもある。
賢明なる読者諸賢に於かれては、言わずとも察してくれることを期待する。
そして何故、その彼女が壇上にいるのか。
元々この役目を負う筈であったのは、前生徒会長であり、私の中学生時代かのら知り合いでもある上田だが、彼は三ヶ月前にさる醜聞によって失脚してしまった。
当時は学内全体が、ロココ期のヴェルサイユ宮殿のような様相をほのかに帯びていたので
真面目な彼女にお鉢が回ってきたのだろう。
上田は、学年一の美貌との呼び声も高い副生徒会長と交際していた。
それで満足すればいいと思うのだが、遺憾なことに上田は生来ドンファンのような男であったので、
飽きもせずに、もう片方の手で桃色の火遊びを繰り返していた。
しかし、とうとうこの火遊びが副会長の耳に入ってしまう。
平生もてはやされて過ごしていた高慢な副会長は、それはもう怒り狂った。
そして或る時、副会長の手になる、いとも卑猥なる告発本「0.03mmの関係」が校内にバラまかれ、彼の色事情が全て白日の下にさらされてしまった。
副会長の捨て身の自爆攻撃である。
上田は告発本の一冊を手にとって、「なんという、ヘンタイ本じゃないか」と素っ頓狂な声を上げた。
変態はむしろお前だと思った。
彼の評価は地に落ち、副会長もろとも生徒会の任を解かれた。しかしそれでも彼はまだヘラヘラとしていたのだから大したドンファンだと思う。
このことに関しては大いに笑わせてもらったので、意外にもこの一年間は笑いに事欠かなかった。
特に、告発本の中に書かれていた内容で、上田が好んで相手にさせていたという、制服だけを身につけたラインダンスのような踊り
「破廉恥・カンカン」の記述を見たときは腹を抱えて笑った。
彼
女はゆっくりと息を吸い、そして「私たちは…」と静かに口を開いた。
彼女は、自身の半生と三年間の出来事を軽く語り、親や教師への感謝と現在の感慨を語った。
彼女は不安と希望との内に沈み込み、人生の一つの最高潮を迎えていた。
彼女は舞台上にあって全き卒業生であった。
一方の私は百余人の只中で途方に暮れていた。
彼女が感慨を儀礼的に代弁している“私たち”の内に私は含まれてはいない。
私は何故、こんなところにいるのか。
何をするためにいるのか。
何やら場違いの会場に迷い込んだようである。
前列生徒のパイプ椅子や制服の染みが目についた。
これらも同様に場違いである。
足のしびれと眩暈とがとうとう耐え難いものになった。
視界の右端で音を立てずに生徒が崩れ落ちた。貧血だろうと思う。
彼女の演説が終わると、私達は着席が許された。
しかし先の教師はすぐにマイクを手元に上げ、間髪入れずに起立を命じた。
国歌と校歌とが流れ、合唱をする流れとなった。
校歌を歌う機会はこの三年間で幾度となくあった。
私は今まで殆ど、口だけを動かしてさも歌っているかのように振舞ってきたので、今回もその様に事を済まそうかと考えていたが、ピアノの伴奏が流れ、結局歌うことにした。
特に理由はないように思う。
しかし、校歌が2番、3番に差し掛かると、歌詞が曖昧だったので、やはり口をつぐむことにした。
歌うふりなどしなくても、卒業式で歌わないからといって、見咎めるような人はいないだろうし、いたとて、もう会うことはないだろうからそう不利益もないだろうと考えてのことである。
ところが、事情は誰もそうは変わらないらしく、校歌の合唱は2番の中程で突然に弱弱しくなり、自信なげな揺らめきを見せた。
あちこちで歌詞が間違ったり、歌唱が途切れたりしているのが聞こえた。
壇上のピアノ伴奏だけが正しい拍を刻み、気まずかろう時が流れた。
合唱が終わると、吹奏楽部の必死の演奏が流れ、私達は会場を後にした。
金管楽器の演奏の難易度がよくよく感ぜられた。
素っ頓狂の金管の高温は放課後の夕暮れの校舎と一纏めの記憶を形成している。
私達はぎこちなく列をなして退場し、会場の外へ出ると私達は行き場を失ったように扉の前に滞留した。
今まで受動的に式に臨んでいたので、次にどうすればいいのか考えることもしないでいる。
4月の空気の匂いは3年前に初めて足を踏み入れた時と、寸分変わらないように思う。
私自身の方が少し萎びただけの事だ。
大学卒業の時や、退職時、その時がどんな風であるか、全く想像もつかないが、以前よりも生気の無くなった私が同様の感慨で、それまでいたどこかから放り出されるに違いない。
数分が経ってようやく私達は教室へと向かった。
彼らは終始昨日までと何も変わらない風にはしゃいでいる。
教室は昨日の内にすっかり掃除がなされていて、さっぱりとしていた。
教師が前に立ち、私たちは思い思いに座った。
教師は淡々と、証書やその他の配布物を一揃い配り、一群の連絡事項を伝え終わると
一息ついて「それでは諸君、今生の別れです、さようなら」と言った。
私はこの表現が良いと思った。
「そうですね、今生の別れです」と、確認するように繰り返し言った。
この一言が今日の出来事の全てを表しているように思う。
教師が挨拶を終えて立ち去った。
もう、私たちもいつ帰宅しても構わないようだ。
しかし誰も帰ろうとはしなかった。
彼らはいつもと変わらずにそれぞれの仲間と談笑している。
私はこの三年で友人と呼ぶべきものを作らなかった。
最期に、幾らかの知人と話し、幾らかの知人と話さなかった。
特に、話すべきことも浮かばなかった。
全ての用事が済んでしまえば、とうとう教室にとって、或いは校舎全体にとって私たちはもう異質なものとなって、未来の方へと追放されていく。
彼女は「私たちは新たな世界に飛び立つ」のだと言った。
飛んだ次の飛び石がどんなであるかは飛ぶまでは分からないことである。
そこに、窓から春一番が吹き込んだ。ある種の涼けさに包まれる。
私は何か、急かされるように覚えて教室を後にした。
彼らはまだ殆ど教室に残っている。
私と彼らとの間の“糸”はもう殆ど解きほぐされようとしている。
彼らが私に対して関係する蓋然性はもうない。
教室の戸を閉め、少し冷えた薄暗がりの廊下を抜けて玄関へと向かう。
玄
関口には逆光が差し、風が強く吹き込んでいた。
粗末な木製の下駄箱を開けて、靴を取り出し、それを履く。
暗い校舎から眩しく日の差す明るみへ出ていこうとする。
二歩、三歩と歩き、しかし私は玄関口の大きな扉の前で歩みを止めた。
扉は開け放たれていた。
出ようと思えばいつでも出ることができる。しかし、そうではない。
私の足を止めたのは驚きあった。
白く輝く扉の奥の世界に、私は柚津さんの後ろ姿を認めていた。
逆光が眩しく、白昼夢の世界の住人のように見える。
そして彼女の後ろ姿のその奥に、彼女の微笑が思い出された。
彼女の意識の内側に希望や喜びが充満すると、彼女の瞳がキラキラと光り、目が少しだけ大きく見開かれる。
そして、その喜びが瞳から溢れて、視線を通して私の意識にも注がれてくる。
そのような瞳が思い出された。
そして、この注がれた喜びの残滓は私に対して、ある一つの可能性をもたらした。
というのも、私は彼女との関係の糸を自ら手繰り寄せるべきなのではないかとそう考えたのだった。
しかし、私自身この考えに、驚かされた。
それは私にとっては、私の今までの一群の他者との関係は大きな力によって、先ずもって与えられた一種の世界の在り方だったからである。
というのも、この有機的関係の各原子としての私たちはウチとソトとを形成する引力、斥力によって凝固、隔離されており、私たち各個人が殊更大きな力で結合せずとも静的で安定的な人間関係が成立していた。
我の世界は開かれつつも、閉じられていた。
自身の人間関係の世界の中に自身の力で何か変化を起こそうなどとは、今迄考えもよらなかったからである。
そして、私は自分の三年間に何かそうまでして保つ価値のあるものはないと信じていたからでもある。
しかし今や、私を三年間の長きにわたり閉じ込めていたこの力、私が絶えず静かな反抗を試みていたこの力はあっけなく崩れ去った。
今や私の世界は完全に開かれ、私は具体的な二つの“私の”可能性に面している。
私は彼女を追いかけるだろうか、或いは、何もしないだろうか。
選択しないという事もやはり一つの積極的な選択である。
私は撰ばなくてはならない。それも彼女が車に乗り込む前に。
この選択は倫理や理性の問題ではない。
今度ばかりは、私の灰色の脳細胞も何の役にも立つまいと思う。
実際、私は私自身の理性になんと問いかけることができるだろうか。
私は一応はこう問いかけることができるだろう
「私は本当に彼女との関係をつなぎ留めておきたいのか」
「私はそんなことをする人間であろうか」
しかし全て無駄なことである。
それらは全ての事が終わってしまって、その後で私が自身の選択の言い訳に使えるに過ぎない。
私が本当はどうしたいのか、その答えを知っているのは私だけだが、
私が私自身の事を偽りなく答えてくれるとすれば、そもそもこのようなことを問う必要もない。
私の焦燥、怯え、三年間の態度、これらの事が私自身を私自身から隠し去る。私自身がどう思っているのか、それが私自身に露呈するのは、私が撰んだ後の事だろう。
彼女は強風に髪を抑え、前かがみになって一歩、一歩と歩みを進める。
そのゆっくりとした歩みを私は注視している。
彼女が迎えの車に乗ってしまえば、すべてが終わってしまう。
あと、20数歩、彼女が踏み出しても、それまではまだ間に合う。
しかし30歩そして車に乗り込む。そうなってしまえば、全てがお仕舞。
29歩と30歩その間に何が起こったわけでもない。
無限に細分化できる些細な時間、この二つの時間の無の隔たり。
時間は経たない様に経っていく、29歩と30歩、もし彼女が踏み込んでしまえば、もう絶対に戻ることはない。
アイスが落ちて地面に接する瞬間、大一番で打者のバットが球の上に空を切る瞬間。
その一瞬で何が起こるわけでもない。
時間が無の一瞬程に流れる、流れたことにすら気が付かない一瞬、ただそれだけである。
なにか騒々しい効果音が流れるわけでもない、時間の断絶が起きるわけでもない。
しかし流れてしまえば、もう戻ることはない。
時間は常に日常性の内に過ぎる。
無の一瞬が無限に蓄積していく。
そして過ぎてしまえばもう戻らない。
そうして未来の方にいきなり放り出されて、愕然とする。
知り合いの夫婦が離婚した時もそうであった。
結婚に際して、彼らは盛大に祝儀を挙げた。
しかし、離婚の時は当然そうではなかった。
最期に市役所に離婚届けを出し、市役所の職員が「ご苦労様です」と言って届けを受け取った。
それでお仕舞。
彼らは茫然として、暫くその場に立ち尽くしていた。
私は今になって、人生の転機に式を執り行う人々の意味を、卒業式の意味を、理解した。
それはその最後の一瞬に大きな意味を与えて、二つの時間の間に大きな断絶を作ろうという、そして未来に追放されることにどうにかして目を向けようという努力であった。
そのような努力は不完全にしか達成できないだろう。
時間は断絶しない。
私にとっての卒業式もそうであったように。
し
かし、この三年間で私が試みていたのもこれと似たようなものに違いない。
三年前私は、物語の主人公のように特別になりたいと考えていた。
しかし後で分ったことだが、私は、何か特別な因果の渦の中心になりたかったのでもないし、
熱烈な恋に身を焦がしたいのでもないのであった。
ただある種の特別な存在の仕方、ただこれだけを欲していたのだった。
例えば、アルジェの浜辺にある男がいる。
彼は昨日母親の葬儀をおわらせたばかりである。
太陽の光が浜辺に眩く差し、彼に迫ってくる。彼は憂鬱である。
彼は太陽から逃げようとして一歩一歩と浜辺を歩く。
彼のポケットにはピストルが忍んでいる。
或いは、もう一人、フランス北西部の港町に住む或る男、彼は18世紀の侯爵の生涯を調べ上げることに情熱を注いでいる。
しかし、その情熱はもう少しで擦り切れんばかりになってしまった。
日曜日である。
彼は市立図書館に向かっている。侯爵の資料は、大部分がその図書館にある。
彼は孤独であり、破壊的な世界観に取りつかれている。
或いは、世界観というものを破壊し、手放してしまったというべきかもしれない。彼は歩いている。
彼は多くの市民とすれ違った。
彼はそのような人々と自身との間に線を画いている。
彼もまた、憂鬱である。
彼らは歩いている。ただそれだけである。
なにが起こっているというのでもない。
しかし、彼らは憂鬱である。
彼らの憂鬱は世界の方に染み出し、彼らの一挙手一投足はそれにむけられており、それ以外のすべても同様に憂鬱である。
この憂鬱こそが彼の生活に意味を与えている。
彼はこの憂鬱さである。
閉じられた世界観がそこにある。
私は全く、物語の内部にいるような、このような方法で存在することを願っていたに違いない。
私がブラームスを聞き始めたのも、小説を書き始めたのも、芸術やある種の生き方、態度が純粋な価値を私に示してくれることを期待したからであろうし、
又、私が文学研究会を、余りに低俗だと言って辞めた時、多くの人間関係から手を引いた時。
私は閉じられた世界を作るために、見なされるより、見なす者であろうと考えていたのだろう。
スリルや冒険などは全く問題でない。
しかし、その願いは少なくとも十分には叶えられなかった。
私の身の回りの存在はどれも乾燥していて、私の日々は無意味のままにすぎていく。
或いは過去の私はそうでなかったように思うのだが、これは分からない。
私は何か自身の存在に意味を与えようとしていたのだった。
それは、何か特殊な使命や目的ではなくて、もっと些細な筈である。
彼
女は更に歩みを進めている。
後ろ姿も、徐々に小さくなっている。
私は尚も立ち尽くしている。
彼女はあと数歩で車に乗り込んでしまう。
一歩、一歩、しかしまだ間に合う。
しかし、終わりの時はもうすぐそこである。
終わってしまえば真っ逆さまである。
時間が流れていく。
私はこの瞬間に意味を与えてほしい、こう強く願った。
しかし、それはかなわぬ願いである。
或いは、何か音楽でもかけられていれば、
例えばどうであろうか、今ここに、ラフマニノフのピアノ協奏曲でも流れていたならば、この瞬間、私は彼らの様な何者かであっただろうか。
私のこの瞬間が何か意味を持つならば、私の判断がそれに向けて秩序付けられる。
そして、可能的なすべてがそれにむけて固定されるだろう。
しかし、そのようなことはありえない。
この無機質な生活世界の上空に全ての可能性は浮遊している。
そして、依然私は世界の内側にいる。
太陽がそれまでより一層強く輝いた。雲を抜けたのだろう。彼女が立ち止まる。彼女が立ち止まる。彼女が立ち止まる。
彼女は手を頭に翳しながら、はるか空を仰いだ
私は、はっとした。
しかし何に驚いたのか、それは分らない。
しかし、私の足は動いた。
黒い靴が地面を離れる、
私はきめたのだった。
彼女を引き留める。
私は動かねばならぬ。
一歩を踏み出す。
この薄暗い玄関口から脱出せねばならぬ。
彼女を呼び止めねばならぬ。
肺の辺りに力を込める。
彼女の名前を思い浮かべる。
そして、あとは声に出すだけだ。その時、格段に強い強風が吹いた。
鋭い轟音が眼前で響き、視界が一瞬で暗くなる。
玄関口の扉が風に吹かれて閉じたのだった。
私は茫然としていた。
10分から20分そこにいた。
再び扉を開くと、もう夕日が差し始めていた。
背後からは騒がしい声が近づいていた。
全ての事が終わった。
私は最後に外から高校を一瞥して、
自転車に跨り、走り出した。
その間中、今の出来事に何か解釈を与えないように努めていた。
宿身代の悪魔「不撓の高潔と未熟な純潔 短編集」
(締切の関係で、今回は時系列バラバラの息抜き回となります)
☆幾度目かの嘆息
「……うん、ずいぶん良くなったと思う。これならそうそう後れを取ることは無いんじゃないかな?」
彼は剣を下ろした私のその言葉にしばし呆けていたが、やがてその意味を理解すると頬を紅潮させた。
「本当か! これであの蟹野郎に……!」
「蟹……うん。油断せず、相手の一挙手一投足に気を配って慎重に立ち回れば、今の君なら十分勝てる相手だと思う。よく頑張ったね」
「っ、ありがとう! 俺はこの恩に報いることは出来ないだろうが、せめてこれだけは言わせてくれ。ありがとう!」
深く頭を下げる彼。違和感。
「頭を上げてくれ。私がしたことなんて、本当に大したことじゃないんだ。君は強くなりたいと願い、本気で取り組んだ。当然の結果に過ぎないさ。恩を感じるなとまでは言わないけれど、深く捉えすぎる必要はないよ」
「だが……いや、しつこくしても却って迷惑になってしまうな。あんたがそう言うなら、このくらいにしておく」
不承不承ではあったものの、なんとか頭を上げてくれた。違和感が和らいだ。
「そうしてくれると、私としては助かるよ。
……これから、『泥濘のワーゲルン』に?」
「あぁ、再挑戦するつもりだ。今度こそ踏破してやる。
あんたが付いて来てくれると心強いんだが……」
「それはやめておいた方が良い。見ての通り、私は『一つ持ち』だからね。私と一緒では、君にも一段と強力な敵が襲い掛かってしまう。当然、そうなっては蟹に勝つのも荷が重いだろう」
「……そういやそうだったな。わかった、自分の力で頑張るとするさ。
改めて、世話になったな。いつかまた会うことがあれば、この借りはその時に返させてくれ」
「はぁ……んっ」
無意識のうちに漏れた嘆息。後ろ手を振って離れていく彼の背中を見送りながら、私は口を押さえた。彼を指導している間は収まっていた溜め息癖が、一人になった途端にぶり返してしまったようだ。原因はわかっているのだが。
「いつまで引きずっているんだ、私は……」
今でも耳に残り、ふとした時に蘇る『絶叫』。あれからしばらく経つというのに、その呪縛から解き放たれる時はまだまだ遠いらしい。
「ままならないものだな……」
『竜の楔』に背を預け、ずるずると座り込む。天を仰げば、『あの時』と変わらぬ銀色の月が私を見つめていた。
☆遥かなる幻想
──あぁ、これは幻だ。わたしは不思議な確信を得て、改めて『これ』に意識を向けた。そう思ってしまえば、お話を読むみたいに楽しめそう。
『リアお姉さまっ。これ、見てください!』
『ん? わぁ、綺麗な花冠! ありがとう、リリィは本当に器用だね』
『えへへ……』
二人の白髪の女の子がじゃれあっている。比較的年長で、花冠を受け取っている方が『オフィーリア』。より幼く、頭を撫でられて顔を綻ばせている方が『リリウム』というのだと、誰に聞くでもなく理解していた。
唐突に場面が変わった。二人とも少しずつ背が伸びており、並んでなんらかの特訓をしているようだった。大変そうではあったけど、それでも二人ともどこか楽しそうにしているのが印象的。
その後もぱらぱらと書物のページを捲るように場面が移り変わっていき、そのたびに時が経過しているみたいだ。『リリウム』のほうは相変わらず『オフィーリア』にべったりで、一緒に居さえすれば幸せそうだったけど、『オフィーリア』のほうは徐々に笑顔が減っているように感じられたのが気になった。
そして──
「ん……」
「っと、おはようかな、リリィ?」
ふと気づくと、地面とは違う柔らかさに、くすぐったいような幸せな感触。上から降ってくる声。えっと、確か……。
「わたし、『竜業』をつかって、それで……」
「思い出してきたかい? 記憶に欠落が生じるタイプではないのかな」
だんだん思い出してきた……のと同時に、今自分がどんな状態なのかも理解できてきた。えっと、もしかしなくてもとっても恥ずかしい感じなんじゃ……。
「ああ、まだこのままでいいよ。さっきの戦闘の余波で、ここら一帯に敵の気配は無い。だから、今は大人しく労われていて欲しい」
……今すぐ起き上がるつもりだったけど。こんな風に言ってくれたし、もうしばらくこのままで。あっさりと欲望に負けた自分自身に軽く呆れつつ、わたしはこの幸せを堪能しようと決めるのだった。
あとがき
キラキラの魔法 横澤フルーツポンチ
㊟筆者はこんなにキラキラな青春を過ごしていません。プリクラ…いつの間に500円になってたんですか…?
わたしの王子様 李音
拙い作品ですが、楽しんでいただければ幸いです。
愛しき隣人(再掲作品) 登校は登山
Vol.165の『隣人』号に寄稿した物を再掲させていただきました。フレッシュマン祭という折にも良い作品だと思っています。思っていた三倍は忙しい日々になると思いますが、どうか生活に堕されませんように。
ストニュー部分部 第二回 タイトルの「意図」の部分 尾井あおい
連載型の部分投稿欄、「ストニュー部分部」の第二回です。部分のご投稿、ありがとうございました。フレマン号なので説明を加えておくと、部分とは、ある言葉のなかに潜む部分―すなわち同音異義の言葉を見出す言葉遊びの一種です。「ストニュー部分部」ではさまざまな部分を募っていますので、ぜひご投稿ください。よろしくお願いします。
断崖と浮遊 怜悧
思うに、この主人公は、同級生を「彼ら」と呼び、自己自身を疎外することによって、当事者から降りていた。
そして「彼ら」から完全に離れ、浮遊状態になることで当事者を取り戻した。しかし、彼は正しくものを見ようという意志を気付かない内に歪め、悪しき信仰を敷いてしまったので、失敗したのではないかと思われる。
本稿は長編の一部として薄ぼんやり考えていたものだったが、締切直前に書くと決めたので、未消化の観念を塊のまま書きこんでしまった。
そして結果的に、本稿の9割が締め切りを過ぎてから書かれることになった。
さらに、眠気とアルコールによって文章が破壊されてしまった。
前回よりはましな文になっただろうが、読むとなると多大な苦痛を伴うだろうと思う。
そこで最後に校閲の方々、編集の方々にここで謝意を述べておこうとおもう。
不撓の高潔と未熟な純潔 短編集 宿身代の悪魔
今回はちょっと趣向を変えて、一人称にも挑戦してみました。いい経験になったと思います。
さて、次回こそクライマックス。死闘の行く末をお楽しみに。
過去の作品はnote(https://note.com/nanzanbungaku)にも
掲載しています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
