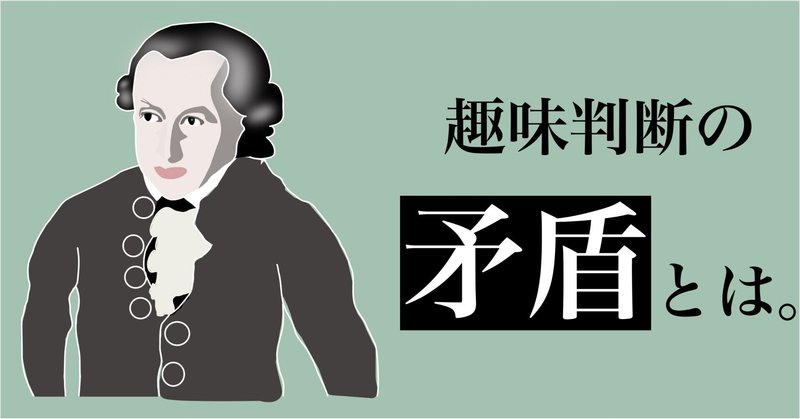
芸術と哲学の共通点を、趣味判断の矛盾から考える。【PhilosophiArt】
こんにちは。成瀬 凌圓です。
今回は、18世紀の哲学者、イマヌエル・カントが書いた『判断力批判』を読みながら、哲学とアートのつながりを探していきます。
この本を深く理解するために、全12回に分けて読んでいきます。
1冊を12本の記事に分けて読むため、読み終わるまでが長いですが、みなさんと学びを共有できればいいなと思います。
第11回の今回は「趣味判断の矛盾」について考えていきます。
これまでの記事は下のマガジンからお読みいただけます。
趣味判断は、実は二律背反?
ここまで主に趣味判断について議論してきたカントは、第一部「美的判断力批判」のまとめに入っていきます。
まず、趣味判断は快・不快という主観的な感情に基づいています。
カントは、客観的なものから判断する“認識判断”と区別しました。
趣味判断は、自分が快だと感じる判断のことで、客観的な概念を基に判断していないと言えます。
このことから、「趣味判断は概念を根拠としたものではない」と導くことができます。
そして、趣味判断には「主観的な普遍性」があるとも言っています。
ある人が花を見て、「この花、綺麗だね」と言った(=趣味判断を下した)ことに対して、自分もそのように判断できることがあります。
でも、人によっては「自分は綺麗だと思わないなぁ…」と感じることがあるかもしれません。
しかし、趣味判断は普遍的です。「綺麗だね」という判断は、すべての人にとって一致していなければならないとカントは考えています。
一致させるには、何らかの概念を持ち出して自分の判断の正当性を主張する必要があります。
つまり、「趣味判断は概念を根拠としている」とも導くことができるのです。
これまでのことを振り返ってみると、
「趣味判断は概念を根拠としたものではない」という主張と、
「趣味判断は概念を根拠としている」という正反対の主張が出てきてしまいました。
このことを、「趣味判断は二律背反(2つの命題が矛盾していて、両立できないこと)の命題をもつ」とカントは呼びました。
正反対のことを言っているのに、どうしてどちらも筋が通っているように見えるのでしょうか。
カントは「根底にある考えが同じだから」と考えているようです。
このようにして趣味の二律背反は提示され、調停されたわけであるが、その根底には趣味の正しい概念が、すなわちたんに反省的な美的な判断力としての趣味についての正しい概念が存在している。趣味について見掛けの上では抗争しあう二つの原則は、どちらも真でありうることが示されることによって、たがいに合一したのであり、この二つの命題を調停するには、それで十分なのである。
368 趣味の二律背反の解決の道筋 より(太字は文献では傍点)
根底が同じであれば、一つの結論にすることができるかもしれない。そんな考えから、カントは二律背反を解決しようと試みます。
しかし、説明すればするほど、元々していた「美しいもの」の説明が崩れていってしまいました。
カントとウィトゲンシュタインの共通点
読んでいく中で僕が思ったのは、カントは、趣味判断をどう説明すればいいかわからなくなったのではないか、ということです。
カントは趣味判断をまとめていく中で「二律背反が起こるのは、わたしたちの認識を超えた違いがあるから」と言っています。
僕はここで、以前読んだウィトゲンシュタインを思い出しました。
カントは18世紀のドイツ人哲学者、ウィトゲンシュタインは20世紀のイギリス人哲学者と、活躍した時代や場所は違います。
ただ、“認識を超えた”という表現から、前期ウィトゲンシュタインの主著『論理哲学論考』に書かれた有名な言葉「語りえぬものについては、沈黙せねばならない」に近いものを感じました。
著者は丁寧に説明してきた考えを自ら放棄し、読者としては見捨てられたような感じがしたのです。
あるテーマに対して「こう思うし、でもやっぱりこうかもしれなくて、別の捉え方もあると思うんだよ…ま、知らんけど。」と言われた感じが僕の中にあります。
えぇっ、「知らんけど」…!?
終盤に突然言われるので、「僕が読んできた時間、返してくれよ…」って気持ちになります。
カントの“認識を超えている”とか、ウィトゲンシュタインの“語りえぬものは沈黙せねばならない”とか、曖昧な結論付けにモヤモヤっとした気持ちが残ります。
「そんな曖昧なわけがない!」という対抗心が、2000年以上哲学という学問をし続けている理由なのかな、とも思ったりします(結論は結局どれも曖昧に見えるのですが)。
話が脱線してしまいました。『判断力批判』に戻ります。
カントは第一部のまとめとして美の判定を説明することにしました。
すなわちわたしたちは美一般について判定する際には、美のアプリオリな基準をわたしたち自身のうちに求めるということ、あるものが美しいかどうかという判断については美的な判断力はそれ自身で立法的なものであること(中略)が証明される。
389 自然の美しいものの合目的性の観念性 より
カントは美的判断は、アプリオリ(先天的)で、自分自身の中で筋が通ったものだと結論づけました。
これまで取り上げていた趣味判断は、美的判断の一つなのでこの文章で説明できたとしています。
芸術と哲学のつながり
さらに読み進めていく中で、僕が気になった部分が2つあります。
まず1つ目は、こちら。
あらゆる芸術における学問的なものは、客体の描出における真理を目指すものであるが、こうした学問的なものは、たしかに美しい芸術における不可欠な条件ではあっても、美しい芸術そのものではない。だから美しい芸術にとっては手法(モドゥス)というものはあるが、教授法(メトドゥス)というものはないのである。
399 手法と教授法 より(太字は文献では傍点)
ここでは、芸術における学問の位置付けについて述べています。
芸術にとっての学問は、表現するために欠かせないけど、学問そのものを芸術と呼ぶことはできないよね、というのがカントの考えです。
どれだけ美学を学んでも、他の分野の知識を手に入れたとしても、その知識が芸術になることはありません。
だからと言って、その知識が欠けた作品を「美しい」と判断するのは難しいと思います。
哲学という学問は難解ですが、アートに携わる人にとっては欠かせない物だと僕は考えています。
その入り口として僕のnoteが、役に立てば嬉しいです。
もう1つは、こちら。
師匠は弟子にたいして、何をどのようにして作るべきかを手本によって示さなければならない。あるいは師匠は、自分の手続きを最終的にまとめあげた普遍的な規則のようなものを作るかもしれない。しかしそうしたものは弟子にとっては、準則として役立つのではなく、その手続きの主要な要素を、折に触れて想起するのに役立つだけである。
ただしその場合にもある種の理想を考慮に入れなければならないが、芸術は作品を完成する際にこうした理想を完全に実現することは望めないとしても、それを明確に念頭においていなければならないのである。
399 手法と教授法 より
僕が注目したのは、後半部分です。
実現できなくてもいいから、常に理想を明確に持て、という内容。
理想を形にすべく全力で走る弟子をそっと支えるように、師匠は手本を作らなければならない、とカントは考えたのだと思います。
常に問い続け、試行錯誤しながら答えを更新していく姿勢は、芸術と哲学に共通したものかもしれません。
次回は、ついに『判断力批判』最終回になります。
全体のまとめと『判断力批判』を読んだ上で、自分の考え方がどう変わったかを書いていきます。
次回の記事は下のリンクからお読みいただけます。
参考文献
「PhilosophiArt」で『判断力批判』を読むにあたって、参考にしている本を並べました。
カント『判断力批判』(上)(中山元 訳、光文社古典新訳文庫、2023年)
この訳書では、内容に応じた改行がされていたり、すべての段落に番号と小見出しが振られていて、非常に読みやすいです。
荻野弘之 他『新しく学ぶ西洋哲学史』(ミネルヴァ書房、2022年)
古代ギリシャ哲学から現代思想まで学べるテキストです。
カントについては、1つの章が設けられています。
小田部胤久『美学』(東京大学出版会、2020年)
『判断力批判』を深く読むことができる1冊だと思います。
『判断力批判』が書かれた当時の歴史的背景や、現代における影響についても書かれています。
高木駿『カント 『判断力批判』 入門 美しさとジェンダー』(よはく舎、2023年)
『判断力批判』を解説しながら、ジェンダーについて考えられる1冊。
他の解説書に比べて薄い(150ページ程度)ですが、わかりやすくまとめられています。
最後まで読んでいただきありがとうございます! いただいたサポートは、書籍購入などnote投稿のために使わせていただきます。 インスタも見ていただけると嬉しいです。
