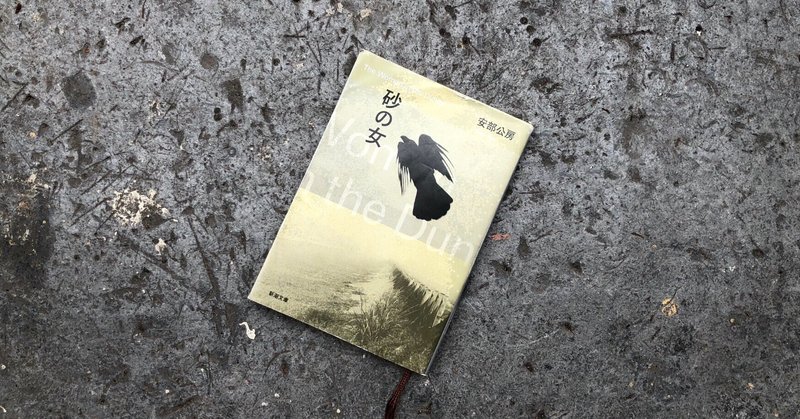
『砂の女』を読んで『パピヨン』を観る
ご存知の通り、主人公が砂の穴から出られなくなってしまう不条理な物語です。
穴の中に住む女は彼の質問になかなか答えてくれないし、読み手も主人公と一緒に困惑します。一体どうしてこんなことになってしまったのか。これは一体なにかの間違いじゃないのか。
監禁されるのも身体的に怖いけど、意味が分からない状況に突然放り込まれ、誰も質問に明確な答えをくれないというのがさらに精神的な恐ろしさを掻き立てます。
それにとても臭い匂い漂ってくる文章です。不衛生な穴の生活。自分の常識が通用しない小さな世界に閉じ込められる恐怖。人が狂っていく様子、誰がおかしいのか常識の境界線が曖昧になっていく様子にハラハラします。
自己評価が高すぎるため他人を馬鹿にして、いちいち読みが甘く深みにはまってしまう主人公。でも危険を察知したくない、大丈夫って思い込みたいという無意識の効果で状況を都合よく解釈しちゃうことってよくあります。厭世的な主人公はときどき鬱陶しくも感じますが、こういう読みの甘さには人間味があってなかなか目が離せません。
主人公と同じ状況に陥ったら頭がおかしくなっちゃうだろうな、絶対に嫌だなと、ハラハラしながら一気に読みました。
しかし「絶対に嫌だ」と思ったのにも関わらず、読み終えると果たして彼は不幸だったのか?と疑問が浮かびます。
一体彼の穴の中の生活と、私たちの人生にどれほどの違いがあるのでしょうか?
私たちが希望や夢と呼んでお家の棚に大切に飾ってあるものも、現実から目を逸らさせるために巧妙に仕組まれた幻なのかもしれません。
毎日繰り返している日常生活も、余暇も、物欲も、本当は霞のように掴めない意味のないものなのに、意味があると信じ込まされているだけなのかも知れないと、ドキッとしました。
本当の自由とはなんなのか?そして”本当の自由”は存在しているのでしょうか?
自由とは、生きるとは、生活とは、仕事とは、存在意義とは、と多くを問いかけてくる一冊です。
『砂の女』 安部公房
あらすじ
新種の昆虫を探すため砂地へやってきた教職員の主人公は、砂の中に埋もれていくように家が建つ奇妙な村へと迷い込む。砂の穴の底にある廃屋のような家に一晩泊めてもらうことになるのだが、しかし翌朝目が覚めると穴から出られなくなっていた…

初めは穴の中の生活に反抗する主人公。砂かきも手伝わず、ふて寝を決め込みます。ところがしかし、すぐに従順になります。何もしないと退屈で頭がおかしくなってしまうから、何か手を動かす必要があるのです。終わりのない砂かき作業でも慣れてしまえばそれなりの心地良さが生まれます。
次第に脱出方法を考え試してみたり、カラスを捕まえる罠を作ったり、何か打ち込むことができてくると穴の中にいながらにして人生全体に意義が生まれます。外の生活では感じられなかった自分の存在価値さえ感じ始める主人公。
人生に最低限必要なのは水と食べ物、人との関わり、退屈を紛らわせるためのルーティン。そして、なにか主体的に夢中になって打ち込めることが見つかれば、どんな環境にあってもそれは案外良い人生なのかもしれません。
主人公が作中言及するように、我々はただ「時間を潰すための選択肢は多い方が良い」と思いこまされているだけなのでしょう。
家を買いたいとか、ショッピングしたいとか、綺麗なお洋服を着たいとか、レストランに行きたいとか、旅行したいとか、本を読んだり映画を観たりしたいとか、みんなそれぞれに欲があります。選択肢は多いほど豊かです。そしてその欲を満たすことが幸せになることや夢を叶えることだと信じて働いています。欲しいものが手に入ると満足感を得られます。でもそれは本当に自分のほしいものなのでしょうか。必要だと思わされているだけなのではないでしょうか。それは一瞬気を紛らわせてくれるだけの儚い快楽ではないでしょうか。
物欲よりも人生を根元から豊かにしてくれるのは、"希望"です。
カラスの罠を仕掛けある発見をしたことから主人公の生活に希望が生まれます。突然やるべきことが見えてきます。
天気を調べ、砂の動きを調べる主人公。研究すること、主体的に取り組むことが見つかるとウキウキしてきます。
人生に意義が生まれるのは、こんなふうに何もないところに希望を見つけ、夢中になって主体的に打ち込むとき。
そのうちに、"逃げられない"という制約がいつのまにか生きるための希望になっているのです。
逃げられないからこそ、逃げようという希望が生まれるのです。
私たちの生活も、制約だと感じていることが実は生き甲斐を得るための根源的な条件になっているのかも知れません。だとすれば生活とは何と哀しい皮肉なのでしょう。
果たして彼の人生は不幸なのか幸福なのか?
わたしは限定された条件下における最大限のハッピーエンドだったと思いました。これ以上ぴったりな終わり方は考えられない、最高の終わり方です。
本を閉じるとき、改めて冒頭の言葉が蘇ってきます。
罰がなければ逃げる楽しみもない。
生活全体が霞のように揺らぎだし、全てが幻で築かれたお城だったと気付かされるような、そんな読書体験でした。
読み終えたあと映画『パピヨン』のことを思い出し、久しぶりに見返しました。
かわいい題名とは裏腹に脱獄ものの名作で、印象深い作品です。リメイクもされていますが、手に取りたくなるのはやっぱりスティーブ・マックイーン&ダスティン・ホフマン版。
『パピヨン』はまさに人生の縮図です。
囲いの中で工夫して自分らしく暮らすか、囲いの中に安住せずあくまで自由を求め続け危険に飛び込むか(しかも囲いの外の世界の方が快適だという保証はない)。
昔観たときは断然、囲いの中の暮らしで衣食住に困ることがなくとも自由を求め続ける姿こそカッコいい!それこそが本当の人生だ!と思っていたのですが、見返すと印象がかなり変わりました。
囲いの中でもなるべく自分の居心地の良いように、工夫して楽しく暮らしに取り組むダスティン・ホフマン演じるドガは全然負けてなかったなと今なら思います。彼のように自分で何とか工夫して、制約の中でもよりよくあろうとする生き方は、思っていたほど簡単ではないのだと、今ならわかるからです。
ほとんどの人生は囲いの中で不満を言いながら、自分で工夫することもなく足を引っ張り合いぬるま湯で傷を舐め合って、いつか外的要因で状況が変わることを待っているだけ。もしくはドガのような人生を馬鹿にして自分はスティーブ・マックイーン演じるパピヨン側だと思っているくせに一生波に飛び込むことはないのが”普通”の人生だと思います。
そうなってしまうこともさもありなんという社会の仕組み。
そんななか、ドガのように楽しく暮らせるのように工夫することはすごいことだったんだと見直しました。ドガは頭が良いし世渡り上手だけれど、身体が軟弱なところになんとも言えない哀愁を感じます。『ミッドナイト・カウボーイ』と重なって、最後の彼の表情が特に胸に残りました。彼は彼なりのベストな選択をしたのでしょう。
一方で、身体的にも精神的にも粘り強いパピヨンはやっぱりかっこいい。健康体なのはもちろんなのですが、独房に何年入れられても頭がおかしくならない精神力が圧倒的。どんなことをしてでも脱走する、とことんまで自由を求める強い"希望"
が精神と肉体を支えていたのでしょう。これが自伝的小説を基にした作品というのだから恐れ入ります。
『砂の女』も『パピヨン』も、脱走をテーマにした非日常的な極限状態を描いた作品ですが、どちらもむしろたわいのない日常や毎日の生活について改めて考えさせられる普遍的な問いを持った作品です。比べてみるとまた違った味わいを楽しめるかも知れません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
