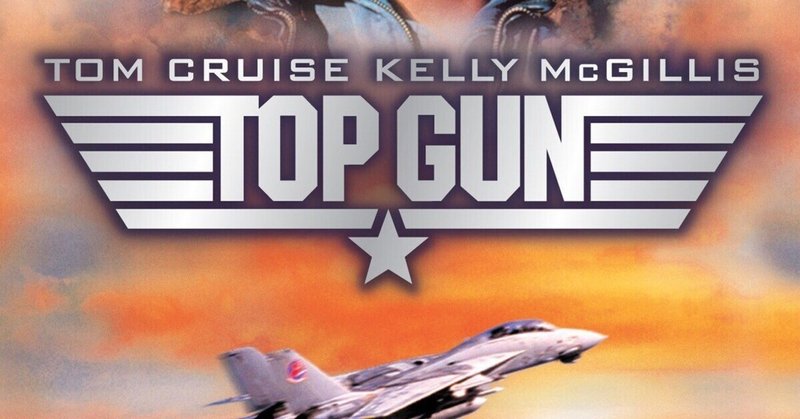
初代『トップガン』 映画をつくるのは誰?
パリでもロングラン公開中の『トップガン マーヴェリック』。
戦争をかっこよく描く作品は好んで見ないため、流行っているなあと横目で眺めつつなかなか食指が動きませんでした。
が、本作公開によって海軍への入隊希望者が殺到したという噂を耳にし、試しに初代『トップガン』を見てみることにしました。
というのも、今まで戦争映画とは戦争に反対するための有効な手段だとしか考えていなかったのです。むしろ、軍隊のPRやリクルートとして非常に有効な手段なのだと初めて気がつき、自分の視野の狭さを痛感しました。
軍隊ものの映画を見ることで、実際に軍に入隊するというのが現実的なひとつの選択肢になると言うことに、これまで考えが及んでいませんでした。
映画製作と米軍の関係が気になり、『トップガン』の製作と国防総省の関係について調べていると、ワシントンポスト紙のこちらの記事を見つけました。とても興味深い記事です。
‘Top Gun,’ brought to you by the U.S. military
The Washington Post 2022/5/27 By Theo Zenou
https://www.washingtonpost.com/history/2022/05/27/top-gun-maverick-us-military/
記事によると、『トップガン』は米軍から破格値での機材とパイロットの提供など非常に好意的な協力を得たおかげで製作することができたこと、また協力を得る代わりに国防総省(DOD : the Department of Defense)には映画のプロットを確認し修正を求める権利があったことが分かります。
『トップガン』は本国において興行的に大成功を収めただけでなく、本作の公開を機に海軍航空隊への志願者数は500%も増大したのだとか。
DOD Entertainment Mediaは新兵募集係とは連携していないと断りつつも、DODのロバート氏は「『トップガン マーヴェリック』が新世代のアメリカ人を鼓舞するものであってほしい」と語っているのも非常に興味深く感じます。
新世代のアメリカ人を"inspire"するとは果たしてどのような方向に向けてなのでしょう。
また1990年にトム・クルーズ自身がプレイボーイ紙に「中には『トップガン』が海軍を宣伝するための右翼映画だという人もいましたし、多くの子どもたちがこの映画の虜になりました。でも僕は子どもたちにこれは現実の戦争ではないと知ってもらいたいのです。だからこそ、『トップガン2』や3、4、5をつくろうとはしなかったのです。そんなことをしてしまったら無責任になっていたでしょう」と語ったと引用されています。
ではどうして新作を作るに至ったのか、また新作は戦争についてどのような描き方をしているのか、俄然気になってきます。
今まで映画を見るとき、映画とは監督や脚本家だけでなく、出資者や協力者、後援機関、プロデューサーの意図を如実に反映し作られているものなのだという視点に欠けていたと気づかされました。
画面に映っているものにしか注目していませんでしたが、その映画がつくられるプロセスや背景についてももっと注意を払うようになれば、また違った視点から作品を解釈することができるのでしょう。
映画に限らずテレビでも新聞でも、自分が目にするものの裏側には製作者の意図があり、見る側は良くも悪くも影響を受けるものです。そのことを頭の隅に置いて時に一歩引いて観察することは、プロパガンダに簡単に洗脳されてしまわない批判的な精神を鍛える一助になるのではないかと改めて思いました。

※ここから初代『トップガン』のネタバレがあります。
さて、初代『トップガン』。
若々しいトム・クルーズのヘラヘラっとした笑顔と歌の下手さがめちゃくちゃかわいい!だけでなく確かに面白い物語で、みんなで楽しめる金曜ロードショー的な作品でした。
印象的だったのは教官たちの優しさ。
軍の訓練というと『フルメタルジャケット』のイメージがありましたが、『トップガン』ではシゴキなど一切ありません。ミスをすると上官は理解を示し休息をとるように勧めてくれます。
どちらが現実の軍隊生活に近いのかは分かりませんが、『フルメタルジャケット』を見たら絶対に入隊したくなくなるけれど、『トップガン』を見たら危険なミッションを乗り越えながら育まれる男たちの熱い友情に憧れを抱くかも知れません。
さらに上手いなと思ったのが敵の国名が不明かつ敵兵の表情は絶対に見えないところ。
トム・クルーズ一行は操縦中ニックネームの書かれたヘルメットを被り、マスクをしていても顔が判別できるように撮影されているのですが、敵兵の顔は常に黒いマスクで覆われていて人間味がありません。
敵を記号化することで、人を殺しているのだと思わせない。想像力が奪われるお陰で敵機を撃ち落とした時に歓声をあげることができるのです。
逆に言えば敵の顔や表情、苦しむ叫び声などが聞こえてしまったら殺せなくなってしまうのでしょう。劇中、仲間を失う苦しさは語られても、敵を殺す葛藤は描かれません。
たとえ国のため防衛のためであっても、人が人を殺すというのは尋常でないことなのだと改めて思い知らされます。
最後に、超優秀なパイロットであるマーベリックが教官になることを望むのも、海軍航空隊の物語でありながら戦場をイメージさせないアイロニックな終わり方であり、だからこそたくさんの人が入隊したくなるお手本のような作品なのだと感じました。
子どもの時にこの作品を見ていたら軍隊や戦争について想起することなく軍隊に入ってパイロットになりたい!と思っていたかも知れません。
『トップガン』を見終えたら、ぜひシドニー・ルメット監督の『未知への飛行』も見てほしいです。
全く異なる作品ではありますが、『トップガン』が米軍から圧倒的な協力を得て製作された作品である一方、『未知への飛行』は米軍からの協力が一切得られなかった作品です。そのため爆撃機を映すシーンでは、隠し撮りした一機の映像を編集して使用したのだとか。
米軍が協力したい作品と協力したくない作品、2作に込められたメッセージを比べてみると、また違った視点を得ることができるかも知れません。
『トップガン』とは異なり、『未知への飛行』は一人の命と大勢の命どちらを守るべきかと言う究極の命題や、機械による管理システムの是非、非常事態のプロトコルによる致命傷、核兵器の恐ろしさなど様々なことを否応なく考えさせる示唆に富んだ名作です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
