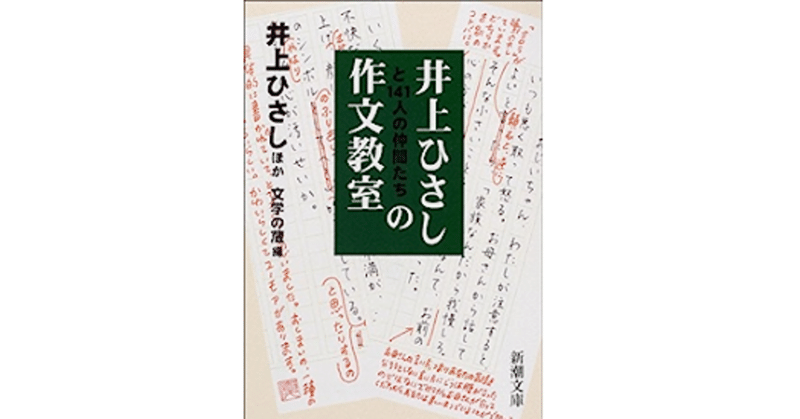
井上ひさしと141人の仲間たちの作文教室
作文は前置きをバッサリ削って、いきなり核心から入ることが大切。
『井上ひさしと141人の仲間たちの作文教室』を読んでいて、ギクっとしました。
noteを書くとき、だらだらっと意味のない文章を重ねてお茶を濁して書き初めがちです。これはよくありません。
本書曰く、書き出しの良い例は川端康成の『雪国』。『雪国』が素晴らしいのはトンネルを抜けてしまったところから書き始めたところなのだと、井上ひさしさんの解説は明快です。
トンネルに入る前の景色を描写して、長い長いトンネルの中で考え事をして、いよいよトンネルを抜けると雪国だった、ではあまりに蛇足になってしまうでしょう。なるほどなあ。井上ひさしさんは説明が上手です。
『井上ひさしと141人の仲間たちの作文教室』は、井上ひさしさんが岩手県で行った作文教室講座を一冊の本にまとめたものです。
作文を書く上で大切なポイントがすいすい頭に入ってきます。
書き方の技法やマナーを教えるだけでもなく、精神論だけでもない。読みやすいながらも読み応えのある、とてもバランスの良い書き方講座です。
方言に対する受講者の質問があると、井上ひさしさんの返答は、言葉についての話に留まりません。
自分で選んで決めること、話す言葉に責任を持つこと、他人から押し付けられた言葉を話すのではないこと。どんな言葉を話すかは、つまり良いか悪いかは自分で決めることだ、という大切な教えを柔らかな言葉で語ります。
日本語の成り立ちから、日本人の精神や文化の成り立ちを想像したり、戦争には大いに反対します。
これはただの作文教室ではありません。作者の思想が大いに反映されているところが好きです。
イギリスでノイローゼになった夏目漱石の逸話から、文章を書くには”自己本位”であることが大切と語るのも、抜群にうまい。決して自己満足でもなく、自分本位でもなく、"自己本位"とは自分に集中するということ。
自分を見つめて、自分を研究して、自分がいったいどういう人間なのか、考える。自分が中心に立って生きているその世界に、もう一度、自分を位置づける。
自分がどこに立っているのか、把握する。そこから新たに世界を自分の目で見つ直すのです。
これは文章を書く人にも書かない人にも大切なことではないでしょうか。
書くということは、ただ文字を綴ることでは終わりません。
書くことで考え、考えることで書く。一歩づつ確かに進んで自分で判断を下す。
書くことが生活することに、考えることが生きることに波及していきます。
言葉の力について改めて実感させられる一冊でした。
わたしたちは文章を綴ることで、言葉の力を自分の中に取り込むことができるのです。それってもしかして、とんでもない可能性を秘めた凄いことかもしれません。
井上ひさしさんの小説『東京セブンローズ』もおすすめです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
