
【5/15 4時半 窒素固定菌について一部追記済み】固定種、在来種野菜🍆の自然栽培は、ほかの栽培と少し違ったコツが要ります。水やり、管理など。自然栽培では好気性の微生物が大切なので、水のやりすぎ=窒息に。
「施肥」する通常の栽培と、「無施肥(低施肥)」栽培の夏場の水やりの違い
慣行栽培の屋上菜園の水やり
わたしは以前、慣行栽培(化成肥料の栽培)の屋上菜園にいたのですが、そこで一緒に働いていた農業学校の先生から、夏場の水やりの方法をしっかり教わったことがあります。
ホースで畝間になみなみの水をやる。ぶくぶく水が溢れるまでやっておく。それで、利用者のみなさん栽培は問題なくうまくいっていました。
今の農園で、自然栽培、無施肥、低施肥でやっている方には、その方法はあまり合っていなかったりします。
ちなみに、屋上菜園では、栽培の30cm層の下(底)に発泡スチロールを敷き詰めていて、その上に黒土が入っています。(この黒土、愛川町などの畑から運ばれていると、たむそん自然農園の農園長 吾郎さんから教わりました。これはこれで複雑な問題なのです。)
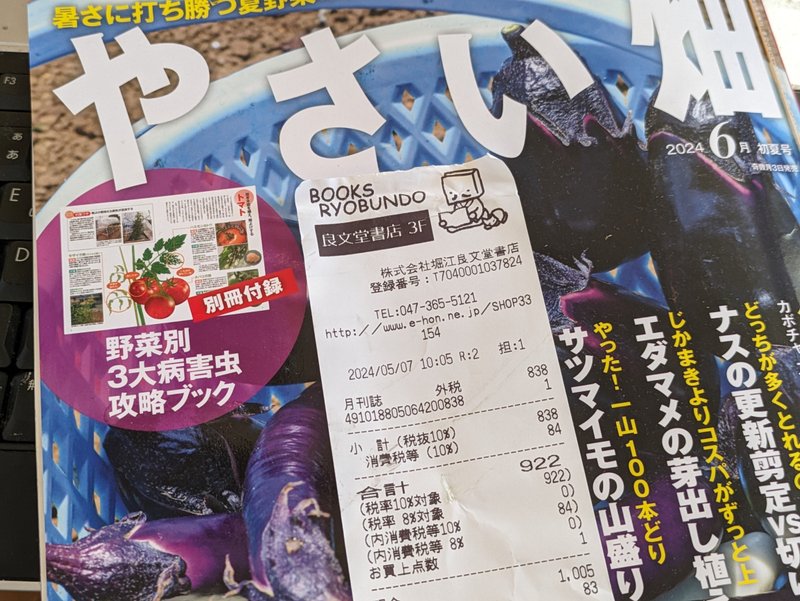

今の農園の水やり
無施肥(低施肥)の場合、水やりは「微生物のため」という考え方をします。(無施肥×在来種、固定種の栽培で、いちばん勉強になるのは、わたしの場合は関野幸生さんの本でした。この方の本を読んだり、実践したりしながら学びました。)
無施肥(低施肥)自然栽培=微生物の分解(※情報追記)
(関野さんの本で学んだのは、野菜の根のまわりには、根から出る蜜や酸などの有機物を目当てに20種類以上の微生物(細菌)が集まっている。その微生物が空中の窒素を固定しているということです。根粒菌以外にそれだけいるというのです。農学博士の木嶋利男先生も、未確認の窒素固定菌は無限にいるとおっしゃっていました。)による栽培なので、水を多く与えすぎてはいけない、野菜の根を冷やしてはいけないということです。
水を与えると土のなかの酸素が一気に減ります。すると、「好気性微生物」が活発に活動できません。なので、畝が乾いている状態を維持することが最優先ということです。夜、土に水を含ませていると野菜の根が冷えるのもよくない状態とされます。
屋上菜園のときには、夏場の水やり(特に午前10時以降~夕方前くらい)はとにかくたっぷり、なみなみやらねばならないという教えでした。
ジョウロなどでちょっとだけ(表面が濡れる程度)与えると水分が一気に蒸発して根傷みを起こすと。熱を持っている土に染みるとお湯のような状態になるので根が焼けるという内容を利用者さんに共有していました。
つづきはまた追記します。
