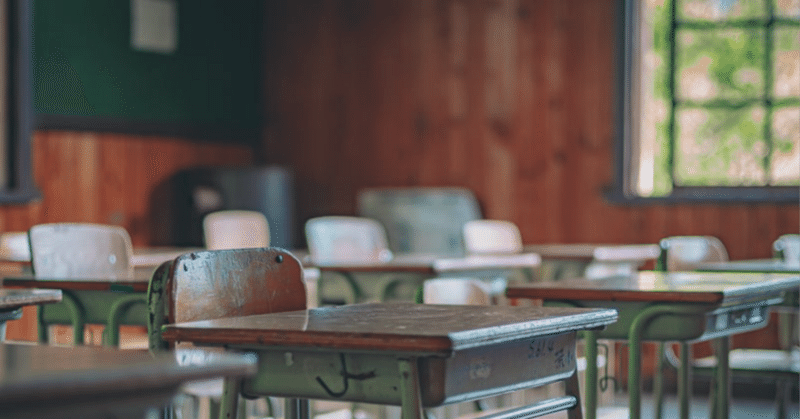
斜線の通知表
先生が伏目がちに手渡してきた通知表には、縦にずらりと並んだ斜線が記されていた。金縛りにでもあったのだろうわたしはそこから目が離せなくなって、けれどもこんな通知表もあるんだなあと、どこか他人の成績を見せられているようでもあった。
来月から息子は小学生になるという3月の日に、期待よりもこれから飛び込む学校生活に浮足立っていた。「大丈夫、なんとかなるよ」そう誰かに言ってほしい心とは裏腹に、恐らくこの子は支援から漏れやすい子でしょうから小さな変化も見逃さないようにねお母さん、と釘を刺された。学校生活に向かない子かもしれないと支援員の人に言われては、学校を出たあとの人生の方がずっと長いのだからムリをさせることのないようにと諭されていた。
小学校にあがった息子はというと、自分の身に降りかかった環境の変化についていけずにとにかくよく荒れた。えんぴつがダイニングテーブルの上を転がってそのまま床に落ちたときには、何で落ちたんだ!とえんぴつに向かって憤慨していたんだから、怒る理由なんてどれでもよかったんだろう。この子は不安の強い子だねと四方から言われていたのにも頷ける。自分ではどうにもできない苛立ちに、小さな体で精一杯の抵抗をしているようだった。
支援学級の先生と初めて面談したのは7月の終わりで、毛穴から湧き出る汗を拭きながら支援計画書の文字を追った。入学してからわずか3ヶ月半程の時間で、担任の先生は息子という人間のほぼ全てを把握して次の2学期と、来学年までの道すじを立てていた。さらに二回目の面談のときには息子の3年後の未来を想定して話されていたんだから、尊敬しない理由なんてなかった。
その先生は息子の学習進捗から生活、社会性に至るまで短期目標、中長期目標を提示してくれた。学校としてはこう進めていきたいのだけど家庭の考えはどうでしょうと尋ねてきて、同じ方向を歩けるように共有しようと努めてくれた。気になることがあれば小さなことでも言ってきて欲しいと声をかけてもらえたことで、それまで背負い込んでいた荷もいくらか軽くなったような気がする。一人で抱え込まなくてもいいんですよ、学校と家庭が連携しないと良い支援はできないんですから。向けられた一つ一つの優しさを噛み締めていた。あんなに暴れていた息子だったのに、夏休み明けには憑き物が落ちたように大人しくなっていた。
「私達はプロですから、信じてついてきて欲しい」
そのプロポーズのようなセリフに、これまで積み上げてきた支援を小学校は繋いでくれるだろうか、難しいんじゃないかと、入学前に不安になっていたあれもこれもが嘘のように消えていった。
3年生に進級すると、担任だったその先生は他校へと異動した。そして息子は登校を拒否するようになった。
「学校行きたくない」
聞き間違いならどんなに良かったことだろう。それまでどんなに気分が落ち込んだ日でも、登校を渋るなんてこと一度もなかったのに。
それからは学校との話合いの場を幾度か持ったけれど、どうやっても埒が明かなかった。支援級の子だからこそ尻を叩いてやらないといけない、社会は厳しいのだから今のうちに教えてやらないといけない。そんな意図があったんだか、なかったんだか。それ以上に危ぶんだのは、これまで積み上げてきた療育の努力が、土足で踏みにじられて泡となっていくようで許せなかった。
支援と怒ることを同等に扱っている人の前では、言葉を尽くしても根本の理解には及ばなくて、だったらベタ褒め作戦からの宜しくこうしてと伝えてみるも砕け散った。療育の考えを知らない人に、療育で培ったものを話してみても共感は得られないんだと知った。わたしは成す術なく途方に暮れていた。そうやってなんにも解決しないままに、今度は一年生の他害は我慢してあげなさいだとか、環境設定は充分にやってると言い張るけれども声かけはしていなかったりだとか、学校の門を出たら校内で起こった癇癪も全て家庭の責任なんだとか、では何があったのかと聞くと楽しくやっていたはずだと言うばかりでその申し送りはしてくれないだとか、気まぐれに変わるルールに子供は不安になっていたりだとか、親がしっかりしないからダメなんだとか。どれもこれもが正面から飛び蹴りしてもいいかしらと思うほどに胸糞が悪かった。
「先生に質問したら違う先生に聞いてって言われた」
自分の感情で子供を振り回す傍若無人っぷりもここまできたかと。付き添い下校から帰宅すると息子の体をチェックして異変がないか調べていたんだから、狂ってるとしか言いようがなかった。先生は『支援』を知らなすぎた。もう息子を休ませるしか方法がなくなって、欠席は2週間のときもあれば3日のときもあったし、1ヶ月を超えることもあった。
「先生」が信じられない。
だから息子が中学に入ってもわたしにとって「学校の先生」とはそういう人で、社会に出たときに本人が困るから指導と称して叱るという、それしか指導方法がない先生に出会ったときにも「またか」という思いでいた。
やればできるのに家庭の指導が足りていないからだと言われたときは、さすがに全身のムダ毛が逆立ってはらわたが煮えくり返った。けれどもどこか妙に冷静でいて、一旦は頭を下げながらも「では学校ではどのように指導されているのか具体的に知りたい」と、学校と家庭で同じ対応にしたいと申し出たら相手は口を閉ざした。
怒りに任せて叱っても、子供には恐怖心しか与えない。白黒思考の息子では相手を敵か味方かで判断するから、叱られたあとに残るのは「あの先生は自分を攻撃してくる敵」と思わせるだけなのに。子供のためと言う人もいたけれど「あの時先生は僕のために叱ってくれた」と先生が怒った背景を知ろうと思い起こして感謝することはまずない。怒られたことが事の全てで、それ以上でも以下でもない。叱ってくれてありがとうと息子が感動する日など、一生やってこない。
叱る代わりに正しい行動を教えてもらえないかと言ってはみたが、自分の決めた指導の範囲から出られないのか怒っていないと生きられないのか、答えはいくら待っても返ってこなかった。
「言えば分かる子やればできる子」と思われてしまう息子のそれは、知能検査WISCの数値にもよく表れていた。そのために困っているのに分かりにくく、悲しいかな放置されやすくて、だから気付かれにくかった。小学校入学前に言われた「支援から漏れやすい子」とは、そういうことなんだろう。指摘されていた通り、息子は支援に漏れやすく外されやすく努力が足りない子とみなされやすく、そして潰れやすかった。
発達障害は「見えない障害」と言われるけれど、よくできた表現だと思う。まったくもってその通りだと思うので。
支援学級に在籍していてもなお理解されない障害に抗わないといけないなんて、なかなかにやるせない。親のわたしが思うんだから、息子本人はもっとやり切れないでいるんだろう。けれどもあなたのつらさは知っているよなんて言ったら、軽く聞こえてしまうんだろうか。
尊敬してやまない先生もいるのに一体どうして、何故伝わらない。自分の通知表に溜息を吐く横顔に胸がつまる。ほんとうは学校へ行きたかったのに行けなかった息子の斜線の通知表は、学校と家庭が歩み寄れなかった姿を映し出しているようで、少しだけ泣いた。
スキしてもらえると嬉しくてスキップする人です。サポートしてもいいかなと思ってくれたら有頂天になります。励みになります。ありがとうございます!
