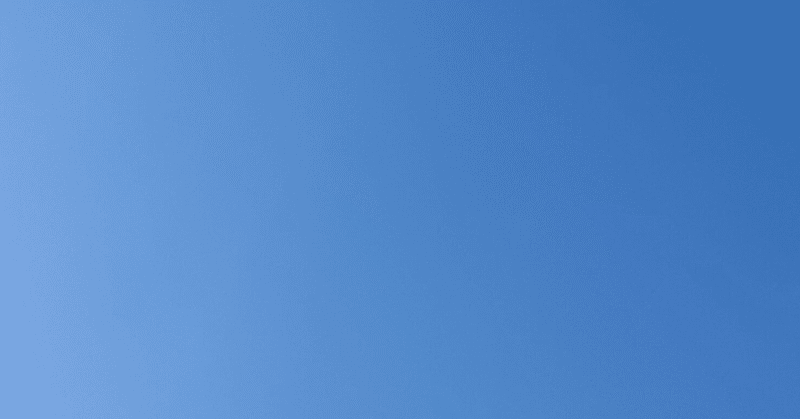
andymoriは若者とともにある
andymoriが話題になっている。
そんな日がまた来るとは。彼らが活動を止めてから10年が経つ。
その月日の速さに目が回りそうになる。
andymori「すごい速さ」
1分47秒という短めの曲。
andymoriらしさは間違いなく凝縮されていて、あっという間に過ぎ去っていく時間、夏、人生と響きあう。
きっと世界の終わりもこんな風に
味気ない感じなんだろうな
あのバンドの新譜と牛乳を買いに
部屋をでたけれど
この感覚がわかる気がする。
ドラマや映画で世界が終わるとき、隕石や宇宙人や地殻変動やウイルスやらすごいことが起きて、世界が大騒ぎして、壮大な音楽が流れてというイメージだけど。
実際は突然壊れた電化製品みたいに、プツンと何かが切れて終わり。そしてそれが終わりだったことにほとんどだれも気づかないみたいな。味気ない感じなのかもしれない。学校で何気なく「バイバイ」って言ったあの瞬間が関係の完全な終わりだったのかとか、こんなにあっけなく恋が終わるんだって思ったこととか。
実際の終わりには、実感は伴わなくて。でもかなり冷徹で、取り消しを認めない強固さで終わってしまう。
くだらないTV消して
はじまりのおわりのはじまりのおわりの話をする
チャーチルの名言に「今は終わりではない。これは終わりの始まりですらない。しかしあるいは、始まりの終わりかもしれない。」というものがある。元の英語は”It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning.”らしい。
この「はじまりのおわり」という言葉は、映画の作品でもよく引用されている。パッと思い浮かぶのが、「キングスマン」のゴールデンサークルでのセリフ、邦画では三谷幸喜の「ラヂオの時間」だ。
「はじまり」と「おわり」ですべてを見てしまうが、時の流れはもっと壮大で「はじまり」にも「はじまりとおわり」がある。ので、「はじまりのはじまり」があれば、「はじまりのおわり」がある。
この歌詞は「はじまりのおわりのはじまり」がおわる話をする、ということだろう。
そういえば映画キッズ・リターンにも「俺たちもう終わっちゃったのかな」「まだ始まっちゃいねえよ」というセリフがある。
青春は人生のはじまりで、青春の終わりは「はじまりのおわり」だ。思ったより人生は、いろんな場面や関係ではじまりがありおわりがある。おわりから振り返ってみると、いつもそれは『すごい速さ』だったのだ。
そのセンチメンタルはいつか
お前の身を滅ぼすのかもしれないよ
自分のことを言われているかのように刺さる。
自分はセンチメンタルに心を浸すことで癒されてきた。
センチメンタルは感傷的とも言い換えられる。傷つきやすい弱く繊細な自分の心を、感情に酔うようにして紛らわしてきた。
自分の場合、映画・音楽・読書・詩作が、センチメンタルと結びついて青春時代のこころを支えてくれていた。
薬が用量によって毒にもなるように。
「そのセンチメンタルはこの身を滅ぼすかもしれない。」
そういう危うさを感じながら、日々に疲れ果て心をすり減らしながら、この曲を聴いていた。
ボーカルの小山田さんのandymori解散前の出来事への、何か予言めいたものを感じないでもない。この歌詞は聞き手に言っているようで、歌い手自身のことを言っていたのかもしれない。
感傷中毒の患者 禁断症状 映画館へ走る
でもなんかやれそうな気がする
なんかやらなきゃって思う
だってなんかやらなきゃできるさ
どうしようもないこのからだ何処へ行くのか
感傷中毒という言葉にもドキリとするが、とてもよくわかる。感傷は癖になるし。禁断症状も出る。
手っ取り早く感傷を摂取できるのは映画だ。2・3時間で登場人物に感情移入して、カタルシスを感じて、役者の演技やBGMで劇的に心が浄化される。
何かやりきったようなスッキリした気持ちになる。自分もやるぞという気持ちだけを抱えて、あまり何も変わらない日常に戻る。
「すごい速さで夏は過ぎたが」のあとに「ラララララララ」で濁されている部分は、結局何も起こらなかったという虚しさなのかもしれない。ただ胸騒ぎがするだけで、何も起こらず何も変わらないまま時間だけが過ぎてしまった。少なくとも自分はそうだった。
andymori「16」
実は一番いいなと思うのはこの曲。
16のリズムで空を行く
というのが、サビの歌詞で繰り返し出てくる。
自分はどうしても啄木のこの短歌を連想する。
不来方のお城の草に寝ころびて
空に吸われし
十五の心
16のリズムというのは、8ビートや16ビートといったリズムのことを言っているのはわかるのだが、「16のリズムで空を行く」と「空に吸われし十五の心」は似ている気がするし、ここが自分がハマった要因の一つだと思う。どちらも十代の行き場のない気持ちの行く先を空に求めているのだ。
駅の改札を出たり入ったり
変れない明日を許しながら
なんとなく嘘をつくのさ
(略)
可愛くなれない性格で
全然違うことを考えながら
優しんだねって嘘をつくのさ
(略)
昔の誰かに電話して
もらった花をまた枯らしながら
今度呑もうねと嘘をつくのさ
この辺も日常と人間関係の虚しさを上手くすくい上げている。毎日同じことを繰り返し、会話も集中して聞くことができず他のことを考えてしまう。
何でもない日々も、人間関係もあまり積み重なっていかない。
すぐに枯れてしまう花束も、社交辞令の約束も、空洞だらけでうつろな日々を象徴している。
空がこんなに青すぎると
なにもかも捨ててしまいたくなる
空がこんなに青すぎると
このまま眠ってしまいたい
この部分の歌詞は、谷川俊太郎の詩を思い出させる。
かなしみ
あの青い空の波の音が聞えるあたりに
何かとんでもないおとし物を
僕はしてきてしまったらしい
透明な過去の駅で
遺失物係の前に立ったら
僕は余計に悲しくなってしまった
この谷川俊太郎の詩とandymoriの歌が響きあって、
「16のリズムで空を行く」先に波の音が聞こえる気がするし、
「改札を出たり入ったり」する駅で
「何かとんでもないおとし物」をしてしまった気もする。
でも「かなしみ」と嘘に埋もれて、
心のほとんどは空に吸われてしまっているのだ。
andymori「FOLLOW ME」
歌詞のことをあれこれ書いてきたけれど、彼らの魅力はこの疾走感だ。
アルバムをはじめて聞いた時の、いきなり全速力で駆け抜けていくドラムの衝撃が今でも心に焼き付いている。
wikiによるとandymoriの名前の由来は「アンディ・ウォーホルと『メメント・モリ』(藤原新也によるインドの写真集)」らしい。
音楽はもちろん、美術や映画、小説などの文芸などの要素が歌詞に散りばめられている歌も多い。
「CITY LIGHTS」の歌詞に出てくる「名前なんかない猫」は漱石のあの作品を思わせるし、曲名はチャップリンの映画「街の灯」からかもしれない。
andymori 「1984」
「1984」という歌でも、曲名はジョージ・オーウェルの小説を思わせるし、1984年は小山田壮平・藤原寛の生まれた年でもある。
1984 花に囲まれて生まれた
(略)
1984 裸で泣いてた君は
サビのこの2つの歌詞は、自身の誕生のことを歌っているのかもしれない。
この曲の底流にはセンチメンタルがあるし、ふるさとを思い出すときのような懐かしさがある。
「5限が終わる」「椅子取りゲームへの手続き(=受験?)」「公園」「自転車」「5時のサイレン」「6時の一番星」あたりは全部幼少期の思い出を感じさせるフレーズだ。
繰り返し出てくる「ファンファーレ」と「熱狂」は1984年に開催されたロサンゼルス五輪のオリンピック・ファンファーレのことだと思う。
『スター・ウォーズ』『E.T.』『インディ・ジョーンズ』『ホーム・アローン』『ジョーズ』『ジュラシック・パーク』『ハリー・ポッター』など数々の映画音楽で知られるジョン・ウィリアムズが作曲していることでも有名なこの曲のことだ。
andymori「愛してやまない音楽を」
最後は僕のandymoriの思い出。
自分はandymoriの関西最後のライブに運よく参加することができた。
ワンマンではなく室内フェスだったのだけど、とても熱く盛り上がった。
客席のみんなとこの曲を合唱した夜を、今でもたまに思い出す。
愛してやまない音楽をどこまでも鳴らそうぜ兄弟
andymoriは自分の青春の大きな一部だ。
解散してから何年経っても、andymoriが若者とともにあることがファンの一人としてとても誇らしい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
