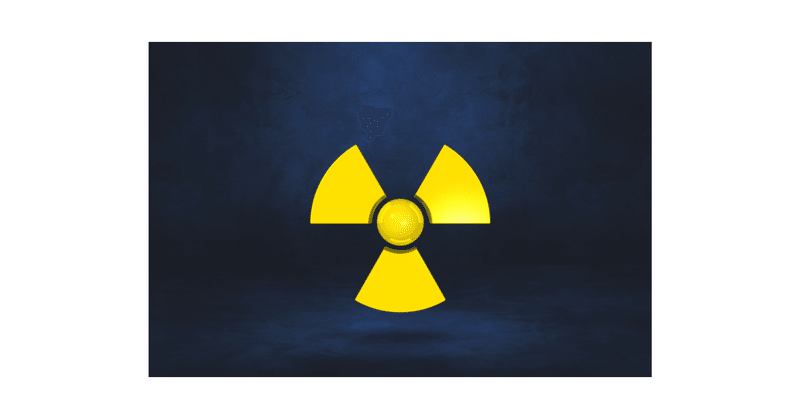
2017年 98冊目『放射能に克つ農の営み』
先日福島県の棚田で稲刈りをした際に知り合った長谷川浩さんの本です。
長谷川さんは、日本有機農業学会副会長で福島県有機農業ネットワーク理事を務められています。
偉い方のはずなのですが、まったく偉ぶるところがなく、フラットなコミュニケーションをされる素敵な方です。
ご自身で豚も飼われていて、今度つぶす際に、分けていただくことになっています。
これも楽しみです。
長谷川さんが著者なのですが、様々な方が寄稿されています。
同じく稲刈りで知り合った福島県有機農業ネットワーク理事の浅見彰宏さんや私がフランス大好きになったきっかけを作ってくれた友人の阿部直実さんも寄稿されています。
個人的には、知っている方の文章はさらに興味深く読めますね。
この本には、福島第一原発が放射能をまき散らして、数か月後から1年後くらいの様々な立場の方々の意見が載っています。
農家、生活者、大学関係、専門家、農産物販売者などなどです。
その時の葛藤、努力、成果、落胆などが等身大で伝わってきます。
いくつも興味深い話が載っていたのですが、最大のものは放射能がどうやれば農作物に含まれなくなるのかというところです。
素人なもので、土の表面を削って除けばよいと思っていました。
もちろん、物理的に除くわけですから、効果があります。
しかし、その土をどこかに保管しなければいけません。
しかも、表面の土地を削ると農業ができなくなる可能性も高いのです。
なかなか悩ましい話です。
ところが、他にも方法があったのです。。
土自身が放射能を吸着するのです。
福島の土地の性質が、この吸着を行うのです。
しかも、この吸着は安定化しているので、根から農産物に行かないのです。
農業により、土を撹拌することがの吸着を促進します。
この吸着により、国の想定の10分の1以下になったそうです。
目から鱗でした。
この効果のおかげで、被害の1年後の農作物でも、驚くほど放射能レベルが低い(測定できないレベル)のものもあったそうです。
それも、場所によっては、大半が低レベルのところもありました。
もちろん、高いレベルのものもありました。あるいは、農作物の種類によっては高いものもありました。
例えば、キノコ類などは高い数値のものが多かったのです。
現場では、自分たちで放射能を測定していたので、これらを把握していました。
そのメッシュや頻度も国や県の実施よりも細やかなものです。
その動機は、販売できるかを知りたいだけではなく、自分たちの農作物を孫に食べさせて良いのか知りたかったのです。
当然、細やかになりますよね。
国は決して、これらの情報を上手に活用できなかったようです。
残念です。
現場の実際の人たちの話が伝わってきます。
この話の現在が知りたくなる本です。
お薦めです。
▼前回のブックレビューです。
▼新著『業績を最大化させる 現場が動くマネジメント』です。
よかったら、手に取ってみてください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
