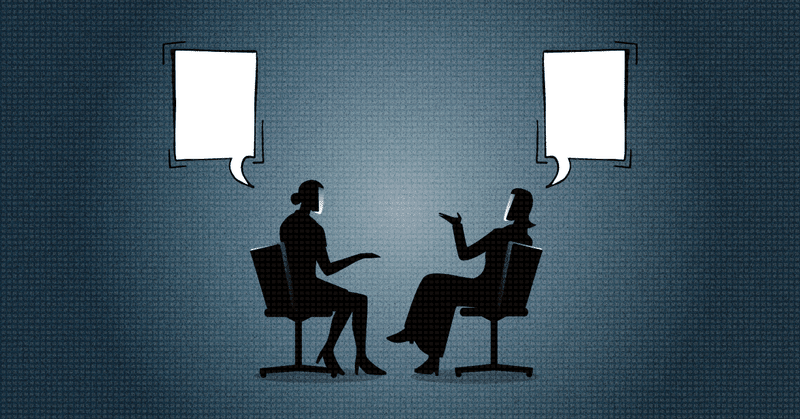
2016年89冊目『人材覚醒経済』
慶応大学の教授で経済産業省や内閣府で雇用問題改革をリードされている
鶴光太郎さんの著書です。
働き方改革の全体像が理解でき、この分野に興味がある方は必読の1冊です。
ドッグイヤーをつけたところを備忘録的にメモしておきます。
この本は、ワークス研究所の仲間の久米さんがデータ分析等でサポートしています。
・日本的雇用システムの3つの事実は相互補完関係にある
「長期(無期)雇用」「後払い賃金」「遅い昇進」
・日本の正社員の「無限定性」とは何か
「勤務地」「職務」「労働時間」が限定されていない。→転勤、異動を受入れる義務がある。
・無限定性正社員というレンズから見た日本の雇用システム
「メンバーシップ性」「企業別労働組合」「後払い賃金」「遅い昇進」「頻繁な配置転換」「水平的なコーディネーション」「解雇ルール」「家族システム:男性が働き、女性が家を守る、家族給も支払う」
・企業から見た無限定正社員のメリット
「内部労働市場(社内)の柔軟性」「企業の特殊能力への投資」「部門間情報共有→すり合わせ→改善型イノベーション」
・労働者から見た無限定正社員のメリット
「雇用保障」「配置転換による仕事の幅」「未熟練な若年層を採用して、教育してくれる」
・90年代以降の環境変化に対応できず、無限定正社員システムが生み出した雇用問題
「有期雇用の大幅増加」「ワークライフバランスが進まない事」「女性の労働参加への阻害」
・ジョブ型正社員をデフォルトにする働き方改革
「ジョブ型正社員:職務、勤務地、労働時間いずれかが限定された正社員」
「ジョブ型正社員は、無限定正社員と比較すると、労働時間が短く、所得は少し低く、満足度は高く、ストレスは低い」
「ICTで働く場所の制約を外し、生産性を向上させられる」
「異質性、多様性は、欧米では、イノベーションにプラス、マイナス両方の研究結果がある→コストとベネフィット両方があると解釈すると良い」
「多様な組織を束ねるには、ミッション志向型雇用システムが有効」
・女性の活躍を阻む壁
「マミートラックに乗ると戻れない。職場、自宅、保育園の三角形を小さくすると良い」
「3歳未満の子供を持つ親に対する育児サービスの公的支援は女性の労働参加にプラス」
「育休期間延長は影響を与えない」
「子供が1歳まで育児休暇を取る人は将来所得が最大2-3割減少する。育児休暇を取らない人は不利にならない」
「オランダは女性のフルタイム就業が高いが、フルタイムとパートタイムを同一企業で変更できる事が貢献」
「ワークライフバランスで、仕事を減らさず、人を増やさないと、しわ寄せをうける人がいる」
「日本の女性管理職比率12.3%は、軒並み30%を超える先進国と比較してかなり低い」
「女性役員比率の割当制は、企業の収益や価値を高めるとは限らない。阻害要因を丁寧に除去する事が必要」
「日本では、長時間と昇進は男性では有意でないが、女性では有意である」
「夫がジョブ型社員であると、夫の育児参画が高まる」
「妻の就業には日常的なサポートが有効。ベビーシッターのサポートの影響は小さい」
・労働時間
「日本の平均労働時間は下がっていて、イタリア、アメリカより短くなっている。」
「しかし、それは短時間労働者が増えたから」
「パートを除いた一般労働者では93年2045時間→15年2026時間とほぼ同じ」
「週49時間以上労働者は2割で、欧米諸国の1割台と差は依然多い」
「特に働き盛りの30代男性は16%が週60時間以上。ただし、04年は24%なので減少中」
「週当たりの労働時間は変化なく、週休2日になっているので、平日の労働時間は増えた」
「2万ドル/年・人あたりまで労働時間と相関があり、それ以降は関係性は明確でない」
「自発的長労働時間要因:中毒、残業代、出世、投資回収、プロ意識」
「非自発的長労働時間要因:市場の失敗、職務の不明確さ、ローテーション、雇用調整バッファー、周囲の影響」
「アメリカはお金で解決。欧州は時間規制。日本は中途半端」
「EUは11時間のインターバル規制。日本の一部企業も導入しているが、インターバルが短い」
「EUの一部の国では、労働時間貯金制度導入」
「モジュール型:業務の切り分け により労働時間短縮が可能」
・非正規労働者
「OECDでは、パートタイムかフルタイムか。有期契約か無期契約かで分類する事が通常」
「非正規労働者の割合増加は、企業の戦略レベルの問題が大半」
「2018年に有期→無期の変更(5年継続就業)が起きる」
「フランスでは、雇止め時に、支払給料の総額の10%が慰労金として支払われる」
「パートタイムとフルタイムはいろいろな条件を加味しても世界各国でフルタイムが高い。」
「しかし、オーストラリアはパートタイムが高いと言う研究結果もある」
「イギリスでは、同一企業で、同一職種でフルタイムとパートタイムが存在しない事が多い」
「日本では横断的な賃金体系が無いので、同一労働同一賃金、均等処遇のハードルは高い」
「期間比例(勤務年数の長さ)への配慮が重要」
「アメリカでは、(急激に)最低賃金を上げると若年未習熟者の就業に負の影響を及ぼす」
「日本では、最低賃金を10%上げると、下位所得の2.8-3.9%上がる。10代男女の就業率を5%強下げる」
「欧州では最低賃金を年齢別に設定している」
「最低賃金のスピードを穏やかにすると、負の影響は限定的になっている」
・入口、出口の整備
「新卒一括採用は無限定正社員と強い補完性がある」
「新卒一括採用は、低スキルの若年層を採用してくれるメリットがある。若年層の失業率は極めて低い」
「新卒一括採用のルートの多様化は望ましい」
「インターンシップを魅力的にし、キャリア教育時期を早めにすることが望ましい」
「日本の定年制は、法制度で定められている。年金支給時期の影響を受けている」
「定年後の雇用継続は、同一労働なのに給料が大幅に下がるので、おかしい」
「英語圏諸国では、年齢差別が許されないので定年制度がない」
「日本は高齢者の労働参加意欲が、欧米よりも著しく高い」
「定年廃止と言う劇薬も一つの妙案。60歳以降有期雇用のような形で70歳までの延長はリアリティが無い」
「日本は解雇しにくいと言うが、それは大企業の話で、中小企業は欧米よりも解雇しやすいと言う研究結果もある」
「日本は不当解雇は無効(地位回復)で、解決金を適用できない」
・オンラインジョブサーチの効果
「アメリカで、利用者は未利用者よりも失業期間が25%短い」
「賃貸住宅業界でも、不動産情報サイトは空き室率低下に寄与している」
・スキル教育
「非認知スキルの重要性」
「非認知(性格)スキルは5つに分解できる。開放性、まじめさ、外向性、協調性、精神的安定性」
「学歴や報酬、犯罪に影響を及ぼす性格スキル」
「真面目さは、IQの半分程度、仕事の成果と強い相関がある」
「真面目さは、仕事の複雑さと関係なく、より広範な仕事に有用である」
「どのような職を選ぼうと、真面目さは家庭や教育現場で身に着けさすべきである」
「所得に対して、男性は真面目さが、女性は、外向性や精神安定性が正の相関がある」
「教育年数に対して、日本では、協調性が正の相関があり、アメリカでは負の相関があった」
「日本での家庭の教育、うそをつかない、ルールを守る、親切にする、勉強をする、は所得に正の相関があった」
「日本では家の蔵書の数と子供の所得が高い。学生時代の無遅刻と学歴と初職の正社員比率に正の相関があった」
・社会保障制度改革
「困っていない高齢者を増やし、困っている現役世代をサポートする 事が重要」
「高齢者の就業促進のための健康確保、病気予防」
・2050年の働き方未来図
「日本の人口は1億人を切り、65歳以上が4割を占め、労働者人口6500→4400万人になっている」
「高齢者、女性、外国人など多様な人と働いているはず」
「無限定社員も一部残るが、大半はジョブ型社員になっている」
▼前回のブックレビューです。
▼新著『業績を最大化させる 現場が動くマネジメント』です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
