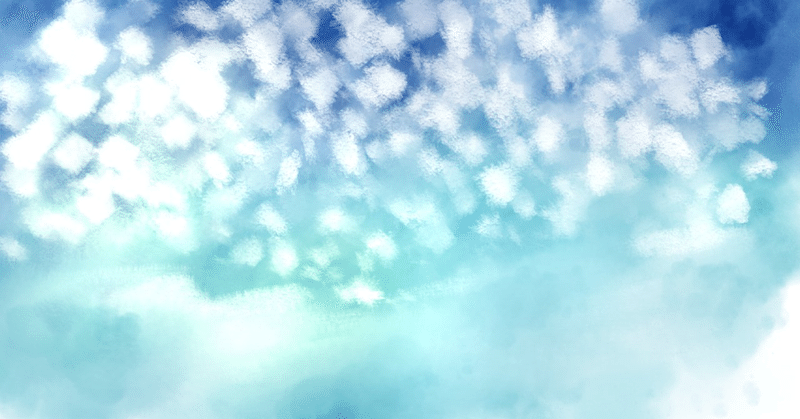
生きづらさを生きる子供たち
2023年5月6日にNHKで、「いじめから逃げない」という企画がありました。
大阪吹田市の小学校3年生のクラスでの4ヶ月の取り組みを、追ったものでした。
シンキングエラーについて考えを深める。
デスカッションをすることで、認識を統一して、自分の考えのまちがいに気づけるようにする。 そして子供にも先生にも一人で抱え込ませない。という主旨だったと、思います。
まず感じたのは途方もないなという感覚でした。
海外でもいじめ問題は深刻で、いじめられたことの影響は生涯に渡ることが多々あるので社会としても大きな損失です。
日本だけでなく少子化問題を抱えている国は少なくありません。
せっかく生まれてきた子供たちが、お互いをつぶしあってしまうのだったら、早い段階でお金をかけてでも、取り組むべき問題と認識されています。
子供や先生に一人で抱え込ませない。という点には、できることかなという共感がありました。
しかし最初からあきらめてはいけないのでしょうが、デスカッションをすることで、認識を統一するというのは、難しい気がしました。
むしろ多種多様な認識があることを、共有することの方が、現実的に思います。
先生には学業を教えるという本文もあるなか、凄い労力を必要とする上に、いじめを芽から摘み取るのは不可能なのではないかと、思いました。
人というのは集団の中にいれば、嫉妬だったり羨望だったり、感情の摩擦がおきるのは、自然の事だと思います。
そんな感情を自分の中でコントロールして、時には折り合いをつけて大人になっていくものだと思います。
それがエスカレートしてしまった時に、おかしいという認識を持って、対応できる傍観者を育てて、フォローする、体制を、確立できたらいいと思うのですが、どうでしょう。
いじめに対して過敏になりすぎても、おかしなことになります。
私の息子が通っていた高校は、息子が入学した前年度かなり子供たちが荒れて、問題も多発していたようで、先生方はピリピリしていました。
それこそ、小さな芽だって、見境なく摘み取るような勢いでした。
一つ、息子が先生のターゲットにされやすかったのは、悪いグループの一番後ろにくっついていたこと、そして、家が母子家庭だったことです。
たとえば、二人組で倒立かなんかしていて、ちょっとふざけて笑ってじゃれていたら、いじめだといわれて私まで呼び出されました。
言いがかりとしか言いようのないことで、再三学校に呼び出され、「今、本人から事情聴取している」というのです。ここは学校ですよね。警察ですか?と言いたくなります。
授業中の事ですから、その場で、「ふざけてるなよ」とでも注意したらいいじゃないですか。
また髪なんか染めたこともないし、地毛申請もしているのに毎回頭髪検査にひっかかるので、頭髪検査の前日は黒染めしていました。
カラスみたいに真っ黒なら文句ないだろうって。 いじめを抑圧しようとして、すべてを抑圧している気がしました。
私自身は社会人になって、しかも60を過ぎてから、陰湿で壮絶なハラスメントを経験しました。
そして、思うに暴走するいじめを止めるのは「傍観者の認識を変える」こと位しかできないと思いました。 安易に同調しない、冷静な目をもつ傍観者がいたら、加速しないのではないかと思うのです。
ちなみに息子が高校生の時といったら、18年位前のことなので、頭髪検査も進化いているだろうなと思っていたのですが、先日報道番組で、同じようなことを言っていて、何も変わってないのだなと思いました。
『僕が僕をやめる日』の衝撃
松村涼哉さんの小説です。
生きることに絶望した僕は自殺寸前で、彼に救われ、彼として生きることになった。
「死ぬくらいなら僕にならない」そこから物語は展開してゆきますが、想像を絶する展開でした。 この話にフィクションの部分があったとしても、私たちの知り得ないところに、こんな闇が、あることを思うと、切ない気持ちになります。
親の都合で戸籍を持たない子供。 障害もないのに障害手当の為に障害児認定させられる子供。 ネグレクトで餌を与えられるような食事を貪る子供。
児童売春をさせられる子供。 自分の手では変えることのできない状況のなかで逃げる力も持たない子供がいると思うと、大人として、辛いです。
『くるまの娘』宇佐見りんさんの小説です。
この作品は、繰り返されるDVがテーマです。
家族というのも、また世間から隠れたところで、人の目に触れないところです。一度あまりの騒ぎに、近所の人が通報して、警察がきますが、誰かを加害者にして、被害者づらもできないんです。
これを共依存というのかも知れないけど、 救うなら、家族まるごと救ってほしいといいます。
最後は殴る蹴るでしか、終わらないんです。
お兄ちゃんたちは愛想を尽かせて家を、でていくけど、高校生の彼女だけは捨てきれず、折り合いをつけていこうとします。
いつか解決する日が来るのでしょうか。
この2作品からは、無力さだけ感じました。 運命として受け入れていくにはあまりに過酷です。 でも少なからずそういう子もいるんです。
それから最近問題視されているヤングケアラーと子供を取り巻く問題は山積みです。
私の子供時代と違って、これだけ多種多様な環境に置かれている子供たちを、30人40人一つの箱に入れて、同調圧力の中で、教育する事自体が、もう破綻しているのかとも思います。
一億総中流化と言われた時代の価値観では、それぞれの思いにそう事は難しくなっているのでは、ないでしょうか。
そして、先日YouTubeのイマジン大学と言うチャンネルで、脳科学者の茂木健一郎先生が天才についてお話されていました。
ニュートンやイーロンマスクやアインシュタインのような、いわゆる天才といわれる人達は、幼少期に自閉症だったり、虐待されていたりと、必ずしも恵まれた環境で育ったわけではないようです。
そんな中、天才は共通してポジティブだそうです。
ネガティブ思考をポジティブ思考に変換できる人だそうです。
その資質と時代の出会いが、ごくまれに天才を生み出すようです。
そう考えると天才でなくても、ネガティブ思考をポジティブ思考に変換できたら、それだけで解決することも多々あると思います。
教育環境が時代に則して変わることも大事ですが、個々の乗り越える力を養うことも重要になりそうです。
世の中が急速にAI化していく中、身体を持つ私達人間の脳と身体のつながりのサイエンスは興味深いところです。
AIとの差別化と言う意味でも、そういうことを学ぶことで、俯瞰して見られることも増えるのではないかと思います。
風の時代のモノローグより
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

