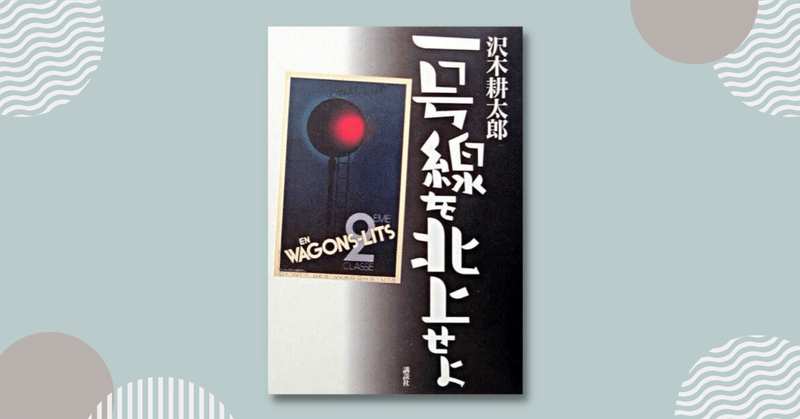
【書評】『一号線を北上せよ』沢木耕太郎(紀行文)
いきなり話が逸れるのだけれど、先日、沢木耕太郎さんの講演を聴く機会があった。
姫路で行われた「第25回司馬遼太郎メモリアル・デー」における講演で、タイトルは「紀行の方法―司馬遼太郎を中心として」というもの。
司馬遼太郎さんの『街道をゆく』を引き合いに出しつつの、ユーモア溢れるお話だった。
その中で、司馬遼太郎の紀行文のすごいところは、「ただ、今、旅をしている」ということだけで書くのではなく、
歴史の知識など、4つぐらいの層を縦横無尽に行き来しながら文章を書かれているところ、と話されていて、強く印象に残った。
そしてそれは、沢木耕太郎さんも、同じではないだろうか。
ただ、今、旅をしているだけでなく、思いを馳せる題材が心の中にたくさんあって、
だから文章が深く、重層的になるのだろう。
沢木耕太郎さんの紀行文と言えば、何と言っても『深夜特急』が挙がると思うし、いずれまたそちらについても書きたいのだけれど
今回は、もう少し読みやすい『一号線を北上せよ』を挙げたい。
こちらは短めの紀行文を幾つか集めたもので、どれか一つだけぱっと読んでも充分引き込まれる。
例えば「メコンの光」はホーチミンを旅する話。
とりわけ沢木さんが旅の最初の食事にフォーを注文する際の、地元の人との交流にほっとさせられる。
言葉が通じなくても、身振り手振りで温かい食事をとることができる。
初めて会った人達の輪に入ることができる。
大いなる旅の醍醐味だ。
写真家、ロバート・キャパの足跡と、自身の旅を重ね合わせるように描かれた「キャパのパリ、あるいは長い一日」は、
キャパの生涯に思いを馳せながらパリ中を歩き回る著者の姿が印象的だ。
しかし何と言ってもこの本のメインは「ヴェトナム縦断」だろう。
ホーチミンからハノイまで、旅行者用の乗り合いバスで北上してゆく。
町の人との会話もスリリングでドキドキする。
食堂やホテルを見つける際のいきいきとしたやり取りも眩しく、
読者もすぐに旅に出たくなるような、そんな心地にさせられる。
海外はもちろん、国内旅行すら自由にできなかったここ数年。
そんな中で、この紀行文は旅に出る楽しさや冒険心を思い出させてくれた。
ちなみに冒頭の話に戻ると、実は沢木耕太郎さんの講演を聴くのは2度目だったのだが、よくよく考えると約20年振りで、時の流れにくらくらと眩暈がした。
(2002年の日韓ワールドカップと中田英寿氏の話をしていた記憶がうっすらある)
20年振りの沢木さんは変わらぬチャーミングっぷりであり、そんな風に歳を重ねたいものだ、とつくづく思ったのだった。
さて、私の重層的でもなんでもない【旅の記憶】は、いったんイタリアから離れ、しばらくオーストラリアの旅を綴ってみたいと思う。
この度、刊行させていただいた歌集の中にオーストラリアの旅の一連があるのだけれど、
この旅については散文でも書いておきたいという気持ちがずっとあったからだ。
相変わらずゆっくりとした更新頻度ですが、しばらくお付き合いいただければ、嬉しいです。
(2003/2 講談社)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
