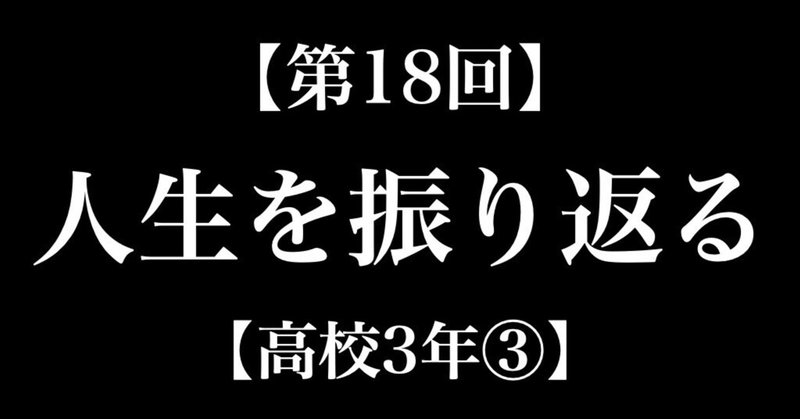
【第18回】人生を振り返る【高校3年③】
今回は高校3年編③大学受験について。
僕は進学校に通っていたので同級生はみんな大学受験していたし3年の後半は授業も受験用のカリキュラムになってました。
高校受験の時(その頃の記事はこちら)に、僕はペーパーテストが得意なようで苦労しなかった、という感じのことを書きましたが大学受験はそう甘くなかったです。
志望校は最初冗談半分で一橋大学と書いてました。
東京でバンドをやりたかったので関東の公立大学(親が国公立ならお金を出すけど私立は無理だぞ、と言っていたので)というのは必須条件でその中で二番目に難易度が高い大学(文系についての話、ちなみに一番は東大)。
学力は学年全体で見て中の上くらい(調子の良いときで)だったような。
うちの高校のレベルと合わせて考えると、一橋にはちょっと足りないけどがんばればいけるかもしれない、というくらい。
ただ高校3年で部活引退してみんな受験モードになってきた頃、一橋大学の入試の過去問(赤本)を見て、これは無理だ、と志望校を変更します。
そこからちょっとずつ志望校の難易度を落として過去問をいろいろ見るんですが(東京都立大学、横浜国立大学、横浜市立大学、埼玉大学、などなど)、どれを見ても2次試験の問題を解ける気がしない。
大体の傾向で言うと2次試験は総合的な知識と理解力、そして文章力が問われる問題という印象でした。
例えば歴史で言うと、〇〇時代の〇〇が〇〇した事件において、〇〇について300字以内で答えなさい、という感じ。
歴史上の年号とか人名とかを覚えなきゃいけないのは当然だし、その上でその人物や事件の相関関係や時代背景など様々な知識が必要で、それを問題に沿って的確に文章にする、という文章力まで問われる、ということ。
今考えると、ちゃんと勉強すればできるんじゃないか、と思ったりもしますが当時の僕は無理だと思ってしまったので別の方法を考えます。
別の方法というのは、2次試験が無理なら2次試験が無いところを受けよう、というもの。
2次試験が無いところがあるのか、と驚く人もいるかもしれませんが、学部や学科によって、また前期日程か後期日程かによってそれなりに2次試験が無いところはありました。
いろいろ調べてみるとちょうど上に書いた条件に当てはまる前期と後期の志望校を発見。
2次試験が無い場合は合否が何で決まるかというとセンター試験(現在の共通テストのようなもの)の点数です。(内申点が入る場合もあり)
なので志望校を決めてからはひたすらセンター試験の勉強のみやることにしました。
と言ってもなかなか夏から秋くらいは勉強に身が入らず、冬休みに入ったくらいでようやく本腰を入れます。
と言っても1日2時間程度。
センターの過去問をやって答え合わせして復習、くらいの内容だったと思います。
真面目に大学受験をしていた人からは怒られそうですが(とはいえ僕はこれでも真面目に勉強したつもりでしたが)これでなんとか目標点に近い点数を取り無事に合格します。(ちなみに受けたのは横浜国立大学の経営学部でした)
2次試験が無い関係で僕の受験が終わるタイミングは早かった(センター試験が終わった時点で終了)んですが、むしろ同じクラスの人に迷惑にならない程度は予習復習しよう、という思考になった結果センター後の方がけっこう真面目に勉強してました。
あとは大学に備えてExcel、Wordのことを勉強してみたり。
というわけで次回からは大学編。
もしサポートをいただけた場合はなにかしら記事に関連する活動費用にあて、記事にも購入したもの、用途などを書く予定です。(例えばギター動画に使うギター関連の消耗品、植物用の土や肥料、DIY用のネジや工具、などなど)
