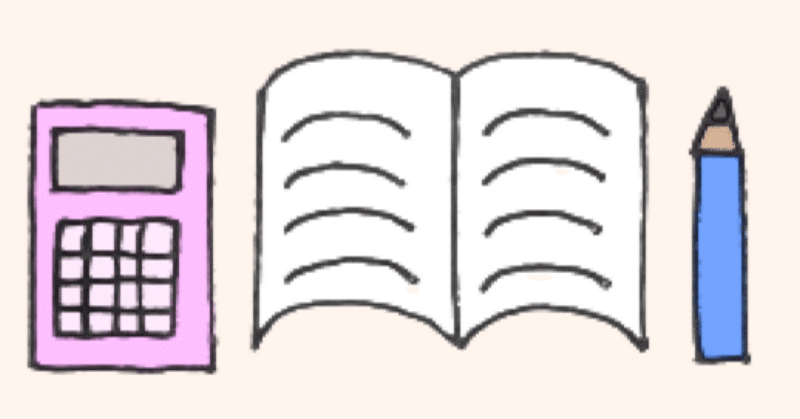
ESの教科書
こんにちは、現役外資マーケターのえるです🉐
就活生のみなさんが、就活を始めた時から本選考まで避けては通れない壁がESです。どんなに高い能力や熱量があっても、ESが通過できないと戦う土俵にすら立てません。
私はこれまで、優秀なのにESで落ちてしまい悔しい思いをする就活生を数多く見てきました。「あとちょっと早く相談してくれたら助けられたのに、、😂」そう思ったこともたくさんあります。私をフォローしてくれているみなさんには、そんな不必要な悔しい思いをして欲しくないです。
このノートでは前半部分でES作成における基本事項を解説し、後半部分で無双する就活生のESに共通している8つの応用ポイントを解説していきます。
これを読めば、ESに関して基礎から応用まで一通りの内容を網羅できるようになっているので、何度も読み込んで自分のものにしてください。
今まで100人以上の就活生と面談する中で分かった、無双する就活生たちに共通するポイントを大放出しちゃいます💪
また補足資料として、私が実際に使っていたガクチカ400字と700字を公開します。コンサル、メーカー、金融で内定を取っているものなので、幅広い業界で使えるものかと思います。構造に迷ったら参考にしてみてください。
私の構造丸パクリで大手に内定したメンティーも多数います👏
(まじで使えるものを作りたくて、しっかり書いていたら10000字超えていました😂😂特大ボリュームですが、必ず購入いただいたみなさんの力になるものになっていますので最後までお付き合いください🙇)
追記:早速購入してくださったフォロワーさんから丁寧な感想送ってもらったので載せます。購入迷われてる方は参考までにどうぞ!


はじめに:自己紹介
初めましての方もいると思うので、私の簡単な自己紹介と支援実績を載せておきます。
私は普段、外資系消費財メーカーでマーケティングの仕事をしています。名前は伏せますが、全国のドラッグストアで販売されている某ブランドの担当です。
就活支援は4年ほど行っており、過去100人以上の就活生へメンタリング実績があります。以下に複数回面談をした就活生たちの内定実績の一部を記載しておきます。
・コンサル
DTC/KPMG/PwC/EY/DTFA/アクセンチュア/NRI(経営)/ベイカレ/アビーム/IBM等
・外資系
PG(マーケ)/ロレアル(マーケ)/JJ(マーケ)/ネスレ/Amazon(コンシューマー)等
・日系
三菱商事/豊通/資生堂(マーケ)/花王(マーケ)/博報堂/ADK/野村不動産/DNP/富士通/NRI(IT)/NTTデータ/3メガ/SMCC/3大損保/アサヒ飲料/ミツカン/ヤクルト/中外製薬/レバレジーズ等
また私自身は就活生の時に
外資メーカー(マーケ)、big4、fas、大手金融等から複数内定をもらっています。
私の紹介はこれくらいにして、早速ESについて話していきましょう!
前半:ESの基本事項
👑ES落ちする就活生の共通点圧倒的第一位👑
“人に添削してもらっていない”
これに尽きると思います。
OBG訪問、先輩、親、友達、キャリセン、等々、ESを添削してもらえる機会は無数にある中で、添削の依頼に踏み出せない理由は、「このES人に見せて恥ずかしくないかな?」という不安が大きいのではないでしょうか。
まずはESの基本事項を押さえ、その不安と決別しましょう!
ESの位置づけ
最初に、ESってどういうマインドで書けばいいのってことを整理しておきます。
ESとはずばり「内定を取るためのロードマップ🗺」です。
どういうことかと言うと「ES通過のためのES」ではなく「最終選考を通過するためのES」 を書きなさい、ということです。
よくある質問で、選考を進む中でESで話したいことが変わったから最終面接で違うガクチカを話してもいいか、ということを聞きますが、もちろんNOです。厳密には変えても通過する場合も稀にありますが、基本的には変えることによってそれまでの面接での評価が意味をなさなくなります。企業からすれば、最終でいきなり新しいことを言う学生なんてリスクしかありません。最初から準備していない時点で、志望度が低いとみなされても文句は言えないでしょう。
ではどうしたら「最終選考を通過するためのES」になるのか、具体的なポイントは後半でお話します。まず次の項でESがなぜ必要なのかお伝えします。それが分かると内定を見据えたESとはどのようなものか、しっかり理解していただけるはずです。
ES(ガクチカ、志望動機)の必要性
ここでは、ESにおいて2大質問であるガクチカと志望動機がなぜ必要なのか、企業目線で理由をお伝えします。
以下に示す3つの要素を理解してESに落とし込みましょう。これが内定を見据えたESです。
①ガクチカの必要性
企業がガクチカを聞く理由は何でしょう。企業は何を知りたくてガクチカを聞いているのか、みなさんは考えたことありますか?
それは「仕事でどれだけ活躍できるかイメージするため」です。
就活生のみなさんは当たり前ですが職歴がありません。そのため仕事でどのような活躍ができるか客観的に判断する材料がありません。だからガクチカを通して、どのような思考でどう行動する人間なのか判断するわけです。ということはガクチカで示すべきは、仕事で活躍できる人材であることなわけで、そのために必要な要素を考えましょう。
私はガクチカで見せるべき要素は2つあると考えています。
要素1:人と関わる中で目標を達成する力🤝
仕事は1人で何かをするよりも、複数人で取り組むことの方が圧倒的に多いです。また仕事である以上、明確な目標があります。この目標を達成するために、周囲と適切に関わり生産的な関係を築ける能力は必須です。よくガクチカは人と関わるものがいいと言われるのはこのためです。
要素2:成長する力✏️
新卒で会社に入ったばかりの頃はみんな仕事ができません。そのスタートはみんな一緒です。企業にとって新卒を採用するのはある種の投資であるため、期間を経て経験積むことで成長することは求められます。投資に見合ったリターンを得られないと判断されれば内定まではたどり着けません。よくガクチカの質問で、困難だったことを聞かれるのはこのためです。問題や失敗から何を得て、それを次に生かす力があることを示しましょう。
②志望動機の必要性
次に志望動機について考えましょう。志望動機はなぜ聞かれるのでしょうか?そりゃ会社に入りたい理由を知りたいからに決まってるだろ、って思いますよね笑
そうじゃなくて、志望動機を聞くことで就活生の何を知りたいのかということです。
それは「入社後のモチベーション」です。
ガクチカから分かる内容って、あくまでその就活生の持っている能力にすぎないんですよ。どんなに能力が高い人でも、その人が活躍できる土俵に立たないとイマイチな結果に終わってしまいます。例えば、野球の大谷選手もサッカーのプロを目指していたら今ほどのワールドクラスになってはいなかったでしょう。
入社後のモチベーションを示すために志望動機で見せるべき要素はこれです。
要素:自分がモチベを感じる瞬間と会社の提供する価値が同じ方向であること👫
会社は業務を通して社会に価値を提供し、その対価として報酬を受け取っています。その提供価値の方向性(誰にどんな価値を提供するか)が、自分にとってモチベーションを感じる瞬間と一致していることを示しましょう。
よくある志望動機への質問で、それうちじゃなくてもよくない?って聞かれる人いますよね。それってここで言うところの、会社と就活生の方向性が合ってるか分からないって意味なんです。自己分析と企業分析を進めることでここの言語化は上手くなります。というかこの質問受ける時点で準備不足だよと言われてるのに等しいです。私は就活を通して一度も言われたことがないので、未だにこの質問は就活神話だと信じています。
ESの文体
ESを書き始めてすぐの人にありがちな悩みとして、ESの文体を「である調」か「ですます調」のどちらで書くか迷うというのがありますよね。
結論、基本的には字数が短い「である調」で書いて問題ありません。
今までほぼ全業界へ内定者を送り出して来ましたが、「である調」で書いて誰も内定を取れなかった業界など存在しません。人事は大量のESを見るので、少しでも端的で読みやすい方がストレスなく頭に入ってきます。そういう観点からも「である調」の方が読みやすいんですよね。同じ理由で、ES内での過剰な敬語も要らないです。特に身内への敬語(先生や教授、先輩等)は助長です。
ただOBG訪問等を通して添削を受けた際に「ですます調」を強く推奨される企業があればそこだけは従いましょう。稀にそういう話をされることがあると聞きます。
ガクチカの基本構造
ここでガクチカの基本構造についてお話します。
ガクチカの基本要素は以下5+2つです。
①〜⑤の要素は制限字数に関係なくマストで入れるもの、⑥と⑦は字数に余裕があれば入れましょう。
ガクチカを上手く書けないなと思っている人は、まずこれらの要素を全て入れたものを書いてみましょう。基本の型を押さえる前に我流を押すのはオススメしません。基本を理解したのちにアレンジを加えればいいです。
マストの5要素
①結論:ガクチカで成し遂げたことを端的に一行で書く。この一行で読む人に何の話が書いてあるのか、ゴールがどこなのかを明確に伝える役割のため非常に重要。「私が学生時代に力を入れたことは〜。」みたいな枕詞は要らない。いきなり「○○を達成したことだ。」といった書き方でOK。
②目標:何を目指したのか書く。数字で分かるものでもそうでなくてもよい。大事なことは、その目標が達成されたかどうかの基準が第三者から見て明確であること。数字で目標を示せと言われるのは、目標達成ができたかどうかの基準が明確であるから。
③課題:目標を達成する上で一番の障壁となるものを書く。これが解決できれば目標達成ができるというものをチョイスする。
④施策:課題を解決するためにやったことを書く。施策と課題が本当に対応しているかの確認を常にする。求められる字数に応じて入れる施策の数を変える。
⑤結果:施策をし、課題が解決できたことで目標達成に至った流れを簡潔に書く。施策の前後で何が変化したのかを入れると分かりやすい。
プラスの2要素(目安:300字なら両方入れない、400字なら片方は入れる、500字なら両方入れる)
⑥背景:このガクチカに取り組んだ背景を書く。入れるのであれば、結論の後、目標の前に入れる。背景は、自身の価値観等の定性的な要素を伝えられる要素なので、ガクチカ全体を通して定性的な内容に触れられていないのであれば積極的に入れて良い。
⑦学び:正直一番不要な要素。慣例的に入れられることが多いが、普通のガクチカから学んだことを入れてもありきたりなものになりがち。人と違う特別な内容や、その後の志望動機に繋がる内容であれば入れてもよい。また制限字数が多い場合は最後に入れておくと収まりが良い。
志望動機の基本構造
ここでは、志望動機の基本構造についてお話します。
志望動機の基本要素は以下3つです。志望動機に関しては業界や、職種別採用/総合職採用などの採用方式によっても書き方が少し変わるので、あくまでも基本の形として押さえてください。この書き方が出来れば応用はいくらでも利きます。
①結論:会社を志望する理由を一言で書く。内定者のESを見ると色々な書き方があると思うが、会社の価値提供の方向性と自分のやりたいことが一致していることが伝わればよい。「会社のビジョンに共感した」や「○○がしたいから」等会社or自分の方向性の片方しか示していないものはNG。
②業界志望の理由:その業界を志望する理由を一言で書く。結論の具体的な内容を書くイメージ。自分の過去の体験から生まれた価値観と業界が社会に与えている価値が同じであることを示すため、具体的な経験を入れる。
③業界の中で御社である理由:業界の中で御社に入ることが自分にとって最適な選択であることを示す。他社になく、御社にしかない魅力的な要素を書く。その際他社と比較する必要はない。例えば、業界の中で特定の層への価値提供が強い会社があれば、自分が価値提供したい層に一番アプローチできるのが御社である、と簡潔に伝えればOK。「他社と比較して〜。」みたいな枕詞は不要。
ここまでが前半のESに関しての基本事項です。
ここからは無双する就活生のESに共通している9つの応用ポイントを解説していきます!
後半:無双する就活生に共通する8つの応用ポイント
ここからは具体的にESを書く際に使えるポイントを解説していきます。
今まで100人以上の就活生と面談し、無双する就活生に共通するポイントを言語化したものです。
ただし、こちらは前半の基本事項を押さえられた人のみ実践してください。基礎がない人が応用に手を出しても無駄なのでやめましょう。
①フックを作る
ESは面接時の質問材料になるので、面接で聞いてほしいところを敢えて全部は語らず、面接官が聞きたくなるように伏線を貼りましょう。
面接では短い時間で多くのことを伝えないといけないので、聞いてほしいところを聞いてもらえずに終わることも多々あります。ただ実際自分が話したいことを話せば言い訳ではなく、面接官が知りたいことを伝えてあげることが大事です。伏線を貼っておけば、面接官が知りたいと思えばそこに触れてくれるので、効率よく相手の知りたいことを伝えられるわけです。
例えば「ディベートを遊戯王に例えて教えてました」とか書いている後輩が実際にいました笑
こういう伏線を貼っておくと、印象にも残りやすいのでおすすめです。
②定性的な情報を織り込む
ガクチカも志望動機も、何をしたかだけではなく「なぜそれをしたか」を書くことが大事です。
上にも書いたけど、新卒採用とは企業にとってある種の投資行為なわけです。投資する対象に、投資に見合ったリターンを期待できるかというのが採用の判断軸になります。そうなった時に「なぜそれをしたか」という行動理由を伝えることで、その人が投資に見合ったリターンを将来期待できる人材かどうか、ある程度判断できるのです。
就活で落ちるパターンは2種類あるかなと思っていて、具体的には
・ミスマッチで落ちる(会社に合わないと判断された)
・人格が分からず、判断不能で落ちる
です。
前者の場合は入社後に会社と合わなくて辞めそうだと判断されてるから、学生的にも入らなくて正解かなと思ってます。わざわざ渋い会社に入るのは時間の無駄なので。
一方、後者の場合はすごく勿体ないです。なぜ人格が分かってもらえないかというというと、あなたの定性面が見えてこないからです。
面接官が知りたいのは「何をしたか」じゃなくて「何でしたか」なので、事実を羅列するのではなく、自分の人柄が見えるように書くべきです。
例えば、漫画の主人公(ルフィ、コナン、桜木花道・・・)って実在はしないけど、何となくどんな人で、どんな時に頑張れて、何をしたら怒るのかみたいな人柄が分かりますよね。
それは漫画を通じて彼らが「何でそれをしたか」という行動の理由が明確に分かるように描かれているからです。
逆に新キャラは、例え経歴が書かれていたとしても、どんな奴なのか分からないから気になりますよね。
それはまさに、事実を羅列されてるだけではその人の人柄が見えてこないからです。
就活においても、自分の定性面が見えるようにESを書くのが評価される上で非常に大切なポイントになります。
③抽象と具体の行き来(例えばを入れる)
志望動機を書く際に「××がしたいからだ。」とだけ書く人が多い印象ですが、それだけだと面接官としては納得できません。それを読んだ面接官としては、何でそう思うん?って感じるはずです。その「なぜ」の部分を補強するために具体例を入れましょう。
例えば「○○の経験から、××がしたいと考えるようになったので、御社の△△な点に惹かれました」のように書くのもいいと思います。ここで大事なのは、「××がしたいと考えるようになった」という考え方の部分を入れることです。経験は自分を作るきっかけにすぎないので、その経験から自分がどうなったから御社に興味があるのかまで丁寧に書いてあげましょう。
④読みやすい文章を書く
ESの書き方に関して、面接官が読みやすくなるように「構造化」と「1文を簡潔に」と「結論ファースト」を徹底しましょう。
構造化とはまさに上に書いた基本構造を押さえた書き方をしよう、ということです。慣れてきてアレンジする人も、構造化がしっかりできているかは確認が必須です。構造化するということは、読む相手の頭を整理してあげることであり、次に出てくる内容を予測しながら読んでもらうことです。これができると初見でも面接官の頭にすっと入る読みやすい文書になり、結果的に覚えてもらいやすくなります。
これをしっかり鍛えたいという人は、バーバラミントという人の「考える技術・書く技術」って本を読むことをおすすめします。
1文を完結に書けない人も多いです。目安ですが1文30字〜40字程度が読みやすいかなと思います。長くなるようであれば句読点を入れて読みやすくしましょう。文章の校正にchatgptを使うのはありだと思います。
結論ファーストも徹底しましょう。これはESだけでなく面接もです。まずは結論を書いてその後に理由を書く。普段からこの話し方を意識することでいつの間にか身につきます。就活の間だけでも頑張って実践してみてください。
⑤嘘は1→100のみ
ガクチカ、志望動機を盛る際の話です。0から1の嘘をつくとほぼ確実にバレるし、ストーリーが薄くなります。(唯一P&Gマーケに行った後輩だけは、ガクチカのストーリーを1つ0→1で創作してたけど、普通の就活生では破綻するのでやめましょう。)
とは言え、当時実際にやったこと、考えたことだけを正直に話す必要はないです。今ならこう考える、というのを話すのは全然ありだと考えています。というのも面接官が知りたいのは、その人の今の考え方やであり、当時のものじゃないからです。(もちろん過去と今を比較して成長をアピールするのはOKですが。)
だって会社に入るのは過去のあなたではなくて、今のあなたなわけですからね。
ただし、それも怖いという方へ。数字を盛るのは絶対バレないのでおすすめです。(限度はありますが笑)
そのため盛るときは事実を繋ぎ合わせて、数字とかだけ盛るといいよ!
例えば
・○○の新人大会で優勝→全国大会優勝
・20 名で行う 1 か月の活動のサブリーダー→40 名で半年行う活動のリーダー
といった感じです。
⑥ドラマチックに書く
倍率が特に高い会社を受ける場合、選考では1/1000にならなくてはいけないこともあります。そうなると当然ガクチカも 1/1000 になるべきですね。ただそれって意外と難しいことではなくて、とてつもなくすごい経験をしていなくてらダメってわけではないんです。
例えば、リーダーシップを発揮した経験をガクチカにするとして、同じような内容のESを書いてる人って多分3000人くらいいます笑
だから同じリーダーシップを書くにしても、自分なりのストーリーにする必要があります。②でも少し書いたように、定性面を書くことで深い「読ませる」話にするのが大事です。
簡単な方法の一つに、「時系列を広げる」ことがあると思います。
ただその瞬間リーダーを務めました、とかだと薄いし聞いてて面白くないです。
そこで例えば、
「昔から引っ込み思案な自分」
→自分の考えを言えないことがコンプレックス
→大学のサークルで自分の意見を堂々とぶつけあう先輩たちにあこがれ、自分を変えたいと思った
みたいな前書きを入れたうえでリーダー経験を語れば少し読ませる内容になります。
こんな感じで、昔の出来事や定性面、または自分が持ってる信念などを入れ込むと1/1000に近づくESが書けると思います。
設問をまたいでも、一貫して自分のモチベーションの源泉を語れると本気度や定性面を納得感を持ってドラマチックに見せらます。そのためにも自己分析は必須ですが。
⑦専門的なことは書かない
面接官は社会人でありビジネスの専門家なので、当然知ったかぶりをすると殺されます笑
例えば、広告研究会の人とかによくあることで注意すべきなんですが、広告代理店の面接で広告についてのガクチカ言ったりすると、ボクサーに素手の喧嘩を売るようなもので、返り討ちに合うのでやめましょう。
事業会社の人にビジネスについて語るとかも同様です。
例えば意識高い高校生が「大学生が授業を真面目に受けるような改革がしたい!」とか言ってたら「お前大学の授業受けたことないのに語るな、しばくぞ」ってなりますよね笑
専門知識とかビジネスの話を語るより、学生にしかわからない「見たこと・感じたこと」を背伸びせずに等身大で伝えましょう。
その生の声の方がよっぽど社会人響くし定性面を伝えられます。
⑧ライバルを意識する
例えば「リーダーシップ」をガクチカとか強みにしてる人って、同じ企業の受験者でも最低1000人くらいいるので、淡々とそれだけ書いてしまうと当然埋もれるし、面接でも他社と差別化できないです。
具体的には音楽業界で「バンドやってました!」みたいなガクチカ言っても「またバンドか~」ってなりますし、商社とかで「留学してました!」とか単に言っても「またか、、」ってなるわけです。
強みを語るにしても「粘り強さです!」だと飽きられるし、ガクチカを語るにしても、志望動機を語るにしても、常にライバルはどんなことをいうのか、どうやったら彼らに対し頭一つ抜けるのか、を常に考えることが大事です。
そのためには定性的 面を深ぼったり、一貫した時系列でドラマチックに経験を書くのがいいです。あとはギャップも大きな武器になりますよ!(真面目そうなのにDJしてましたとか、ムキムキなのにロジカルとか笑)
以上の8項目を押えられれば内定を踏まえたロードマップ的なESに仕上がっているはずです。
最後に
ここまでお読みいただきありがとうございます。
しっかり目を通していただけたのであれば、あなたのESに関する知識は就活生の中でもトップクラスに入るものになっています。
ただし、「知っていること」と「実際にできること」は全然違います。
まずは読んだものを形にしましょう。手を動かしとにかく書いてみるのです。最初は字数がオーバーしてもいいから多めに書いておきましょう。そしたら書いたものを第三者に見せてください。人に見せてフィードバックをもらうことでESは洗練されていきます。
あたの就活ライフがよりよいものになるよう願っています😌
補足資料:えるのガクチカ
私が使っていたガクチカ貼っておきます。
参考資料としてご活用くださいね!
ガクチカ400字
大学二年次、○○劇大会に○○大学○○(チーム名)の演技指導者として参加し、チームを十年以上ぶりの優勝に導いたことだ。私は過去の敗因を分析し、チーム内に理想とする演技の共通認識がないことだと結論付けた。審査員にプロの役者を呼ぶため、「プロが見て楽しい」と感じる演技を共通の理想とすることを提案した。そこでプロの役者との交流が必要だと考え、プロの舞台に何度も通い、私たちの練習やリハーサルに来てもらえる関係を構築した。その中で「プロが楽しめるか」を基準にアドバイスをもらい日々の練習に生かした。チーム内に共通の理想を持つことで、自分たちの現状と理想の差を客観的に判断できるようになり、理想から逆算して完成までの順序を立てることができた。その結果、最後には役者全員を理想の状態まで押し上げることに成功し優勝に繋がった。この経験から具体的な理想の共有が組織の方向性を一つにし、成功に繋がることを学んだ。
ガクチカ700字
大学二年次、○○劇大会に○○大学○○(チーム名)の演技部門責任者として参加し、大会の全賞を取る完全優勝をしたことだ。チームは一、二年生約200人が責任者である10人の三年生の下で各部門に分かれる構造で、三年生が組織の運営を担う。例外的に演技部門は結果への影響が大きく、実力を重視するため、二年生が責任者に選ばれることもあった。私は一年次に大道具部門に所属し、努力したが負けて悔しさと無力さを感じた経験から、二年次は演技部門の責任者として参加したいと考えた。約半年かけて実力をつけ三年生からの信頼を得て選ばれた。活動が始まると演技部門内外で影響を与え組織を変えていった。演技部門内では、長い活動期間を通して役者のやる気を高く維持することが重要課題だった。そのために様々な方策を取ったが、その一つに他大学の卒業生を説得し、敵同士では初の合同練習を組んでもらったことがある。それ以降役者は敵を具体的に想像することで、本番まで高いやる気を維持できた。これらの結果練習の質が高まり演技の底上げに成功した。演技部門外では、責任者が集まる話し合いの場で組織の問題点は出るが、具体的な改善策が出ないという問題があった。各部門の実態が他の部門責任者には分からないことが原因だった。私は二年生で責任者という立場を生かし、各部門の同期と後輩から実態を直接聞き、各々の問題を俯瞰した。それらを三年生に共有することで、一つの部門で解決できない問題を組織全体で協力して改善していく体制を作った。その結果本番までに組織の問題を大幅に改善できた。この演技部門内外での働きにより、大学史上初の完全優勝に貢献し、人生で最も大きな達成感を得た。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
