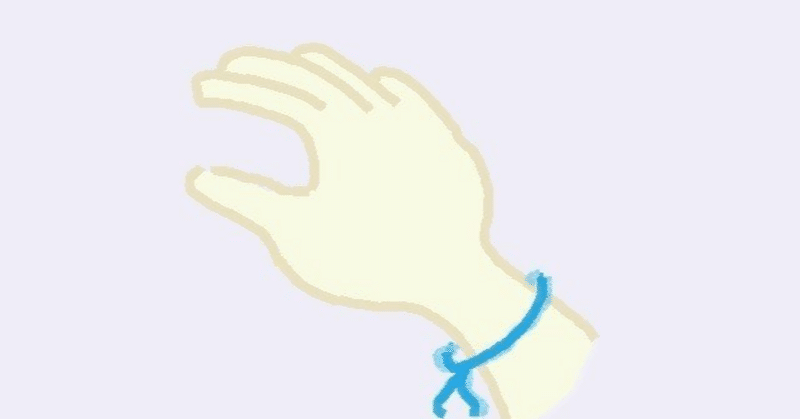
【短編小説】君に届かない(#青ブラ文学部)
《約2400文字 / 目安5分》
誕生日にミサンガを貰ったことがきっかけだった。
部活が終わって、外はもう暗くなり始めていた。ぞろぞろと部活仲間は帰っていく。友達からは一緒に帰ろうと誘われたが、今日は一人で帰る気分だと言って断った。カッコつけんなよとバカにされたが、僕はそれでよかった。
なぜなら、同じ部活の女子から一緒に帰ろうと誘われたからだ。
その人のことが好きだったわけではないけれど、こんなチャンスはこの先無いような気がして誘いに乗った。
僕と彼女以外のみんなが帰るのを待とうとしていたら、彼女は何も気にしないような素振りで僕に声を掛けた。
「早く帰ろうよ!」とさつきは笑顔で言った。
目線が気になって周りを見てみると、他の女子がこっちを見て騒いでいるのが目に入って顔が熱くなった。
夜が少しだけ顔を出しているような空で、三日月の首飾りが美しく光っていた。ぽつぽつと街灯が灯っていく下で、僕の隣にはさつきがいた。
「一緒に帰ろうなんて、珍しいね」と僕は言った。
「だって、今日はあんたの誕生日でしょ」
「そうだけど、それがどうかしたの?」
「実は、渡したいものがあるの」とさつきはいって、ポケットからミサンガを出した。
「もしかしてこれ、僕にくれるの?」と僕が驚いていると、さつきは僕の手を強引に広げて、ミサンガを手に押し付けた。
「いっつも頑張ってるから、プレゼント」とさつきは顔を赤らめていった。「それじゃ、もう家近いから! ばいばい!」
さつきはそのまま走っていって道を曲がってしまった。
手からはぬくもりが感じられた。
これが、中学三年生の夏の出来事だった。
その次の日から、僕は早速ミサンガを付けて、学校に行った。腕にはピンクとレッドとオレンジの三色が光っていた。
友達にミサンガのことを聞かれる度に、僕は自慢するようにさつきから貰ったと言った。大抵からかわれたが、飽きるまで自慢し続けた。
さつきは他のクラスだった。そのせいであまり喋るチャンスがなかったけど、廊下ですれ違ったときはいつも喋った。部活ではさつきのことを目で追ったり、たまに一緒に帰ったりした。
そんな毎日を過ごし、いつのまにか、僕はさつきのことが頭から離れなくなっていた。
恋をしていた。
そのことに気づいたのは、中三の冬だった。
冬が本格的に始まって、さつきはマフラーをしていた。この頃はさつきと毎日登校する仲になっていた。
朝はよく冷える。さつきは手を擦って白い息を吹きかけた。そのとき、腕にぶら下がって揺れるひもが見えた。
「それって、ミサンガ?」と僕は聞いた。
「そうそう。付けようか迷ってたんだけど、今日から付けることにしたの」とさつきは言って、ジャケットの袖でミサンガを隠した。
「色、ピンクだけ僕と同じだね」
「他の色が無かったから」とさつきは言った。
毎日が楽しかった。
だけど、僕とさつきが付き合っているという噂が流れ始めてから、楽しい毎日は一変した。
僕とさつきの噂を耳にした日の放課後、僕は浮かれていた。僕がさつきと付き合う、それは24時間毎日考えていた夢でもあったから。
そして今日が、想いを伝える日なんじゃないか、そう思った。
今日は部活がある。だからその帰りに告白しようと僕は決意した。
掃除が終わって、班の友達と部活に向かった。
「なあなあ、お前とさつきが付き合ってるって本当かよ」と友達は言って、歩きながら肘で突っつかれた。
「そんなんじゃないよ」と僕は強がった。
「まあ、そうだろうな」
そう言った友達は、急な落ち着きを見せた。それはどういう意味かと聞くと、友達はさつきについて淡々と話し始めた。
「あいつさ、結構いろんな男と遊んでるらしいぜ。だから一部の女子から嫌われたりしてんのよ。あいつって普通に可愛いし、モテるだろ? 女子が言うには、性格がだいぶきついらしいぜ」
「そんなわけないだろ。でたらめ言うなよ」と僕は強めに言った。
「なんだ? やっぱりお前、さつきの彼氏なの?」
「そうじゃないけど……」
「まあ、お前がさつきと付き合えるわけないよな」と友達は言った。「ワンチャンあるかもしれないけど、さつきはやめとけよ。今のお前は、さつきに遊ばれているようにしか思えないし」
友達の話が、頭をぐるぐる回った。僕は今にでも倒れそうだった。
友達の話を百パーセント信じるわけではない。しかし、妙に信憑性のある話だと、そのときは思ってしまった。
なぜなら、ちゃんと考えてみれば、おかしな話だったからだ。
さつきは可愛いし、勉強ができて、スポーツもできる。みんなから尊敬され、男からはよくアプローチされている。
それに比べて、僕はどうだろう。顔も勉強もスポーツも、すべて平均以下。
よくよく考えてみれば、僕とさつきが付き合うだなんて、ありえない話だった。そして、ここまでさつきが僕に構ってくれるのも、遊ばれているようにしか思えなかった。
最初から僕は、君には届かない存在だったんだ。
その後、部活ではミスを連発して、初めて監督に怒られた。
そして、僕は逃げるように一人で帰った。
それから、僕はさつきと距離を置くようになり、終業式があって冬休みが始まった。そうして、自然にさつきとは疎遠になった。
気がつけば違う高校へと進学していた。
あれから、もう10年が経った。
実家に帰ると、僕はいつも昔のことを思い出してしまう。
中学生のときに着ていた制服を見て、さつきとの思い出を噛みしめた。
制服には埃が被っている。昔はこんなに小さかったのか、そう思い一人で笑った。
よく見てみると、制服のポケットからミサンガが飛び出していた。
それは、さつきが付けていたミサンガのように見えた。気になって取ってみると、一枚の紙きれがミサンガと一緒にひらりと出てきてこぼれ落ちた。
紙きれにはこう書いてあった。
「あなたのことが、本当に好きでした」
ミサンガはさつきのもので、繋がったままだった。
◆長月龍誠の短編小説
◆自己紹介
気が向いたらサポートしてみてください。金欠の僕がよろこびます。
