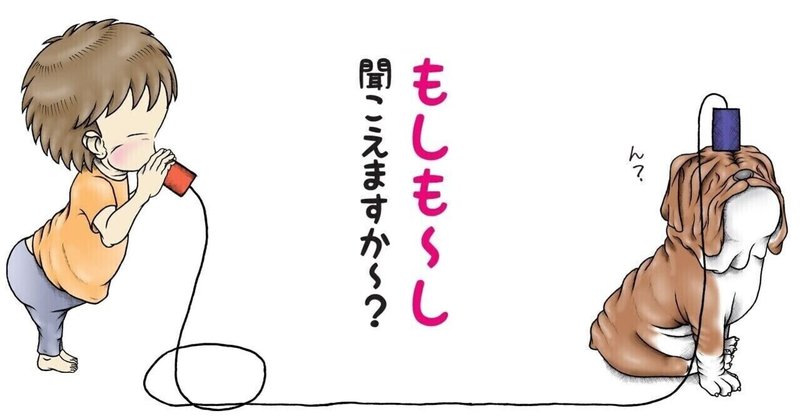
聞こえること、聞き取れること
今回のテーマは「聞こえること、聞き取れること」です。
よく患者さんから、『音は聞こえるんやけど何言うてるかがわからん』という内容の訴えがあります。
聞こえるのに何を言っているかわからない・・・???となると思いますが、なぜそのような事が起きるのかを書いていこうと思います(^^)/
~音の聞こえ~
音のきこえについて、皆さんはどのようなイメージをお持ちでしょうか?
大きな音を聞くと耳が悪くなる、若者にしか聞こえない高い音がある、高齢者は高い音がきこえにくなどなど仕事や育ってきた環境などにもより音に対するイメージは様々かと思います。
まずはその音について、耳鼻科で行うような検査をベースにお伝えしようと思います。
・純音聴力検査
「耳がきこえにくい」「こもったような感じがする」「耳鳴りがしている」といった症状で病院を受診すると、聴力検査を受ける場合があります。受けたことがある方はわかると思いますが、健康診断で受ける聴力検査とは異なる部分が多くあるのです。
【健康診断での聴力検査】
一定の音、一定の周波数を出し聞こえているかを調べる。きこえない音がある場合は病院での聴力検査を受けるように指示される。
【病院での聴力検査】
聞こえないような小さい音から、やかましいぐらいの音を出すことができ、数種類の周波数ごとに「聞こえはじめる音の大きさ」を調べる。
どちらの検査にも共通するのが「㏈(音の大きさ)」と「Hz(音の高さ)」です。結果は、何Hzの音が何㏈で聞こえはじめるかを表します(健康診断では、一定の周波数と一定の音圧を聞いてもらいそれが聞こえるかどうかを調べます)。
・日常生活に溢れる音
聴力検査でわかるのは音の聞こえはじめる大きさになりますが、それを日常生活の音に当てはめていくと、「インターホンのチャイム」「電子レンジの通知音」「体温計の終了音」などがあります。
よく「体温計がきこえないんやけど・・・」とか「誰かが来てもピンポン聞こえへんねん」という話を聞きますが、初めて補聴器を使用した際にこれらの音が聞こえるようになることで自身の聞こえにくさがどれ程のものかを実感される場合もあります。
音が聞こえる事の大切さを、補聴器を通じて感じてもらえると嬉しいですね♬
~言葉の聞き取り~
音を聞くことについては前述の通りになりますが、言葉の聞き取りについてはどうでしょうか?
そんな聞き取りを調べる検査はあるのですが、病院や補聴器販売店では省かれる(実施していない)という話も聞くことがあります。それがどんなものなのかを後述していこうと思います。
・語音聴力検査
単音節(「あ」とか「き」)を聞こえたとおりに復唱(または記述)し、一番良い正答率を求める検査と、聞こえた数字を同じように復唱(または記述)し音のきこえ初めが大体どのぐらいかを求める検査があります。
今回は、前述の単音節の聞き取りの検査についてです。
この検査の注目したいところとしては、音の聞こえの検査結果が同じだったとしても言葉の聞き取りの検査結果は同じにならないということです。
例えば、「音のきこえの検査結果が50㏈の人でも、言葉の聞き取りの検査では100%の人もいれば50%の人もいる。」という事になります。
そして、補聴器により音を大きくしても50%の正答率が100%になるという事は厳しいのが現実です(※だからといって補聴器の効果が無い訳では無い)
・聞き取れるとは
上記の2つの検査から、聞こえる事と聞き取れる事は同じようなニュアンスですが別物という事がお判りいただけたでしょうか?
「補聴器を使えば聞き取りが昔のように良くなる」とか「あの人は補聴器を使っているから聞こえに関しては大丈夫だ」という認識がまだまだ散見されていますが、実はそうではない事を皆さんに知って頂ければ嬉しい限りです。
補聴器は、言葉の聞き取りの検査結果が良いうちに、「どうせ行く行くは使うであろう」という方は早めの使用をお勧めします。
最後まで読んでいただきありがとうございました(^^)/
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
