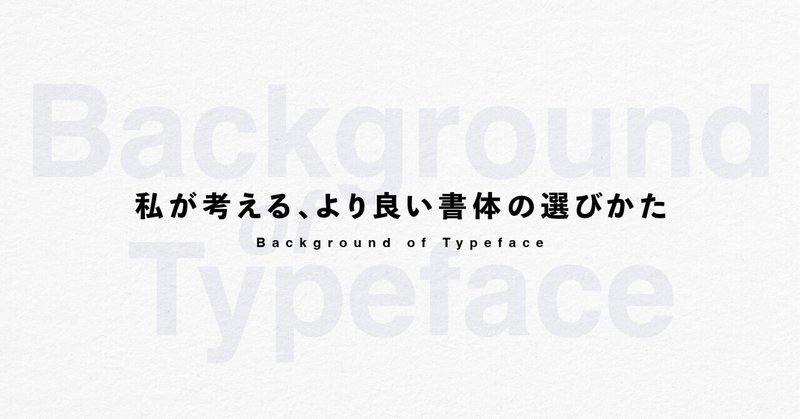
私が考える、より良い書体の選びかた
デザイナーの室橋です。
印刷物を作る時、サイトを作る時、映像を作る時、ほぼすべての制作活動に文字は欠かせない要素です。 そして書体選定は発信したいメッセージに合わせて適切に選択する必要があります。
みなさんは書体選びで何を基準に選んでいますか?
読みやすさでしょうか?
それとも装飾?
扱いやすさ?
雰囲気?
確かに、すべて大切です。
読み物の場合は読み取りやすく、読んでいて疲れないことが大前提ですし、大きなポスターの場合は装飾やインパクト重視のこともあるでしょうし、WEBフォントの場合はWEB上での扱いやすさにも気をつけなければならなくなります。
このように様々な選定の理由が思い浮かぶと思いますが、上記だけだと書体を活かしきれない事がある気がしています。
書体には必ず作った人がいて、意図を持って作られ、特有の来歴を持っています。こういった書体の持つバックグラウンドはパッと見た印象以上の本来の書体の能力を教えてくれると私は考えているのです。
選定基準に書体のバックグラウンドを加えることで、より効果的で説得力のある書体選びができるのではないでしょうか。
そこで、この記事では具体例をあげつつ書体選定において、書体のバックグラウンドを知ることのメリットについて書いていきたいと思います。
メリット1. 書体デザイナーの意図を汲める
メリットとして真っ先に挙がるのはやはり書体デザイナーの意図した使い方ができることです。
書体は全体の設計を行うタイプフェイスデザイナーによって想定使用場面やユーザー、コンセプトが考えられて制作されています。
私はそのコンセプトに沿った使い方をすると、より効果的な使い方ができると考えています。 また、使われていく中で本来の用途から離れて広く使われるようになった書体もありますが、 そういったものも、元々の成り立ちを知ることで活用の幅が広がり、真価を発揮すると思います。
ここで2つ具体例を挙げます。
1. Helvetica
1つ目はみんな大好きHelvetica。
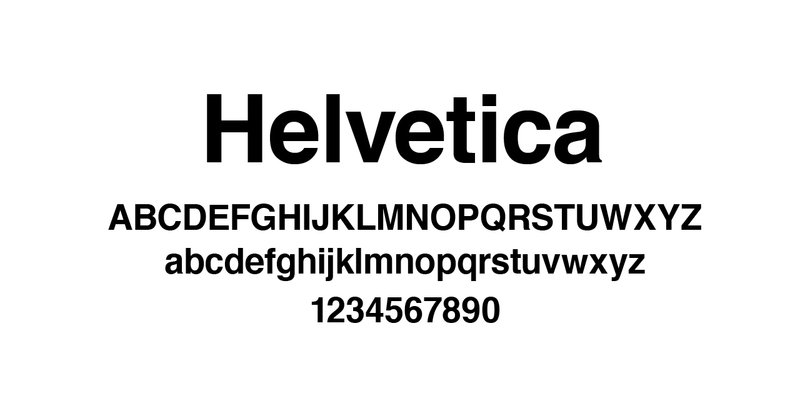
Helveticaはスイスのタイプデザイナーのマックスミー・ディンガーとエドゥアルト・ホフマンが中心となって企画・設計され、 ハース鋳造所からNeue Haas Grotesk(ハース鋳造所の新しいサンセリフ体の意)の名前で1957年に発売されました。 ※1
その3年後の1960年にステンペル社からHelvetica(”スイスの~”という意味)と名前を変えて発売され、 同社とライノタイプ社の積極的なマーケティング活動により世界中でスタンダードな書体の代表として使われるようになっていきます。 この書体はそもそもの源流を100年以上前に制作されたと言われるドイツ産のAkzidenz Groteskに持つと言われています。 ※2
Akzidenz Groteskは古典的な書体ではあるもののシンプル且つ視認性に優れていた書体であり、 当時ハース鋳造所の社長だったホフマン氏はこれを改良して普遍的な究極の書体を作ろうとしました。
そしてミーディンガー氏が原図を描いて今のHelveticaの原型ができます。 ライノタイプ社のマネージャーを20年間務めていたマイク・パーカーはHelveticaにはスイス人特有の気遣いが込められていると、 Helveticaにフォーカスしたドキュメンタリー映画「Helvetica」の中で語っています。
「スイス人は背景(地の白)に気を遣う。背景がインクの黒をがっちりホールドして全く揺らがないバランスがある。それがHelveticaを語る上での全てだ。」
ネガとポジの話ですね。
シンプルで普遍的な字形設計は永世中立国たるスイスのお国柄を体現してるとも言えそうです。
このバックグラウンドから言えるのは、Helveticaは読者を文意に集中させたい時に活躍してくれるであろうということです。
Helveticaは字形的特徴を持たない(Helveticaの字形こそが特徴を持たないと言われる基準になったとも言えますが)スタンダードな書体を目指して設計されたために、 字形そのものに意味を感じづらいからです。
映画「Helvetica」の中でオランダのグラフィックデザイナー、ウィム・クロウェルは
「書体に意味があってはならない。文意は文言にあるべきで書体に含むものではない。だからHelveticaを愛した。」
と語っています。
このクロウェル氏のインタビューは少し極論気味かもしれませんが、 書体は文言を構成するためだけにある派の思想の元ではHelveticaを選択する以外はないと言っているのでしょう。
使い方と使う場面にもよりますが、この意見には概ね同意できると私は思っています。
2. Frutiger
2つ目の例は巨匠アドリアン・フルティガー氏の設計したFrutiger。

Frutigerは、元々フランスのシャルル・ド・ゴール空港のサインに使用する目的で設計された専用書体でした。
1960年代末期に誕生した書体で、「文字が矢印のように明快である」がコンセプトとして掲げられており、遠くから見たときの視認性に優れるように設計されています。
1976年にライノタイプ社から一般販売されてから広く印刷物など様々な場面で使われるようになっていきました。
現在でもサイン表示に採用する例は多く、アムステルダムのスキポール空港や東京メトロの各駅名表示の欧文などに見ることができます。 ※4
Frutigerは従来のHelveticaなどのサンセリフ体に比べ、柔らかな曲線を多用している書体ですが、 特筆するべきはカウンター(Rやgの円形部の中、Cの線の内側など、文字の中に含まれる空間)が広く、特に数字はより強調して取られている点です。
これは遠距離から見たときに文字が潰れて見えづらくなるのを防ぐためです。
つまり、もともとサイン用書体なFrutigerは、悪条件下での視認性が重要視される場面で活躍できるとわかります。
ここから、屋外で大きく表示する必要があり、且つ誤って伝わるとインシデントが発生してしまうような場面では Frutigerに代表される視認性を重視した書体が適任と学べます。
このように書体が生まれた経緯やその設計思想への理解は、場面ごとに適切な書体選定をする手助けになるのです。
バックグラウンドを調べる癖をつけていけば、こういう場合はこの書体が適切だなぁと、ある程度あたりがつけられると思いますし、 逆にここはあえてハズそうといったような応用にも使えます。
メリット2. リスクヘッジができる
二つ目のメリットとして考えられるのはリスクヘッジです。
書体は通常使っているぶんには気づかない、思いも寄らないリスクを抱えてしまったものが少なからず存在します。
言いがかりに近いものや風説の流布によるものもありますが、一度ついてしまった評判はなかなか消えるものではなく、 デザイナーとしてはリスク回避のために一度立ち止まって、本当に適切なのか一度考えたたほうがいい場合もあると思います。
その書体が想定もしていなかったメッセージをアウトプットに付加してしまうのは本意ではないでしょうし、 個人の信条には反していなかったとしても、パブリックな場では無関係ではありません。
事前にこのリスクを察知するには、やはり書体を調べるのが一番です。
政治思想や作者の人格と制作物の関係に話が発展する非常に複雑な問題でもあるので、ここでは例示は控えますが、 一度あなたのいつも使っている書体が作品にネガティブな影響を与える要因になっていないか調べてみるといいかもしれません。 ※5 ※6
頭の中のまとめ
長くなってしまいましたが、以上が私の考える書体の持つバックグラウンドを知るメリットです。
書体は制作物のある種の”顔”を担う重要な要素で、専用の書体を1から開発でもしない限り書体選定は避けられない課題ですので、デザイナーの方は特に業務に際して慎重になる部分かと思います。
そんな中で、書体のバックグラウンドを知る・調べるという方法は前述したメリットを得られるので、選定理由の大きな補強になると思っています。 「こうこうこういう来歴を持つ書体なのでこの制作にはピッタリです」と説明することが可能になり、説得力をもたせることができるからです。いつも自然とやっているという方には釈迦に説法ですが、書体選定に自身がない方はこの機に少し深く書体を知ることに意識を傾けるとうまくいくかもしれません。
書体のバックグラウンドを武器にして、効果的に、且つリスクを抑えて書体を使って行きましょう。
- 参考・引用元 -
※1 米倉明男. “世界中で愛される書体、ヘルベチカとは”. Think IT. 2008/12/15. https://thinkit.co.jp/article/727/1 , (2022/08/04)
※2 山田晃輔. “Akzidenz Grotesk — 歴史のある古典的サンセリフ書体”. フォントブログ Fonts & Typography Blog – since 1998.. 2008/10/01. https://blog.petitboys.com/archives/akzidenz-grotesk.html, (2022/08/04)
※3 ゲイリー・ハストウィット監督. 『ヘルベチカ ~世界を魅了する書』. 2008. 角川エンタテインメント, 2008, (DVD).
※4 小林章. “世界的な書体デザイナーって(1)”. デザインの現場 小林章の「タイプディレクターの眼」. 2009/05/23. https://blog.excite.co.jp/t-director/10294161/ , (2022/08/04)
※5 城下沙緒里. “デザイナーは善き人であるべきか”. 2019/02/24. https://note.com/shiroshitasaori/n/n6d6de1907ab8 , (2022/08/04)
※6 AGYEI ARCHER . “Type Choice, Political Choice”. Typographica. 2019/02/21. https://typographica.org/on-typography/type-choice-political-choice/ , (2022/08/04)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
