
【読書コラム】ハマったゲームの世界に住んでいた記憶って、存在しないはずだけど、たしかに覚えているんだよね問題 - 『かつてそのゲームの世界に住んでいたという記憶はどこから来るのか』郡司ペギオ幸夫(著)
ゲームが好きだ。熱中すると時間が嘘のように溶けていくというか、もはや、ゲームの世界で生きているに等しくなってくる。
最近だとSwitchの『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』がヤバかった。あまりに面白過ぎて、休日は朝から晩まで、ノンストップでプレイしてしまった。さすがに仕事はサボらなかったが、頭の中はハイラルのことでいっぱい。あらゆる業務が疎かになっていた。
どちらが現実かわからなくなっていた。特にゲームの中でご飯を作ったり、労働したり、いろいろな人たちとコミュニケーションをとったりするので、職場と家の往復であくせくしている現実よりも、それはよっぽど現実らしかった。
一応、三人称視点でリンクを操作しているわけで、常にゲームをプレイしている感覚はあったはず。なのに、不思議と、ゼルダの伝説で遊んだ思い出はどれも一人称視点。はっきり言って、わたしはあの世界に住んでいた。
これは自分だけが経験している錯覚なのだと思っていた。しかし、あるとき、ネット上で『かつてそのゲームの世界に住んでいたという記憶はどこから来るのか』というタイトルの本を見つけて、普遍的な現象らしいと驚いた。
著者の郡司ペギオ幸夫は街中を歩いているとき、薄暗い空間に対し、むかし住んでいた場所に似ていると感じたという。でも、そこは人が暮らすような場所ではなくて、なぜ、こうも懐かしい感覚になるのだろうと奇妙さを覚えた。そして、それがかつてハマった『ピクミン』のステージみたいであると気がついて、自分はゲームの世界にノスタルジーを感じていると発見したそうだ。
暮らすって、普通、身体がその場所にいることを意味する。というか、身体がその場所にいなければ、暮らすという状況は成り立たないとされていた。端的に言えば、身体に依存している動詞と思われていた。
ところがゲームの世界で我々は仕事をするし、稼いだお金で衣食住を営み、他者との関わりを楽しむようになることで、意識だけで暮らすことが可能になっている。そして、脳はこの変化を自然と受け入れ、行ったことのない世界で暮らした記憶を形成しているようなのだ。
たぶん、これはゲームだけで止まらない。SNSなどのネット上のやりとりに対しても同じことが言えるはずで、要するに、直接会ったことがなくてもメッセージのやりとりだけで、楽しくおしゃべりした生き生きとした記憶を人間は持ち得てしまう。
実際、わたしはnoteを書く中で、みなさんとコメント欄でやりとりしているけれど、その思い出は1文字2バイトのテキストデータなんかではなくて、もっと楽しい華やかな記憶として認識している。見たことないのに、〇〇さんの笑顔を知っている気がする。聞いたことないのに、◇◇さんの声に元気をもらっている気がする。
そういう意味で、noteの世界にはたくさんの人が実態を伴って存在している。わたしもその一人として、みなさんと実態のある交流を繰り返している。それぞれ、その世界の中でアイデンティティを築き上げ、この人はこういうことを言うんだろうなぁとか、こういうことを考えるんだろうなぁって、傾向もしっかりついている。言わば、これはこれで完結している。
しかし、一方で、noteに記事を投稿しているわたしはnoteの外の世界で生きている。noteに関係なく、日々の生活を送り、いまはそんなに働いてないけれど、最低限度の生活費を稼ぐための労働に勤しむ。このことを細かくnoteに書くことはないから、noteの世界のわたしとは無縁な出来事だけど、わたしという人間を考えるとき、その瑣末な日常は本来なら切っても切れない要素である。
そして、これはわたしだけの話ではない。noteの世界にいるみんなにきっと当てはまる。すべてを書き記すことは不可能だから、必ず、ズレが生じてしまう。ただ、そのズレたものたちだけでも完結した世界が構成できて、わたしたちの意識はそこに現実と変わらないビビッドな記憶を見出せてしまうのだ。
郡司ペギオ幸夫という人はこのことを脳科学や認知科学、人工知能の領域まで拡大しようと考えている。つまり、どんなに学問として確立していたとしても、その完結した世界の外側にもわたしたちがいるとするならば、それだけですべてを語ることはできないと批判である。
どうやら、内側と外側がつながることに価値を置こうとしているらしい。それこそがクリエイティブである、と。
前述の本の中で、Netflix配信中の『ル・ポールのドラァグ・レース』について論じている箇所があり、なるほど、内側で完結すると同時に、外からの視点が入り込む面白さとはこういうことなのかぁ、と思わせる記述があった。
ちなみに、ル・ポールとはアメリカで最も有名なドラァグ・クイーンであり、『ル・ポールのドラァグ・レース』はそんなル・ポールが次世代のドラァグ・クイーンを選抜する勝ち抜き式のリアリティ番組である。
問題・解答の枠組みに留まる競技者として想定されていた者が、人間としてやってくる。そう言いたくなるが、それは正しくない。競技者だけでなく、その人への情報が増え、「わかってくる」のではなく、姑息でいやらしくて、面倒くさいと同時に、人への思いやりや豊かな感受性を持った彼らはレースが進行するほど、「わからない」人間になっていく。情報が増えることはあまわかってくる」ことを意味するのではなく、視聴者である私に、「わからなくてもいい」ことこそがその人を見ることだと思わせてくれるのだ。見せられたものを見るのではなく、見えずわからない部分があることこそを許容し、見えない部分を愛でること。それはまさに、他者と接する態度ではないか。『ル・ポールのドラァグ・レース』は、他者をみるとはどういうことなのか、ということをショーとして切実に実感させてくれる。それこそが、この番組の核心なのである。
わかるとわからないの共存。
本来、矛盾している二つの性質が重なり合っていくところに、郡司ペギオ幸夫は量子力学的なものを感じているらしく、図や公式を使って様々な理論を展開していた。正直、わたしにはあまりに難し過ぎて、その真偽のほどはさっぱり理解できなかったけれど、物事はそう単純じゃないという点だけは頷けた。
わかった気にならない。それが重要なのだと思う。意識というやつはゲームの中に住んでいたという存在しない記憶を作れるほど器用なわけで、油断すると、簡単に完結した世界をでっちあげてしまう。それをもとに正しいと思うことを発言していたら、外の世界から見たとき、大いなる間違いを犯してしまう危険は否定できない。
なにか大きな事件があったとき、ネットで調べた怪しい情報をもとにして、無関係な人や組織を誹謗中傷するケースは後を絶たない。書き込みをする彼ら、彼女らは正義感から攻撃的になっているので、弁護士や警察から連絡が来るまで、自分は正しいことをしていると信じ切っている。
これが正しいと確信を持ったときほど、実は、確信を持てていないのかもしれない。なにせ、外の世界が見えなくなってしまっているんだもの。
ちなみに、ゼルダの伝説中毒となったわたしはラスボスであるガノンドルフを倒し、ハイラルの平和を取り戻すことで、これはゲームなんだと認識し、こちらの世界に戻ってきた。戻ってみれば、あれがCGで作られたものであると俯瞰することもできる。仮に終わりがなかったとしたら、いまも、ハイラルの平原を馬に乗って駆け回っていることだろう。
とはいえ、こちらの世界にしたところで、本当に現実なのかはわからない。水槽に浮かんだ脳が見ている夢でしかないのかも。
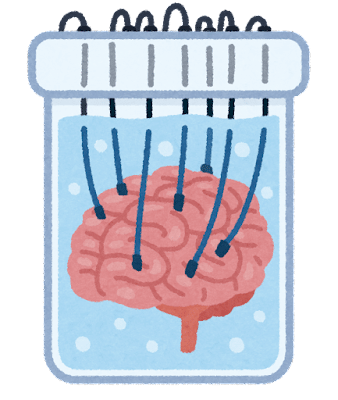
いずれにせよ、外の世界に目を向けよう。完結した世界は完結している故に未完なのだから。
マシュマロやっています。
匿名のメッセージを大募集!
質問、感想、お悩み、
最近あった幸せなこと、
社会に対する憤り、エトセトラ。
ぜひぜひ気楽にお寄せください!!
ブルースカイ始めました。
いまはひたすら孤独で退屈なので、やっている方いたら、ぜひぜひこちらでもつながりましょう!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
