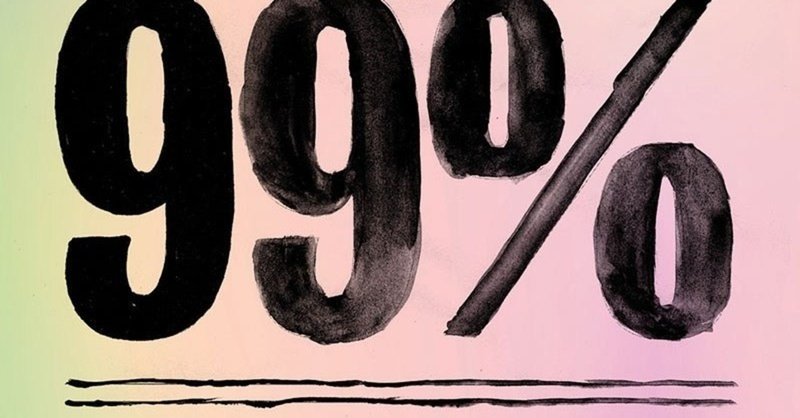
新自由主義と反資本主義『99%のためのフェミニズム宣言』の感想
「もっと女性が働ける場を、女性を経営層に、女性の起業家を」という言葉を見る機会が増えた。私も女性として働く場でマイノリティであることにうんざりしているし、女性の起業家を応援するイベントを企画したり運営に関わってきた。
ゲームのルールを把握してうまく立ち回らなければと思っていながら、何故自分が生きづらい仕組みに最適化しなければいけないのか、という疑問がある。
「フェミニズム」という言葉は実際の生活で語られることは少ない。SNSでこの言葉を書くだけで私を敬遠する人がいる。そういう人がいるから余計にこの概念を深く知りたくなってしまう。
『99%のためのフェミニズム宣言』の冒頭部分にある「支配の機会均等」に加担する/できなければ独立した女性として認められないのかという問いかけが自分の疑問に響いて本を買ってみた。
企業(コーポレート)フェミニスト
「99%」という数字は、2011年の「反ウォール街デモ」での"We are the 99%" のスローガンと関連しており、世界の最富裕層1%、富の82%独占という、ピケティの世界的ベストセラー「21世紀の資本論」で指摘されている格差を表している。
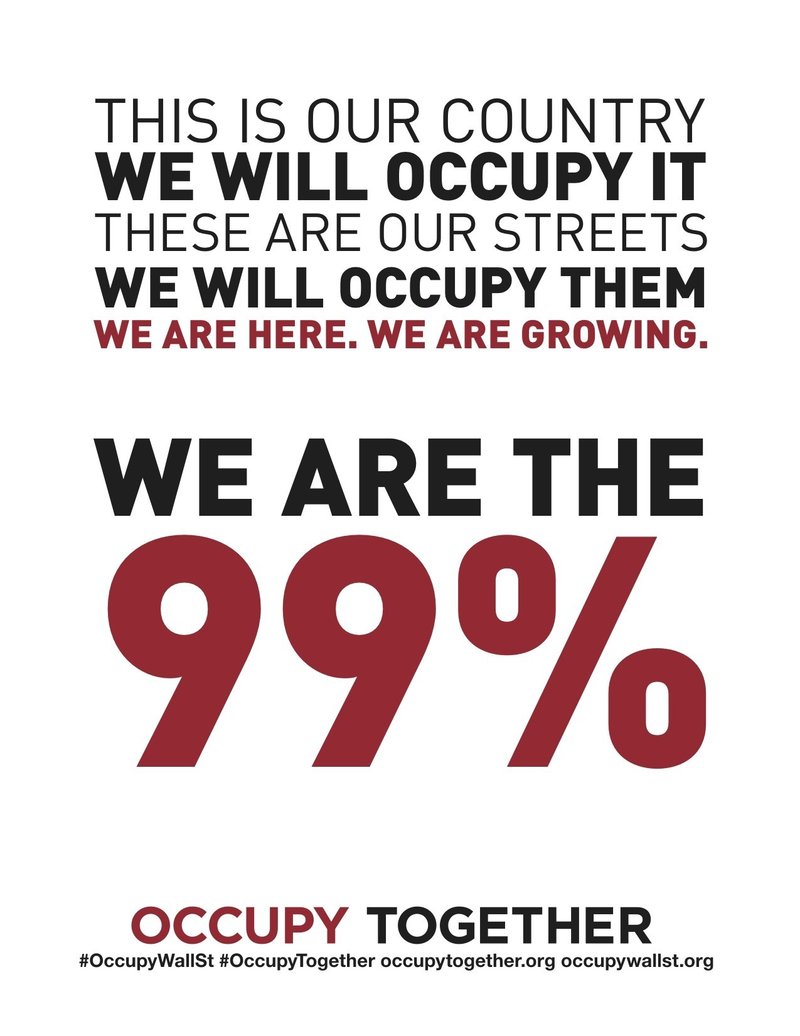
社会的に成功した女性たち(例えばヒラリー・クリントンやFacebookのCOOシェリル・サンドバーグのような)は資本主義の侍女とされ差別に加担する者として批判されている。
女性には不可視の評価されない労働がついてまわる。
それは企業(コーポレート)フェミニズムには含まれない家事、育児、感情労働などのケア。コロナで話題になった「エッセンシャル・ワーカー」の重要な仕事。
「シェアリングエコノミー」「ギグエコノミー」といった、新自由主義が生み出した一見新しい雇用形態は、非正規雇用の多い女性たちが社会保険や労災を受けられない隠蓑になる。
企業フェミニズム(リーン・イン・フェミニズム)は、体制の一員として内部から変化させようというが、平等ではなく能力主義(メリトクラシー)でもともと社会的に優位性のある人しかゲームに参加できない。
企業フェミニズムの実現には、薄給の移民女性に家事やケアを外注する現実がある。
この本では階級や人種を無視して実現されるフェミニズムには矛盾があると強く指摘している。
闘争としてのストライキ
著者たちはInternational Women’s Strike(国際女性ストライキ)の発案者。
国際女性ストライキは女性国際デーと同日に開催し、ポーランドの中絶禁止法案への抗議運動や、アルゼンチンでのフェミサイドへの抗議運動など#NosotrasParamos #WeStrike #VivasNosQueremos #NiUnaMenos #TimesUp #Feminism4the99 など、様々なハッシュタグありの社会運動と連動している。
99%の人々、インターセクショナリティに当てはまる人々である、エッセンシャル・ワーカー、有色人種の女性、先住民族の女性、障害のある女性、移民の女性、イスラム教徒の女性、ユダヤ教徒の女性、レズビアン、クィア、トランス女性と、特権から外れる女性たちに参加を呼びかけている。
For years women in Poland have been in revolt against abortion bans. Last week a full ban was finally passed by the constitutional tribunal. Tens of thousands are blockading the streets. Today they began a general strike. Their tag line: this is war. pic.twitter.com/BGqi0skRUT
— Chloe (@basicflowrrr) October 28, 2020
Marcha #VivasNosQueremos @ValeraNoticia | #28Sept pic.twitter.com/Q0HAh0JqWp
— |Abdiel Bonilla| 🇵🇷 (@AbdielBonillaPR) September 28, 2020
3月8日の女性国際デーは、1904年にニューヨークで女性の参政権を求めるデモとして始まり、世界に伝播していった。
第一次世界大戦中にロシアで行われた女性労働者を中心としたデモも共鳴し、ドイツの社会主義フェミニストのクララ・ツェトキンが「国際女性デー」と名付け、今や世界中の女性、特にラテンアメリカとヨーロッパの女性たちがこの日の運動を守っている。
1975年にアイスランドの女性の約90%が行ったストライキは賃金の公平性を保つ法改正を実現し、今も語り継がれ、ジェンダーギャップ指数で差の無さが例年1位を誇っている。
反資本主義の具体性のなさ
支配構造の再生産に加担する企業(コーポレート)フェミニズムより、「99%」のためのフェミニズムを!というマニフェストは耳ざわりがいい。
ただ、主語が大きい割に反資本主義を掲げる先に機能する実現方法や持続可能性が見えない。
このマニフェストの通り、資本主義からドロップアウトした場合、99%の人が生活を維持できるのか、何も保証がなく蜂起を煽るだけ。
法改正を求めたりする具体性がないので、マニフェストで繰り返される新自由主義批判が若干、陰謀論のような実態の無さを感じた。
先ほどあげたアイスランドの女性たちのストライキは、結局40年以上経って、女性の平均年間雇用収入が男性より30%低いまま、それでもジェンダーギャップ指数ランキングで格差がないとされている。
ただ、資本主義と結託しすぎたフェミニズム批判は納得できる点が多い。
個人の「自己責任」の名の下に「自由な労働」と「賃金契約」で抑圧を合意させるしたたかなシステムは、ジェンダーだけではなく、セクシュアリティを広告の表層に利用し商品化している。
一見マイノリティの進歩のようで「標準的なゲイ」から外れる人々を不可視にしていく。
(以前ピンク・キャピタリズムについて書いたnoteは下記)
内容はアカデミックに寄りすぎず、マルクス主義フェミニズムを基礎にしていて、「人間を育む仕事=社会的再生産労働(Reproductive labor)」や、エコフェミニズムについて書かれているが、事前知識がなくても理解できる書かれ方をしている。
この本に書かれていること全てに素朴に賛同できないものの、階級や人種問題を無視して、資本主義に寄りすぎる現代のフェミニズムへの問題提起として充分読む価値はあった。
サポートされたらペヤング買いだめします
