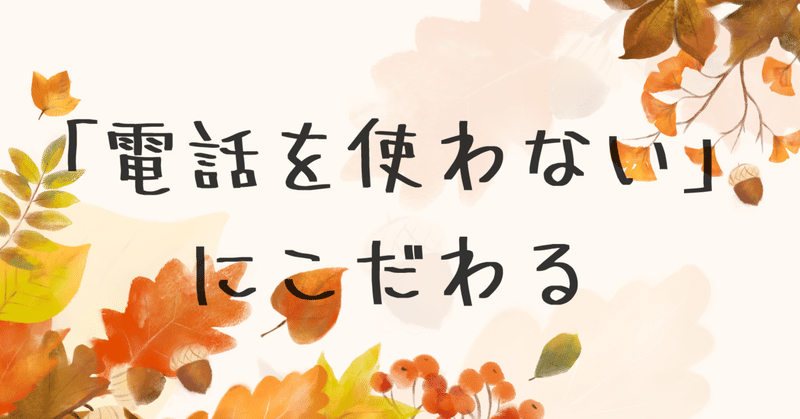
「電話を使わない」にこだわる
音声版はこちら
電話(音声通話)は、なるべく使いたくありません。
理由はいろいろありますが、一番大きいのは、一方的に相手の時間を奪う、自己中なツールだと思っているからです。
電話は、かける側にとっては都合がいい道具です。
例えば、何か聞きたいことがあったときに、即時に質問しその場で回答をもらうことができます。メールやチャットを書く手間も必要なく、言いたいことが整理されていなくても、大体のニュアンスを相手がくみ取ってくれて意思疎通が図れる可能性が高くなります。
一方、受ける側にとっては非常に労力がかかります。
まず、いつかかってくるかわからず、かかってきたら何をしていても最優先で電話に出なければなりません。
食事していても、昼寝していても、関係なしです。もちろん、出れる状況でなければ出ないで折り返すことになりますが、「電話にでれずすみません」という立場になるのが違和感があります。(個人的には、電話をかけてくるほうが悪い、と思っているのですが)
「同期」状態でのコミュニケーションをする必要があるか
少し理屈っぽく考えますが、電話は「情報をやり取りする手段」の中の一つであり、ほかには以下のようなものがあります。
=同期ツール=
・オンライン会議
・電話
・直接会って話す
=非同期ツール(有形)=
・紙の文書
・FAX
=非同期ツール(無形)=
・動画録画して共有
・音声録音して共有
・メール
・チャット
・文書ファイル(PDF、エクセル、ワード、など)
情報のやり取りにおいては、可能な限り「非同期」かつ「無形」のツールを使う、ということが望ましいです。
非同期情報であれば、相手の都合がよい時に読む、聞くなどの方法で情報を把握することができます。
そのうえで、非同期ツールよりも効率的・効果的にコミュニケーションを行うことができるときに限り、同期ツールを使います。
顔合わせ、会議、ブレインストーミング、などが一例かと思います。
電話やオンライン会議をするときは、必ず、事前に目的を伝えたうえでアポイントメント(行う時間の決定)を取ります。チャットでやり取りしているときに、明らかに相手が電話に出れそうなときは、「いまちょっと電話いいですか?」といって、電話することはありますが。
つまり、「非同期ツール」で限界が来た時にはじめて「同期ツール」を使うということです。
電話を取らないためにやっていること
電話の弱点は、番号が知られていると、私を知らない人が誰でも、いつでもかけてくることができる、という点です。
したがって、可能な限り、電話番号を公開しないようにしています。
HP、名刺、メールの署名などには当然記載しません。
また、税理士会が運営する公式の税理士検索サイトというがあるのですが、申出をすると電話番号を非掲載にすることができます。

また、どうしても電話番号を伝えなければならないときがあります。
そのため、電話は常に留守電設定にしており、自分で録音したアナウンスを流すようにしています。
特に独立した当初は、税理士関連サービスの企業から、かなりたくさんの営業電話がかかってきます(Xを見る限りですが)。
それらに今のところ、一度も応対せずに済んでいます。
ちなみにDMも山ほど来ますが、すぐに捨てればよいのでそれほどストレスは感じません。
どうすれば生産性を高められるか
顧客の生産性を高める、と謳っている事務所が、電話でいたずらに経営者の方の時間を奪うようなことはポリシーに反しますのであり得ません。
デジタルツールを使うことで、非同期でもかなり効率的に情報伝達をすることが可能になっています。
例えば、エクセルをスプレッドシートに置き換えていくことで、常に最新のデータに全員がアクセスできますし、データの送受信も不要になります。
ちょっとしたツールの使い方をレクチャーするときは、画面操作+音声を録画・録音し、そのデータをシェアしてみてもらっています。
少し複雑だけどわざわざ打合せするほどのことではない、という程度の情報やり取りに重宝しています。
生産性を高めるためには、新しいツールを取り入れていくことは不可欠です。AIなどもどんどん性能が上がっていくと思いますので、今後も日々研鑽していければと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
