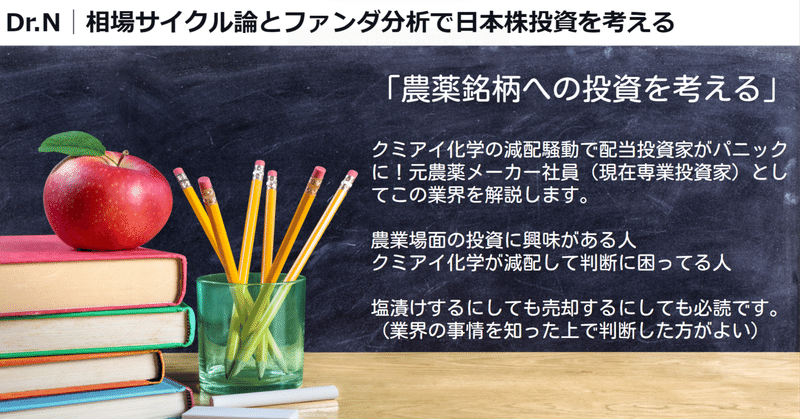
農薬銘柄への投資を考える
2023/12/16
先日のクミアイ化学(4996)の減配ニュースを受け、SNS界隈では嘆きの声がかなり多く聴こえます。また、同じく農薬事業も手掛けている住友化学(4005)も同時にトレンド入りしていましたね。
私は今でこそ専業投資家ですが、会社員時代は日本農業の最前線(北海道)で農薬業界に11年務めていました。元農薬業界の人間として投資家の皆さんに提供できる業界の話は非常に沢山あるのです。
農業場面の投資に興味がある人、クミアイ化学の株を買って今後どうしようか迷っている人にはぜひ読んでほしい内容になっていますので、ぜひ最後までお付き合いください。
1.農薬の市場規模
会社を辞めてから細かい数字は把握していませんが、調べてみると
世界市場:約2350億ドル(2023年)
日本市場:約3400~3500億円市場(ドル換算すると24億ドルくらいか)
これが最近の市場規模の様です。世界からすると日本は1/100くらいしか市場が無いようです。ちなみに私が活動していた北海道は、ご想像通り国内では大きな市場ですが、その金額は400億円くらいと言われていました。実際はもっとありそうな気もしますが、それでも日本市場の10~15%くらいの範囲でしょうか。
私が入社した当初は「国内は豆腐業界と同じくらいの市場規模」と教わった記憶があります(真偽は定かではありませんが)。金額を見るだけでも、農薬メーカーにとって海外市場がいかに重要であるかがわかると思います。また、後で説明しますが、様々な理由から国内市場には成長の余地も殆どありません。企業姿勢として海外展開をどう考えているかも重要となります。
2.投資家として農薬ビジネスをどう見るか
クミアイ化学は今年の中盤頃から配当株投資の対象として話題になりました。配当持続性が良い、農薬専業の化学メーカーということで「農業場面は手堅いのでは?」という意見がXでもよく見られました。しかし、業界に居た人間からすると、先に述べた様に「成長性が小さくジリ貧」というのが私の意見です。
何故なら、メーカー各社はこの小さな市場を奪い合っているわけですが、はっきり言ってどの企業も労力に見合った利益を出せていないからです。言ってしまえば、これは旧時代(デフレ時代)を代表するビジネスモデルです。市場が限られている、または縮小している分野に投資をしてもリターンは大きくなりません。投資家目線では、市場自体が拡大している分野の方が遥かに投資しやすいのです。
こういった点から、農薬ビジネスはここ10年以上向かい風の中にいる状況です。投資家目線では間違いなく難易度の高い分野です。
補足
市場が縮小している理由は、シンプルに耕作面積が減少していることが挙げられます。後継者不足の割に利権の問題もあって法人は農業に参加しにくいのも問題です。更に良し悪しはどうあれ、世界中で農薬の使用量は減らしていく方針に傾いています。
3.農薬業界の複雑な販路
農薬業界の販路は独特です。販路は大きく2つあります。
①全農(北海道はホクレン) ⇒ JA ⇒ 生産者 という系統ルート
②全農を通さずJAに卸したり、生産者に直売する商系ルート
全農やJAを通すか否かが大きな違いです。JA側からすると、②のルートで販売する業者、特に直売業者は敵対勢力となります。
クミアイ化学は①の系統ルートでしかビジネスをしていません。住友化学などは②のルートも持っています。何故①のルートしか持たないのか。直売もした方が儲かるのではないか、という疑問を持つ人もいるでしょう。これは資本関係の問題も背景にある(全農が筆頭株主)と思いますが、系統ルートの安定感というメリットも大きいのです。ある程度決まった売上を維持出来るし、自社で代金回収もしなくてよいので人件費も制御できます。
そして何より、系統ルートを販路に持つ企業は少数なのです。簡単に言えばライバルが少ない。大きな市場である北海道でも、系統ルートで販売しているのは3社しかありません。商系ルートは小さな商店も含めると把握しきれないほどの数があります。私が勤めていた企業もこの3社の内の一つで、残る一社は北興化学(4992)です。この会社はスタンダード市場に上場しています。こちらの会社はアルツハイマーウイルスのワクチンでも注目されました。私が勤めていた会社は北海道でしか活動していませんが、替わりに本州では協友アグリ(非上場かな?)という会社が系統ルートに属していますので、やはり3社体制です。ちなみにこの会社の株主にも全農がいますし、住友化学や石原産業(4028)もいます。
先ほど、北海道の農薬市場は約400億円だと書きました。そのうち約200億円が系統ルートからの販売で、これを3社で競争しつつも確保している状態です。もう半分の200億円市場は、他に数多く存在する商系企業で競い合っています。ライバルの少なさは業績の安定に直結します。どう見ても安定感としては系統ルートに軍配が上がります。ただし、安定感はあっても、市場自体が縮小傾向にある時点で系統も商系も国内における売り上げや営業利益が飛躍的に成長することはまず期待出来ないのが事実です。
4.農薬ビジネスの難しい点① 協力関係と敵対関係の乱立
クミアイ化学をはじめ、大きい会社は農薬の有効成分(「原体」といいます)を自社開発しています。風邪薬なども同様ですが、農薬も有効成分の組み合わせで新製品が作られていきます。例えばクミアイ化学の製品である「キタシーブ」という除草剤は、ピロキサスルホンとジフルフェニカンという2つの有効成分が配合されています。ピロキサスルホンはクミアイ化学の持つ有効成分で、ジフルフェニカンはバイエルクロップサイエンスが持つ有効成分です。それぞれの有効成分が得意な雑草は異なるため、他社の有効成分と組み合わせて製品が作られます。
ここからが更に複雑な話です。他社と一緒に新製品を拡売していくという点において両社は協力関係にあります。お互いに自社の有効成分が入った薬が売れればOKですからね。
しかし、バイエルは自社の有効成分ジフルフェニカンと他のメーカー(仮にA社とします)の有効成分で組んだ製品も持っているので、A社とクミアイ化学は競合関係となります。バイエルとしてはどちらの製品が売れても自社の有効成分の売り上げは伸びるので問題はありません。
しかし、例えば殺虫剤などの別の分野ではクミアイ化学とA社が組んでいる製品もあるわけです。この様に、例えば水稲の除草剤場面では協力し合うけど、かぼちゃの殺虫剤場面では敵同士…の様なことがメーカー間では当たり前のようにあるのです。新しい分野の市場を取りに行ったらそっちの利益は増えたけど、別の分野の市場で組んでたメーカーとは敵対関係になったから不仲になってその分利益が減った、なんてこともあります。これが利益を大きくしにくい背景の一つでもあります。
有効成分を開発する際は、とにかく他のメーカーから「ウチと組んでほしい!」と言われるようなものを開発して、その薬が効かなくなるまで安定的な売り上げを期待するしかありません。他社と組むことが前提になるので、ニュースサイトを見て「クミアイ化学から新規有効成分が登場!こんな雑草に期待されています!」という情報だけでは投資判断には足りないのです。その成分がどのメーカーのどの有効成分と組んでどの販路で拡売出来そうなのか。ここまで見ないと本当に利益が増加するかは見えてきません。おそらく、業界を知っている投資家でない限りはこのあたりの事情は調べてもピンと来ないでしょう。
5.農薬ビジネスの難しい点② 開発難易度と耐性
もう一つ投資判断が難しい点があります。よく「バイオベンチャー株は宝くじみたいなもの」と言われることがありますが、農薬の開発もこれに近い性質があります。有効成分の開発は、数ある化学物質から研究者が数年かけて探し出す必要があるのです。当然、研究員の人件費も膨大になるわけで、最悪何も見つけられないこともある。偶然使えそうな化学物質を見出したとして、今度は安全性等の厳しい試験各種が待ち構えている。これを全て終えるにも数年を要します。
これも乗り越えていよいよ発売されたとしても、早いものだと3年程度で雑草(病気も虫も同様だが)側に耐性が付いて効かなくなってしまうこともあります。大抵の場合、すごく良く効く薬ほど早くに耐性が付いてしまうのです。
最近話題の「トコジラミ」には合成ピレスロイドという成分に耐性が付いて効かなくなっています。何故耐性が出来てしまうのか?これは遺伝子の交換が人間よりも虫や菌の方が早いからです。遺伝子の交換とは、言い換えると世代交替のことです。人にもよりますが、人間は生まれてからだいたい20~30年すると結婚、出産をして次の世代へ遺伝子を引き継ぐわけですが、虫や菌は違います。1年の間に数世代に渡り遺伝子を引き継ぐものも存在します。第一世代には良く効いた合成ピレスロイドも、個体差などによって生き残ったものが繁殖して第二世代を形成する。この第二世代は合成ピレスロイドに強い遺伝子をもった奴らの子孫なので、当然薬が効きにくくなる。こうして農薬は効かなくなっていくのです。
有効成分を開発出来る大きな会社でもこういったリスクを抱え続けています。だから尚更海外展開は重要となります。日本で効かなくなった有効成分も、海外ではまだ効く可能性はあるからです。「海外展開の考え方がどうか」という点は、農薬メーカーに投資してもよいかどうかの判断材料の一つになります。
こういった投資リスクを低減させたいなら、そのメーカーが農薬専業なのか、総合化学メーカーで農薬部門は事業の一つでしかないのかも注目した方がよいでしょう。クミアイ化学は専業メーカーだが、住友化学や三井化学、日本曹達などの総合化学メーカーにとって農薬は部門の一つでしかなく、半導体など他の部門を抱えているので、先に挙げた農薬業界特有のリスクで利益が急落する可能性は低減され得るのです。
まとめ
〇国内の農薬市場は縮小傾向であり、海外展開が重要となる。
〇国内の販路や新製品開発の事情は複雑で、開発には博打要素も強い。
世間の流れも影響して農薬業界ははっきり言って斜陽産業になりつつあることは認めざるを得ないでしょう。無くなることはない業界かもしれないが、急成長する分野ではない。その点において、簡単に投資のリターンを得られる分野でないことは明言しておきます。
また、JAの在り方が前時代的であるという批判も年々強くなっているわけで、系統ルートや商系ルートいった販路の在り方も変わってくる可能性もあります。これらを踏まえて投資の可否を決めるとよいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
