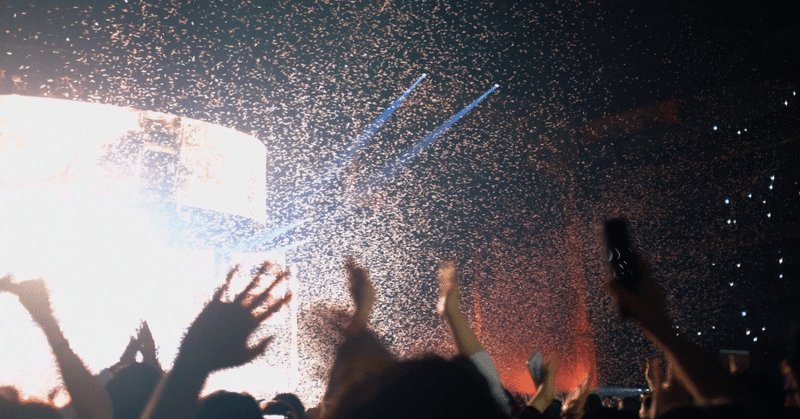
【コラム】フレディ亡きあとのクイーンは歩みを止めるべきなのか?──QAL東京公演直前に考える
2023年を締めくくる紅白歌合戦に出てきたQALは、なんか、凄かった。そりゃまあYouTubeだけでも9億回再生されてる曲を、半世紀ものキャリアを第一線で走り続けるバンドが、彼らの選んだ最高のヴォーカリストと一緒に披露しているのだ。なんかもう航空ショーを見ていたら突如巨大UFOが出現してただ通り過ぎて行ったみたいな感じだった。SNSで感想を眺めていても「凄すぎてわけわからん」みたいな感じだったので、多分UFO見た時の人間の反応と同じだと思う。
さて、QALの活動が報じられるたびにSNSでは「フロントマン亡き後、バンドが新たなフロントマンを迎えて活動することの是非」が議論される。
で、その議論の筆頭に挙がるのがQAL、つまりフレディ・マーキュリー亡き後のクイーンと、若き(とはいってももう42歳)アダム・ランバートのコラボバンドの存在である。
まあ、議論が起こること自体は当然だし、ブライアンやロジャーにしても承知の上だろう。結局こういうのは個人の好みの問題なので、誹謗中傷にならない限り批判したい人は批判すればいいと思う。
ただ、ちょっと言わせていただきたい。クイーンは過去の伝説などではない。2024年現在も「最高」を更新し続ける、最強のバンドなのだ、と。
まず、音楽的に言えばクイーンは必ずしも「フレディ・マーキュリーの音楽性を中心としたバンド」ではない。フレディがいなかったらクイーンはビッグなバンドになってなかったと思うけど、そこは逆もまた然り。ソロ歌手としてのフレディが成功してたかと言われると、そこは議論が分かれるところであろう。
フレディはバンドの“顔”としてこれ以上ない存在であり、“クイーンらしさ”の概念的部分を担っている。しかしコーラスやアレンジなどのクイーン的理論面、そしてサウンドといった“骨格”部分はブライアンの貢献が大きい。実際、今でこそフレディの存在が伝説的に語られるクイーンだが、当時の売りは圧倒的なヴォーカル&唯一無二のギターサウンドの2本軸だった。
ロジャーとジョンにしても、いわゆるキース・ムーンやジョン・エントウィッスル系の派手な個性派ではないものの、それぞれ特徴が強い。特にロジャーのドラムは高音域における独特の華やかさがよく話題に挙がる。
そしてフレディが顔、ブライアンが骨格、ロジャーとジョンが血肉を担うならば、クイーンの精神と心臓とは「楽曲」だろう。メンバー全員が作詞・作曲するバンドは数あれど、全員がここまでのヒット曲を書いているバンドはなかなか無い。クイーンの楽曲はドラマチックかつキャッチー、ポップなのにゴージャス。聴く人を選ばないけれど、単純というわけでもない。バンドにビジュアル派や技術派などの分類があるならば、オリジナルメンバーの4人が作り上げたクイーンはかなり「楽曲派」のバンドである。
バンドメンバーの入れ替えが激しい洋楽界においてオリジナルメンバーの4人で活動することにこだわったクイーンは、フレディという巨大な個性を喪い、そしてジョンが音楽業界を引退したことにより、バンドとしての歩みを止めたかに思えた。一時期はポール・ロジャースとのコラボツアーを行っていたものの、あまり長続きはせず。やはりクイーンほどのバンドでは、コラボという形だとしても“別のメンバー”を舞台に立たせることは難しいのだろう。
しかしここに、アダム・ランバートという個性がピタっとはまった。
アダムとフレディは、全く違う声質のヴォーカリストである。フレディは鋭く直進的でどこかエキゾチック、アダムは演劇的にドラマチックで包み込むような声質を持つ。
それでもロジャーとブライアンは、アダムを選んだ。私が思うに理由は3つあると思う。
ひとつは「フレディと全く似ていない」ところ。
フレディと似てるヴォーカルを探すだけなら候補はいっぱいいる。かの有名なマーク・マーテルはもちろん、世界一と呼ばれるコピーバンドGOD SAVE THE QUEENのヴォーカルは容姿も含めてかなり良い感じで、映画『ボヘミアン・ラプソディ』の主演探しの際にファンから名が挙がったほどである。
しかしフレディと似た声のヴォーカリストを選ぶと、観客は無意識に「フレディとの違い」を探し、それによって優劣をつけてしまう。双子やモノマネ芸人を見ているとき、似てる部分よりも似てない部分が気になるのと同じことだ。「やっぱ似てないしフレディより下手だな」と思われてしまえば、もうおしまい。その観客は二度とライブに足を運ばなくなるだろう。
それに何より、オリジナルメンバーがそっくりさんと“クイーン”を名乗ってショーをやるのは、単発企画ならともかく、なんか、違う。
次の理由は「フレディと共通点がある」ところ。さっそく前項と矛盾しているが、ちょっとツッコまずに聞いてほしい。
フレディとアダムの歌声には共通する点がある。それは「歓喜に満ち、すべての弱い者の声を代弁するような歌声であること」だ。
何度も音楽性を転換させ、多種多様な楽曲を持つクイーンだが、「リスナーのために音楽を作りたい」という想いは一貫している。クイーンはお客様視点でステージを演じ、求められるものを与えようとするバンド。福利厚生に厚いのである。
そんなクイーンの楽曲は、いつでもリスナーの幸福のためにある。それを最もうまく表現できるのが、歓喜に満ち溢れてスタジアムの隅々まで届くフレディの歌声だったわけだ。
そしてアダムの歌声にもまた、歓びが詰まっている。さらに歌声とパフォーマンスの向かう先は常にリスナーへと向けられており、最も弱い者を包み込むような歌い方をする。
端的に言えば、フレディとアダムはどちらも「外向きのベクトル」を持つ歌手である。自らの心の内で感情をじっくり噛み砕くタイプではなく、腹の底から湧き出る音楽をそのまま放出するタイプ。これがクイーンの楽曲にバッチリはまったのだろう。
アダムが出演し注目を浴びたオーディション番組『アメリカン・アイドル』決勝戦での両者の歌声を聴き比べると、その“外向きのベクトル”がいかにクイーンの楽曲と合うかがよくわかる。後攻のアダムが歌い出した途端に“音楽が花開く”感覚は、フレディの歌声のそれと近い。
ちなみにこの決勝戦、声質的には対戦者のクリス・アレンのほうがむしろフレディに似てるのも面白いところである。
最後の理由は、「有名になった時点でアダムのキャリアがあまりなかったこと」。あんまり語られることはないポイントだが、私的にはこれが結構デカかったんじゃないかと思っている。
全てのバンドには、どこかに「魂の置き場」がある。ギャラガー兄弟のいないオアシスが無いならば、オアシスの魂の置き場はあの兄弟。ジョン・ボーナムを喪ったレッド・ツェッペリンが解散を選んだのは、彼らの魂の置き場が“4人の個性”だから。トニー・アイオミ以外全員メンバーが変わってもブラックサバスが存続したのは、魂の置き場がアイオミのギターとリフにあるからだろう。
それでは、クイーンの「魂の置き場」は何処か。私はこれを「ナラティブ(物語性)」だと思っている。
映画『ボヘミアン・ラプソディ』が公開されたとき、作品から初めてクイーンに触れた多くの方がクイーンの持つ物語性、キャラクター性に驚愕した。そりゃそうだ。異国の地から飛来し、とてつもない歌声で世界を揺るがせたヴォーカリスト。廃材からギターを自作する天文学者のギタリスト。甘いマスクにロックンロール魂を秘めて超高音のコーラスをこなすドラマー。柔和な雰囲気ながら名曲を書き続け機材をも自作するベーシスト。容姿も端麗ながら、全員“バンドメンバー”としてキャラが立ち過ぎている。
そんな4人のバンドは紆余曲折を乗り越えて数え切れない名曲と幾つもの伝説を残し、ライブ・エイドという大舞台で「時代遅れ」の烙印からの華麗なる復活を果たして、フレディの死をもバンドの物語のひとつとして歩んできた。
だって考えても見てほしい。ラストアルバムに『イニュエンドウ』を作り、そのラストナンバーで「ショウ・マスト・ゴー・オン」を歌い切るバンドは、あまりに“物語的”すぎやしないだろうか。
たぶん『イニュエンドウ』は、もとよりフレディの遺作として制作されたアルバムである。なぜなら楽曲内容から構成から、あまりに“偉大なるロックスターの遺作”として計算されすぎているからだ。そしてそれはきっと、フレディとクイーンの徹底した“バンドとしての物語を作る姿勢”のあらわれなのだろう。
己の死をもバンドの歴史の中に刻んだフレディに、メンバーたちはアルバム『メイド・イン・ヘヴン』を返す。そして遺された3人でのクイーンは、「ノー・ワン・バット・ユー」という名曲でひとつの幕を下ろした。以降、ジョンはステージに姿を現していない。
改めて振り返るとクイーンは凄まじい物語性を持つバンドである。
そんな彼らが新たなヴォーカリストを迎えることには、ひとつの大きな壁があった。それは「バンドの物語性が凄まじすぎる」ところ。
フレディがステージから去ったあとも、クイーンが世界トップレベルのバンドであることは変わらない。だからこそ、そのサウンドをバックに歌えるヴォーカリストは大物に限られてくるわけだが、それほどの大物は「そのひと自身の物語」を持っている。だからこそ特別ゲスト感がぬぐえないのだろう。
たとえばフレディ・マーキュリー追悼コンサートを見てほしい。出演者は全員超一流どころではない大物ばかりだが、クイーンのメンバーとは壁がある。彼らはいわば“別の家族同士”なのだ。隣町に住むレッド・ツェッペリン家の長男ロバートくんが、クイーン家の3兄弟と一緒に演奏してるみたいなことである。これは後年のクイーン+ポール・ロジャースでも同様の感覚がぬぐえなかった。
名演と言われるジョージ・マイケルの「愛にすべてを」にも、“彼が歌うことにより付加される物語”がある。
その問題を「バンドと共に物語を積み上げる存在」としてのアダム・ランバートが打ち破った。
アダムはクイーンを聴いて育ち、まだ無名だった頃にオーディション番組の予選で「ボヘミアン・ラプソディ」を歌った青年。あのときのアダムは、“クイーンのリスナーのひとり”であり、“ここからロジャーやブライアンと共に新たな物語を積み上げられる、まっさらな存在”でもあった。
(※とはいえこれはメジャーシーンでのキャリアに限ったことで、『アメリカン・アイドル』出演時点でアダムは業界の注目株だったことには留意されたい)
そしてQALは、フレディを讃えながらもまったく新しい歴史を歩み始める。アダムは歌唱力・パフォーマンス・ビジュアルともに申し分なし、当時のアメリカではスキャンダラスに伝えられた性的指向に関しては、クイーンにとって何の問題にもならない。というかそんなことがスキャンダルになるほうがおかしいのだ。
ミュージカルの畑で育ち、演劇的指向が強いアダムはドラマチックな歌声を持ちつつも己の主義主張を強く感じさせないという傾向も持つ。それもまた、クイーンの“リスナーのための音楽”とよく合っている。
当初はフレディと比較されていたアダムであったが、今となっては批判的なリスナーさえも「フレディはフレディ、アダムはアダム。比較するものではなく違うもの」と言う。それはひとえに批判者をも黙らせるアダムの歌唱力がなせる業であり、オリジナルメンバーのふたりが「今ステージに立つアダムと共に新しい物語を作っていくこと」と向き合った結果であると思う。
というかQAL、よくよく考えてみると批判の隙があんまり無いコラボバンドなのだ。もともと超絶技巧派ではないということもあってロジャーとブライアンは演奏面での衰えが少なく、サポートメンバーの技術は高い。アダムは音程・音域・声量・表現力すべてにおいて文句のつけどころナシ。ダンディでグラマラス、そしてプリティなパフォーマンスはフレディも大いに気に入りそうだ。
楽曲についてはフレディがステージで披露できなかった後期のものも歌うし、スクリーンにはフレディやジョンの笑顔も映る。ジョンの姿は無いけれど、彼は楽曲歌唱を許可している。これは「オリジナル・クイーン」と「QAL」を同時に成立させている見事な演出である。
「バンドの持つ物語性とアイデンティティ的に、オリジナルメンバー以外が入ったクイーン、4人揃っていないクイーンはクイーンと認められない」は真っ当な批判ではあるが、そのほかはほとんど好みの領域だ。そりゃあアダムが苦手な人はいるだろう。好みは仕方がないことだ。私もタイ料理大好きだがパクチー大嫌いなので、ライブに行って文句を言う気持は正直わかってしまう。
だから願わくば、アーティストや気分よく楽しむファンには聞こえぬようにコッソリ批判してほしい。私もパクチー、噛まずに飲み込んでるから。
近年、QALのパフォーマンスはますます豪勢になっている。最新鋭の舞台装置を持ち込んで世界中を駆け回り、ド派手な演出で会場の隅々までをも楽しませる様は、まさに“今を生きるバンド”。「ロジャーもブライアンも老齢なのだから、もっと年相応の活動をしてほしい」と願う声もあるにはあるが、ロジャーとブライアンからすれば身体が動く限り最先端のものを試したい気持ちがあるんだと思う。子世代のヴォーカリストと組むのは、高齢のミュージシャンが最先端の演出に見合うエネルギーを保ち続けるという意味でも最良の選択肢である。
あと、フレディが生きていたら、クイーンのステージ演出は年相応に落ち着くどころか、もっともっとド派手になっていたと思う。
偉大なるフレディ・マーキュリーは、もうステージのどこにもいない。高画質のビジョンを通して一瞬だけその姿を見せるのみだ。
しかし彼の“魂”は、客席を埋めつくす観客たちの中にある。メロディを聞いて懐かしみ、世界最高峰のヴォーカリストの歌声に酔いしれながらも、心のどこかにフレディのいない寂しさを想い、帰り道でなんとなしに古い音源を聴きたくなる。
その瞬間にこそ、アーティストの“魂”は存在する。人としての生を終えても、思い続ける人がいる限りアーティストの魂はそこにある。たとえメンバー全員がこの世を去っても、バンドが消滅することはない。
そこにいなくてもいるひとがいる。心の中にいるその人に会うために、今ここに生きているひとに会いに行く。そしてアーティストが遺した贈り物を全身に浴びて、みんなの心の中に住み着いたそのひとと手を取り合い、今ここで生きている人と共に思いっきり歌って、ただただ幸せになって帰る。ベッドに入って、眠りに落ちるその前に、思い出の音源をひとつ聴く。メンバーを亡くしたバンドのライブに行くことって、そういうことなんだと思う。
2024年現在のQALは、間違いなく“世界最強”のバンドである。会場に行ってみればわかるが、あれはオリジナル・クイーンと比較できるものではない。ベクトルと物語性が全く別物なのだ。
しかし、だからこそ、フレディとジョンの“不在の在”もひときわ輝く。「オリジナルの4人のほうがいい」なんていう好みの問題ではなくて、QALを聞けば、フレディとジョンがいるオリジナルクイーンの音の特徴がよりはっきりと聞こえるようになる。
そしてQALは、フレディとジョンを「過去の存在」にはしない。ふたりは輝ける日々の記憶の中にとどまらず、今も変わらず共にある者。そうわかる演出が随所に散りばめられたライブは、ひとつの壮大な舞台作品を眺めているようでもある。
2月初めから続いた日本ツアーも、残すところ東京ドーム2公演。「フレディとジョンがいないし……」「アダム・ランバートのことよく知らないし……」と思って行かないのはあまりにもったいない。クイーンが、そして彼らが選んだアダム・ランバートが作るライブは“すべての人を楽しませるためのステージ”だ。
その“すべての人”の中には、もちろんあなたも含まれている。
Text:安藤さやか
記事を気に入っていただけましたら、こちらから安藤にCD代やごはん代を奢れます。よろしければよろしくお願いします。
