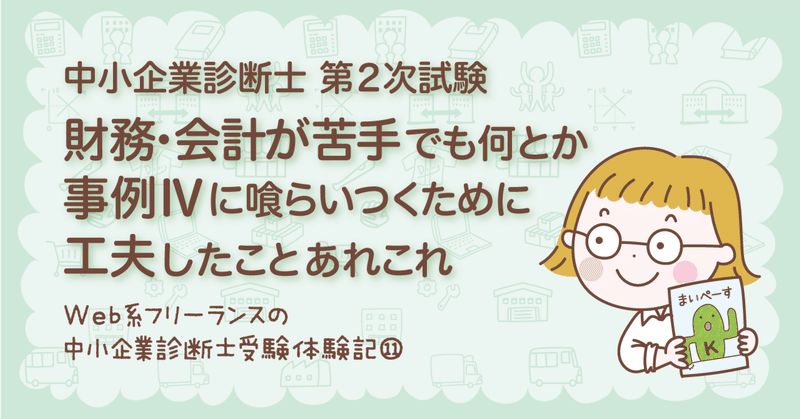
財務・会計が苦手でも事例Ⅳに喰らい付くための工夫(中小企業診断士2次試験)《第11話》
早いものでもうGWがやってきました。
本年度のストレート合格を狙う人は、2次試験の問題がどんなものかGW中に1度くらいはちらっと見ておくことをおすすめします。まだ全然解けなくても大丈夫です。
私の令和4年度中小企業診断士試験 2次筆記の得点は、結果的に事例1〜3がギリギリ61〜62点、事例Ⅳが78点での合格でした。(詳しくは連載第2話をお読みください。)しかし、この事例Ⅳの得点はほとんどの受験生が全然解けていなかったことによる得点調整の結果であり、素点では良くて半分というところでしょう。決して財務・会計が得意だったわけではありません。事前知識も乏しく、学生時代も計算が苦手で、全科目の中では圧倒的に苦手分野でした。
なので、学習にあたっては「事例Ⅳで足を引っ張らないようにする」というのを最重要課題に設定していました。
その課題のもと、どんな工夫をしていったのかを紹介します。
この記事の対象読者は、財務・会計に苦手意識がある方です。FPや会計系の資格持ってるとか、仕事で普段から財務に覚えがあるという方はスルーしてください。
※本記事内の書籍販売ページへのリンクはアフィリエイトを含みます
基本は過去問と論点別問題集
おそらく苦手な人は、いきなり事例Ⅳの過去問を解いても全く歯が立たず、心が折れてしまいます。2時間以上かかっても終わらず涙が出てくるかもしれません。本格的に過去問に取り組む前に、論点別の問題集で基礎固めから始めることをおすすめします。
以前の記事に書いたとおり、私は早稲田出版の『TBC速修2次テキスト』の演習パートに加え、TAC出版の『事例Ⅳの解き方』を1周して頻出論点の基礎を固め、その後も過去問と並行して2周・3周と演習問題を解き直していました。

私は使いませんでしたが、同友館の『30日完成』を使っていた人も多かったようです。『事例Ⅳの解き方』か『30日完成』、どちらかをやれば良いと思います。ストレートで時間がない人や苦手な人には『イケカコ』は不要です。
令和6年度向けに、第2版が出ていました。これから購入するならこちらをどうぞ。
経営分析に時間がかかるとお悩みの方へ
「第1問(経営分析)に何分かけるべきか?」
これは意見が分かれるところだと思いますが、プロセスを短縮できるに越したことはありません。
私が拠り所としていた『TBC速修2次テキスト』には目標時間として「30分以内」と記載されていましたが、講義動画では「できれば20分をきりたい」という話でした。自分も過去問では20分をきることを目標にするも、当初は30分以上かかってしまい、なかなか短縮できないことが悩みでした。
理想は、与件文からD社の特徴を見極め、そこから指摘する指標のあたりをつけてから必要なものだけ計算する、という流れです。しかし、勉強を始めたばかりでそんな美しい解き方なんてできるはずがありません。
結局、主要な指標約12個を全部計算してから特徴のあるものを指摘するほうが試験的には低リスクです。そのやり方も試してみたのですが、どうしても時間がかかりすぎてしまい、どうしたものかと困っていました。
いろいろな経営分析の解き方を模索している中で、最終的にこちらのブログで紹介している「比率を使って優劣判断」という方法に落ち着きました。
苦手な人は時間をかけてよい
ただし、このブログでは「10分以内」と書いていますが、10分というのは事例Ⅳで高得点を狙って他事例の苦手を補いたい戦略の人向けだと思います。計算苦手な人が、経営分析で「10分以内」を目指すことは非推奨です!
計算問題が苦手な人ほど、経営分析と記述問題で確実に得点することが必要です。指標の選択と計算時間を短縮できたとしても、焦ってミスをしたら逆効果ですし、記述部分もある程度ちゃんと練るべきだと思います。
特に令和4年度のようにいきなり「生産性指標」という過去問にない問われ方をされた場合、練習よりも確実に時間がかかります。変に経営分析の解答時間ノルマを厳しく設定してしまうことで、本番で変な焦りを招いて全コケしては目もあてられません。第1問は難易度の割に配点が高いため、投資の意思決定問題の時間を削ってでも確実に点を取りに行くべきでしょう。
ちなみに…同期合格者で
「事例Ⅳは第2・3問をまるまる白紙で出して、第1問と第4問だけ解答して40点で受かった」
とおっしゃっていた方がいました。配点は第1問が25点、第4問が20点なので、ある意味9割取れたとも言えます。(※その方実際はとても優秀な方で、計算問題もメモ段階では解けていたようなのですが、なんか解答に納得いかなくて書かなかった、とのことです。部分点とか一切取りにいかないのは性格なのでしょう。おそらく事例1、2でめっちゃ取ってるはず)
上記は極端すぎる例ですが、そういう方も現実にいらっしゃるのです。事例Ⅳ苦手な方で足切りが心配な方ほど経営分析(とくに記述)に解答時間をあてることをおすすめします。
あるある単位ミス対策
けっこうあるあるなのが、「〜回転率」の指標で、わかっているのに単位を誤って「%」って書いちゃうミスです。
私は、指標名を書いた後、先に単位を書いてから数値を書くようにしてました。ついやってしまう方、お試しください。
正味CF計算はボックス図を描く
正味キャッシュフローの計算問題も頻出ですが、長い与件文を読みながら式を書いていると、どうしてもミスがなくなりません。
そんな中役に立ったのが、YouTubeチャンネル『ダンシ君のサブノート』の動画です。
解く時に面倒くさがらずに毎回ボックス図を書くようにすることでミスを減らせました。
CVPもボックス図を描く
合否を分けると言われるCVP分析の問題。
ここでも、苦手な方はボックス図を使って売上高・変動費・限界利益・固定費・利益を可視化することをおすすめします。

簡単な基礎問題を解くときでも、式だけでやろうとせずに面倒でもボックス図を描くようにしてから、CVP問題のミスと苦手意識が減っていきました。
実際に過去問をやっていた時の問題用紙が残っていたので共有します。もしかしたら数字は間違っているかもしれませんが、こうやってボックス図を使いながらCVP問題の練習をしていたということが伝われば幸いです。

ここに書いてある数字が正しいかは不明ですのであしからず。
損益分岐点比率・安全余裕率の計算を速くする
ところで、損益分岐点比率を問う問題が出た時、どうやって計算していますか?
損益分岐点比率 = 損益分岐点売上高÷売上高 × 100(%)
っていうのはどのテキストにも載っていると思いますが、これって結局まず「損益分岐点売上高」を求めないといけないですよね。
損益分岐点売上高 = 固定費 ÷ (1-変動費率)
これもどのテキストにも載っている式です。
ですが、この式で損益分岐点売上高を求めてから損益分岐点比率を求めようとしているあなた、ちょっと待ってください!時間のムダです!
損益分岐点比率 = 固定費 ÷ 限界利益 × 100(%)
安全余裕率 = 利益 ÷ 限界利益 × 100(%)
こっちのほうが早いです。
両方の式をがっちゃんこして約分したら結局こうなります。

少なくとも私が使った複数のテキスト・問題集の解説にこの式は1回も出てきませんでした。計算が得意な人には「いやいや当たり前でしょ」って言われるかもしれませんが、苦手な人は教わった式を使うだけで精一杯だと思います。なので上記の式を覚えてください。
変動費率は特に指示がなければ分数のままにしておく
私は学習初期、CVP問題が出るとまず反射的に「変動費率の計算」をしていました。でも、これ時間のロスが出るなーと感じたので、「変動費率を答えよ」という設問があるとき以外は、意識的に「変動費率を計算せず、分数のままにしておく」という癖をつけるようにしました。
理由は、
端数処理で時間かかったりいらないミスをするかもしれない
端数処理で解答に誤差が出るかもしれない
最後に電卓で一気に計算したほうが早い
からです。
些細なことですが、ミスの出るおそれがある箇所をできるだけ減らす工夫として、けっこう重要だったと感じます。
NPV問題の注意点
直近3年間(R2〜4)は、NPV問題が明らかに解ききれないボリュームで、捨て問になっている印象です。
こういった年は、(b)欄に
減価償却費・初期投資など、簡単なものだけでも書く
原価係数の使い方知ってますよアピールをする
くらいをあがいておきましょう。合否の分かれ目になるかもしれませんので。
逆にもし、例えば令和元年度のように全体的に簡単な年度だった場合、苦手な人はちょっとしたミスで差をつけられてしまうおそれがあります。その最たるものが
「初期投資額の引き忘れ」
です。
私は、初期投資額を最後に引くのではなく、一番最初に「マイナス初期投資額」で計算式に記載し、電卓のメモリーにもセットしておくようにしていました。最後に引くから忘れるのです。初期投資なのですから、最初に計算する癖をつけておきましょう。
タイムマネジメントが最重要
過去問学習時の理想
本番に望む前は、おおよそ以下のような時間配分をイメージしていました。
経営分析 18分
CVP 20分
投資の意思決定 30分
記述問題 7分
見直し/空欄埋め 5分
理想も理想ですね。この通りいくわけないことは分かっていましたが、それでも自分なりにおおよその目安を作っておくというのは、本番の体内時計のコントロールのために良かったと思います。
解く順番・解答欄の埋め方を工夫する
苦手な人ほど、練習の時から問題用紙を開いた直後に「80分をどう割り振るか」を考えて取り組むことが最重要です。
まず問題全体を俯瞰し、第1問、第2問、第3問、第4問(、あれば第5問)をどの順に対応するかをおおよそ決めます。
おすすめは、
経営分析
記述問題
CVP
投資の意思決定
の順です。もちろん年度によりばらつきはありますが、ある程度決めておくと無駄に悩まなくて済みます。
H30年の企業価値とかR2年のROIなど、上記4大論点以外が出てくる場合でも、基本は経営分析と記述を優先します。3番目にCVPの難易度と天秤にかけてどっちを先にやるか決める、というのが無難でしょう。
さらに言うと、今後の難易度がどうなるかはわからないのですが、必ずしも頭から解いていかずに各大問の(設問1)を優先していく戦法(※注)がおすすめです。
本番でいきなりやろうとしても無理なので、過去問を解く時から、
設問の順番通りに解かない
解いてる途中でも詰まったら別の問題に移る
最後に一気に書こうとすると焦って何も書けなくなるので、問題を何度も行ったり来たりしながら、徐々に(b)欄を埋める
といった練習をしておきましょう。
※注: 過去問をやっていくとわかりますが、「実は設問(3)は独立していて(1)(2)の数字を使わず解ける」「実は設問(1)じゃなくて明らかに(3)が簡単」という年度もあります。そういうのを見逃さないのが、計算苦手勢の戦い方です。
おまけ: 事例Ⅳ用ファイナルペーパー
以下は実際に1次と2次を並行学習していた7月頃に作成した、事例Ⅳのポイント整理メモです。その時はファイナルペーパーのつもりではなかったのですが、ここに解答時のチェック項目などをどんどん追記したりして、最終的に私にとってのファイナルペーパーとなりました。生産性指標もちゃんと分解式まで書いていました!1次試験用に書いていたものですが、まさか2次試験で役に立つとは考えていませんでした。

次回は、上記のような練習を積んでいった結果、本番の80分がどうだったのかを、再現解答を交えながら振り返ります。
質問があれば、コメントかTwitter、マシュマロにてお寄せください。
この記事が気に入ったら、サポートをお願いします! 育ち盛りの子の📕絵本代、もしくは🥛牛乳代になります🙇♀️
