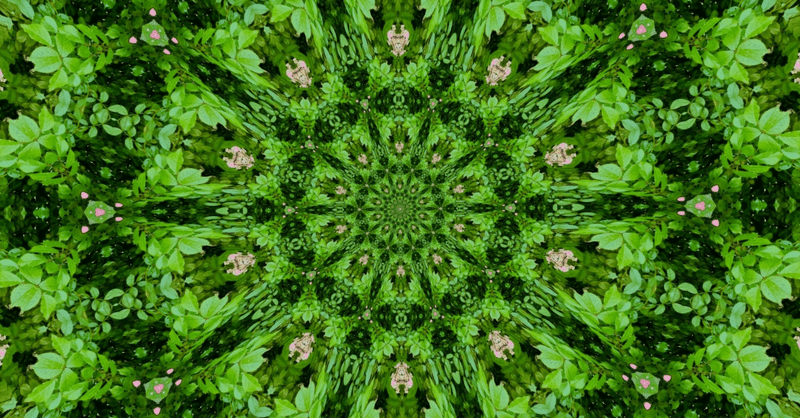
『中論』4: 心頭滅却すれば火もまた涼しいのか
『中論』中村元著の一章「原因(縁)の考察」
禅やヨガには集中力と同時に瞑想の訓練や修行が求められるのであるが、瞑想にもいろいろあってサマタ瞑想は一つのものに集中することで、止(サマタ)は思考を止めることであり、その意味や実体はどのようななものであるかは知られていないので先ず体験ををしていただくことにしたい。
集中力には外部からの影響を極力避けて静かな環境が必要だと考えられているが、学生が勉強するときには思考力を低下させる可能性はなきにしもあらないから、学生がラジオを聴きながら勉強することが多いのである。
夏目漱石は集中力を高めると見つめているものの意味が喪失してゆくことを発見したことは、あまり知られていないかもしれないが『門』において「今日(こんにち)の今(こん)の字で大変迷った。紙の上へちゃんと書いて見て、じっと眺めていると、何だか違ったような気がする。しまいには見れば見るほど今(こん)らしくなくなって来る。というが」、現代ではゲシュタルト心理学派によってゲシュタルト崩壊としてしられている。
スポーツでは集中力が極度に高い状態を「ゾーン」というが、集中力が極度の不振スランプを招くことをご存じであろうか、その障害の単純なものでは緊張といわれる集中力が重要な大会試合などで一時的に起こるもので実力をだせないことや、野球のピチャーなどの標的に向かってボールを投げる選手は極度の集中力が必要なのであるが、一流の投手、エースと言われる投手の陥るスランプを「イップス」といい、集中力の高いエースがそこえ投げてはホームランを打たれるとわかっていながらそのコースに投げてしまう深刻な障害である、集中することによって思考が止まって理性の働きが止まるからである。
集中力は高ければ高いほど良いということではなく、悩みや絶望状態も極度の集中状態であるが、思考が止まって理性の働きが止まるから悩みや絶望状態も解決できないのである。
極度の集中力が、思考を止めるので、その障害になる実験を行うが、それは思考を止めて理性の働きを止めるから煩悩も止める働きがある。
『中論』中村元著の一章「原因(縁)の考察」はなぜ思考が止まってしまうのかという疑問にこたえたもので、それはかんたんな実験として誰でも何処でもできるので実験で体験することもできる。
夏目漱石発見した方法とは白紙のプリント用紙に簡単な画数をたった一文字たとえば「今」だけを中央にプリントして集中して見つめることであるが、すると文字は見えているがいみが消えてゆく不思議な現象であるが、評論家には異常現象と思われていたが現代でも解明されていない現象であるがヨガの止観における止(サマタ)で思考を止めることであり一時的であるから驚くことはないのである。
夏目漱石は北鎌倉の円覚寺管長の釈宗演に一か月ほどであったが参禅したことは知られているがその修行の効果が表れたのが六年ほどたってからである。
「原因(縁)の考察」(二)
集中力が高ければ文字の意味が消えてゆくのは四縁の影響をうけないからであり、また四縁の影響を断続的にうけないことがないから悩むのである。
四縁とは因縁、等無間縁、所縁縁、増上縁であるというが、『中論』中村元著の一章「原因(縁)の考察」(二)で解説されているのでこれからはいいちいち断らない限り引用は同書とする。
我々は袖触れ合うも何かの縁というが触れたもの見たもの聞いたもの六感でかんじたものすべてが縁であるがその縁によって考え行動を行う。
例えばおいしそうなケーキを見れば食べたいと考えお腹が空いていてお金を持っていて時間があれば買って食べることになればそれを縁という。
先ず見ることが原因となり食べたいと考えお腹が空いていてお金を持っていて時間があればが縁になって行動を起こすのであるが、その腹が空いている、金を持っていてる、時間があるがそろっていて初めて行動が成立するのである。
「原因(縁)の考察」の(一)
ケーキを見ることは「原因としての縁(因縁)」であるが目の前にケーキがあっても見なければ原因にはならないとは、「もろもろの事物はどこにあっても、いかなるものでも、自体からも、他のものからも、【自他の】二つからも、また無因から生じたもの(無因生)も、あることなし。」と龍樹はいう。
長いかいせつであるが言っていることはケーキが目の前にあっても見なければ原因にはならないといっているだけであり、みれば原因になるが見なければ原因にはならないのであり、ゲームのソフトを見てケーキを食べたいと考える人は居ないということである。
それではチラシや本、テレビでケーキの画像を見たら即座に食べるかといえばケーキが目の前になければ食べられないばかりではなく、現物が原因(縁)によって所縁縁が起こって食べるのであるが、所縁縁とはケーキを所有したいという欲求すなわち食べたい食べる行動に繋がるのであるが無ければ食べれないのである。
そんな日常の行動を人間の認識行動の原理を解説しているのが『中論』であるが、知覚と認識の心理構造の解釈は現在の心理学とは大変違っていて、人間の眼は鏡のように映すのであるが意識的に認識するのと行動は別機構よって行われるのである、動物が意識せず反射に反応する機構と同時に人間は意識による制御が加えられる構造になっていることである。
その意識が人間の思考と煩悩を引き起こす原因になるから障害や悩みが生じることになる。
例えば薬物中毒者は麻薬に接することによって習慣が始まるのであるが、麻薬が体内に入ることによって言葉では表現できない感覚をかんじて一時的な享楽に満足したとすれば、次回からは麻薬を見たり想像対象を『中論』では「所縁縁」といい、所縁縁は6つの対象である色・声・香・味・触・法の六境であるから、麻薬を見たり想像するだけで欲求という縁とともに働いて行動になる。
それでは何故止めようとして止められないのか、それは野球のピッチャーがそこへ投げてはいけないと考えるとそこへ投げてしまう現象と同じで集中すればするほど思考と理性が制止されて行動だけが実行されるのである。
ゲシュタルト崩壊と同じで意識が混乱している間に別回路の行動が意識の制止を待たずに実行されるのである。
意識と行動は感覚器官で色・声・香・味・触・法の六境を感じるところまでは共通であるが、意識と行動は別回路を使って機能しているとは現代の脳科学で明らかにされていているが、その事実を良く理解していないようで、特殊な状況においてのみ実行される機能であるとかんがえるのである。
行動は動物と同じ機構により反射的に行動の準備をしていて意識が一定の時間内に止めない限り自動的に実行されるシステムであり、自動車でいえばアクセルとブレーキは別の機構と機能によるものであるのと同じである。
それは動物である犬でも食べ物が目の前にあっても「待て」と人間が言えば外部から制止すれば待つことから解るのであるが、人間の姿が見えなくなると、我慢できずに食べはじめるのよく見かける現象である。
我慢とは辞書によれば「他を軽んずること」と定義されていて、その意味は人間の命令を「軽んずること」ではなく、目の前にある食べ物を「軽んずること」であるとは、食べ物に注意を集中することによって食べるという働きが制止されるからであり、犬には意識がないと考えられているが人間の言葉を理解しているとは自動車のブレーキにあたる機能が犬にも備わっていると考えられるのである。
「心頭滅却すれば火もまた涼しい」
「心頭滅却すれば火もまた涼しい」とは動物によっては天敵に出会うと逃げることをせず死んだ真似をすることがあるが、それは考えた行動ではなく危険を感じてその天敵を見つめ続けることは集中することを意味していて行動の機能が失われるからであるとかんがえられ極限すれば人間であれば意識を失った状態で熱いも冷たいも感じないことである。
禅では今、ここ、自己の目の前で起こる現象を唯一の真実と考えていて、そのことからも目の前に有る物が原因(縁)といわれるのである。
龍樹は『中論』中村元著の一章「原因(縁)の考察」で「もろもろの事物」(意味)は四縁「今」より生じることはないといっているが、一文字だけでは縁は結果(意味)を残さないのであり、集中力の後に観照の時間がなければ意味は発生しないと書かれているのである。
観照とは観察すること俯瞰することであるとは、言い換えれば集中しないことでありケーキを見ても集中して見続づけないことであるとは、見続づけることは思考を混乱させることであり、ゲシュタルト崩壊を起こさせることである。
逆説的かもしれないがケーキを見て集中して見続づけるとケーキを食べることが制止されることになることは、ケーキ屋さんの子供はケーキを見ても食べたがらないと言われているからである。
通常はケーキを見ればそれが原因(縁)として「所縁縁」が起動されるのであるが、見続づけることによって「所縁縁」が制止され食欲が制止されると考えられるのであるが食べてはいけないと拒否することはケーキを断続的にイメージ(等無間縁)として見続ける結果になる、その結果「所縁縁」が継続されるので食欲が生じるのである。
「原因(縁)の考察」(三)
ここでは「自性、本質」が取り上げられているが「自性、本質」とは色・声・香・味・触・法の六境ではなく、「感覚器官の作用」が「自生」だといっていて「作用」がなければ見る対象である色・声・香・味・触・法の六境は存在しないと言っているのであり、「自性、本質」をそなえているのは人間であり人間の見る機能作用(六根)がなければ色・声・香・味・触・法の六境は存在しないと常識的で当たり前のこと言っているだけである。
そのことについては第三章「認識能力の考察」で言及する。
以下「原因(縁)の考察」は全て普通の現象を抽象的、論理的に表現しているだけでそれを難しく考えると意味が解らなくなるが、注意すべきところは前提条件を省略してい(一)では「目の前のものを見る」という言葉をいれて読むこと(二)では「自性」のところを「人間」と置き換えることによって意味が通じるのである。
最後になったが「心頭滅却すれば火もまた涼しい」
最後まで読んでくださり、ありがとうございました。
参考文献
『中論』 ナーガールジュナ著 中村元訳 講談社学術文庫
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
