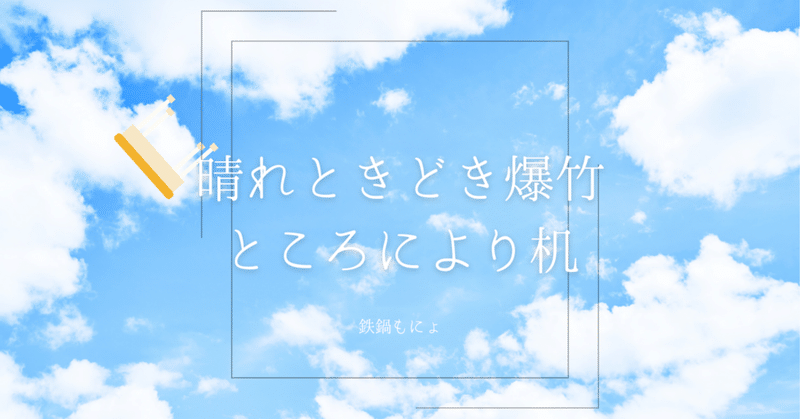
晴れときどき爆竹、ところにより机
ゴールデンウィークに中学の同級生と集まったので、中学校の話題。
風間俊介くん演じる兼末健次郎に衝撃を受けた金八先生の第五シーズンが終わるころ、中学に上がった。卒業した小学校から、二つの中学に学区が分かれる。そのうち、わたしが進学した先の中学校は市内でも有名なとても荒れた学校だった。そこに進学するのを避けるため、クラスの半分近くが中学受験をするほどだった。
五年生の秋に転入して、いじめもあったし、母親が働いていて他の親と接点がないため「とにかくやばい」というふんわりした情報しか聞こえてないまま中学生になり「治安が悪い」というのがどういうことなのかを知った。
一年生は一階、二年生は二階、三年生は三回に教室があり、それぞれ昇降口の場所が違う。一年生が門から一番遠い昇降口で、三年生が門から近い昇降口。昇降口を入ると目の前に階段があり、他学年に干渉することなく自分の学年のフロアに向かうことができる作り……のはずなのに当時の三年生はわざわざ一年生のフロアでたむろして、制服や髪型、持ち物のチェックをしていた。校則を守っているかが重要なわけではなく、生意気かどうかを見ている。校則で靴下とスニーカーの色は白と決められていた。大変馬鹿馬鹿しい校則だと思っていたけれど、こうした治安の悪い先輩から新入生を守るためにあったものなのかもしれない。先週まで小学生だったのに、窮屈な制服、窮屈な環境。小学生と中学生では世界が変わる。
荒れていたのは入学時の三年生だけだった。二年生は他学年に干渉せず、不良っぽい人でも保健室で授業をさぼる程度のかわいいものだった。学年によって色がだいぶ違った。
大荒れの三年生は、授業中に階段で爆竹に火をつけたり、一年生の教室の外にある手洗い場から窓を開けている教室へ水を飛ばしたり、水風船を投げ入れたり。授業中の一年生の教室に怒鳴り込んできたこともあった。ある女子生徒を指名して「あいつを出せ! あいつのねーちゃんにあたしらは締め上げられていたんだ!!」と。指名された子は、とても穏やかな優しい子だったので、どんな姉なのかとても気になった。彼女たち曰く、上の代に締め付けられていたので、今やりたい放題しているとのことだった。彼女らの言う「締め付け」がどんなものだったのかわからないけれど、手綱を握られていた程度の話の可能性もゼロではない。
夏の暑い日、泳いでしまうカーテンが開け放たれた額縁のような窓の向こう。少し騒ぐ声がして、机が降ってきたことがある。少し遅れて椅子も。治安が悪いと、机や椅子が降ってくることもあるらしい。大きな音を立てて落ちた机と椅子は、意外にも原形をとどめていて誰かの「机、つえー」とつぶやく声が聞こえて笑ってしまった。
そんな状態だったので、パトカーが学校に来ることもあった。
暴力、妨害行為が目立っていたけれど、こんなこともあった。
演劇部か剣道部に入ろうと思っていたけれど、どちらも入学時に廃部になった。親からも運動部を反対されていた。結果、ダイヤルアップ接続が主流の時代にインターネットが使い放題だったパソコン部に入部した。記録メディアはまだフロッピーディスクが主流だった。
パソコン部で何をしていたかというと、ネットサーフィンをしたり、当時ハマっていたジャンプ漫画やリズムゲームの同人小説を書いたり、友達とノートに書いて見せ合いっこをしていたオリジナル小説をデータ化して推敲したり。
顧問の先生は常駐しておらず、下校までの時間、鍵の開いたパソコン室への入退室は自由だった。運動部ではなかったので、特に目標があるわけでもなく、部活に来るも来ないも自由だった。今日はいっぱい人がいるな、という日もあれば全然いない日もあった。
その日は入れ違いで何人かが帰っていった。三年生の面倒な人がいて、この人が部活に来ると、帰ってしまう人が多かった。
しばらくすると、例の三年生――仮名をワカメとする――がどういうわけか馬乗りになっていた。他にも二人いて、気まずそうな顔で気持ちていどにわたしの腕を抑えている。
「服脱がせちゃうぞ~」
ワカメ野郎は小柄でやせ型だった。対する自分も小柄だけれど、見た目よりも腕力がありケンカが強かった。小学校で同じクラスだった男子の一部は知っていたけれど、中学生になると発揮する場面が少なく知らない人がほとんどになっていた。
ワカメ野郎が逃げ出すていどにやり返し、残りの二人は声も出さずに首を振っていた。自分がやりすぎてしまった自覚があったので「先生に言ったらどうなるかわかってるよな?」と釘を刺した。よく考えてみれば、正当防衛で許されたような気がする。高校進学の際に奨学金がほしい件がちらついて、つい自衛に走ってしまった。
中学校一年生でも、生徒間でこういったトラブルはあるのか……と、とてもげんなりした出来事だった。周知されていないだけで、他にもこういったことはあったのだと思う。これが治安の悪さ。
できれば先生方に「校内で一人になるな」くらいのことは注意喚起してほしかったかも……と思う。一年生なんてちょっと前まで小学生だったので。
こんな具合の中学で、一年生はどうなったか――。
意外にも「荒れた中学を変えないと!」と団結した。三年生の卒業までは耐えに耐えて、卒業後は生徒会が希望を募って校則を緩めた。靴や靴下の色が黒・紺・白のいずれかであればよくなった。ポイントでデザインが入っているものも緩和された。ベストやセーター、カーディガンの色も黒・紺・グレー・茶を選べるようになった。小さなことだけど、選ぶ自由があるのは治安の良さの象徴だった。
わたしたちが三年生になった時の一年生が、もう荒れていた時代の名残を知らずに生活しているのが誇りだった。
今でも同級生との間で話題に上がることがある。
卒業式の壇上で、校長先生からの言葉。校長先生は、わたしたちが入学するときに他校から赴任してきた先生で、あまりの荒れた様子に険しい顔をしていた。その先生が、壇上で涙した。この三年間にどのように学校が変わったか、生徒が変えていったかをよく理解していて、校長という立場からも非常に苦しい思いをしていたことが伝わった。誰もやりたがらない役を引き受け、逃げ出さず立て直そうとしたのは生徒だけではなく、先生も同じだった。時に涙は言葉よりも多くのことを感じ取らせてくれる。
当時からこそこそっと話題に上ることがあった。「この環境、先生たちの方がつらいよな」って。色んな所から板挟みになっていただろう。いい対応ばかりじゃなかったと思うけど、大人でも涙してしまうほどつらい状況で投げ出さなかった先生方がいたことをわたしたちは憶えていて、二十三年経った今も話題にしてる。
晴れ時々爆竹、ところにより机。
これを笑い話として話せるようになったのは、卒業までに平和を実感できたからなんだと思う。平和がいちばん。
ご覧いただきありがとうございます!

