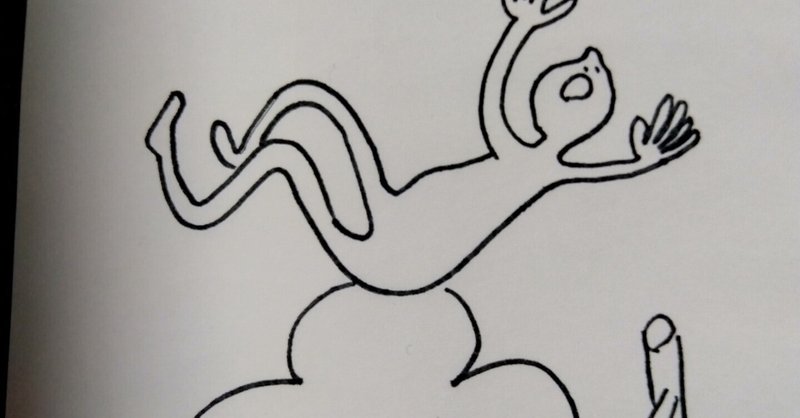
『しりもちをつく』という言葉を知ったいつかの『葵祭』
40年近く前の、5月15日の思い出
さまざまなことを目で見て耳で聞いて、その目の前で起こった事柄をさすのは・当てはまるのはこの言葉なのだと聞いたり教わったりして認識してきた
しかし、日常的に使う言葉などはいちいちその認識したことを覚えていることってほとんどない
小学生の頃、習うまではその漢字を使ってはいけないという妙な決まりのおかげで早く名前を全部漢字で書きたいなと思っていたりしたことくらいしか覚えてない
5月15日は藤原竜也様のお誕生日、『新しい王様』もう一回見たいなあ
うう、脱線
気を取り直して、京都では『葵祭』が行われる
今年の斎王代(葵祭の主役で、平安時代に神社に仕えた皇室の女性「斎王」の代わりを務める女性のことで、毎年、京都にゆかりのある女性が選ばれる)は、NHKのニュースの報道で耳にした通り申し上げると
”旅行会社に勤務する壬生寺の長女“
何か、言い方に違和感あるの、私だけでしょうか
あと、『祇園祭』のお稚児さんにおける祖父・父・子の三代とも経験とかはまあ”ええしの子やしな“とすんなり入ってくるが、おばあさま・お母さま・娘の三代続いて『斎王代』とくると、いよいよ富の継承というか“ええとこの娘さんはええとこ嫁がはるんやな”という下世話な考えが頭に浮かぶ
富の連鎖
婿養子を代々迎えておられるってこともありますしね
ま、それは置いておいて、幼稚園からみんなで連れ立って御所まで葵祭を見に行った記憶があり、そのとき規制線の手前でお祭りを見物する私たちの目の前でお姫様(斎王代ではなかったと思うけれど)が暴れ出した馬に振り落とされドシン!と音を立ててお尻から地面に落下したのだ
動きにくそうな重たそうな着物と、黒く長い髪から見えたそのお姫様の目からは今にも涙がこぼれそうな顔は私たち園児の見ている場所からから丸見えで、驚いた私たちは、『かわいそう』『痛いって泣いてはる』『ドシン!って音したなあ』と混乱していた
お姫様はただちに沢山の人にかかえられてその場からいなくなったが、しばらく我々は動揺がおさまらずわあわあ騒いでいた
そのあと、先生の口から『お姫様は馬から落ちて“しりもちつかはった”けど、もう大丈夫みたいやから安心してや』と言葉がかけられたことは忘れられない
『お姫様が馬から落ちてしりもちつかはってん、痛いって言って泣いてはった』とお迎えに来てくれた母に報告し、家に帰ってからも学校から帰ってきた姉、会社から帰ってきた父に順番に報告していたのを覚えている
毎年毎年、お祭りは見に行けなくても(不動の日程なので運良く土・日にあたらないと見られないのでそんなに見に行ったことはない)私が興奮して話していた事を大きくなるまで家族の誰かが話題にするので、このときのことを覚えているのだった
5月15日は、京都三大祭のひとつ『葵祭』が行われる日と、私が『しりもちをつく』という言葉を知った日
例年通り行われるありがたさを噛みしめつつ、思い出す


こぶりなのでいくつでも食べられてしまう
美味しくてヤキモチ焼いちゃう

まとめた本が出たとき頂いたもの
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
