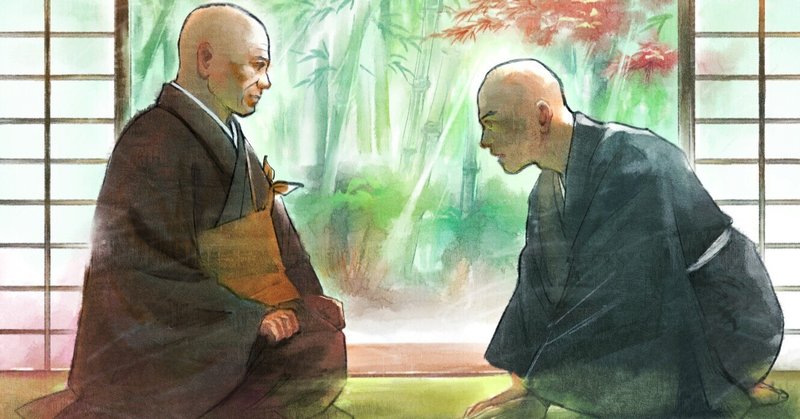
『浄土真宗』から学べること
最近、自分の家系が代々、浄土真宗を宗派としていることがわかった。『南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏』の仏教だ。これまで三十数年生きてきて、あまり宗教を意識したことはなかったが、実際に僧侶の方と話をしたり、開祖である親鸞聖人のことを調べていくうちにライフスキルを学べる思想だなと感じた。今回は、書籍『冒険の書 AI時代のアンラーニング』(著:孫泰蔵)と書籍『図解 歎異抄 たよる まかせる おもいきる』(著:齋藤孝)を参考に、浄土真宗から学べることをまとめてみる。
「悪人正機」と「他力本願」

親鸞聖人曰く、「善人なをもて往生をとぐ、いはんや悪人をや。」
善人ですら浄土にいけるのだから、ましてや悪人が往けるのは当然だ。
ということだ。これは悪人正機説と言われるもの。素直に考えると、なんで悪人が浄土に往けるの?て思うが、これを紐解くには、「他力本願」を考えてみる必要がある。他力本願とは、他人の力をあてにすることではなく、本来の意味では、阿弥陀仏の本願をよりどころにするというもの。では、阿弥陀仏の本願とは何か。それは、生きとし生けるものの苦しみをすべて救いたい、という阿弥陀仏の願いのことである。つまり、「南無阿弥陀仏」とは、すべてのものを救うことを本願された阿弥陀様にすべてをおまかせするお祈りだということだ。本気で他力を信じ、念仏を唱えれば、来世での悟りが確約される、現世では悟れない我々でも来世では仏になれる、そう信じて「他力本願」するのである。「阿弥陀様を信じて生きていけば大丈夫だ!」と思い、心のよりどころにすれば、死んだあとのことを考えて暗くなる必要はないし、欲望とか怒りに執着する必要はなくなってくる。ある種の安心感。穏やかな心の状態がおとずれる。
ここまでは、なんだか宗教っぽいなと思う。
だが、「善人」や「自力」という概念を対比させていくと示唆深くなる。
「善人」とは、「私は善い行いをしている!」と自力で善いことを行う人のことである。しかし、何を持って”善い”と言えるのか。例えば、人を喜ばすために、〇〇商品を開発し、販売し、市場シェアNo.1になった!その結果、競合他社の商品は売れなくなり、その会社の売上は激減し、従業員のボーナスがなくなった。あるいは、環境破壊につながった。ということもあるだろうし、友達のためと思ってテスト範囲のノートを貸したところ大変喜ばれ感謝されたが、それが常態化し、断れなくなり、良好な関係とはいえなくなってしまったということもあるだろう。つまり、善いと思って行ったとしても、それが悪い結果になるということもあるということだ。これを無自覚なままでいると、自惚れや独りよがりになったり、独善的になってしまいがちになる。あるいは、自分はこんなに頑張ったのに評価されない!むかつく!という考えになるかもしれない。なので、善いことをすること自体が良い悪いではなく、そのような自分本位の態度には気を付けるべきだとも解釈できる。
そのように考えると、「悪人」ははなから他力にすがっている。日々、煩悩にとらわれて生きており、「私は善いことを行っている!」という観念がない。つまり、自分の行動がどのような結果を生むのかわからないという自覚を持っている。だからこそ、大きな力に身を委ねることができ、心安らかな状態をつくり、ネガティブな感情に左右されずに精一杯生きていける、そのような悪人こそ救われるのは当然じゃないだろうか。逆説的です。

3つの学びポイント
①自力優先の世界観に気をつけるべし
自力に重きを置くと、自分本位、他責、執着が生まれやすい。「自分はこんなにやっているのに…!」「自分はなんで評価されない…」自己決定していくことは大事なことだが、時には、大きな流れに身を任せ、自分自身をメタ認知していくことが大切。夜空の星をみて、自分はなんてちっぽけなんだと思うように。(自分をなくしていく、これはある意味フロー状態をつくるうえで必要な要素なのだろうか)
②安心感がチャレンジを生む
「他力」に任せた安心感が行動を生む。ちゃんと支えられているとホッとする。信じられないと怖くてできない。支えがあるからチャレンジできる。失敗しても帰る場所がある。そう思うと勇気がどんどん湧いてくる。これは身体技法でも実践できるとあった。後ろで仲間が支えてくれるから、真後ろに倒れてみなさい、と。
③独善的思考に気をつけるべし
「善いことをしよう!」と強く思っている人は、他人に対しても「善いこと」をさせようと押しつけがちになる。更には、「なぜそうしないのか?」と言いかねない。これはよくある。このような時は、自分が行動した結果、誰かがハッピーになればすごくラッキーだなと思うくらいがちょうどいい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
