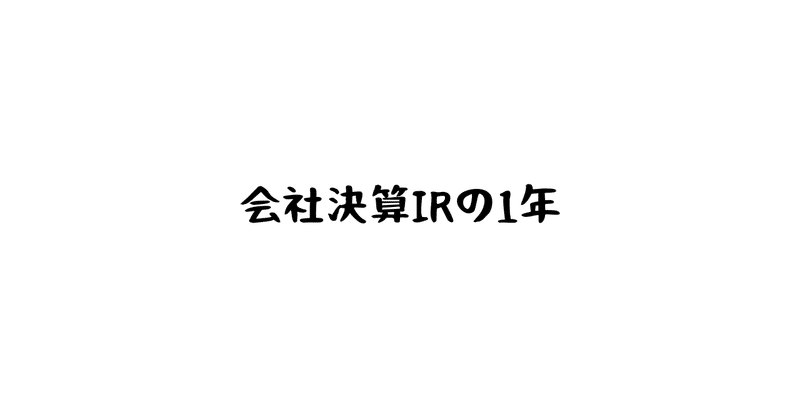
■会社決算IRの1年
目的:上場会社の決算IRの背景を理解し、株式投資の参考とする
所要時間:20分
Goal:会社の業績管理のサイクルを理解し、決算IRの背景を把握する。
はじめに
株式投資の手法として、「決算プレイ」なる言葉がある。
あまり好きな言葉ではないが、四半期ごとにリリースされる決算IRにより株価が動くことは事実。
この決算IRがどのような背景でリリースされることを知ることは、株式投資において重要と考える。
■決算IRとは?
上場会社が三か月ごとに、企業業績を開示すること。
法律により、四半期(3か月)ごとの決算を四半期決算日の45日以内に決算短信として公表することが義務付けられています。
1年を3か月ごとに、1Q・2Q・3Q・本決算に区分し、その期間ごとの累計(3か月・6ヶ月・9か月・1年)の損益などの情報を開示します。
また、任意開示(実際は、ほぼすべての会社が開示)ですが、本決算の際には、新年度の業績の予測を開示し、また、業績予想に変化があれば、一定の条件を満たす場合は、業績予想の修正を開示する義務があります。
(注)45日ルール
決算日(3月決算会社であれば、3月・6月・9月・12月の各月末日。ただし、決算日が月末日でない会社は除く)から45日以内に、決算情報を開示しなければならないというルール。
(注)業績予想の変更
一度開示した業績予想の数値に対し、売上高の10%、各段階の利益の30%以上の変動が見込まれる場合は、業績予想の修正値と修正理由を開示しなければならない。
ただし、タイミング的に正しく開示されているかは、実際は疑問のあるケースも多い(筆者の個人的印象)。
■業績予想の前提=事業計画
会社を経営するうえで、事業計画は不可欠。通常は月次の損益計画を作成し、これをもってPDCAサイクルを回す。
この事業計画が、業績予想IRの基礎となる。
事業計画値をそのまま業績予想に用いる会社もあるし、社内用の事計と公表計画を分ける会社がある。社内計画は高めに、公表計画は保守的にという会社は結構ありそう。
会社は、年度を通じて事業計画と実績をモニタリングしつつ、その達成度を勘案しながら、翌年度の事業計画を策定していく。
なお、日本の会社は3月決算の会社が多いが、海外の会社は12月決算の会社が多い。中国は12月決算であることが強制される。
そのため、連結決算では、海外子会社の損益は三か月前の数字を連結するケースがほとんどです。
また、事業計画作成のサイクルも、海外は日本よりも三か月前倒しになることが通常です。
事業計画の作成サイクルは、海外子会社の年度初めの1月の前の年の11月ごろから開始し、12月に事計を承認し、1月の業績管理に適用する、という所から始まります。
それを整理すると下図のようになります。

■1月
海外子会社の新年度の開始
前年12月までの数字をまとめて、3Q決算数値の速報値を社内で共有。
4月からの新年度に向けて、事業計画作成を開始。
■2月
3Q決算短信を開示
新年度の事業計画を承認
■3月
新年度の事業計画を承認(2月に承認できなかった場合)
■4月
国内会社の新年度の開始
3月までの数字をまとめて、年度の決算数値の速報値を社内で共有。
■5月
本決算短信を開示(本決算実績/新年度の業績予想)
株主総会の招集通知発送
海外子会社の上期業績見通しを整理しつつ、下期(修正)計画の作成開始(下期計画を作らない会社も多い)
■6月
海外子会社の下期計画承認
株主総会(会社にとって、超重要イベント。ここで役員が入れ替わる)
■7月
6月までの数字をまとめて、1Qの決算数値の速報値を社内で共有。
(会社によっては)株主通信を発行
■8月
1Q決算短信を開示
国内会社の上期業績見通しを整理しつつ、下期(修正)計画の作成開始(下期計画を作らない会社も多い)
■9月
国内会社の下期計画承認
■10月
9月までの数字をまとめて、2Q(上期)の決算数値の速報値を社内で共有。
■11月
2Q決算短信を開示(上期決算実績)
1月からの新年度に向けて、海外事業計画作成を開始。
(会社によっては)中間株主通信を発行
■12月
海外子会社の事業計画承認
■ポイント① 決算IRの出る時期
・1月下旬~2月上旬(3Q決算)
・4月下旬~5月上旬(本決算)
・7月下旬~8月上旬(1Q決算)
・10月下旬~11月上旬(2Q決算)
※上記は、3月決算会社の場合。
決算月がずれれば、決算IRの時期も動きます。
なお、業績予想の修正は、決算IRの想定日の一か月前辺りから要注意です。
■ポイント②時期ごとの特徴
・1Q:7~8月は、役員が変わったばかりであったり、まだ業績の進捗が少ないので、目立つ決算IRは少ない。そのため、材料不足から夏枯れ相場の一因になると考えられる。
・2Q:10~11月は、上期決算、折り返し地点。上期の業績予想との対比など、計画と実績の対比が厳しくみられる時期。
先手管理のできている会社は、下期の事計の修正➡業績予想の修正を開示することもある。
・3Q:1月~2月は、国内は3Qまでの数字、海外は年度の数字が締まっており、ほぼ年度決算が見えている時期。
このタイミングで業績予想の変更の数字を出す会社が多い。
・4Q:4月~5月は、本決算であり、注目されるのは新年度の業績予想。
通常は3Qまでで、本決算の数字は大体見えているはずなので、このタイミングで業績予想の修正を出す会社は、基本的に予想の数値の信頼性が低いと考えられる。
■ポイント③四季報
四季報は、3月決算会社の決算発表のピーク月の翌月に公表されるので、各四半期で意味合いが変わってくる。
また、会社の決算月によっても、意味合いが変わってくるので、会社の決算月を把握しておくことは重要になる。
■まとめ
今回は、かなり文章量が多い内容になりましたが、会社にお勤めの方には常識なのだと思われます。
1年のサイクルで活動しているので、季節変動の要因にもなります。
季節的なアノマリーは、馬鹿にできないのかもしれません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
