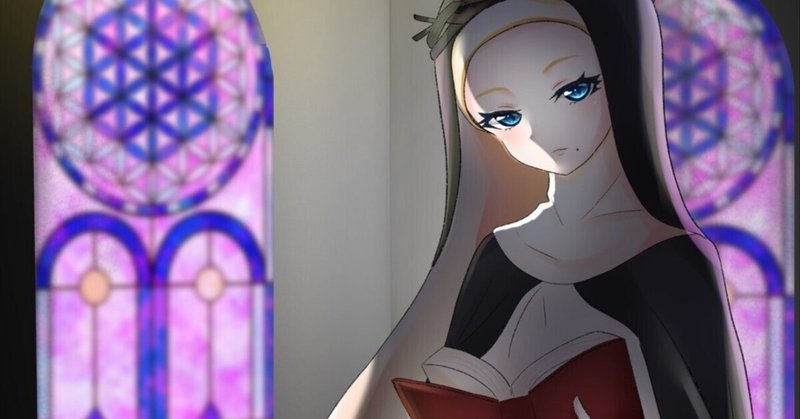
西欧音楽史 補講2:古典調律と平行五度
お久しぶり。
次回から講義のやり方を変えるって言ったけど、前提知識に基礎的な楽典とか管弦楽法の講義をしなきゃ皆さんに古典派音楽とロマン派音楽の違いを伝えられないから、そういう原稿をいくつも書くのに時間がかかっててなかなか「和声法の講義」に進めないの。
だから、2回連続で補講になっちゃうわ。
講義には流れってものがあるから補講って言ってるけど、バロック音楽と古典派音楽の過渡期に起きたことの講義だから、今回は西欧音楽史の講義の一部みたいなもの。
必修じゃないけど、飛ばしても構わなかった前回の補講よりずっと大事な内容よ、ぜひ受けていって頂戴。
さて、始めましょう。
今回はクラシック理論で最大の難問、平行五度の禁則を古典調律と絡めて説明するわ。
この補講じゃ、古典調律の歴史とか理念と、平行五度の問題を同時に扱うってこと……って言ったら凄く複雑そうって思われるかもしれないわね。
だけど、きっと皆さんが関連して意識する機会が少なそうなこの2つを一緒に講義する方が、体系的な説明になるからどっちも理解しやすいでしょって判断したの。
今までことあるごとに言ってきたけど、平行五度は「クラシックの定義は平行五度が無いこと」って書いてる本もあるくらい、クラシック最大の禁則よ。
他の禁則とは重さが比べ物にならないし、禁忌って言っても過言にならないんじゃないかしら。
ドビュッシーさんがモダニズムの幕を開けてからは意図的になら使っても許されるようになったけど、モダニズム以降でも民族音楽の要素を入れたい(ドビュッシーさんがガムランの影響を受けたのは有名よね)とか、Common Practice Periodのルールから外れた曲を書きたいって意図がはっきりしてないと批判で袋叩きにされるわ。
じゃあ、平行五度はどうして禁則なのかしら?
これも繰り返しだけど、こんなに強い禁則なのに理由のコンセンサスが無いの。
適当に和声法の本を何冊かお読みになって頂戴、「中世っぽくて調性音楽に合わない」って書いてる本もあるし、「濁りすぎてて汚くて聴くに堪えない」みたいな意見の本もあるわ。
平行五度にもモーツァルト五度みたいな例外はあるけど、理由にコンセンサスが無いから、モーツァルト五度はどうして認められてるのかしら?ってなった時に答えに窮するのよ。
大体、「モーツァルトさんがよく使ってて、聴いても違和感が無いから慣例で認められてる」って触れて流すのが普通ね。
確かに、これは正しい説明よ。
和声法はアルス・ノーヴァとか十二音技法みたいに誰かが作ったんじゃなくて、Common Practice Period、特に古典派音楽の頃の曲から後追いで規則性を抜き出して体系化した理論なんだから、モーツァルト五度が例外な理由を「モーツァルトさんがよく使ったから」って説明するのは正しいわ。
……だけど、だったら平行五度の禁則だって、Common Practice Periodの時期の作曲家が避けてたって慣習でしかないわよね。
「どうして古典派の頃に平行五度が意図的に避けられてたのか」を考えなきゃ、「平行五度がどんな響きに聴こえるか」を論じたってコンセンサスが生まれないのは当然だと思わない?
今回の補講の結論を先に言うわ。
バロック音楽と古典派音楽の過渡期の平行五度と、皆さんの時代の平行五度は響きが違うから。
耳で聴いてる音色が違ってるんだから、誰も同じ議論の土俵の上に立ってないのよ。
じゃ、どうして響きが違うのかしら?
当時の音楽家は中全音律か古典調律の響きを聴きながら作曲とか演奏をしてたけど、皆さんは平均律でそれを聴いてるから。
グレゴリオ聖歌の講義の時、旋法種の成り立ちを説明するために過去の音楽家の思考をトレースしたわよね。
今回は、古典調律と平行五度であれと似たようなことをする講義になるわ。
バロック期以降にいろいろ考案された中全音律でも平均律でもない音律って、古典調律って総称されるけど、音律が作られた目的で2つに分けるべきなのよ。
で、目的に注目しながら古典調律が開発された時系列を遡っていったら、和声法で平行五度が絶対の禁則になった経緯をトレース出来るわけ。
そのために大量の前提知識が要るから、それを順番に説明しながら進めていくのが今回の講義よ。
まず、古典調律の説明のために、ざっくり音律の歴史と性質を話しましょう。
中世西欧音楽じゃずっとピタゴラス音律が使われてたけど、ルネサンス期になって中全音律が使われるようになったわ。
理由は、3度の和音が協和音扱いされるようになったから。
で、バロック期から古典調律がいろいろ考案されて、ロマン派期にピアノが大量生産され始めたら平均律が普及したけど、これってピアノだけの話なのよ。
そもそも調律って、ギターみたいなフレットがある弦楽器とピアノにしか必要ないんだもの。
そうね、これから話すことを理解していただくために絶対必要だから、前提知識のもっと前提知識で、管弦楽法と調性格論の基礎の基礎に触れましょう。
今は本当に基礎の基礎しか話さないから、ちゃんとした講義は別にやるわね。
#と♭が付いてたら何の音でもいいけど、ド#とレ♭って平均律じゃ異名同音、同じ音よね。
調号の#と♭が違うだけで、変ト長調と嬰ヘ長調は「平均律のピアノで弾いたら」単音も和音も全部同じ音に聴こえるし、当たり前だけどギターみたいなフレットがある弦楽器でも同じ響きになるわ。
だったら、調号をどっちかに統合したら分かりやすいじゃない……とはならないのよ。
理由は、調律が要らない楽器じゃ、#と♭は異名異音だから。
具体的に言えば、フレットが無いヴァイオリンは平均律じゃ異名同音な音を弾き分けられるし、管楽器も息を吹き込む量とか強さを変えて吹き分けられるわ。
交響曲とか弦楽四重奏曲とか、ピアノを使わない編成のクラシック曲だと、調号が #な曲は少し音を高く、♭な曲は少し低く演奏するのが平均律が普及しきった皆さんの時代でもオーケストラの慣習なの。
だから平均律の譜面でも作曲家は異名同音を書き分けるし、書き分けなきゃいけないのよ。
楽器の奏法を知ってなきゃ話にならないから、これは管弦楽法の基礎の基礎になるわね。
管弦楽法って駄目な不正解はあるけど、正解は無数にあって、たった一つの最適解が無いから曖昧で難しいけど、ピアノ曲の感覚で書いたら失敗するって基礎知識くらいは持ってないと試行錯誤しても上手くいかないの。
じゃ、次は調性格論ね。
調性格論は迷信扱いなさる方も多い、管弦楽法よりもっと曖昧な分野よ。
迷信っていうか、どう聴こえるかが感性に依存しすぎてて、体系的に学問にするのは無理じゃない?って意見が多い感じ。
あと、平均律には調性格が無いって意見が目立つのも曖昧さに拍車をかけてるわね。
うちのマネージャーさん(ジャズを共作してる友人 @Missa_Celestial のこと、私のVTuberの準備を手伝ってもらってるからマネージャーさんって呼んでるわ)は平均律でも調性格はあるって意見だし、平均律でも調性格を聴き分けられるって研究結果もあるにはあるけど、調性格が無いって逆の結果も多く出てるくらい、仮にあるとしても平均律の調性格はかなり弱いの。
今話した平均律の調性格の研究にしたって、再現性が無くて結果がまちまちだから、あるのか無いのかよく分からない感じ。
っていうか、「調性格」の定義が問題ね。
平均律で演奏したって、例えばドとド # は誰が聴いても別の音でしょ。だから、ハ長調の曲を変ハ長調に移調したら、音階の構成音が全部半音上がるから、ハ長調の時とは違って聴こえるわ。
半音上に転調するのはポピュラーだと大サビを盛り上げるのによく使われるテクニックだけど、これを調性格って言うなら平均律に調性格はあるのよ。
転調で絶対音高が変わっても音色が同じなら、そもそも転調って行為が無意味になるから、これは当然でしょ。
だけど、本来の意味だと、調性格は単音の音色じゃなくて、和音の響き方を指す意味合いが強いの。
半音を全部機械的に100セントの間隔に分割してる平均律だと、転回とかをしなかったら、どの調でも長三和音も短三和音も縦の相対音高は常に同じよね。
ファが根音のヘ長調のIはハ長調だとIVで、ヘ長調のIの構成音はファドミだけど、ハ長調に転調してもファドミの3和音の絶対音高と相対音高はそのままだから、聴こえ方は同じでしょ。
そういう話をするなら、平均律に調性格は無いの。
だけど、調性格の有無もピアノみたいな鍵盤楽器に限った話なのよ。
例えばヴァイオリンは手で弦を押さえて音を変えるから、演奏に技術が要るけど、調ごとに音の高さを微妙に変えられるから、転調しても常にその調の純正な長三度を奏で続けられるわ。
これも管楽器もそうだけど、調律しなくていい楽器なら、構成音が同じでも調が違ったら和音の響きも違うの。
他にも、平均律がスタンダードな皆さんの時代でも、多声の声楽曲は純正律で歌うのが普通よね。
合唱の音合わせには純正律で調律したピアノを使うし。
純正律はピアノじゃ転調できないポンコツ調律だけど、人間の喉には調律なんて要らないから、どんな遠隔調に転調したって音が取れてたら問題無いもの。
声楽と器楽じゃ事情が違うし、器楽の中でさえ楽器の構造によって違うから一律に語れないってこと。
平均律って、スタンダードになったのは遅かったけど、実用化されたのは早かったの。
ギターとかヴィオラ・ダ・ガンバみたいなフレットがある弦楽器だと、ルネサンス初期には既に平均律が普及してたわ。
理由は、楽器の構造と製作技術。
フレットがある弦楽器を平均律以外の調律で作るのはかなり大変なの。
平均律だったら、フレットを等間隔に並べればいいけど、他の調律で作ろうとするとフレットの配置がばらばらになっちゃうわよね。
仮にそういう形の楽器を頑張って作っても、演奏する側も大変でしょ?
ってことは、元から調律が必要ない楽器と、フレットがある弦楽器じゃ、理由は逆だけど調性格の有無は最初から議論にならないの。
調性格って、凄く厳密に言ったら調律の必要がある鍵盤楽器で特定の和音を弾いた時に、調によって和音の響きが違って聴こえる現象を指す言葉なのよ。
だから、古代ギリシアからルネサンス初期まで、声楽が主流で縦の和音より横の旋律が重視されてた時期の西欧音楽じゃ、ずっとピタゴラス音律が使い続けられたの。
変える必要が無いなら変えなくてもいいでしょ?
逆に言えば、変える必要が生まれたからルネサンス音楽の時代に入ったら鍵盤楽器の調律に中全音律が使われるようになったのよ。
具体的な理由は、以前の講義で触れたわ。
3度っていう「協和音としては異常なくらい度数が近すぎる和音」が協和音として扱われるようになったから。
中全音律のチェンバロと平均律のギターで協奏した時に上手く音色が共鳴しないって、ルネサンス期ならではの問題を論じてる当時の文章なんかも見つかってるの。面白いでしょ?
さて、やっと古典調律の説明に必要な、ピタゴラス音律と中全音律がどう違ってるか説明するための前提知識の説明が済んだわ。
中全音律にはシントニック・コンマを4つ、5つ、6つに割ったものがあるけど、私が注釈無しで中全音律って言ってる時は4つのを指してると思って頂戴。
一般的って意味でもそうだし、長三度が純正になってるって意味でもそう。5つとか6つに割ると長三度が386セントじゃなくなるから、本末転倒なのよ。
で、ルネサンス音楽の講義の時にも話したけど、中全音律が採用されたのって、3度の和音を美しく響かせるためだったわよね。
ピタゴラス音律だと長三度が408セントだけど、中全音律だと長三度が386セントで純正だから。
だけど、中全音律はバロック期にいろんな古典調律が提唱されて、紆余曲折の末に、具体的には古典派の後期くらいの時期に平均律に取って代わられたわ。
そして、皆さんの時代でも調律が必要な楽器だと平均律がスタンダードのままよね。
今回の講義はどうしてそうなったのかの話だけど、これだけ予備知識を話して、やっと本題に入れるのよ。
お待たせしてしまったわ。
結論はとっても簡単で、ルネサンス音楽からバロック音楽に移ると、中全音律がニーズに合わなくなったから。
……だったら、どうしてバロック音楽じゃ中全音律が駄目になったのかしら?って過程の話がとっても長くなっちゃうの。
まず、スタンダードな音律が中全音律から平均律に変わるまでの時期に提唱されたいろんな音律を古典調律って総称するのが普通だけど、中全音律と違って古典調律のコンセプトは長三度を386セントにすることじゃないのよ。
いえ、もちろん、そういうコンセプトの古典調律もあるわ。
キルンベルガーさんは平均律に反対する急先鋒でもいらしたけど、彼が平均律に最後まで抗った理由は「長三度の響きが純正じゃないから」だもの。
だから、彼が提唱なさったキルンベルガーIIとかキルンベルガーIIIには純正な長3度があるわ。
だけど、そうじゃない音律もあるのよ。
一番有名な古典調律はヴェルクマイスターIIIだけど、これには純正な長三度が一つもないわ。
ヴェルクマイスターIIIはどの調も弾けるけど、純正な長三度が全くないのも特徴なの。
じゃあ、古典調律のコンセプトは、どの調にも転調出来るようにすることかしら。
……いいえ、それも違うの。
ラモー音律とかキルンベルガーIIだと、ホ長調みたいに響きが悪くて実用的じゃない調がわりとあるでしょ。
もし当時求められてたものが自由な転調だったとしたら、この辺りの音律は明らかにコンセプトに合ってないのよ。
転調が制限されるのは確かに中全音律の弱点だけど、いろんな古典調律が提唱された理由は別にあるの。
じゃあ、古典調律のコンセプトって何かしら?
答えは、ピタゴラス音律を使った時に聴こえる、408セントのピタゴラス長三度を無くすこと。
そもそも中全音律って、3度の和音を美しく響かせるために長三度が386セントになるようにした音律だったよね。
でも、バロック期に論点が変わったの。
純正な長三度とピタゴラス長三度の間に、シントニック・コンマって呼ばれる22セントの差があるわよね。
バロック期に入ると、純正な長三度より22セント広いピタゴラス長三度の響きが汚いって考えられるようになったのよ。
中世西欧音楽の講義の時も言ったけど、同じ西欧って地域でも聴衆の美的感覚って自然と変わるものなの。
で、中全音律は完全五度を5.5セント縮めて響きを少し濁すのと引き換えに、12個の長三度のうち8個は純正な386セントになるけど、残りの4個がピタゴラス長三度よりももっと広い427セントになるの。
41セントはほとんど微分音に近い間隔だから、ここまで広いと和音として使い物にならないでしょ。
だって、ピタゴラス長三度よりもっと激しく濁ってるもの。
調律には基音が必要だから、中全音律ではそういう長三度が現れる調、言い方を変えたら主音が調律の基音から離れてて調号が多い調の曲は、調律をやり直さないと一切演奏できないのよ。
だけど、鍵盤楽器の調律にはかなり手間暇が要るから、コンサートの時に曲ごとに調律をやり直すなんて非現実的よね。
バロック期に入ると声楽から器楽が主流になって、鍵盤楽器の演奏会も増えたから、そのニーズに応えるために古典調律は考案されたの。
ちなみに、ロマン派の時代でもショパンさんは純正な3度の和音の響きにこだわって中全音律を主に使ってたけど、違う基音で調律したピアノをステージに3台並べて、曲ごとに使うピアノを変えるって手で対処なさってたそうよ。
それともう一つ、和音の響きの問題と比べてこっちはあまり知られてないけど、中全音律にはもう一つピタゴラス音律より半音が広いって弱点もあるの。
調性音楽には導音の概念があるわよね。
ピタゴラス音律だと導音のシと主音のドの間隔は90セントだけど、中全音律だと、これが117セントになるわ。
導音と主音の間が27セントも広いから、中全音律を使って演奏するとメロディの美しさが損なわれちゃうの。
単旋律のグレゴリオ聖歌はピタゴラス音律で歌われてたけど、グレゴリオ聖歌のメロディを中全音律で調律したチェンバロとかピアノで演奏すると、凄く間抜けな響きに聴こえちゃうってこと。
要するに、古典調律のコンセプトは純正な長三度の美しい響きを楽しむことじゃなくて、22セント分濁ってるピタゴラス長三度と、それ以上に濁ってる3度の絶対数をなるべく減らすことなのよ。
だから、ヴェルクマイスターIIIみたいに386セントの純正な長三度が一つもない古典調律があるの。
ちなみに、ピタゴラス長三度の数はヴェルクマイスターIIIだと3つ、キルンベルガーIIだと4つ、キルンベルガーIIIだと2つ。
で、さっきも言ったけど、中全音律は5度の響きの美しさを犠牲に長三度を純正にしてるの。
ってことは、5度が700セントで2セント狭いだけの平均律で聴くのと違って、696.6セントまで狭めてる中全音律の空虚五度はかなりきつく濁っちゃうのよ。
ここまで話したら、皆さんもお気付きでしょ?
和声法で平行五度が絶対の禁忌なのは、中全音律で平行五度をやると空虚五度の濁った響きが過度に強調されちゃって耳が苦痛だから。
だから古典派期の作曲家の皆さんは平行五度を使わなかったけど、これって経験則みたいなものだから、平均律がスタンダードな皆さんの時代だと、後からまとめた和声法で平行五度が禁則な理由のコンセンサスが全く取れなくなっちゃったわけ。
5度が濁る問題に、中全音律は「純正な3度が一緒に鳴ってたら多少5度が濁ってても平気」ってかなり脳筋な発想で対応したけど、これは5度の和音を鳴らす時は絶対三和音にしろって意味だから、教会旋法が崩壊して調性システムに収束する流れにグラレアーヌスさんと同じくらい強く影響したでしょうね。
……さて、ここで一つ、大きな疑問が生まれるわ。
平均律の長3度は400セントだけど、これって中全音律の386セントより、ピタゴラス音律の408セントに近いわよね。
いくら中全音律の長三度がもっと広かったからって、バロック後期にピタゴラス長三度の響きが嫌われてたなら、長三度が全然純正じゃない平均律が他の音律、特に最後まで抵抗してたキルンベルガーIIIに勝って受け入れられたのはおかしいでしょ。
だけど、キルンベルガーさんの論敵で平均律推進派だったマールプルクさんの調律だと、全ての長三度が平均律と同じ400セントで、現実には古典派音楽の初期には既に平均律に近い調律がかなり広まってた、正確に言うとまだ机上の空論だった平均律の支持者が多かったの。
ちなみに、マールプルクさんの音律が完全な平均律じゃないのはフレットがある弦楽器と違って、ピアノを平均律で調律するのは技術的に20世紀まで難しかったから。
平均律が勝ったのは、矛盾した説明に聞こえるでしょうけど、中全音律と違って古典調律にははっきりと調性格があるから。
平均律に調性格がないって立場だと、中全音律にも調性格がないことになるのよ。
もちろん、和音が綺麗な調と和音が激しく濁る調だと3度の間隔が違ってるから、響きは全然違うわ。
だけど、中全音律で演奏して美しく聴こえる調だと常に長三度が386セント、完全五度が696.6セントだから、転調しても和音の響き方が同じ、調性格がないことになるの。
厳密には、中全音律には長三度が386セントで響きが綺麗な調と、427セントで激しく濁ってる調の2つしか調性格が無いって言うべきね。
そもそも、中全音律って名前は「この音律には大全音と小全音がなくて、その中間の中全音しかない」ってネーミングなの。
中全音しかないから、中全音律は転調しても和音の構成音の間隔が同じままなわけ。名が体を表してて、分かりやすいでしょ?
言い方を変えたら、特にヴェルクマイスターIIIは顕著だけど、古典調律には大全音と小全音があって、中全音律とか平均律と違って調性格があるの。
調性格があったら、転調したら構成音が同じ和音が転調前と違う響きになるでしょ。
だったら、古典調律だと中全音律より転調の重要性が強くなるわよね。
そうやって転調が頻繁になったら、今度は遠隔調への転調を難しくする大全音と小全音が邪魔になったの。
マールプルクさん派の皆さんは、純正な長三度より転調を重視なさってたって言うべきかしら。
それに、ウルフの五度は中全音律にも残ってるでしょ。
転調するためにヴェルクマイスターIIIとかキルンベルガーIIIみたいに全部の調を演奏出来る音律が生み出されたんじゃなくて、そういう音律が生み出されたから結果的に転調が頻繁に使われるようになったのよ。
ここの因果関係を理解しないと、平行五度が禁則な理由を掴みにくいの。
もう少し詳しく触れると、不均等音律で響きは調ごとに違うけど、どの調も弾けるヴェルクマイスターIIIがきっかけで濁ってて純正じゃない和音も排除するものじゃなくて味わいよね、って風潮が生まれて、濁った和音でもいいなら平均律でいいじゃない、って結論になった感じね。
ヴェルクマイスターIIIがきっかけなのは、多分ラモー音律とかキルンベルガーII、IIIと比べて癖が弱くて牧歌的な響きの音律だから。
響きが穏やかだから、他の音律だと鋭く聴こえる濁りがヴェルクマイスターIIIだと緩和されて、当時の作曲家とか聴衆の皆さんの耳の許容範囲になったんじゃないかしら。
長三度を純正にしましょう(中全音律)→響きが濁ってるピタゴラス長三度を減らしましょう(古典調律)→もっと転調しやすくしましょう(平均律)って、古典調律はパラダイムシフトが2回起きてるの。
平行五度の禁則は中全音律の副産物だし、転調の増加は古典調律の副産物なのよ。
この辺りはバロック期の自由対位法にも影響を与えてて、自由対位法が同主調をあまり区別しないのは多分ヴェルクマイスターIIIがご本人が「半音階向き」ってコメントなさってる構造の音律だったのもわりと大きめな理由のはずだわ。
ヴェルクマイスターIIIは黒鍵を使うほどメロディが綺麗になるから。
最後に、もう一つ重要なポイント。
古典調律って、ピタゴラス音律に改良を加えた音律と、中全音律に改良を加えた音律の2種類に分かれてるの。
具体的には、ヴェルクマイスターIIIとかキルンベルガーIIIが前者で、ラモー音律とかキルンベルガーIIが後者。
ピタゴラス長三度を減らすのとウルフの五度の濁りを軽くするのは共通の命題だけど、じゃあ両者がどう違うかっていうと、ピタゴラス音律が元の音律はとにかく使える和音を増やすことを優先してて、中全音律が元の音律は純正な長三度をできるだけ残すことを優先してる感じね。
……講義はこんなところね。
今回は平行五度の問題と古典調律の話を両方一緒に、かなりあっさり終わらせられたわ。
並行していくつも講義の原稿を書いてるから、次回の講義が何になるか分からないけど、次こそもっと早く開けるように頑張るわ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
