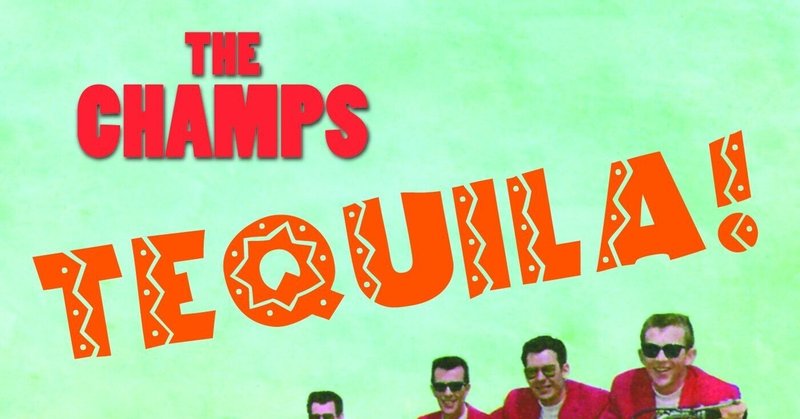
テキーラ TEQUILA / 1958 The Champs & Cover Version
スタンダード・ナンバーのテキーラは、アメリカのカリフォルニアのチャンプスというバンドの1958年にリリースされた楽曲がオリジナル。カリフォルルニア州はメキシコと隣接し、文化も音楽もクロス・オーバーしている。
歴史的に重要な音楽の録音を称える「The Grammy Hall of Fame」、グラミーの殿堂入りもしている。
メロディーも聴いたことがある機会も多いと思われるのでちょっと言語化してみると、「てってれてれてってー」っていう例のアレだ。オリジナルといくつかのカバー・バージョンの中でアマゾン・ミュージックで視聴可能なナンバーをピック・アップ。
The Champs
オリジナルのナンバー。アコギのスタッカートのカッティング、サックスによるメインテーマで展開していく。
この録音時点でまさかスタンダードになるとメンバー全員思っていないので空気がユルい。普通に演奏を執り行っている。
しかし、そんな普通な空気が魅力とも言えるし、なんかツッコミ甲斐が有る=カバーのしがいがある。のかもしれない。
かぶ飲みしてゲップがでそうな感じに聴こえる、下世話な「テキーーラ」の掛け声も怪しくていい感じだ。というかスタンダードなのが分かってるので強引にそう聴こえてしまっているのかもしれない。
The Ventures 1963
ギター・インスト・バンドのベンチャーズは1963年にカバーしている。
ここではもうこの曲が「スタンダード」である確信めいたものが演奏から感じ取れる。
冒頭に「タキーラ」(訛っている)とシャウトするが、結構の自信だし、そうなるとバッキングのアコースティック・ギターも確信を持って掻き鳴らしている風に思えてくる。
エレキ・ギターではオルタネイト・ピッキングで明瞭&明確に弾き、メインのメロディに少しアドリブのフレーズを足している。つまり曲にストーリーみたいなのを付加させて曲の価値を引き上げようとしている。
ベンチャーズの絶対駄作にならないであろうという「暗黙の安心感」に加え独自のワイルドさ、ストリート感覚も溢れている好カバー。
Wes Montgomery / Tequila 1966
ジャズ・ギタリストのウェス・モンゴメリーは、1966年のアルバム、そのまま『Tequila』という作品で収録。
メイン・テーマをまず一巡させ、二巡目で突入するアドリブのソロが予測を巧みにかわす。オクターブ・フレーズの冷静な応酬もオンリー・ワンだ
指板が次にどこに移動し、展開するのか予想しつつもウェスに裏切られる。ギター・ソロの内に秘める燃える魂も健在。
テキーラのように誰もが知っている曲や汎用性の高い曲でも普通に個性を光らせるのが上手い。1970年代以降ももし生きていたら、スムーズ・ジャズとAORをどのように表現していたのか興味深い。
Dr Feelgood / Down by the Jetty
ドクター・フィールグッドは、1975年のデビュー・アルバム『Down by the Jetty』でこの曲をライブ音源で収録している。「Bony Moronie」の中間部でテンポが変わりテキーラが挿入される。ちょっとライブの空気がこのライブでも変わったのが分かる。イギリスでも誰もが知っているという実況音源だ。
幾多の数えきれないギグを重ねた「たたき上げのバンドの音」が聴ける。
投入するタイミングはセンスを問われるが閑話休題的に流れを変えたいときなどテキーラは効果的だと思う。
The Manhattan Transfer 2018
マンハッタン・トランスファーは超ハイ・レベルの男女4人のボーカル・グループ。歌詞をつけて4声で活舌良く歌い上げる。長年の地道な継続によって築き上げられた一体感がパーフェクトで鳥肌が立ってくる。
この曲のコミカルなテイストもちゃんと汲み取っていて、そんなところに細かな愛情を感じる。このグループの強みはジャンル関係なくどんな曲だろうが、とにかく歌うことが好きで好きでたまらないというのがストレートに伝わってくる点だ。
Arlen Roth with Danny Gatton Toolin'Around
「Masters of the Telecaster」、フェンダー・テレキャスターを極めたと言い切ってしまえるギタリスト、アーレン・ロス。彼ともう一人のテレマスターのダニー・ガットンとのデュエット形式のインストナンバー。
アーレン・ロスは温厚でベテランのスタジオ・ミュージシャンと演奏動画のインストラクターだ。
イントロはギターのボリュームを絞るペダル・スチール奏法から始まる。
このギタリストがどんなギタリストなのか知っているとこれが嵐の前の静けさという趣で、地味なのが却って(プレイの)恐怖を感じさせる。
メインのフレーズの2巡目からは一切の遠慮はなく、えげつないピッキング・ハーモニクスの応酬をこれでもかと放つ。メロディのニュアンス1つ1つが繊細でそれぞれ異なったトーンを繰り出す。予想通り、いやそれ以上にギターが上手過ぎる。
アームの無いテレキャスによるアーミングのトリッキーなフレーズも冷静なタイム感で演出。それを数種類のトーンで使い分けたり、執拗に同じソロのフレーズを弾くにしてもハーモニクスやボリューム奏法やら微細な変化が止まらなくてちょっと怖くてヤバい。明瞭なピッキングによって出されるリバーブの残響音も効果的でトーンもえげつない。
多くのギタリストがひれ伏すヘルキャスター、地獄のテレキャスサウンドが数分間で濃厚に味わえる。
Larry Carlton / Friends 1983
ラリー・カールトンのバージョンはテンポを落とし、想像の斜め上のスムース・ジャズ・アレンジに仕上げている。
マイケル・ブレッカーのサックスが1巡目のメロディを洗練に吹く。
ジェフ・ポーカロのドラムも安心して聴ける。彼のドラムのリズムの刻みは何気なくシンプルなのにとても心地良い。ファースト・コール・ミュージシャンなのもこのナンバーを聴いただけでも納得できる。
主役のラリー・カールトンはメイン・テーマ2巡目からソロを弾き始める。チョーキング&ビブラートがねちっこい。音数少な目でブルージーに展開し、マイケルのサックスとソロを交差する。
一歩引いて、少し抜いて、と異色のアレンジながらもやっぱりハイ・レベル演奏のため何回もリピートして聴いてしまう。
何ていうのだろうか「ビバリーヒルズ・アレンジ」とか命名してみたい。
David Sanborn with Steve Gadd
2003年リリースのアルバム「タイム・アゲイン(Time Again)」に収録。
パーカッシブにメインテーマとアドリブ・ソロ吹く。サンボーンのサックスのメロディでほぼ音楽を成立させている。アドリブも淡泊な感じだ。
ドラムはスティーブ・ガッド。パーカションの感覚というかわざと歌心あるドラムを封印して粛々と刻んでいる印象を持つ。メロディ楽器のサンボーンのサックスと対峙してるようにも聴けるし、反対にサックスを引き立てているようにも聴ける。
スタジオ・ライブ的の一発勝負録音の仕上がりになっている。多忙でスケジュールをなかなか抑えることが難しいスティーブ・ガッド。せっかくの機会だしセッション的な曲だったら「テキーラ」かなみたいな選曲理由かなと推測してみた。
こなれていても緊張感は保っていて両雄が音で合わせればこうなるよなという期待通りの出来になっている。
ま、結局ガッド&サンボーンの2人融合する音楽は何をどうのようにやってもカッコいい。ラリー・カールトンともアプローチが異なるアーバン・ファンク的スムース・ジャズと対比的に書いてみた。
総論
シンプルなメロディ・ラインにそれぞれの楽器、管楽器も弦楽器も共通しているのは1音に賭ける思いが濃い点。
このミュージシャンやバンド、またそのメンツでどんな風に取り組むのか、その答え合わせが、期待を裏切ったアレンジでだったり、予想を上回る演奏力だったりと色々楽しめる。
簡単な表現というのは奥が深くて結構難しいものでもある。
終わり
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
