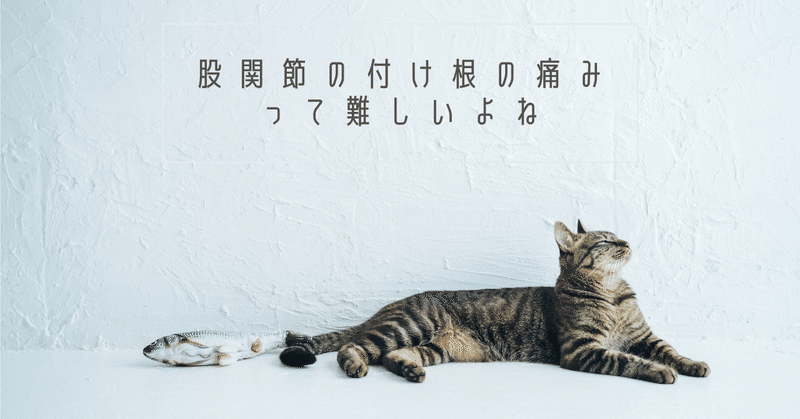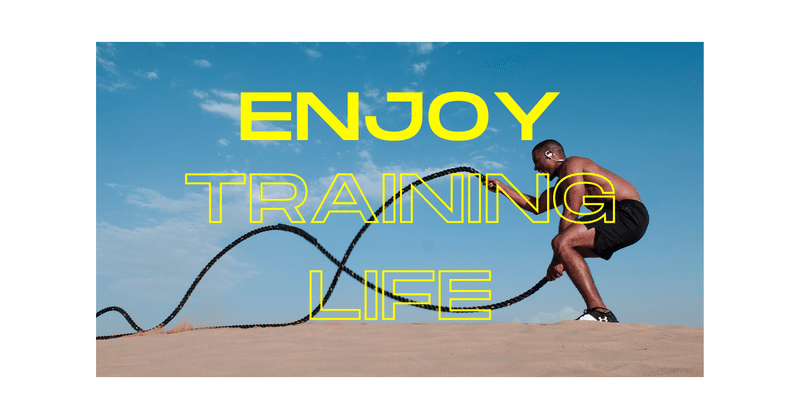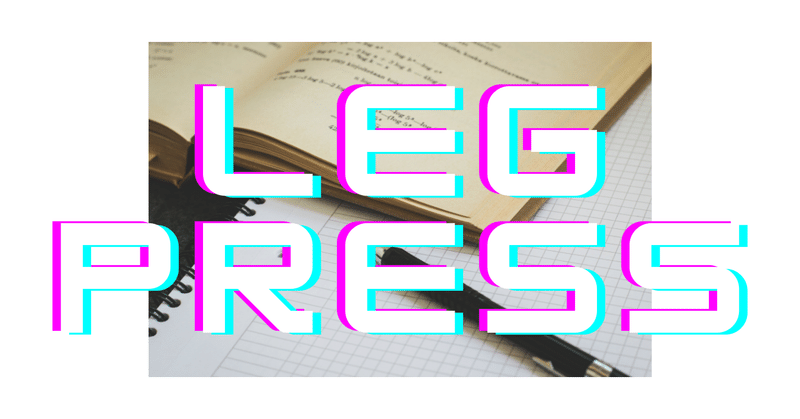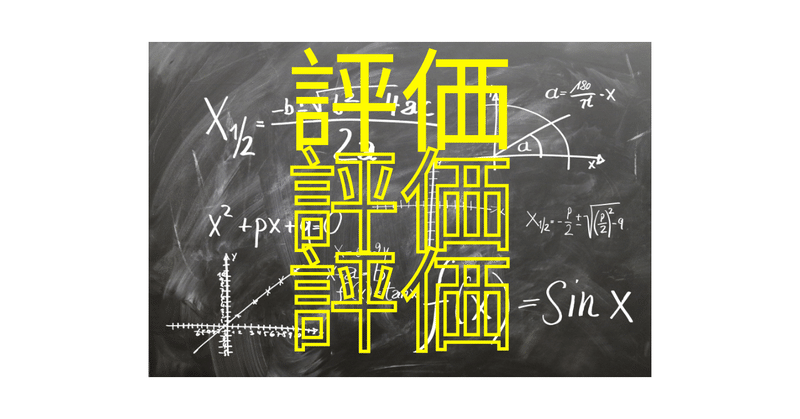記事一覧
(大幅修正後)股関節前方部痛の解釈に必要なことを勝手に深ぼってみた件
臨床で股関節前部のつまり感や痛みを訴える方は多いですよね。
股関節のつまり感というと・・・
後方組織が固くて前が詰まって痛くなる
このようなイメージが勝手にありますが、、、
Femoroacetabular impingement(FAI)をはじめとした関節構成体の形態変化が関与する場合もありますし、何が詰まっているのか?、詰まったから痛いのか?など原因不明なまま介入をしてしまう、なんて場
ピラティスの目的とエクササイズ処方の繋がり−現場編−
本日はピラティス第二章を書いていきます。
前回はこんな感じでピラティスの概念やアラインメントの見方について説明をしました。
今回の記事はピラティスを実際に臨床で使うことを想定し、姿勢などとの紐付け方を私見を交えて解説していきます。
前回の記事でも触れましたが、ピラティスでは良いアラインメント(ニュートラルポジション)の定義が非常に明瞭なため、治療だけではなく評価としても活用することができます
トレーニングやストレッチ処方のコツ(私見を交えて)
世にはストレッチや筋トレの方法は溢れていますよね。
知識が増え始めると
などと考えてしまうことは多いですよね。
自分が極めた知識・技術やお金を払って得た経験は確かに貴重なものですので、それを大切にしたいという気持ちも否定はしません。
適切な治療とは『目の前の人のニーズを最も早く達成する方法』であることは疑いようもありませんね。
なので大切なのは評価と介入の関連性やその引き出しの多さであり
Leg pressを深めてみようの巻
本日はレッグプレスについて書いていきます。
レッグプレスはトレーニングとして用いられることは良く知られますが、研究などではLower Leg Power(脚力)の指標としても用いられており、Lower Leg Powerの低下はFall Injury Risk(転倒障害のリスク)と関連していることが明らかにされています(Winger et al. 2023)。
短編企画 運動力学の視点をトレーニング指導に反映する方法−その1−
私が今、博士課程で運動学や運動力学、筋電図学を専門に研究を進める中でトレーニングへの見方も変化してきました。私が感じる視点を共有したいと考えます。
本日もよろしくお願い致します。
立位でのエクササイズー腰椎を制御する因子・基礎知識後編−腹圧などに着目して−
はじめに本日は腰椎の安定性について腹圧などについても軽く触れていきたいと思います。
修士過程の課題が重量物の持ち上げ動作であったのでこの関連領域を調べていた経験がありますが、沼領域だとは思います。
答えを提供することはできませんが、皆さんの考える力の一助となれば幸いです。ではいきましょう。
立位でのエクササイズー腰椎を制御する因子・基礎知識前編−
前回の記事では腰椎が屈曲してしまう場合の注意点や簡単なトレーニングの方向性について触れていきました。
今月・来月の記事では
腰椎制御に関わる胸腰筋膜の構造や呼吸や腹圧についての理解
を深めていき、8月の記事では実際のトレーニングの話に進んでいきます。
基礎知識系は退屈かもしれませんが、知識が少ないと応用が聞かなかったり、相手の意見を客観的に見れなかったりします。
今回で得た知識を次の記事
長期連載シリーズ 立位でのエクササイズエラー
本日は先月の続きというのことで、”立位でのエクササイズ”について触れていきます。
本日は大殿筋をターゲットとした立位エクササイズの代表格であるスクワットやブルガリアンスクワットについて、代表的なエラーの原因を絡めて解説していきます。
長期連載シリーズ 自重トレーニングの基礎-大殿筋-
本日はトレーニングビギナーの方や高齢者など非ウエイトトレーニングで自重トレーニングを指導するときに着目すべき視点や、エクササイズでなぜその筋肉が働くかを
本日から数ヶ月間(全12回程度になりそう、、、)は字数の許す限り
の順で記載していきます。
本記事は連続執筆企画であり、今年一年でこれらの筋の自重トレーニングについて理解を深めていきましょう!
肩の可動域と動作観察について(屈曲制限とサイドレイズを例に)
本日は肩の可動域制限について、理解を深めていきたいと思います。
方法としては肩の制限因子を事前に把握して、関節運動を変えていくことで絞り込んでいく方法です!