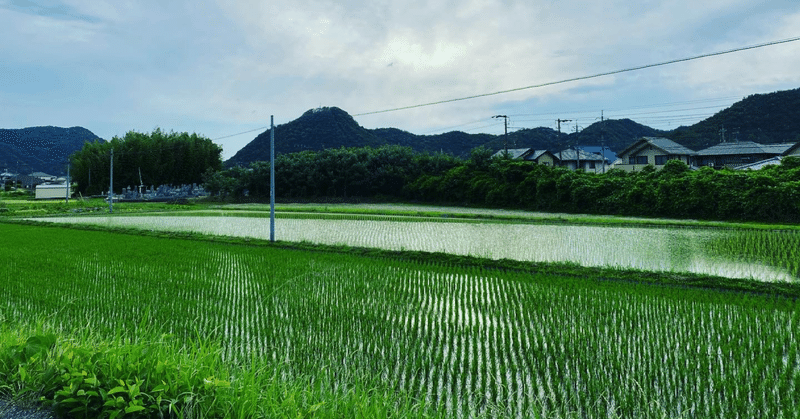
東京ゼロ、大阪1%の地域別食料自給率と日本の食料「自給力」
このマガジンの紹介文で記していますが、
ちゃんと記事にしてなかったのであらためて。
農水省が解りやすい記事を書いてくれています。
「都道府県別食料自給率と食料自給力指標」(令和2年度・2020)
令和2年度の食料自給率について、
カロリーベースで37%、生産額ベースで67%。上記リンク先内の表は令和元年度のもの。そこでは38%・66%と
なっていて、この辺が役所の資料のややこしいところ^^;この資料⇑、は結構面白いです。「飼料自給率」や「国民1年あたりの消費量推移」などあって、消費量推移・「お米」の減り具合がすごい^^;;
「東京都は、1998年度の統計開始以来21年連続で自給率1%だったが、今回は0.49%となり、四捨五入した数値で発表されるため0%となった」
とのこと。(「アグリの樹」より)
ただし「小松菜や春菊といった葉物野菜では全国有数の産地」ですが、
葉物はカロリーがほぼない。生産額ベースでも東京3%。
大阪6%ですので、一部で流通しているということなのでしょう。
本題・・・
先言うときます^^;すんませ~ん!
私が以下のことをちゃんとやれてはおりませんで・・・
自分にとっての「テーマとして」という意味が強いです^^;
いいわけか!!!^^;;
では、本題。
①「都市農業」を盛んにすること。
それが「自給率アップに寄与」していけないか。
② 併せて、食品ロスを減らすこと。
それは都市部に暮らす者の「もはや責務」ではないかいな。
この二つについて考えていきます。
まず「自給」していくにはどれくらいの農地が必要か、です。
農水省HPによりますと、
現在の普段の食生活を続けると仮定して、一人が一年に食べる食料を作るために必要な農地面積を試算すると約11a、テニスコート4面分くらい面積となります
国内の総農地面積は437万haですから、これを人口で割った一人当たりの
国内農地面積は3.5aほどとなり、必要な11aの3分の1程度」
テニスコート1面強ほどはあるのか。
といいつつ「全国平均して」ですよね。
大阪府で考えてみると、大阪府の「田耕作面積」は8,640haで、
人口880万人。1人当たり約0.00098ha。ざっくり0.001ha。
1ha・・・1万平方メートル/100m×100m。
つまり大阪は、
1人当たり10平方メートル/1m×10m或いは2m×5mの面積。
畑耕作面積3,760haを加えても0.0014ha。誤差レベル^^;
合ってますよね?計算^^;
既に文系脳は疲労している・・・><
2×5mって、トヨタのランドクルーザーとほぼ同じです。
ほぉ~・・・あれくらいの面積かぁ。
車一台分の面積しか田んぼはない・・・けれど!!!
家庭菜園で、野菜ならそれなりの収穫はできそうな。
旬の枝豆ならカロリーも。(100gあたり135kcal)
少ない耕地面積ながら、完全自給は無理ではあるけれど。
これとてエリアによって農地が多い所、少ない所でバラツキが。
ベランダ菜園・・・ありですな。
タワマンは厳しいか。はぁ、あれこれ大変やな^^;;
可能性あると思います。
なんなとやりようはあるでしょう(楽観的^^)。
続く・・・・・。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
