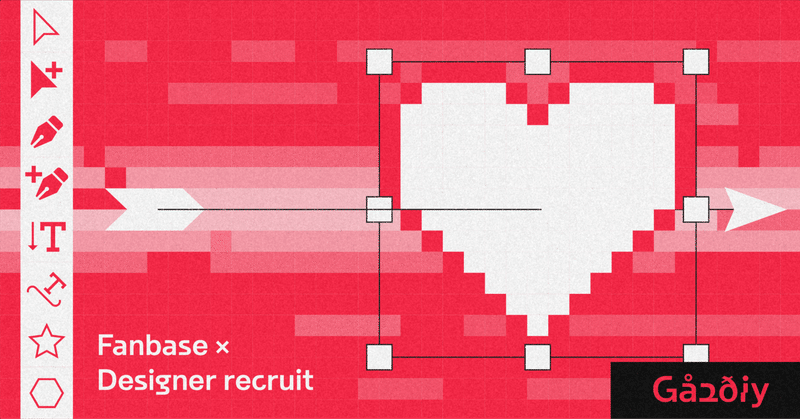
デザイナー×ファンベース採用で実践した全てのことを公開します
こんにちは、GaudiyでProductEnable / DesignOpsをやっている坪内(@mrhiro1112)です。
前職までのPdMキャリアから、現職Gaudiyでは『プロダクト組織・デザイン組織のEnable・Ops』に移り、急成長していく組織課題やプロセス改善、採用に取り組んでいます。デザイナーの採用担当や採用広報に取り組むようになり、はじめて見えた景色や気づきがあります。
まだまだ道半ばで試行錯誤の過程ではあるのですが、デザイン組織では1年で7名ほど(業務委託を含む)採用してきた中で、デザイナーこそ「ファンベース採用」が必要だと気づき、僕なりの視点でnoteにまとめようと思います。
ひとつの形としてなにかの参考になれば嬉しいです!
1. PdMがデザイナー採用担当になるまで
デザイナー採用担当になった経緯
元々はPdMでしたが、GaudiyにはUXデザイナーとして入社し、さらに拡大するデザイン組織のPM的なポジションとして、昨年末ごろからDesignOps(Design Enable)やデザイナー採用に取り組むことになりました。
以前から「プロダクトマネジメントはPdMだけがするものではない」という考え方を持っていたので、「デザインはデザイナーだけの仕事にしない」「採用は人事の仕事にしない」を基本スタンスとして、自分のケイパビリティがデザイン組織の運営やデザイナー採用にどう活かせるか?を試行錯誤してこれまで取り組んできました。その中で、デザイナーの採用活動(採用広報・社外との関係づくりも含む)を1つのスクラム的・コミュニティ的なチーム活動と捉え、実行するやり方を掴みつつあります。
デザイナー採用を通じて解決したいIssue
デザイナー採用に対するモチベーションとしては、「デザイナー不足により、兼務となることでデザインやユーザー、チームに向き合う時間を捻出しきれず、スクラムチームやブランディングの活動にコミットしきれない」という当時発生していた課題を、採用や組織づくりを通じて解決したかったという背景があります。
デザイナーがデザインにも採用にも積極的に取り組める状況・環境をつくることも、1つのデザインであり、採用を含む組織づくりだと捉えています。

2. 取り組む中で見えてきた課題
ex-クックパッドで、稀有なCDO・デザインマネージャーの背中を見てきた中で、デザイン組織づくりや採用活動の難しさは当時PdMだった自分もヒシヒシと感じていました。
僕自身は初めての採用担当なので、まずはドメイン(デザイナー採用市場)への理解を深めるため、先輩方へのヒアリングやリサーチで、構造やドメイン、ヒト、事業、チームの特徴・課題を整理していきました。
ヒアリングでは、デザイン組織づくりやマネジメント、採用など幅広く先輩方にお伺いさせていただき、時にディスカッションさせていただきました。
中でも、 PM経験があり、デザインマネージャーの先輩でもあるファインディのムカイさん ( @osk_kamui )には、面識もない中でも快く相談に乗っていただきました!採用に関することだけでなく、組織や業務設計、役割定義、組織運営に対するスタンスなど、幅広い角度でヒアリングさせていただきました。リファラルと組織状態の関係性、社内推進の考え方など、目からウロコでした。(とてもお世話になりました!)

Mukaiさんがマネージャーとして取り組んだこと
- デザインチームのマネジメントについて他社デザインマネージャーに話を伺う
- 某社CDOの方数名に話を聞いて視座が高まりまくる。その節はお世話になりました
- なぜ入社したのかメンバーに聞いてみました
その後、CDOやデザインマネージャー、Design Program Managerなどにヒアリングさせていただき、課題や構造化の解像度があがっていきました。特にデザイナー採用における再現性の低さ、採用におけるセンターピンでもあるカルチャーフィットとスキルフィットのマッチング、そのための言語化、イベントと発信、リファラル、タレントプール、採用活動へのコミットメントなど、なぜそれらにこだわり、取り組んでいるのか、その背景にどんな課題があるのかを学ばせてもらいました。
採用KPIとファネルだけで、達成する難しさ
その中で、採用計画の達成に必要なアクションや指標の考え方も、他職種と異なるスタンスがありました。基本的に採用活動は「一定科学・管理ができて、成功要因や方程式が存在するもの」という理解・経験はしています。
ですが、その上で「⚪︎月までにXX名採用するには、選考通過率の実績がこれくらいだから、△月までに採用リードをYY件獲得しよう」みたいな形で科学・管理するようなファネル・指標の罠もあり、ことデザイナー採用においては、デザイナーという候補者の性質や、デザイナー採用市場特有の複雑性から、その罠に陥りやすいと考えています。

指標化の失敗:数字に踊られるヒト
問題を本質的に解決ができていなくても、別の方法で設定された指標をコントロールできる抜け道が存在してしまう。測りやすい指標ばかりが取り上げられ、それに引きづられてしまうことがある。
上記のように、認知・関心>面談・応募>内定・承諾>入社というジャーニーを一直線のファネル・KPIとして取り扱い、量を達成するための発信や施策を回していくことは、ときにアンチパターンに陥りやすいという課題です。
上記の活動は、職種の理解や丁寧なマッチングが必要なデザイナー市場および候補者にとって、コストとリスクだけが上がり、デザイナー(候補者・社内)が疲弊しやすい状況に陥る罠があると感じています。
だからこそ、職種がもたらす価値の言語化、N=1で向き合うIssueと機会のマッチングの大事さに気づくことができました。
対象となるパイが限定的で、転職意欲も高くない
デザイナー(特にシニアクラスのデジタルプロダクトデザイナーやコミュニケーションデザイナー)を採用する難しさは言わずもがなです。
UI/UXデザイナーで年間転職者は1,800人、月に150人です。それをエージェントやダイレクトリクルーティングなどチャネル別に分解するともっと少ないです。
実は、国勢調査では、20万人弱と推定されています。デジタル分野以外の方も含んでいるので、デジタル分野に狭めるともっともっと少ないです。ITエンジニアは100万人ほどと言われているので、本当に珍しいですよね。
<中略>
デザインが広がり、デザイナーを求める企業が増え、さらに、デザイナーにはさまざまな専門領域がある。そう考えると「本当に採用したいデザイナーに出会えたら、もうそれは “奇跡” に近いような出会い」だと思うのは私だけでしょうか?
Gaudiyは、スタートアップかつ、複雑な事業・組織で自律性と専門性を高く求める傾向にあるため、採用ターゲットは必然的に狭くなりやすいです。
採用したくなったタイミングで採用できる優秀なデザイナーは存在しない、ということを念頭に事前の土台作りに時間をさきましょう。
世の中には「いいデザイナー」は存在せず、自社にマッチ度が高いデザイナーを、限られた市場の中でじっくりとお互いに見つけ合い、出会うのだと気づきました。
最近は、転職顕在層になってからのアプローチでは遅く、転職ツール外で採用活動を完結する人も一定以上存在します。XやYOUTRUSTなどSNSの投稿や入社エントリーで転職意欲があったことを知るケースも少なくありません。意欲があがったときに、自社の第一想起とコンタクト可能な状態にしていく必要があります。(が、その状態をつくることも維持することも、簡単ではありません)
必然的に、長期戦にならざるを得ない
サービス開発、特にデザインやユーザーリサーチなどユーザーに゙対峙しているほど、ブランドやサービスづくりをしているほど、愛着はあります。サービスや会社、チームへの愛が力になり、長期にわたってブランドやサービス、会社に所属する方も多くいるのが実態です。
また個人でも仕事ができ、単価をあげやすい故に、フリーランスや独立、CXOとして活躍される方も少なくありません。僕の尊敬する先輩方や同僚、後輩もこのキャリアを通っているケースをよく見かけます。
当然ながら、組織拡大に向けて「即戦力採用」という企業都合での採用はうまくいきません。「正社員としてすぐ転職したい」わけでは必ずしもなく、複数回の接点・機会を経て、数ヶ月・数年後に応募があったり、副業や業務委託としてジョインというパターンも発生します。よりよいマッチング機会をつくるためにその必要性も増していると思います。
見えてきた自社特有の課題
また社内で採用課題を振り返ってみて、以下の課題が見えてきました。
ホワイトラベル型BtoBtoCサービスの難しさ
Gaudiyは、Web3を活用したファンコミュニティサービスを提供する企業です。これは、エンタメのIP企業と、そのIPのファンの間を橋渡しをする、ホワイトラベルサービスとしての役割を持ちます。つまり、Gaudiyは自社のブランドを前面に出すことなく、クライアントのブランドとしてサービスを展開し、エンドユーザーに直接触れることはありません。
ゆえに、エンドユーザーには自社のサービスが直接認識されにくい状況があり、デザイナーから「よいプロダクト」として認知されづらい状況です。
コーポレート認知と自分ごと化の壁
Gaudiyは、バリューの1つでもある「New Standard」な取り組みを積極的にしており、ありがたいことに業界内での認知は少しずつ広がってきています。以下のようなお声をいただくことも少なくありません。
Web3の新しいことやってる会社ですよね!
代表選挙とか、ユニークな制度の会社やってる会社ですよね!
リブランディングした会社ですよね!
一方で、断片的には目にするけど、実際何をやってるかわからない、デザイン組織のことをよく知らない、という認知・関心の壁に直面しています。
「Gaudiyって聞いたことあるんですが、なにやってるんですか?」
「その規模のデザイン組織で、デザイナー必要なんですか?」
「どんなプロダクトなんですか?なにをデザインするんですか?」
その取り組みを潜在的な未来のメンバーに知ってもらい、より多くの人々に「自分ごと」として認識してもらえるかが大きな課題となります。
そこで私たちは、未認知や、断片的な認知の状態から、会社のことをよく知っていただいた上で、周囲の人にも推奨いただけるような状態、つまり「推される会社・チーム」を目指して、デザイナー採用にも取り組んでいくことにしました。
3. デザイナー×ファンベース採用
ようやく本題ですが、デザイナーこそ「ファンベース採用」をしていく必要性を感じた自分が、どのように取り組んだかをまとめていきます。
ファンベース採用とは
Gaudiyでは、採用活動を線ではなく円で捉え、候補者との継続的な接点をつくり、企業のファンを増やす活動をファンベース採用と捉えています。

詳しくはHR/PRの山本のファンベース採用に関するnoteやスライドを参照ください。(本記事は、ファンベース採用を教科書的に引用し、デザイナー採用文脈での取り組みをまとめたものです。)
デザイナー×ファンベース採用で大事にしていること
デザイナー採用は特に市場の流動性が高くないため、転職を考えはじめる前の潜在層にGaudiyという存在を知ってもらい、転職を考え始めた時の「第一想起群」に入れるかが大事です。だからこそ、まずは認知の壁を越えることが重要。
そして、第一想起群に入るためには、ただ認知されてるだけじゃ弱いとも思います。もう一歩踏み込んで「関心」を持ってもらい、できれば一度「接点」まで持っていきたいと考えています。

ポイントは、無作為にDの拡大を狙うのではなく、まずA〜Cを非連続・連続的に取り組みを続けていきながら、コアファンを増やしていくことを目指しています。
A. コアファン層…企業ではたらく人。フルコミな人たち。
B. ファン(推奨者)層…企業のことをよく知っており、周囲の人にオススメしてる人。(ex. 卒業生、辞退者/見送り者、株主、外部顧問、クライアント/ユーザー、業務委託メンバー、知人友人など)
C. 関心層…企業や中の人の何らかに関心があり、発信内容をよく見ている人。(ex. 企業や社員のSNSフォロワーなど)
D. 認知層…企業の存在を認知してる人。情報は目にしても中身まで読むほどではない人。
ファンベース採用の実践ポイント
ファンベース採用を実践していくために、以下4つのフェーズで整理をしながら、それに合わせて実践するポイントと取り組みを紹介していきます。
未認知(E)→認知層(D)
認知層(D)→関心層(C)
関心層(C)→推奨者・ファン(B)
推奨者(B)→応募〜承諾・コアファン(A)
フェーズごとのアクション落とし込み
上記の理想を定義・整理していくためのフェーズごとの取り組みをまとめいき、チームのアクションプランを組み立てていきます。

認知・関心の状態イメージの言語化・定義
E→Aに向けた候補者ストーリーの解像度を上げていくため、どのようなデザイン組織として認知・関心を持たれたいかについて、ワークショップを通じて言語化・可視化(=理想の姿)に取り組みました。
まず叩きの段階では、ラフな言葉がいくつか出るくらいの粗めのイメージ感でした。
組織:Gaudiyの中でのデザイナーの立ち位置・役割
デザインプロセス:人間中心設計、アジャイル高速検証×質、メンバーとのコラボレーションによる速度・密度
プロダクト・サービス:プロダクトの中身とデザイナーの役割
文化:おもしろい・尖ってる・ストレッチ・ピンチを楽しめそう
特異性:Gaudiyならでは(Web3・エンタメ・金融・ブランディング)
成長性:成長できる領域(割愛)
ワークショップ
上記のイメージを元に、デザイナー全員で以下のワークを実施し、解像度を上げて共通言語化していきました。
1) 認知されたい状態・選ばれたいカテゴリの選定(20min)
2) 認知してほしい言葉のリストアップ(20min)
3) 1,2のグルーピング、現実と理想のGapを埋めるための機会や経験を挙げる
最後に、現実と理想のGapを埋める過程で、デザイナー候補者が向かい合う機会や経験を書き出します。挙げられたキーワードをもとに、デザイナー候補者に伝えたいこと、そしてその中にどのような機会があるか、一つの身近なストーリーにまとめていきます。


重要なのは、断片的なイメージを繋げてストーリーとして言語化することです。まず自分たちでそれらができていないと、第三者が自分たち以上の解像度で語ってくれることは恐らくありません。

アクションプランをキャラクター・チャネル・ネタでつなげることで、それがより共通認識として言語化していきます。言葉を着飾るのではなく、自分たちの等身大をより解像度高くイメージに落とし込み、アクションの背景を理解していきます。
4. ファンをづくりに向けた取り組み(実践)
E(未認知層)からD(認知層)へ
このフェーズでは、コアファンが拡散してくれたとしても、セグメントの違いによりリーチしづらい層があります。それが未認知層です。
未認知層に届けるためには、企業のことは知らなくても、コンテンツ自体に興味を持ってもらえれば、そこから企業の認知につなげることができると考えています。
例1:ブランディングに関心をもつ人にリーチ → Gaudiy認知につなげる
例えば、ブランドリニューアル時には、リブランディングを認知のきっかけにしてもらう仕掛けを考え、デザイナー向けのPR施策で、CI刷新プロセスを開示するようなコンテンツを制作しました。
CIやBI、リブランディングの背景など、Gaudiyに関係なく学びがある、参考になる情報をコンテンツにすることで、認知の壁を越えられる可能性があがります。またオウンドメディアだけではなく、第三者的なメディアに取材いただくことでリーチできる層や角度を変えることができます。
そうして認知があがったタイミングで、さらに関心層への移行に繋げるため、受け皿となるイベントも仕込みました。
泥臭い戦いのデータ見せてるよー!
— TORAJIRO (@jirosh1998) October 26, 2023
#gaudiy_rebranding pic.twitter.com/KiQYcV8ZAc
BI(ブランドアイデンティティ)やリブランディングの制作プロセス、その課題などデザインにまつわる内容など、リブランディングで泥臭いプロセスをFigma上であえてさらけ出しながら、イベント参加者と分かち合う場にすることができました。
Figmaで見れるのありがたい&めっちゃ細かいところまで見れて嬉しいw
— きなこ (@AsukaOkochi) October 26, 2023
そしてリブランディングに加え、プレスなど外への見せ方がとても考えられてる。実際に外から見てて盛り上がりがすごいなと思ってました!!!https://t.co/xj1duKaCFv#gaudiy_rebranding
例2:推しに関心をもつデザイナーにリーチ → Gaudiy認知につなげる
自社を主語にせず、推しや好きを主語にした場づくりとして企画しました。このイベントを通じて、Gaudiyがファンコミュニティに取り組んでいることの認知につなげるよう意識しました。
登壇者やゲスト、メンバーによる感想・口コミ(UGC)も生まれ、イベント中だけではなく、熱いファンのコミュニティから認知を広げる一歩になりました。(まだまだこれからですが)
#尊ミートアップ 与えられた15分を大幅にオーバーして、30分間熱く語ってしまいました。😂❤️🔥
— 𝗔𝘆𝘂𝗺𝗶 𝗚𝗢𝗧𝗢 🗂️ Featured Projects (@ayupys) March 14, 2024
仕事のリリースとイベント登壇がかぶって準備大変だったけど、櫻坂に興味を持ってくれる人がひとりでも増えたならうれしーです!!!
櫻坂と天ちゃんしか勝たん!!!#櫻坂46 #山﨑天 pic.twitter.com/6fHttiKRmn
ファンダムっていう概念、はじめて知った。コミュニティなんだな〜。#尊ミートアップ pic.twitter.com/CVVWZlyAMM
— 辻井 耀|リンクアンドモチベーション (@DShuhari) March 14, 2024
D(認知層)からC(関心層)へ
このフェーズは、「関心のパイプラインを増やすこと」が大切です。認知層は、企業の存在自体は認知してるがその内情を知らない、もしくは興味がない人です。メンバーの発信をいかに増やすかに注力しました。
発信|テーマだし
発信や接点のバリエーションをなるべく増やしていけるように、デザイナー全員が参加するワークショップ形式でネタ出しを実施しました。自身が話せそう or これから挑戦したい取り組み・アウトプット・代表作をテーマとして、それぞれが付箋に書き出しました。

ワークショップをやってみて、ジョハリの窓(自分・相手と知ってる・知らないの4象限)でいう、盲点(自分が知らないが相手は知ってる)や未知(自分も相手も知らない)の窓のように、他者から提案によって「たしかにそのネタなら書けるかも!」「これも行けるならこれが行けるのでは?」のような発見や相乗り的なコラボ機会にもなりました。
またワークショップで発散して終わらせるのではなく、挙がったネタを発信スケジュールに落とし込み、担当ごとのフローを決めて、発信まで個人・チームの活動として動いていく仕組みづくりと運用にも取り組んでいます。

ネタ出しから、リリースされたnoteがこちら
👇デザインシステム / デザインプロセス / チームづくりへの関心 → 筆者とのカジュアル面談につなげる
社内外のイベントへの登壇→noteの発信も
イベントと絡めて登壇資料を発信する機会も増えてきて、イベントテーマと絡めたnoteの発信にも取り組んでいます。
👇コミュニケーションデザインへの関心 → イベントでの接点やカジュアル面談につなげる
デザインやチーム、キャリアなど、様々な関心ポイントをきっかけに、Gaudiyを知ってもらい、出口につなげる仕掛けをしていくことが大切です。
今後、noteのマガジンに更新されていきますのでお楽しみに!
C(関心)→B(推奨)
このフェーズで、「関心層にいかにファンになってもらうか」のポイントは「直接的な接点づくり」だと考えています。1:Nのマス型のコミュニケーションではなく、1:1の参加型コミュニケーションの場をつくることが、関心層のファン化に有効です。
直接接点を持ったデザイナーに対し、適切に接点を持つことができるか。そして、ファンになってもらえるような体験をどうしたらつくれるか、を試行錯誤しています。
施策1|カンファレンスイベントへのスポンサーブース出展
「Spectrum Tokyo Festival 2023」というデザインカンファレンスにブース出展しました。リブランディングをきっかけにGaudiyを認知したり、関心を持った方向けに、体験型のコンテンツやQAコーナーを設けることで、1:1の接点づくりを意識しました。

詳しくは、ブース・ノベルティ制作を担当したコミュニケーションデザイナーのいなさんの記事を参照ください。
施策2|ガウディ訪問ごはん
社外のデザイナーとの気軽な接点づくりを目的に、Gaudiyメンバー含むデザイナー複数名のグループでゆるくご飯を食べる会です。デザイナーやGaudiyについて知る機会として企画・運営をしています。

運営にあたっては、参加メンバーのモチベーションを保ちながら定期開催できている状態も一つの指標としています。
ガウディ訪問ごはんに行きました🍚
— sumioka pommes (@azusanpome) January 30, 2024
最初見た時からなんて画期的!と気になっていた。デザイン、仕事のことから趣味のことまでゆっくりお話しできて楽しかったです🌼 他社のデザイナーさんと話したいなあという方におすすめです!https://t.co/qtXMsjEOUH #ガウディ訪問ごはん @gaudiy_incより
ガウディさんの #訪問ごはん 行ってきました🍖
— Riona | designer (@riona_design) January 30, 2024
他の会社のデザイン事情とかざっくらばんにお話ししながら、美味しいご飯を食べれてとても楽しかったです!
参加者の人柄とご飯を囲っていたからなのか、全く堅い感じではなくライトに交流できて素敵な企画でした🙌
ありがとうございました〜
これまでに数回開催していますが、満足度の高い感想をいただいたり、ファンになっていただける企画になりました。今後、安定的な定期開催などまだまだ課題はあります…!
施策3|Fandom Dinner Ticket(リファラル)
社員からの紹介を促進したり、一度つながった方と継続的な接点を持つための手段として、HR/PRとデザイナーが協力して「Fandom Dinner Ticket」というお誘いごはんチケットを作成しました。
ファンベースのコアは自社の社員なので、そのコアファンが新しいファンを増やしていく取り組みを全社的に行っています。
最近、どんなコトしてるの?的な近況報告や、Gaudiyのビジョンや制度、取り組みの情報交換などをきっかけに、良い時間になっているようです。社内のSlackには、BBQ、モツ鍋、焼き肉など、美味しそうな写真や、お誘いした人とメンバーとの楽しそうな写真があがってきています…!
\ガウ社からごはんのお誘いです/
— Gaudiy Inc. (@gaudiy_jp) February 27, 2024
友人・知人とのごはんに使える「Fandom Dinner Ticket」を全社員に配布しました🎟️🎟️
Gaudiyメンバーとお知り合いの皆さま、久しぶりにごはんに行きませんか? 逆のお誘いもウェルカムです✨#ファンダムチケット pic.twitter.com/zioxpAb8Zs
今後も継続的な運用と改善を繰り返しながら、施策をブラッシュアップしていけたらと思います。
その他|カジュアル面談
カジュアル面談には積極的に取り組んでおり、自社のカジュアル面談ページのほか、Pittaにも取り組んでいます。実はGaudiy、全社員の1割ほどがPitta経由で、デザイナーでもPitta経由で採用につながったことがあります。
GこれまでPitta(旧Meety)で公開されたカジュアル面談の申し込み数は、全社で600を超えています(デザイナー以外も含む)。
Pitta特集:Gaudiyデザイナー版
自社のデザイナー採用サイト・カジュアル面談
このフェーズでは、直接接点をもつ社員一人一人が、よいCX(候補者体験)を生み出せるかが鍵なので、デザイナーの接点を増やしながら、ファンにする取り組みを増やしていきたいと思います。
B(推奨)→A(応募)
ファンからコアファン(社員)への転換。ここでのポイントは「接触頻度をキープして、タイミングよく声掛けすること」です。
Gaudiyへの関心・推奨を持ってくれている(or持ってくれそうな)層に定期的にアプローチしています。例えば、カジュアル面談、選考辞退された方などに、「Xでつながる→Xで発信し続ける→タイミングをみてDMする」という地道なアクションをすることで、デザイナー採用でも、応募や内定に至ったケースが少しずつ増えてきました。今回は詳細を割愛しますが、1つだけ事例をご紹介します。
内定辞退になったがファン創出につながった話
スカウトがきっかけの出会いから、長期間の接点・機会を重ね、選考機会とファンになっていただけた事例です。残念ながら辞退の結果でしたが、よいご縁をいただけて、またどこかでご一緒できることを楽しみにしております。(採用イベントでも、おしごとでも)
先日はありがとうございました!みなさん想像していた通りの人柄の良さで安心しましたし、CEO石川さんとも話すことができたので最終面談の時よりも人間的な側面を知ることができてとてもいい時間でした。今後のキャリアを考え、結論xxx(他社)に決めました。Gaudiyさんとは本当に何度も話し、その中で自身がなんのためにデザイナーでありたいのかという内省の示唆をいただけたことに本当に感謝しています。内定を辞退するのは心が苦しいですが、今後とも是非関わりをもっていただけますと幸いです。今後ともよろしくお願いします!
実際にGaudiy全体では、この3年で、一度辞退した人が入社したケースが4名以上、一度見送りになった人が入社したケースも1名います。実は僕自身も、Gaudiyでのオファーを辞退したことがあり、その後入社をしたメンバーの1名です。
内定辞退や選考お見送り、アルムナイ(退職)など、様々な理由でGaudiyとの関係が離れる期間はありますが、またいずれどこかのタイミングでご一緒する機会があると嬉しいです!
現在地とこれから
現在地(現状と課題)
ここまでお伝えした中で、もしかしたら体制も取り組みも順風満帆なようにも見えるかもしれませんが、現時点でチームとして取り組めていることは肌感10〜20%くらいで、まだまだ取り組むべき課題は山積みです。
Gaudiyは組織100人規模の組織になり、今年6周年を迎えましたが、プロダクトも組織もまだまだ未熟で、あくまで通過点。10年、20年…と末長く組織でデザインの価値を発揮し続けるために、やるべきこと、やりたいことはどんどん出てきます。
採用
今のGaudiyの課題や機会を伝えきれていない、機会をつくりきれていない
事業や組織状況のスピード感にまだまだ適応しきれていない
再現ある打ち手が限られ、常に状況や機会を試行錯誤し続けること
発信
発信しつづける難しさ(ネタ決め・実績作り・発信のサイクル)
チームのケイパビリティや実績を広げ、発信できることを増やす
デザインや組織運営、採用のバランスで発信が後手にならないように
チーム運営
施策やナレッジは属人化しやすく、仕組みは形骸化しやすい
採用に関わるメンバーとそうではないメンバーの情報差分
入社後のお試し入社の受け入れ体制もより強化していく重要性
特にファンづくりに力を入れていくからこそ、入社が決まった後も地続きで、メンバーとして一緒にファンづくりに取り組んでいく重要性を組織としても大事にしていきたいです。
これから(今後取り組みたいこと)
プロダクトや事業を通じた認知・ファンづくりの実現
コミュニティサービス「Gaudiy Fanlink」の提供価値や取り組みで、認知されるようにしていきたい。Gaudiy×IPならではのサービス体験で、デザイナーにも推されるようにしたい。
メンバーの活躍⇔発信のループづくり
目標→振り返り→発信のサイクルづくりで、継続的に成長とファンづくりを両輪でできるように。より多くのメンバーにも、社内外での発信・関係づくりができる機会や仕組みづくりをしていきたい。
自社コミュニティの強化とデザインコミュニティとのSync
主催・共催を含む持続的なイベントや新しい情報発信チャネルを開拓などにチャレンジしたい。それらを活かし、リファラル・タレントプール活用した関係づくりのさらなる強化をしたい。
まとめ
デザイナーのファンベース採用の実践について、振り返りながらご紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか?少しでも気づきや得られるものが届けばとても嬉しいです!
Gaudiyでは「ファン国家」というビジョンを掲げており、会社や採用をきっかけとするコミュニティ自体も、「ファン国家」の一つだと捉えています。そしてファンベース採用は手法ではなく、概念であり、実践する形で新しい気付きと新たな出会いが得られると信じています。
このnoteではデザイナー採用に関わるみなさんにも、ファンベース採用がなぜ必要で、どんなものなのか、だからこそ、採用活動をファンづくりとして取り組んでいきませんか?というお誘いでもあります。
ぜひ意見交換や何かしらご一緒できる機会を模索したいので、Xでのコメントやカジュアル面談など申し込んでいただけたら嬉しいです!
About Me|ご連絡はお気軽に📮
Twitter(@mrhiro1112)
カジュアル面談(Pitta 雑談枠)
さいごにこのnoteで紹介した概念や戦略、施策、成果などは、Gaudiyや一緒に取り組んでいるステキな方々のおかげで成り立っています。またnoteは得意ではないのですが、HRPRの山本さんや社内のメンバーにもサポートしてもらいながら、世に出すことができました。Gaudiyメンバーや未来の仲間、ファンの方々と共に、デザイナーのファンベース採用に取り組んでいきましょう!最後まで読んでいただきありがとうございました🙌(またね)
参考資料(感謝)
採用に限らず、ファンづくりの基礎は、ファンベースから学びました。
そして、Gaudiyの採用の基礎は、はなかさんの記事から学ばせてもらっています。この記事も多く引用させていただきました。
トミーさんのnoteから、デザイナー採用の複雑さとスタンスを学ばせていただきました。唸りながら読み進めるほど、ドメインへの共感ができている実感を持てました。
Factからドメイン理解するためにも、デザインデータブックは必見です!
デザイナー採用のコミュニティづくりやコミュニティへの関わり方は、こぎそさんに教えてもらったと行っても過言ではありません。改めて感謝!
Cocodaのデザインケースや虎の巻は、デザイン組織やデザイナー採用を担当するようになってから、穴が空くほど毎週読ませていただいてます。
noteのマガジンで気になったものは基本読むようにしています。
デザイン組織づくりに取り組むにあたって、最初に読んだ書籍。概念や構造を把握するのにちょうどよく、時間軸で組織を捉えることが出来る限られた良書です。
組織づくりには、ルールデザインとルールの罠を学ぶ必要があり、同僚であり、先輩ルールデザイナーであるあつきくん推薦書。
コミュニティは、ソースから始まり、Gaudiyという企業・デザイン組織・ファンベース採用の、コアを理解し、組織やコミュニティが動く力学を掴むのにこの本は学びが深かった。
ファンづくりにもつながるエッセンスが入っているコミュニティの教科書。
その他にもたくさん
最後まで読んでいただきありがとうございました!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
