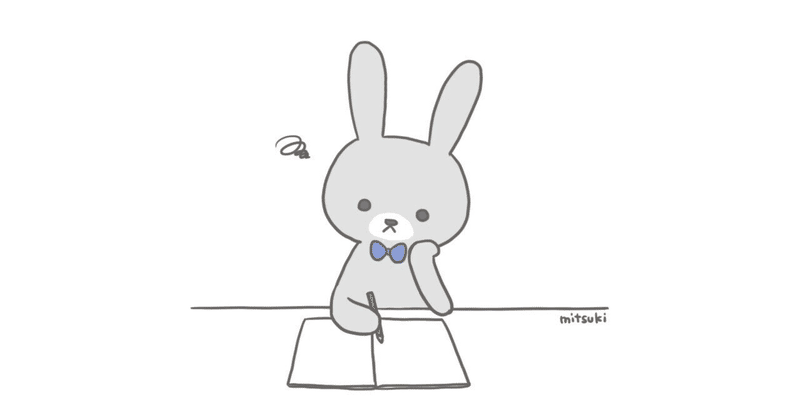
思考様式いろいろ
最近ハマってるYouTubeチャンネル
今回の話題は直近でどハマりしたYouTubeチャンネルからです。そのチャンネルがこちら,「ゆる言語学ラジオ」です。
「させていただく」はなぜ使われつづけるのか?というキャッチーな話題から,統語論(正直よくわかっていない)や方言,オノマトペの言語学的な解釈まで幅広く扱っています。だいたいの動画の流れとしては,パーソナリティの水野さんが持ち込んだ言語学関連の書籍を軸に,聞き役の堀元さんと共に多方面へ話題を広げていく構成となっています。Podcast前提で収録・公開しているので,通勤中などにピッタリ(実際時間的にちょうどいい)。
言語化ディストピア
で,今回話をしていくのはこのシリーズ。
「ビジュアル・シンカーの脳」を軸に3部作,3時間弱のボリュームたっぷりのシリーズとなっています。「ビジュアルシンカー」とは,図または絵で思考をする人のことです。内容はぜひ見て確認してもらいたいですが,この先を読み進めてもらうために,とっても雑な要約を書いておきます。
・世界には言語で思考する人,図で思考する人,絵で思考する人がいる
(これらはグラデーションで存在する)
・現代社会は言語で思考する人(言語思考者)が過ごしやすい,成功しやすい社会である
・一方で,図・絵で思考する人(ビジュアルシンカー/視覚思考者)は能力を低く見積もられがち
・言語・図・絵で思考することそれぞれに優劣はなく,社会が言語思考者に都合よくできているだけである
・言語は万能ではなく,言語にした瞬間そぎ落とされる要素もある
動画内では言語で思考する人のアドバンテージについてかなり触れられていました。絵のような技術や道具が必要とされる表現方法に対して,言語での表現はほとんどの人が(ある程度は)習得済みでかつ身一つで表現可能なため,メインのコミュニケーションの地位を確立していると。そして能力主義的な時代も相まって,言語化できることが能力があるとされた社会構造になっている。そのため,ビジュアルシンカーは不利であると。
言語化することで能力を証明することを強いる様を,パーソナリティの二人は「言語化ハラスメント」,「言語化マッチョイズム」表現していましたが,個人的にはその流れが社会に蔓延してきたら「言語化ディストピア」と表現したいですね。現状半歩突っ込んでいる気がしますが。
アウトプット向きかインプット向きか
ここから先は自分の体験や体感を入れて,動画に影響された”アジテートぽつねん”が考えていきます。動画では,ビジュアルシンカーの不利さにスポットを当てていましたが,一方でインプットにおいては時にアドバンテージがあると思っています。
例えば,複雑なシステムや立体の構造といった,ある種”リアル”ともいえるものについては,言語を介するよりも絵や図で理解できる人の方がロスが少ないためです。動画内では地図の読める・読めないでも言及されていましたね。現実問題,言語で表現しづらいもの,地図もそうですし機械の構造といったものは山ほどある訳です。そういったものの理解はかなり視覚思考が有利なだと思います。脳に入ってくる情報の8割は視覚と言われていますからね。それをロスなくインプットできるのは大きいです。
ただアウトプットする折になると,大方の場合はそれが言語で求められることもあり,途端に「理解していない人」と同じように見えてしまうだけで。
というわけで,動画でもあったように言語思考と視覚思考は優劣ではなく,そういう特性,向き不向きの問題なんだと思います。特に,言語思考はアウトプット向き,視覚思考はインプット向きなんじゃないかと。
……やけにこの辺の解像度が高いですが,それはお察しの通り自分は視覚思考よりの人(だと思っている)からです。
視覚思考者の頭の中(N=1)
この話題は職場の後輩に,「私日本語で考えていないから説明分かりづらくてごめんねー」なんて言っていたので,個人的にタイムリーだったわけです。で,自分はどっちなのかと鑑みると,全体としては図や映像で考えていることが多いな,と。
特にインプットするモードに入ると,明確に図ないし絵で考えています。技術書や人文書のような機構や構成を考えて読み進めるような本を読むときは,脳内で図やCADぽいものを想像しています。小説でも脳内で映像がぼんやりと浮かんでいます。小説とかだと場面の映像を浮かべながら読む人は多いんじゃないかと思っています。
あとは音楽なんかも場面が映像で浮かんだり,捏造されたMVが脳内で映ったり,ということがあります。もしくは音ゲーの譜面みたいに図形が踊っている,なんてこともあります。
一方で,こうやって文章書いているときは言語で思考しています。思考……というよりは一度言語化してみて,それから受ける印象が自分の考えていることと同じ形になっているかを壁打ちしている感じです。と,いうかアウトプットを意識したときは自分のイメージを言語に変換する作業になりますね。
という感じで,インプットから情報の整理までは視覚ないし言語の形をしていないですね。アウトプットになるときにはようやく言語の形を取り始めると感じです。
言語化は賽の河原
で,言語の形に変換するのが大変なわけでして。技術系や人文系の話は書物で情報を仕入れるので,ある程度テンプレができるのでまだ楽なんです。「このイメージは世間でいう〇〇」みたいな,自分のイメージと世間で使われる言語が自動的に紐づくので。
問題は何か感想とかを求められたときですね。イメージと言語を紐づける作業を一からすることになるので,これが大変。例えとしては,パズルです。イメージしている形があって,そこに言葉をパズルのようにはめていくような作業といった感じでしょうか。ただ言葉のピースの形や面積もバラバラ,時には一緒に使えないピースもあると非常に癖があります。それでいろいろ言葉を尽くした後で「この言葉を使いたい!」となると一回ひっくり返してまたやり直すことに……。
で,そうやってパズルを完成させてもイメージした形に対しては隙間がある(=思っていることすべてが言語化されていない)状態になると。結局言語って情報を圧縮しているので,どうしても表現できない部分は出てしまうのも仕様なんでしょう。
一方で,変換して外に出した時点で自分のものじゃないというか,どう伝わったかいうことよりも読んだ人がどう感じるのか大事だとも思っているので。まあいかなと。
人の思考は気になる
自分の思考をもっと深くまで掘り下げて,書こうかと思っていましたが,深度に対して指数関数的に言語化の難易度が上がってしまうので今回はこの辺で。こんな風に考えている人もいるんだと,面白く感じでもらえたらうれしい。
動画内でもいろいろ触れられていたのですが,全く違うストラテジーというかロジックで思考している人がいるのって結構面白いですよね。突飛な行動もそれなりの裏付けがあるってわかったり,考える余白ができるだけで世の解像度(本当は分解能って言いたい)って上がると思うんですよね。
というわけで,今回はハマった動画から自分の思考様式を振り返ってみた回でした。
以上,お納めください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
