
自問自答ファッション講座を受けてから2年間冬眠していた話
はじめまして、moyura(もゆら)です。
初めてあきやさんとお会いしたのは、講座に行った2021年11月。少人数のファッション教室に参加したのが2022年8月。そして、今は2023年12月。
「アウトプットすると良いですよ~」というあきやさんのお声を胸にそっとしまいつつ、長い間外には顔を出さずに過ごしていました。
ですが、先日ガールズさん向けZOOMオフ会に運よく参加できたこと、それから自分の中で「そろそろ冬眠から覚めてもよさそうだな」と思えたタイミングだったのもあって、2年越しにアウトプットにチャレンジしてみようと思います!
ライフイベントが重なってなかなか身動きが取れないガールズさんや、アウトプットする勇気が欲しい! と思っている方に、「こんなに長い間籠っている人もいたんだから、自分のペースで大丈夫」と思っていただけたら幸いです。
冬眠していた理由
せっかく講座や教室でコンセプトに向き合ったにもかかわらず、2年もアウトプットせずにいた理由は、生活するだけでキャパオーバーになってしまったから。
講座を受けた翌月から自分の裁量ではどうにもならないできごとが積み重なり、仕事を休職したり、ほうぼうへ足を延ばして問題に対処したりと、びっくりするほど身動きが取れなくなってしまいました。目の前のことをこなして生きるだけで手一杯!
その後、一番大きな問題が落ち着いたタイミングで、自分自身にも人生の節目が到来し、今度はお祝い事に一直線。
それが終わったと思ったら、片づけたはずの問題が再び顔を出してきてまたもや対処に追われる羽目に。
合間合間で断服式や演歌バッグ探しに取り組んできたものの、アウトプットについてはずっと後回しになってしまっていました。
教室でご一緒したガールズさんたちが積極的にアウトプットされていることもあり、実のところかなり引け目を感じていたのですが、最初に受けた個人講座の資料を読み返した時に、ふとある箇所に目が留まりました。
【何を変えたら理想の自分に近づきますか?】
ガールズの皆さんにはおなじみのこの質問。そこには、あきやさんから引き出してもらった答えが3つ書いてありました。
・暮らす場所を変える
・森に住む
・自分に使える時間を増やす
暮らす場所は、すでに変えていました。
キャパオーバーになった原因の1つは、コロナ禍で仕事や生活のスタイルが大きく変わったこと。そこで、「森に住む」とまではいかなかったものの、今の生活に合うような、自然が多く、のんびりした雰囲気の街へ引っ越しました。
毎日の生活が落ち着くようになって、ようやく大小さまざまな問題に向き合えるようになりました。
でも、自分の時間は、あるだろうか。
仕事をする。生活をする。問題に向き合って解決する。どれも自分がやらなければいけないことではあるけれど、「自分のための時間」というのはほとんどない気がする。
そのことに改めて気づいた時、「あ、冬眠しよう」と思ったのでした。
今の自分に必要なのは、活動することではなく、厳しい季節を乗り切るためのエネルギーを蓄えること。
木々が葉を落とし、小さな動物が巣穴に餌をため込むように、私もまた、冬ごもりする必要がある。そう考えると、一気に気持ちが楽になりました。
今は冬なのだから、無理をしたってしょうがない。活動したくなる春が来るまで、まずは「自分のための時間」を作ってみよう。
理想の自分に近づくために
まずは1日15分、仕事も家事もそれ以外のさまざまな問題にも手を付けない、「何もしない」時間を作ることに決めました。
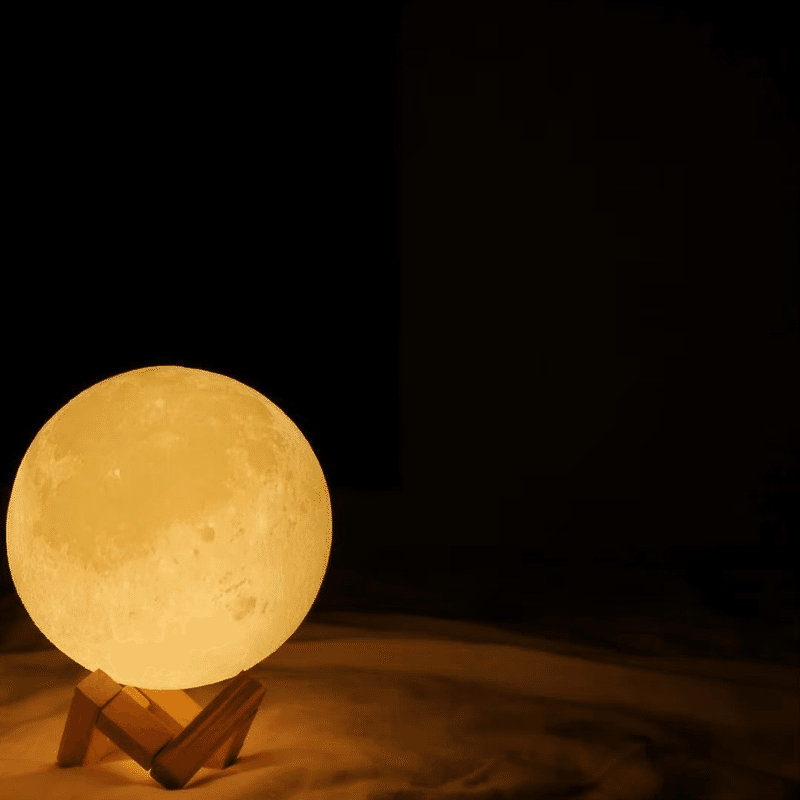
最初は何をするでもなく、ぼーっとしたり、外を眺めたりするだけ。じきにお茶を入れたり、お菓子をつまんだりするようになり、ずっとできていなかった読書の時間を取れるようになりました。
15分でこれだけできることがあるなら、30分なら、1時間なら何ができるだろう。「時間がなくてできない」と思っていたことは、案外やれるのかもしれない。
そこで、「いずれ森に至る」という気持ちで新居に植物を増やしました。
「自分が住む森にはこれがあってほしい」と選んだ花木や果樹を鉢に、料理に入ると嬉しい野菜やハーブをプランターに。
毎朝手を入れながら半年もすると、ベランダに鳥やトカゲが顔を出すようになって、都内にいながら少し森の気配を感じられるようになりました。
ここまでしてようやく、「森に囲まれた、薪ストーブと図書館がある家で、パンを焼いたりピアノを弾いたりしながら暮らすこと」が、自分の人生の目標の1つだったことを思い出したのでした。
コンセプトを思い出す

森の家は私自身の「理想の避難場所」です。
かつて子どもだった私が、安心できた場所の寄せ集め。逃げるようにピアノを弾いていた音楽室、放課後に居座った図書館、湧き水の流れる川、ひとけのない鎮守の森、物語の中の花園や、心許せる誰かのいるあたたかい場を、現実に作るならこうなるだろうという空想の家。
はじめて自問自答ファッション講座を受けた時、あきやさんとも空想の家の話をしました。
その話は、皆さんおなじみの【お金が無限にあったら何がしたい?】という質問に続いていきます。
もしも、自分や家族の生活の心配をしなくて済むのなら、誰かを困らせることのない自由なお金があるのなら、どこへでも行ってよくて、どこに住んでもよいのなら、自分は何をしたいだろう。
こぼれるように出てきたのは、子どもと、かつて子どもだった全ての人に向けた、もう1つの「空想の家」を作りたいという気持ちでした。
うさぎを追いかけた先、クローゼットの向こう側といった、「ここではないどこか」。
それそのものを現実にすることはできなくても、そこに向けて空想の翼を思いきり広げるための、隠れ家のような場所があってほしい。
冒険というほど大きな経験はできないかもしれないけれど、訪れた人が“現実を生き抜くためのちょっとした報酬”を持ち帰ることができる非日常の場があったらいい。そういうものを作ってみたい。
「そこで何をしていたいですか? 管理人さん?」
そうあきやさんに聞かれましたが、答えは「いいえ」。
「ここではないどこか」から持ち帰る報酬はひとそれぞれ。私が何かを与えるのではなく、その人自身が見出して持ち帰ることに意味があると思うから、私がやりたいのはあくまで「場の提供」です。
訪れた人には姿が見えるかもしれないし、見えないかもしれないくらいの距離感がちょうどいい。
ただ、「空想の家」は辛くて厳しい現実を乗り越えるための場所ですから、空想の家そのものの安全を脅かすような人に見つからない、邪魔されないようにする必要があります。
よからぬことを考える人が来ないよう先回りしたり、手を出した人にちょっとしたバチを与えるくらいの役周りは、場の提供者である私が引き受けなければならないでしょう。
「あきやさん」
「なんでしょう?」
「コンセプト、職業はおろか人間じゃないかもしれません」
「大丈夫です!! うさぎさんとかの方もいらっしゃいます!!」
その時のあきやさんの「大丈夫」があまりにも力強くて、思わず笑ってしまった。
コンセプトを考えるのは、正直とても難しかった。「空想の家」に紐づくものとしてどう在りたいか。管理者や統治者ではない。だから、女神や女王のような権力的な存在ではない。かといって、小人やコロボックルほど親しみやすいものでもない。空想の家があるのは森や湧き水のある場所であって、海ではないから人魚でもない……。
二人でああでもないこうでもないと何十分も悩んだ末、「人間と同じくらいのサイズの精霊的なもの」だろうという結論に。
そして、現実に疲れた人のための秘密基地を「家」のイメージの延長で仮に「マヨヒガ」と呼ぶことに決め、「マヨヒガのウンディーネ」という、絵本世界の住人のようなコンセプトが誕生しました。
職業でもなければ、「何をする人」と説明できる役割もない。「制服の作りやすさ」でいえば、扱いにくいことこの上ないコンセプト。
でも、それこそが、私がずっと求めていたものだったのだと思います。
冬眠する前、私はずっと疲れていました。自分で選んだわけではない「女性」「娘」「姉」といった役割に振り回され、そのロールプレイだけでいっぱいいっぱいになっていたからです。
生きていく以上、そうしたロールを全てほっぽりだすことはできません。でも、私の本質はそこにはない。一時的に役を羽織っているだけにすぎない。私の魂は「マヨヒガのウンディーネ」なのだ。
2年越しに自分のコンセプトが腑に落ちて、ああようやく春が来たのかもしれない、と思いました。
「空想の家」をどんな形にするかはまだ決まっていません。本当に家を作るのか、コミュニティのようなものを作るのか、あるいは別の形で「場」と呼べるものを提供するのか……。それはここからゆっくり考えていきたいと思います。
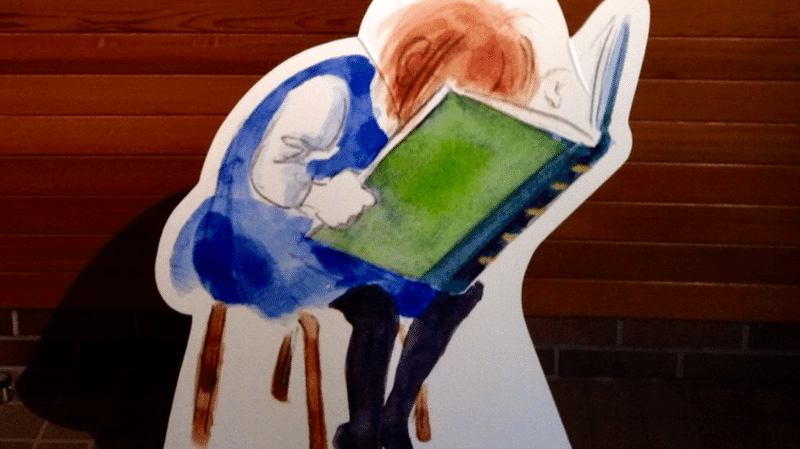
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
