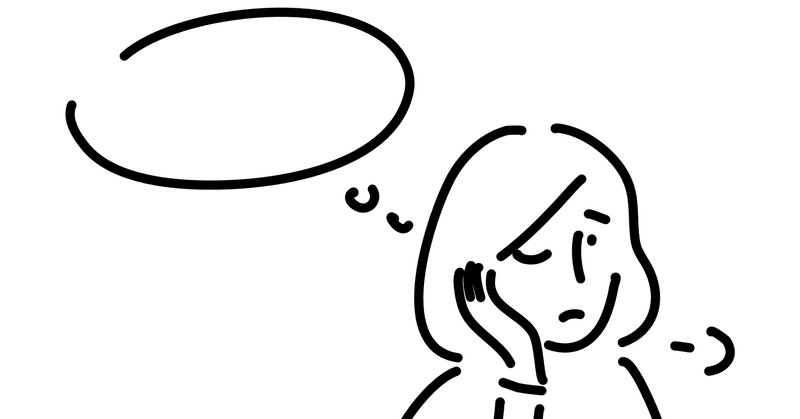
非モテ&コミュ障克服:書籍『なぜ、この人と話をすると楽になるのか』後編(技術編)
元イさんなのだ。『なぜ、この人と話をすると楽になるのか』(著:吉田尚記)の後編、技術編なのだ。
「相手を楽にさせる会話力!」と宣伝文にあるこの本を題材に、非モテ克服という観点からひも解いているのだ。
今回は基本編を前提にして、より技術的なことが語られているのだ。
前編と同じく序盤を無料で開放するのだ。読んで気になった方はぜひ、ご購入をよろしくお願いしますなのだ。また元イさんの記事は要約に加えて、元イさんの感想や解釈も加えてあるのだ。なので書籍を買って読む方が余計な注釈なく直接理解できると思うのだ。
また最終章のまとめは無料公開の別記事としてアップさせていただきますのだ。
6:コミュニケーション・ゲームのテクニック
・話題とは何か?
人と話すのが難しい人にとって「話題」のチョイスはクソデカな難問となるのだ。この本の回答はシンプルなのだ。「質問をすればいい」なのだ。「的外れな質問」でも全然OKで、むしろ間違っていたら相手は訂正してくれるから、その訂正から質問の窓口を探せばいいのだ。そうやって質問を重ねる事が会話になるのだ。「話題とは質問であって、自分の話をするのではない」のだ。
「目の前にいる人が自分の話を聞いてくれて、いろいろと質問もしてくれてうれしくない人なんていない」そう吉田さんは語るし元イさんも同感なのだ。今この時間を楽しく過ごすために質問をして、その反応にのっていけば会話は成功なのだ。
コメント:共通の話題が無い、共通の趣味が無いから会話が弾まない、という言葉がだいぶ的外れなものなんじゃないかと、読み進めていくうちにわかってくると思うのだ。
・相手のために質問をする
例えば出身地を聞いて「ベトナム」と答えられたら、次の質問に進むのだ。例えば…
「えっベトナム。ベトナムのどこですか?ホーチミンですか。ホーチミンって昔、サイゴンっていいませんでしたっけ?」
と、相手の答えに合わせて連想できる限り続けられるのだな。そこから自分も興味があるもの、食べ物について聞いてもいいし、気候の話でも、旅行の話でも、質問をし続ければいいのだ。そしてこれらは全て「相手の話」なのだ。自分についての話題はないのだ。話題は常に相手の側にあるのだ。
相手のために質問をする、もし逆に相手が質問をしてくれたら自分もしゃべりやすい、そうやって互いに質問をしあえれば気まずさが回避できるのだ。
話題とは質問から生まれる相手の受け答えなのだ。この質問をして話題をつくるというコミュニケーションの技術として身につけるのだ。
コメント:共通の趣味、共通の話題が無いならシンプルな話、話題を「相手の事」にしちゃえばいいじゃない、というやつなのだな。
・相手に対して興味を持つ
質問をする時に一番重要なのは、かりそめでもいいので相手に興味を持つこと。自然に興味を持てる相手と出会えていればすごく楽だと思うのだ。たとえばかわいい女の子が相手だったら「彼氏いるのかな?」など質問はすぐに浮かぶのだ。相手への興味はほとんどの場合、即質問につながるのだ。
「相手に興味を持たないよう気をつけてました」というコミュ障あるあるもここでコメントされているのだが、同感なのだ。興味を持つことが失礼みたいな謎の意識があったのだ。
例えば服装でもいいし、持ってる小物でもいいのだ。よく観察をするのだ。興味を持つことが難しければ観察を、そして元イさんのスタンスに近い表現だと「自分が興味を持てる点があるかどうかを探すために質問をする」なのだ。
コメント:相手に興味を持つ、これが勝利の鍵なのだ。コミュ障のみなさんには恐ろしい話になるかもしれないのだが、意図的に相手に興味をもとうとしている人から見ると「相手に興味のない人」はバレバレなのだ。
・「ホレたら勝ち」感じる心のハードルを思い切り下げる
質問をして返事がきたら「あっそうなんですか!」「えっ!」「本当ですか!」「どういうことですか?」などと反応の仕方はいろいろあるのだが、ポイントは感じる心のハードルを思い切り下げる事なのだ。ポーズでもいいからその話題にワクワクする事なのだ。
相手のどうでもいい自慢話にもハードルを下げて「すごい!」とリアクションをできる事、これが大事なのだ。(ここは『人を動かす』にも通じるのだ)
「ホレたら負け」という言葉があるのだが、吉田さんは「好きなものが増えたらラッキー!」「片思いで何が悪いの?」と語るのだ。好きになることは相手に興味をもてるという事だし、好きになる事で相手へのハードルも下がる、コミュニケーションも取れる、いいことだらけなのだ。
コメント:食べ物の好き嫌いが無い人は何でもおいしく食べられる、味音痴はまずい食事も楽しめる、何でも楽しめるという感度の低さは武器になるのだ。
・相手の言い分に乗ってみる
コミュニケーション・ゲームでは、相手の言い分に乗ってみようと決めてしまったらとても楽になるのだ。
これが全ての答え!とすら言い切っているのだ。「なぜ、この人と話をすると楽になるのか」の答えはこれ。楽しく、心地よく、気まずさなんてまったくなく話を聞いてくれる人。自分の事に興味を持ってくれて色々訊いてくれる人。驚いたり笑ったりして話が転がって退屈しない人。
それが会話をしていて相手を楽にする方法なのだ。
コミュ障の克服方法は自分がいかにしゃべるかでなく、相手の話を興味を持って聞ける、その技術を身につける事なのだ。
相手の言い分に乗ることが悔しいと思うのなら、それはまだコミュニケーションを対戦ゲームと思っているのだな。協力プレーを旨とする会話においては自分の意見はいらない、話を続けるために「自分はこう思うんだけど」という事はあっても、主張を押し付ける事はNGなのだ。
コメント:会話は議論と真実の追求、楽しさよりも正しさ・正確さが大事、情報伝達を重んじる、といったようなスタイルでいるとこれは飲み込みにくい話だと思うのだが、ブレインストーミングと同じと考えた方がいいのだ。「相手の考えを否定しない」「相手の話に乗る」というやつなのだな。
・非戦のコミュニケーション
話題は相手の事、言い分は飲み込む、そして相手に興味を持つ、そういった要素のあるコミュニケーション・ゲームはいつだってアウェイゲームなのだ。だからこそ強く意識しないといけないのは「意見を戦わせるなんてどうでもいい」という意識なのだ。非戦のコミュニケーションなのだ。真実を追い求める事よりも、楽しい会話を続けることが大事なのだ。
コメント:断言できるのだ。「戦ったら、議論したら友好的なコミュニケーションは終わり」
・会話で優位に立とうとしない
「ホレたら負け」の負け癖をつけること、相手の言い分に乗ってみる事、相手のフィールドでゲームをすることも全て、相手の優位に立とうとしないという事なのだ。
優位に立ちたくなるという癖は人間なのでどうしてもあるのだ。でも会話は参加者すべてが楽しくなったらそれが勝ちと割り切るのだ。「疑わずに馬鹿正直に受け入れて楽しめれば勝ち、潰しあっても意味がない」なのだな。
コメント:「プロインタビュアー」として有名な吉田豪さんも、インタビューするときには下調べをして、相手を好きになってしまうという事を言っていたのだ。良いインタビュー、つまりコミュニケーションのコツとしてなのだ。吉田豪さんの本もそのうち取り上げるのだ。
・相手に対して優位に立たないで済む3つのテクニック
・ホメる
・驚く
・おもしろがる
この3つなのだ。個別に解説するのだ。
コメント:すごく大事。
・ホメる~ホメると自分が相手に受け入れられる~
全力で人を褒めて、相手が「ありがとう!」って気持ちになると、ホメる側にもいいことがあるのだ。ホメるというのは自分が良いと思った部分を相手に表明することで、ほとんどの人は悪い気はしないのだ。そして、そんなホメてくれる人を受け入れてくれるのだ。
もちろんホメたことに対してのリアクションがきっとあるので、また質問できるのだ。息を吐くようにホメても全然OKなのだ。
コメント:具体的なホメ方に関しては『人を動かす』を参照するのがおすすめなのだ。
・驚く
相手の言い分に乗る、相手の言葉を素直に受け止めている、感じるハードルを下げるという事の一種なのだな。相手の話に純粋な関心を示していることになるのだ。本では「言葉のチョイスを工夫して驚いていることを伝えよう」という話になっているのだ。
コメント:元イさんはしばしば「マジで!?」「マジすか!?」と言ってばかりなのだ。
・おもしろがる
よほどのことが無い限り「つまらない話を最初からしようとしている人はいない」まずこれを念頭に置くのだ。たとえ結果的につまらない話になってしまったとしても、気持ちは面白がらせようとしているのだ。話をしてくれるだけで「気まずくしたいと思っていない」というサインだと思うのだ。
人は生存戦略としてネガティブな記憶の方が多く残りやすいんだそうなのだ。だからこそ「面白い記憶、ポジティブな記憶」は数少ない幸せな記憶として脳に刻まれるのだ。
相手の話を自分が面白がり、自分が楽しませたと相手が思う、そういうポジティブな記憶が次のコミュニケーションにつながるのだ。
コメント:元イさん人の話が楽しくてニコニコしながら聞いて、よくゲラゲラ笑うのだな。こういう時、楽しむ感度のハードルが低くてよかったと思うのだ。
「ホメる」「驚く」「おもしろがる」はコミュニケーションの技術を考えるうえで大きなテーマになるのだ。どれも相手に興味をもたないとできないテクニックなのだ。「相手に興味をもとう」その一言に集約されるのだ。
・元イさんの感想
まずこの章では話題について、大きな参考になる話だと思うのだ。誤解しがちな点は「相手と自分に共通の話題が無いと会話が難しい」という事なのだな。共通の話題なんて極論を言えば、「無くていい」という話なのだ。
相手が自分の知らないことを知っている、それだけで会話は無限に広がっていくのだな。自分が知らなくて、相手が知っていることを聞けば相手が話すことは無くならないのだ。
元イさんの個人的な経験から言えば、相手が嫌がらない限り、相手が喜んで話してくれる限りにおいてなのだが、相手の家族構成や生まれ育ち、小中高の想い出や好きな本、好きな食べ物、好きな旅先、趣味から最近のハマり事までとにかく聞いて聞いて聞きまくってしまうのだ。もちろん嫌がれば聞かないのだ。相手が話したいという事、こちらに聞いてほしいと思う事を探すのだな。
ここら辺はまた次の章に関連する事なのだ。
3つのテクニックや、相手と戦わない、優位に立たない、話に乗るというのは、お気づきの方もいると思うのだが、根底には『人を動かす』と同じものがあるのだ。ぜひ、合わせて読んでみる事をお勧めするのだ。
ここからは有料になるのだ。
ここから先は
¥ 200
いただいたサポート代は記事執筆用の書籍購入などに使わせていただきますのだ。 サポートも嬉しいのだが、Twitterでのシェアやスキをされると喜びますのだ!気軽に感想をコメントして意見交換できると嬉しいのだ!
