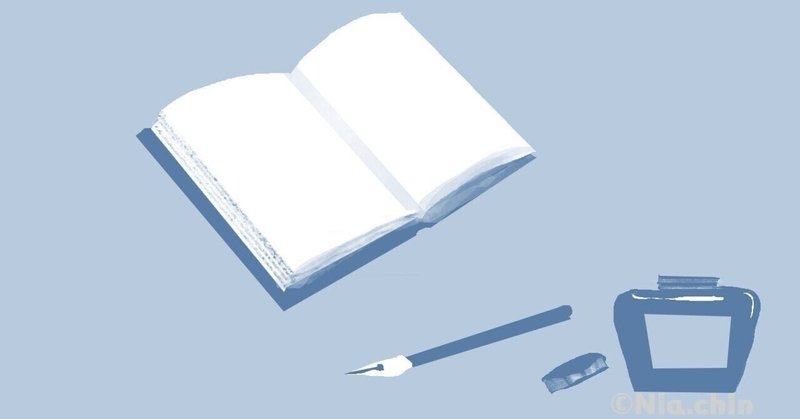
「ドラえもん」の偉大さ。『月面探査記』の藤子・F・不二雄先生への愛を感じて
さて。映画『のび太の月面探査記』の感想を書いていたのですが、
すると「ドラえもん」の偉大さを改めて感じてしまったので、別にひとつの記事を書くことにしました。
この『月面探査記』、過去の色んなドラえもんの映画・大長編に似ている部分やオマージュがいっぱいあって、脚本を手掛けた辻村深月さんの藤子・F・不二雄先生への愛に触れました。
どこまで私の記憶が正しいか分からないのですが、
F先生がご存命だった時代までの映画・大長編と照らし合わせながら、私の気づきを書き留めておきます。
ストーリーのはじめの展開は、ドラえもん映画でよくある「子供たちだけの秘密基地を作る」タイプ。月のうらにうさぎの世界を作ります。
『竜の騎士』『日本誕生』『雲の王国』など。子どもたちのワクワクする感じが楽しい。
このあと、のびたとドラえもんが作った月の世界のうさぎ住民たちとは別に、
ルカ達の「エスパル」という種族と、そのエスパル達を作った「かぐや星人」との対立、
というのが物語の本筋となっていきます。
これは、F先生がよく描いていたテーマ、
創造主である人間と、反乱するロボットたち(『鉄人兵団』や『ブリキの迷宮』)
地上で好き勝手をする地上人と、住処を追われてしまった種族の対立(『海底鬼岩城』『竜の騎士』『アニマル惑星』『雲の王国』『創世日記』)
などを彷彿とさせます。
また地球の成れの果ての姿なのかもしれない、
「かぐや星」という廃墟と化した惑星の姿をみると、
これまたF先生が大事にしていた、
「美しい地球を守ろう」というメッセージと、人間の傲慢さなどを感じます。(これはほぼ全ての大長編で語られているのでタイトルは割愛)
物語の中盤、のび太達は一旦、日常生活に戻ることになりますが、
やはり「覚悟を決めて」友達であるルカ達のピンチを助けに行くという展開が、
『日本誕生』『アニマル惑星』に似ている。
ここでスネ夫が、
現実的に考えて怖くなって迷い、葛藤するところも、
『宇宙小戦争』などで注目されるスネ夫のキャラクター性がにじみ出ている。
(私はこのスネ夫のリアリティさが好き。どう考えても未知のものと対決するのは怖いもんね。私だったらスネ夫の肩を持ちます)
ジャイアンも、
映画のジャイアンらしく『大魔境』のようなとっても友情にあついところや、
最後「声カタマリン」で自分の歌声の破壊力を武器にするところとか最高。
でも序盤のスネ夫と一緒に典型的ないじめっ子キャラで、
「月にうさぎはいるんだ!」というのび太の妙にがんこで鼻っ柱の強いところを逆に引き立てる。これも色んな映画の序盤の入りとして大定番。
ジャイスネが、転校生のルカにちょっかい出すとこも好き。
(あのいじめ方は今のコンプラ的に大丈夫かぃ、と思ってしまったけど、私個人的にはこれももう一種の物語としての「おやくそく」でしょう!と思っちゃいたい…。でも難しい問題だ。)
しずかちゃんの立ち位置も、
「自分のこと可愛いって分かっててやってるでしょ!」とツッコミたくなるお茶目さを感じる『海底鬼岩城』のバギーちゃんにお願いする場面に似ているところがあったり、
その利発さでピンチを切り抜ける『大魔境』や『鉄人兵団』のようなキーパーソンとしても大活躍。
ドラえもんは相変わらず、大事なところでポケットなくすし、ひみつ道具を生かせないすっとこどっこいのポンコツだけど(褒め言葉です)、
かぐや星に連れ去られたルカ達を助けに行く宇宙船を改造できたりする技術はさすが22世紀のロボット。めっちゃ頼り甲斐ある。
のび太とはぐれた時の「壊れてお詫びいたします〜〜」は『海底鬼岩城』のオマージュ。
この、周りを困らせる程の責任感の強さは『雲の王国』でもキーになっているし、
のび太との切っても切り離せない友情は「ドラえもん」という作品全体のベースになっている。
のび太は、根っこからの優しさが言動の端々からにじみ出ているから、
ゲストキャラとは一番はじめに仲良くなる。
恐竜にも動物にも自然にも好かれる(『のび太の恐竜』『大魔境』『雲の王国』etc)。
この『月面探査記』だと、みんなが他の人の話を聞いてるときに、一人ルカの表情の変化を察して、気にかける。しかもその気遣いが全く押し付けがましくない。自然とできる。
(だからこそ普段は一つのことに集中できなくて、色々失敗しちゃうんだろうなあ。ほんとに人間って一長一短だと思う)
のび太とゲストキャラが二人だけで語らう、という場面は『アニマル惑星』『日本誕生』などでも描かれていて、子供心にも大人心にも、なんだかしっとりとした気分になる。
それから、のび太が谷底に落ちてしまうシーンがあるのですが、これは『ねじまき都市冒険記』を思い出したり、
のび太が得意の射撃の腕前を生かして、敵に「空気砲」で狙いを定めるところは、『宇宙開拓史』『銀河超特急』のクライマックスと同じだなあと、思ったり。
最後はお馴染みの展開で、ルカ君とのび太たちは、悪役を倒しに行くのですが、
この敵陣達のおどろおどろしい雰囲気とボスの存在感、
ドラえもんのひみつ道具やみんなの勇気を掛け合わせて突き進んでいくところは、
『海底鬼岩城』『魔界大冒険』『パラレル西遊記』に似ているなぁと感じ。
また「異説メンバーズクラブバッジ」というパラレルワールドを創りだす設定のひみつ道具によって、
世界線がぐにゃっとなって、ちょっと頭がこんがらがりそうになるSF(すこし・ふしぎ)な感覚が、
『魔界大冒険』『パラレル西遊記』『ドラビアンナイト』『夢幻三剣士』『創世日記』を思い起こさせ。
と、こうやって書いていくと、この世界観をひとつの映画に詰め込んだ、脚本を担当した辻村深月さんも勿論すごいんだけど、
何よりも、この「ドラえもん」を生み出した、藤子・F・不二雄先生って本当に天才だなあと思いました。
なんだろう、まずストーリーの構造や技術としての、起承転結とかキャラクター設定とか、そういうもののバランスがすごいし、
「未来のロボット」という設定が、例えご都合主義なストーリーになっても誤魔化せるような(言い方悪いけど笑)、仕組みを作り出したのが秀逸だし、
人間の描き方も、ひとりひとりにフォーカスしてしまうと、ちょっと両極端だったりしてしまうんだけど、作品として全体を見たときのバランスが絶妙だし、、、
(弱虫主人公・可愛い女の子・ガキ大将・ずる賢いヤツと、このキャラクター設定を定番というか、一つのお手本としてF先生なんじゃないかなと勝手に思っている私。ほんとに勝手に思ってるだけで、リサーチはしてないのであしからず)
あとはF先生が一貫してテーマとして持っている
SF(すこし・ふしぎ)の観点と
人間・子供たちの未来、そして地球の未来を思いやる気持ちとが
私の琴線にがんがん触れてくるんですよね。
これは人それぞれ好みの観点が違うと思うのですが、でもやっぱりより多くの人の心を揺さぶるから、これだけ長く広く愛されてるんじゃないのかなと。
最近、「ドラえもん」が好きだからこそ、
多様性を認めようとする社会の流れで生まれてくる「ドラえもん」への批判が、気になって目に入ってしまいます。
ジャイアンたちのいじめ方はひどすぎない?
「廊下に立っとれ!」はもうだめだよね
しずかちゃんはいつもスカートを履いて「女の子」のイメージを固定化している
のび太がしずかちゃんのお風呂覗くのは、まじでダメだ
のび太は所謂ADHDなのでは?
一軒家、家事をしないお父さん、専業主婦のお母さん、という設定が古い
etc...
これ「ドラえもん」に限らず、子供が見やすい時間帯のご長寿アニメ、いや、もはやアニメやテレビにも限らず、人々の目に入りやすいもの全てやり玉に上げられているのを見かけて、いつも正解が見つからないなあ、ともやもやしてしまいます。
批判的に見る人の理屈も、わかる。
わかるからこそ「それはちがう!」とこちらも否定で返すのは解決にならないし、
「じゃあ」と受け入れ全てを変えていくのはどこかで無理が生じてくるし。「もう時代にあわないし止めようよ」となったら、やっぱり悲しい。
結果、なんとかぎりぎりを保って、隙間を縫い合わせるように辿っていくしかないんだろうけど。
「ドラえもん」は、
表向きに見えているわかりやすいものより、
内面の奥底にある、言葉にはし辛いけれど確かにそこにあるものが、多くの人々の心を揺さぶるから(それは良い揺さぶりも悪い揺さぶりも両方かもしれない)、
50年以上付かず離れず、日本人の生活に寄り添っているんじゃないのかなと、私は思っています。
(まあ、これも、「ドラえもん」に限らずですね)
要はどんな形であれ、長きに渡って残っている「もの」って、
人を動かす力強いパワー、運命の流れに乗る術、を持っているんだろうと、
それを兼ね備えているのが、やっぱり「すごい!」んじゃないかな。
否定も受け止めるけど、「やっぱりすごいのはすごいんだよ!」と大きな声で言いたい!!
、、、あかん、また話がずれていった。
とにかく私は「ドラえもん」が大好きです。
藤子・F・不二雄先生の作品が大好きです。
(ドラえもんの次に好きなのは「エスパー魔美」。またSF大全集も読み返したくなった)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

