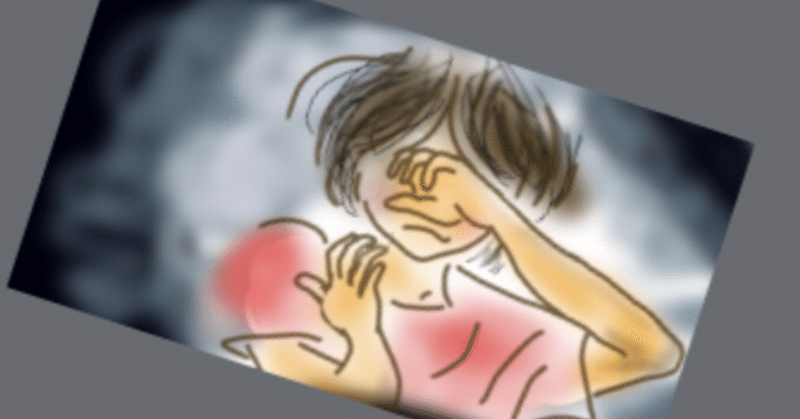
「娘がいじめをしていました」感想文・環境調整の提案
とんでもなく後味の悪い漫画を読んだ。
小学生の女の子の間に、いじめが起きるところから話が始まる。
もうこれだけで、いやあな気持ちだ。
以下、ネタバレを含むあらすじを載せる。

いじめた側の女の子(愛・まな)の母(加奈子・かなこ)には、子供の頃、いじめられていた過去がある。
そのせいで、娘がいじめた女の子と、自分の姿が重なる。
大勢でたった一人をいじめるという、卑劣な行為をした娘を許すことができない。
「謝罪したところで、心の傷は消えない」
と、後悔している娘に寄り添えず、責める気持ちが抑えられない。
一方、いじめられた側の女の子(小春・こはる)は、いじめが収束した後も、学校に行けない状態が続く。
その母親(千春・ちはる)は、遅れた勉強を取り戻すべく自主学習に付き合い、明日の学校の支度を手伝っているのに、朝になると不調を訴え登校できない娘に苛立つ。
家庭から平和な日常が消える。
「なぜ被害者である私たちが、こんな目に遭わねばならないのか?理不尽だ」
彼女もやはり、傷ついた娘の心に寄り添えず、自分の望む解決を求めて暴走し始める。
事態はやがて周りを巻き込んで……
いじめの話は、フィクション・ノンフィクション問わず、世の中にあふれている。
そして、その解決策らしきものをもっともらしく載せているサイトも、ごまんとある。
だが、現代のいじめは、発端も拡散も収束も、あらゆるところにネットが絡むのに、解決策だけがネットに存在しない。
娘がいじめの加害者だった、というショックと嫌悪感に混乱する加奈子も、はじめは、どう娘の話を聞けばいいのかとネットの中に答えをさがす。

「適切な対応」「正しい謝罪方法」。
作者は、これらの言葉をあえて選んだのだろう。
どこかにあるはずの正解を探す親の姿は、それしかやり方を知らないまま、大人になってしまった私たちを映す鏡だ。
多種多様な人たちが、そのコミュニティの数だけ作り出してしまう人間関係の問題に、たった一つの正解など、あるわけがない。
自分の感情と向き合い、他人の感情とすり合わせながら、答えを作っていくしかない。
だから、難しいし、だから、解決できないことが多いのだと思う。
ただ、解決のためのヒントはある、と思っている。
それが環境調整だ。
環境調整とは、障害支援の基本的な考え方だ。
障害は、障害者本人の中にあるのではなく、環境の側にあると捉え、環境の方を変えることを考える。
わかりやすく例に挙げられるのは、車椅子ユーザーだ。
彼らにとって「段差」や「階段」は障害となるが、車椅子で使えるスロープやエレベーターがあれば、障害は消える。
認知症、自閉症といった脳の機能障害であっても、まず考えるべきは「本人を環境に合わせようとすること」でなく「環境から障害を取り除くこと」である。
「困った行動」の裏には、「本人の困り感=うまくマッチしていない環境」があるのだと捉えて、障害になっているものを、環境から消すのである。
実際、それで、本人も周囲も、穏やかに暮らせるようになることは多い。
たとえば睡眠。
発達にトラブルを抱えた子どもは、眠るのが下手なことが多い。
ある程度の年齢になっても、夜にまとめて眠れない。
眠らない子どもを、ワンオペで育てていると、子は親にとっての「障害」になる。
親は、いつも睡眠不足で朦朧とし、できるはずのこともできなくなっていく。
だか、その子を三交代で見ていられるなら、子はただの「寝ない子」でしかない。
善も悪もない。そういう子なのだ。
実際には、三交代制育児システムなどという「母親だけに負荷をかけない状態」が作れないから、寝ない子どもは「悪」と見做される。
そして、なんとか寝かせようと躍起になるあまり、他の部分にも、ほころびが広がっていくのである。
「よその子はみんな、夜はちゃんと寝てるのに」
と嘆いたって仕方ない。
そういう子どもなのだから。
寝かせようとするより、寝なくてもうまく行く仕組みを作るしかない。
発想を変えなくては、お互いつらいままだ。
いじめについても「いじめる子」「いじめられる子」といった「人間」を問題とせず、いじめが起きてしまう「環境」にフォーカスすれば、自ずと「子どもにとっての障害」が見えてくるはずだ。
いじめの対策として「道徳教育に力を入れるべき」という人がいるが、私は全く賛同できない。
道徳教育とは「理想を提示し、そこに近づけようとする」ことであり、子ども自身を変えようとするものだ。
「環境には問題ありません。
悪いのは、いじめる子、いじめられる子。
だから、そういう子達に、正しい人間像を教えて導きましょう」
「優しくないとダメですよ、強くないとダメですよ、明るく生きなきゃダメですよ。
前を向いて、良い人、正しい人になりましょう」
これが道徳の伝えたいことだと思う。
イマドキ、そんな「大人の望む姿」を知らない子どもはいるのだろうか?
みんな知ってて、でもそうなれないから困っているんでしょ?
ここで考えてみて欲しい。
なぜ「優しくないとダメ」なのか?
なぜ「強くないとダメ」なのか?
なぜ「明るくないとダメ」なのか?
優しくできない相手もいれば、強くなれない時もあるし、他人から見て暗い性格であっても、人生が充実している大人はいくらでもいるだろう。
それこそが「ヒトの多様性」なのに。
「こうあるべき」という考え方が行き過ぎると、そこから外れる「冷たい子、弱い子、暗い子は、排除されて当然」となる。
「冷たくても、弱くても、暗くても、みんな大事な子どもだよ」
そう言われて「もやっ」としない人は、かなり珍しいだろう。
それが、他人から自分の子にかけられた言葉なら、尚更だ。
みんなどこかで「優しく、強く、明るい子ども」を望んでいる。
その方が、めんどくさくないから。
「意地悪でも、頑固でも、すぐ人のせいにしても、みんな大事な子どもだよ」
だと、どうだろう?
ますます、受け入れにくいのではないだろうか?
「だって、そんな子どもは、手がかりそうだし、他人とすぐトラブルになりそうだし、なんだか卑怯だし?」
程度の差こそあれ、大人は子どもをジャッジしている。
大人は子供に、価値を与えたり剥奪したりする環境の一部なのである。
私は、変えれば子どもが楽になりそうな環境の一つとして「大人の考え方」を、挙げてみた。
ほかに、いくらでも変えられそうなものはあるだろうし、子育て中の人なら「私もひとこと言いたい」と思っている人もいるだろう。
数多ある環境要因の中で、どれを変えたら子どもは生きやすくなるだろう?
あなたが変えられる権力を持っているとしたら、何を変えてあげたい?
または、自分が子どもだった頃、何を変えて欲しかった?
それを大人が想像し、生きやすい学校を作ろうと試行錯誤することが、今起きているいじめの解決策であり、未来に起きるいじめを根絶する方法だと思う。
**連続投稿455日目**
最後まで読んでくださって、本当にありがとうございます。 サポートは、お年玉みたいなものだと思ってますので、甘やかさず、年一くらいにしておいてください。精進します。
