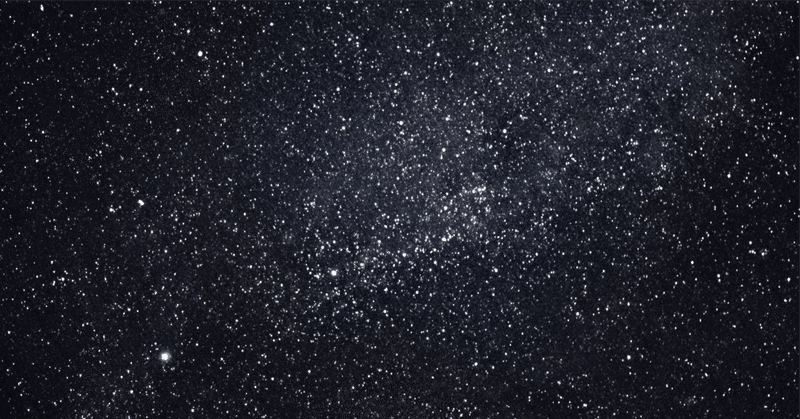
「スター・トレック」のテーマ
「スター・トレックのテーマの考察」に書いた文章を転載します。
「スター・トレック」シリーズ全体としての中心的なテーマは、一言で言えば、「あるべき人間性の追求」ということだと思います。
その「あるべき人間性」は惑星連邦の理念である「人道主義」と言い換えることもできるでしょう。
細かく展開すれば、「平和主義」、「同盟主義」、「利他主義」、「生命尊重」、「個の重視」、「異文化の尊重」、「多様性の尊重」などです。
また、「フロンティア精神」、「成長」、「自立」といったものも含まれます。
フロンティア精神
「スター・トレック」製作開始時のコンセプトは、「宇宙を行く幌馬車隊」でした。
つまり、西部劇のフロンティア精神を、宇宙に置き換えたものです。
これにはアポロ計画進行中という時代背景もあったのでしょう。
ですから、最初のTOS(オリジナル・シリーズ)の主なテーマは、ナレーションでも語られる「フロンティア精神」であり、「探索」、「出会い」です。
そして、これは、以降の各シリーズによってその重要さには差がありますが、すべてに継承されています。
特に、最初のワープ船による宇宙探査を描いたENT(エンタープライズ)では、重要なテーマの一つになっています。
ですが、ワープ以前の文明には不干渉、ワープ以降の文明には惑星連邦への加盟を促すという連邦のルールに示されるように、「フロンティア精神」は、かつてのアメリカが原住民に対して侵略的開拓を行ったこととは異なります。
これには、当時の製作者のロッデンベリーのベトナム反戦思想も反映されているようです。
知性と感情と論理
TOSでは、先に書いたように「フロンティア精神」が主要テーマでしたが、「人間性」のテーマも、異星人のスポックを鏡として、カーク、マッコイのキャラクターとの対比の中で描かれました。
スポックとマッコイの関係は、「論理」と「感情」の対立として、面白おかしく、そして、分かりやすく描かれます。
また、スポックとカークの関係は、「論理」と、「論理の前提を覆す知性」として対比されています。
それは、チェスとポーカーにも対比されます。
TNG(ネクスト・ジェネレーション)では、最初のエピソードと最終回のエピソードで、Qがピカードに果たしたテストとして「あるべき人間性」が描かれます。
それは「知性」の成長です。
具体的には、「既成概念に捕らわれない知性」です。
これは、TOSが描いたものとは少し異なりますが、その延長線上にあります。
TOSでは「感情」を否定するスポックを鏡として人間性を描きました。
そして、「感情」をプラス、マイナスの両面があるけれど、人間にとって大切なものとして描かれていました。
例えば、エピソード「タロス星の幻怪人」では、豊かな感情体験を求めるタロス人と、その元に半身不随になった船長のパイクを送り届けるスポックが描かれます。
それに対して、TNGは「感情」を持ちたいと望むアンドロイドのデータを鏡として人間性を描きます。
スポックとデータは、「論理的な知性」を持つ点では共通しますが、「感情」に対する姿勢は正反対です。
そのため、TNGでは、「感情」の是非は主要テーマとなりませんが、データに「人権」が認められるかというテーマが描かれます。
これは、「人間性」を持つすべての存在には「人権」を認めるべきという主張です。
「人権」のテーマは、VOY(ヴォイジャー)では、ホログラム・ドクターの「人権」として継承されます。
また、VOYでは、効率性・合理性を重視する元ボーグ・ドローンのセブン・オブ・ナインが、人間性を取り戻す物語として「感情」の重要性が描かれます。
ですが、ここでは「集合体/個」という観点が中心となります。
TOSのスポック、VOYのトゥボック、ENTのトゥポルに代表されるヴァルカン主流派の思想は、「感情の抑制」です。
ですが、映画第5作「新たなる未知へ」ではスポックの兄のサイボックの思想、ENTでは非主流派のシラナイトの思想として、感情を見つめ、肯定するヴァルカン人が描かれました。
そして、DIS(ディスカバリー)では、スポックが、姉マイケルを「論理と感情のバランス」と表現します。
そのマイケルは、ロミュランのクォワト・ミラットに入った実の母から「絶対的な素直さ」で導かれます。
否定説的な鏡としての敵対種族
「スター・トレック」では、敵対的種族、あるいは非敵対的種族を逆説的、否定的な鏡、つまり、悪い例として対比して、惑星連邦の人道主義的理念、「あるべき人間性」を描きます。
先に書いた、感情を否定するヴァルカン人も、人間にとって感情の重要性を表現するための鏡と考えることができます。
ENTでは、フロンティア精神、リスクを取らない種族として描かれます。
同様に、戦闘的なクリンゴン人や、ノーシカン、ケイゾン、ヒロージェンなどは、あるべき非暴力主義、平和主義を示します。
陰謀工作に長けた秘密主義のロミュラン人は、あるべき透明主義、同盟主義などを示します。
経済(金儲け)至上主義のフェレンギ人は、それ以外の価値の重要さを示します。
ちなみに、連邦の多くの種族では貨幣経済がなくなった設定になっています。
また、集合意識、専制的・全体主義的支配が特徴のボーグ、ドミニオンなどは、あるべき個の尊重、自由、平等などを示します。
また、種族ではありませんが、平行世界(ミラー世界)のテラン帝国も、対比的に惑星連邦の理念を示します。
そのテラン帝国/惑星連邦の対比は、帝国主義/同盟主義、覇権主義/平和主義、権威主義/人道主義、暴力主義/平和主義、といった具合です。
集合意識と個の尊重
中でも、TNG、DS9、VOYで、敵対勢力のボーグや創設者のドミニオンを鏡とした集合意識/個の尊重の対比は、大きなテーマでした。
ボーグは基本的に「個」を許容しません。
創設者の「偉大なるつながり」は「個」を許容するようですが、配下のボルタ、ジェムハダーら固形種の異種族に対しては、奴隷のように支配し、「個」の自由は許されません。
TNGではピカードが、「個」という概念・機能を持ったドローンのブルーをボーグ集合体に与えることで、集合体を揺さぶろうとします。
先に書いたようい、VOYでは、ボーグ集合体から切り離されたセブン・オブ・ナインが、個としての人間性を取り戻す過程が、一つの物語のテーマになっています。
PIC(ピカード)では、個を取り戻したセブン・オブ・ナイン、ブルーは、他の元ボーグが人間性を取り戻すことを援助する活動をしています。
DS9では、ドミニオンに卑下にされたカーデシア人の一部が反乱を起こすことが、ドミニオンの敗戦につながりました。
可変種のオドーは、「偉大なるつながり」に魅惑されながらも、個を持つ固形種の連邦の側につきました。
理想と現実の矛盾
基本的には、惑星連邦や宇宙艦隊は人道主義的な理想を持ち、各シリーズの艦長や主人公はそれを体現します。
ですが、各シリーズで描かれる理想と現実の矛盾、そして、連邦や艦隊と主人公の対立は、興味深いテーマです。
多くのシリーズでは、敵との戦いという現実の中では、連邦は必ずしも人道主義的な理念を守りきれません。
自身を守るという大義のためには、人道主義を捨てる選択も行います。
各シリーズの主人公、艦長は、それぞれに、この理念と現実の中で揺れ、苦悩します。
TNGのピカードは、誰よりも連邦の人道主義的理念を体現し、それを守る人物として描かれます。
TNGの後継シリーズであるPICでも、キャラクターは同じですが、連邦は理念を失った存在として描かれ、ピカードは連邦と離れて行動します。
それに対して、DS9の物語は、複雑な政治状況や全面戦争下の設定であるため、シスコは連邦の理念を守ろうとしつつも、厳しい現実の中で、何が正義かを悩み、妥協を迫られます。
TNGは冷戦中のシリーズですが、DS9は湾岸戦争後のシリーズなので、全面戦争や現実主義との矛盾が描かれたのかもしれません。
VOYはクルーを「家族」として捉えることが一つのテーマになっています。
ジェインウェイは、何度か早く地球に帰還できるチャンスがあったにも関わらず、連邦の理想の方を重視しました。
ですが、そのために帰還が遅くなり、クルーに多くの犠牲が出たため、連邦のルールを破って過去にタイムトラベルして歴史を変え、ヴォイジャーを帰還させました。
VOYのエピソードには、時間兵器を使って、歴史を自分の思い通りに変えようと(家族を生き返らせようと)何度も試みるけれど失敗するクレニム人が、時間が自分の傲慢さを罰していると語る物語があります。
ところが、同様のことをしながら、ジェインウェイは成功者となります。
ですが、その是非には議論があるでしょう。
ENTのアーチャーは、連邦設立の礎を築いた人物であり、理念を体現するスーパーマン的人物です。
それにも関わらず、ズィンディから地球を守るという大義のために、やはり、シスコ同様に理念から外れる判断(異星人からの強奪や拷問)を強いられます。
ENTは放映中に9.11同時多発テロが起こって、その影響を受けたシリーズです。
シーズン3のズィンディの地球攻撃は9.11テロを反映したものでしょう。
ですが、アメリカがテロや中東との戦争に突き進んだのに対して、アーチャーはズィンディを説得して戦争を止めようとしました。
ここには、明確に、米政府に対する批判があります。
DISのマイケルは、船を守るために、連邦の理念、上司の命令に反して、クリンゴンに先制攻撃を仕掛けようとして、反逆罪に問われました。
ですが、クリンゴンに追い込まれた連邦は、理念に反してクリンゴンを母星ごと破壊しようとし、今度はマイケルがそれを阻止して戦争を終わらせます。
最初と最後で、連邦とマイケルの立場が逆転しています。
また、理想主義的な連邦の理念が現実に持つ矛盾を象徴する組織に、セクション31とマキがあります。
両者は、連邦の建前に対する影の存在です。
この2つの組織が特に重要な意味を持って描かれるのはDS9です。
これらの存在は、連邦の理想や「あるべき人間性」のテーマを深めています。
検索エンジンのインデックス状況が弱いので、以下に目次を掲載します。
◆シリーズ全体
・シリーズ全体としての主要テーマ
・製作のタイムライン(基礎データ)
・正史のタイムライン(基礎データ)
・ミラー宇宙のタイムライン(基礎データ)
◆各シリーズのテーマ
・オリジナル・シリーズ(TOS)
・ネクスト・ジェネレイション(TNG)
・ディープ・スペース・ナイン(DS9)1
・ディープ・スペース・ナイン(DS9)2
・ヴォイジャー(VOY)
・エンタープライズ(ENT)
・ディスカバリー(DIS)1
・ディスカバリー(DIS)2
・ピカード(PIC)
◆個別テーマ
・惑星連邦と合衆国の比喩
・絶対的な導き手
・感情の肯定と否定
・バルカンとロミュランとその少数派の思想
・連邦の理念と妥協
・セクション31とマキ
・個の重視と集合意識
・アンドロイドとホログラムの人権
◆個別エピソードと様々なテーマ
・「あの頂きを目指せ」(DS9)
・「ドクターの家庭」(VOY)
・「ドクター心の危機」(VOY)
・「死の観察者」(ENT)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
