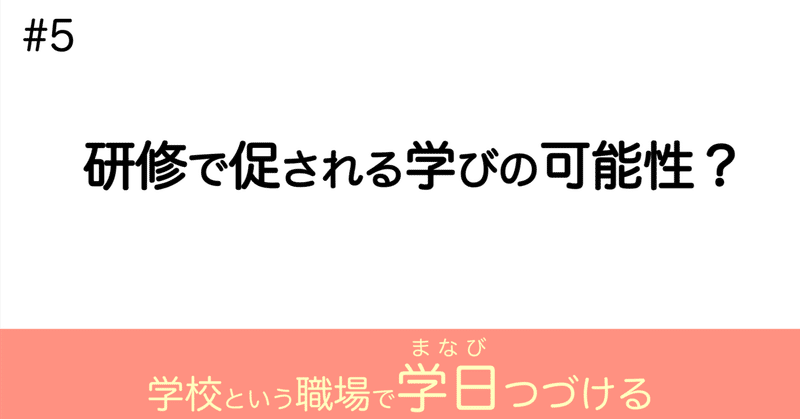
「研修」で促される学びの可能性?
先回の記事では,人材育成を大きく分けると,「Off-JT(いわゆる研修)」「OJT」「自己啓発」の3つがあり,それぞれのやり方に特徴があるということを確認しました.
中原(2014)によれば,2000年代以降は,「どちらかというと『経験重視(OJT)』の方に,振り子が揺れている状況」と述べられています.
同著で取り上げているのは,MORRISON and BRANTNER(1992)が言及している次の内容です.
成人が仕事をするに当たって必要な業務知識量を身につけるのは,仕事の経験が70%,上司の薫陶が20%,研修が10%
"What Enhances or Inhibits Lerning a New Job : A Basic Career Issues."
Journal of Applied Psychology.Vol.77 No.6 pp.926-940
なんと,研修では10%しか学べていない(!?)という・・・これだけ見ると,確かに「経験が大事なんだなぁ」と思いますよね.
しかしここで中原(2014)は,このようなデータの受け止め方を考えるためには,「時間」と「外的コントロール」のことを忘れてはならないとし,この「10%」の意味を考えています.
一般に22歳から60歳まで働く6万8400時間のうち,研修を受けている時間は何時間あるでしょうか?これは会社によって異なりますが,若年労働者を除く一般社員の場合,一年のうち3日程度が研修に充てられる日ではないでしょうか.それらをすべて積み重ねたところで,22歳から60歳まで,100日も見たいないことが予想されます.
つまり,時間的にはわずかな機会で,成人の能力発達の10%分が保証できるのであれば,非常に効率がいい,という考え方もできるのです.
確かに,校内研修も,年間数回行うのが関の山です.この数回の研修が支える効果について,さらには,日々の業務経験との連動を考えて行うことで,よりよい学びが生まれてくるのかもしれません.
今回は少し短めでしたが,そもそも「研修」で促される学びってどの程度なんだろう?ということを考えました.次回は,OJTについて述べていきます.
読んでいただきありがとうございました.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
